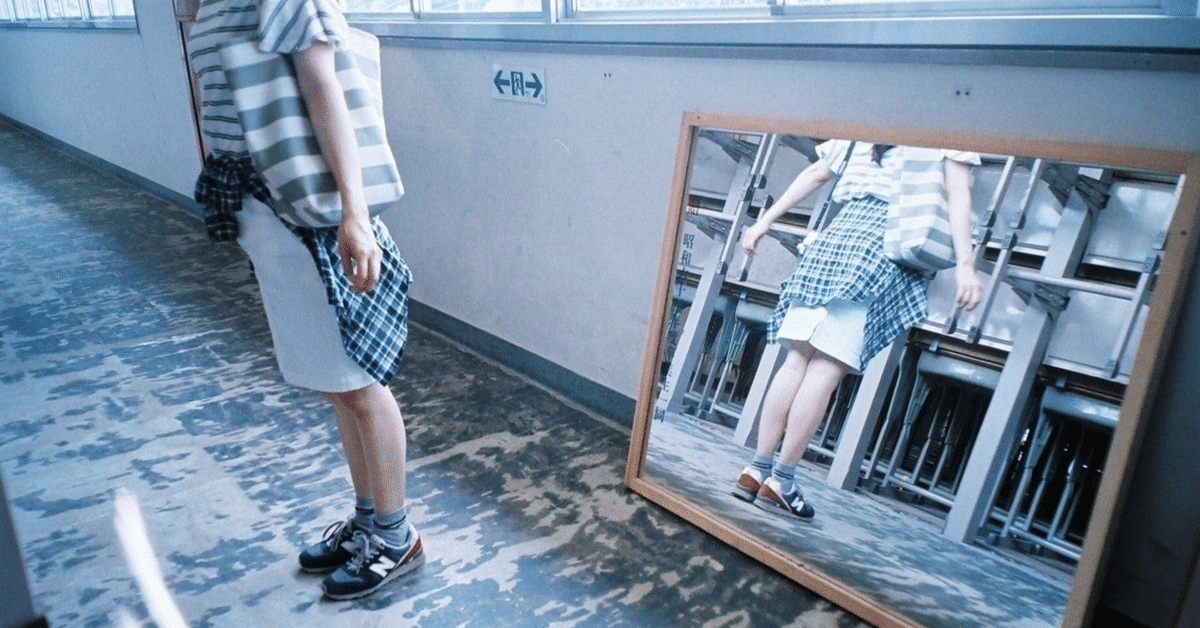
【愛恋掌編②】面倒くさい男と別れる方法
僕の数少ない趣味は、休みの日に家の近くのドトールに出かけて、人の話を聞くことだ。古い商店街の一画にある店では、必ず面白い話が耳に入ってくる。休みの日のたびに競馬新聞を持って予想をしているおじさんとか、高校の同窓会帰りのおばさんたちとか、若い女性が中年にネットワークビジネスの勧誘をしている様子とか。(でも、これは、かわいい年下の女性への下心のためだまされている中年男性の姿が自分と重なるから、あまり好きではない)
何といっても聞いていて心が浮き立つのは、今ではもう接する機会がなくなった若い女性たちの恋の話だ。世の中では草食系男子が増えているとか、若い世代は恋愛に対する関心が失われているとか言うけれど、そんなのまったく嘘ではないだろうか。少なくともこのドトールでは、若い女性が二人で長く話し込んでいれば、それは必ずつき合っている相手、もしくは気になる相手の話なのだ。そして露出が激しめの服装をしている女性より、控えめな服装をしている女性の方が必ずと言っていいほど、大胆な話をするのだった。
「今つき合っている彼、束縛がひどいんだよね」
長い髪を指でくるくると巻きながら、リサが言う。
「会社からマンションに帰るころを見計らって、必ず家に電話をかけてくるし、休みの日もメールでどこに出かけるか報告させられるし」
「えっ、それやばくない」
「最初はね、私に関心がある証しなのかと思ったわけ。でも、最近ちょっと違うかなって思うようになってきた」
なぜ、この世の女性たちが、女性を相手に話すときのスピードは、男性と話すときの一・五倍なのだろうか。男にはまったく立ち入ることのできない世界だ。これは、いい話に出会ったと思う。僕は読みかけの文庫本のページを繰るのを止めて、耳をそばだてる。
「そんな彼、別れた方がいいんじゃない。りっちゃん、かわいいんだし」
「だけど、彼、泣くんだよ。別れ話をすると」
ナツキは、リサと向かい合わせに座っている。眉のあたりにしわが寄った。
「泣くって、なに」
「別れたくない。リサに見捨てられたら、おれ、死んじゃうって言うの」
「それって、将来、DV男になるパターンの典型じゃない。やばいよ、早めに別れた方がいいよ」
「でも泣いた後は、すごく優しくなるんだよ。ずっと抱き締めてくれて、いつまでもキスしてくれるし」
「それが、やばいんだよ」
テーブルに置いたリサのスマートフォンが、先程から、何度も短い振動を繰り返している。しばらく無視をしていた彼女がうざったさそうに手に取った。
「ほら、これ見てよ」
液晶画面には、男からの居場所を知らせてほしいというショートメッセージが何通も来ていた。
「友達いないのかな」
「やばいね、それ絶対、やばいやつ」
やっぱり、もっとおかしくなる前に別れた方がいいのかなと言って、リサは再び、指先で髪をくるくるっと巻いた。よく見ていると、彼女はずっと髪の毛先ばかりをいじっている。髪を触るとは、性的に何かを求めていることの隠喩だと書いてあったのは、どこで読んだ本だっただろう。二人の話を聞きながら、僕はリサが男と絶対に別れる気がないと確信する。
それって、ただののろけでしょう。本当はリサ、全然、別れる気がないよね。許されることならば僕は思いっ切り突っ込みを入れたい。だが、それを口にした瞬間から僕は変質者になってしまう。僕にできることは、コーヒーカップに口をつけることだけだ。
「じゃあ、教えてあげる」
ナツキが突然、意を決したように言った。
「何を」
「だから、そのDV予備軍の彼ときっぱり別れる方法だよ」
今まで以上の早口になって、彼女が説明を始める。
まず、このドトールのようなチェーン系の喫茶店にその彼を呼び出す。
向かい合わせで座る席に座って、あなたは束縛が常軌を逸してひどいから別れたいと、きっぱりと言う。
「でも、そしたらいつものように泣くじゃない」
リサが不安そうに言う。
「最後まで、話をきちんと聞きなよ」
彼が泣き始めたら、泣き終わるまでじっくりと話を聞いたふりをする。一息ついたところで、でも、やっぱり嫌いなのとはっきり言う。
あんた、自分では自分が女を大切にする優しい男だって思ってるかもしれないけど、単に自信がないだけだよね。こんなに、しょっちゅう電話とかメールとかかけてさ、暇なの、ああ暇なんでしょう、私のことばっかりかまけている時間があって、要は勉強とか、仕事とか、することがないだけだよね。そのくせ、私のことは全然見ていないじゃない。髪を切ったって、新しい洋服を買ったって何にも気づいてくれないし。最近は、二人で会っても、家で黙ってテレビゲームをしているばっかりだし。たまに、外でデートをするにしても、計画を立てるのは全部、わたしだし。どういうつもり。本当に別れたくないの。
じゃあ今から、わたしのいいところを今からノートに百個ほど書き上げて見せなさいよ。全部、感動させてくれる言葉じゃなきゃだめだからね。そのうえで知性があって、レトリックがあって、うっとりさせてくれなきゃだめだからね。えっ、そんなことできないって、その程度のつもりで、わたしのことが好きだったの。その程度で、束縛してたの。縛りつけるんだったら、もっと本気でかかって来いよ。そんなぬるい気持ちで、わたしのこと好きになるんじゃねえよ。大体、あんた、キスとか下手なんだよ。感性がないんだよね。生きるセンスがそもそも、あんたには備わってないんだよ。
呆気にとられた様子で、リサは罵倒の言葉を並べ続けるナツキを見る。
「相手が再び話し始める前に、機先を制して言うのがこつだからね」
「これでかなり、いいところまでいけると思うけど、最後の仕上げも教えとくね」
「最後の仕上げ?」
ナツキは、机の上でリサの手を取って指を重ねるようにして組ませた。目を閉じるように言った後、組んだ指と指の間にスプーンを挟ませる。
指と指の間に、リサは金属の冷たい感触を覚えた。
「スプーンに念を送って」
「念って、なに」
「念じるの、スプーンに向かって、集中して念を送るんだよ」
「なに、それ」
「ほら、やって」
スプーンを持ったままリサが目を閉じ、みけんにしわを寄せた。その細い首が急に、舳先と柄を結ぶ首であろうとする意志を失い、役割を放棄したように、ぐにゃりと曲がった。三十度とか少し角度がおかしいといった感じではなく、九十度を超え、大きく百二十度は折れ曲がった。
「えっ、どういうこと」
「知らなかった。スプーンなんて、その気になれば誰でも曲げられるんだよ」
そして、これ以上、わたしにつきまとったら、あなたのことを一生、苦しめてやるってささやいてみてと言った。
ナツキはもう一度、リサにスプーンを持たせた。二十代の女性らしい白い血色のいい手の上に包み込むようにして自分の手を重ねて、もう一度強く握りしめた。
店の中で、突然にコーヒーを飲んでいた客の間から小さく声が上がり始めた。さざなみのようなざわめきは次第に高まって、やがてはっきりと悲鳴に変わった。
見回すと、二階の店内でコーヒーを飲んでいた客たちのスプーンが、みな折れ曲がっていた。
カップの隣に置いていた僕のスプーンも、くの字に形を変えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
