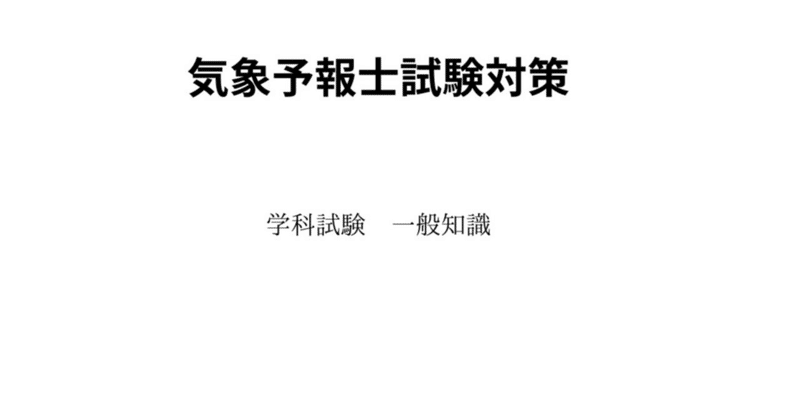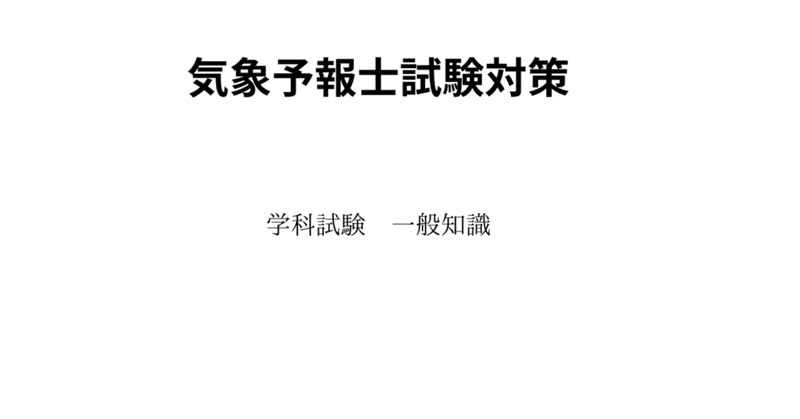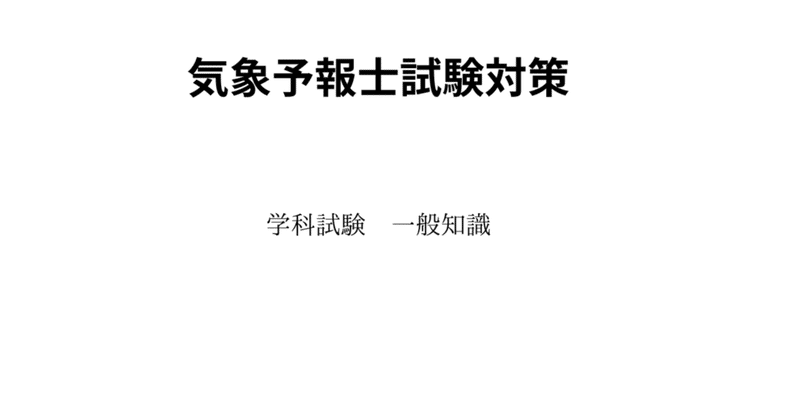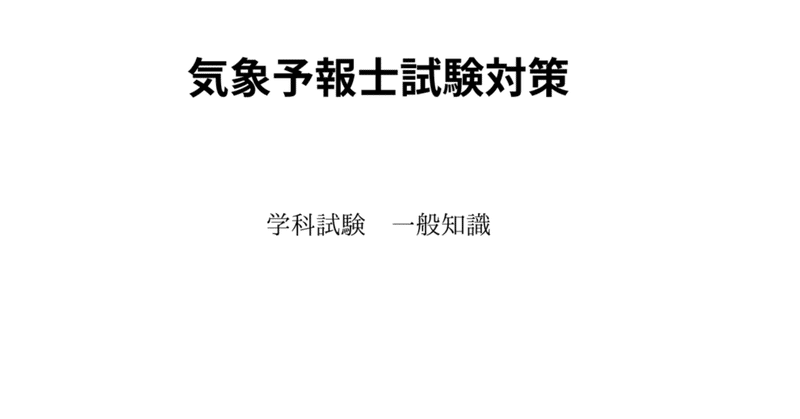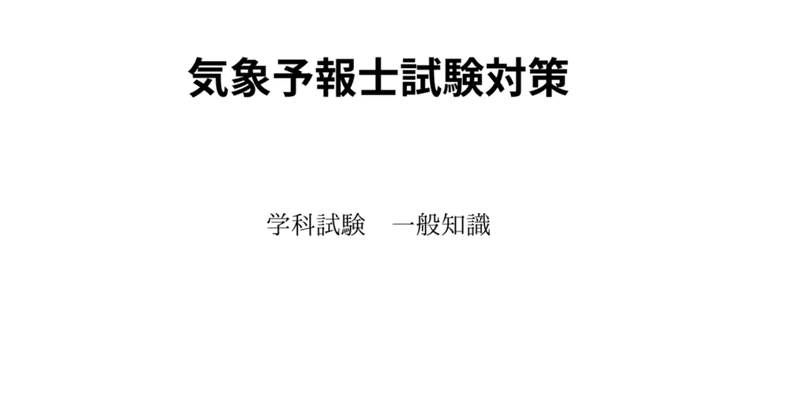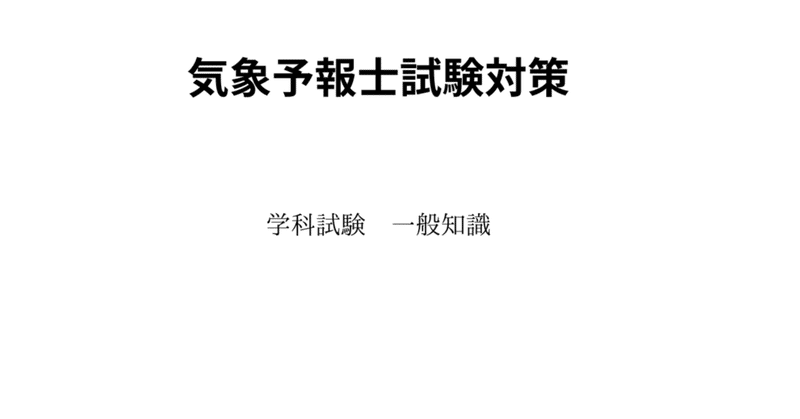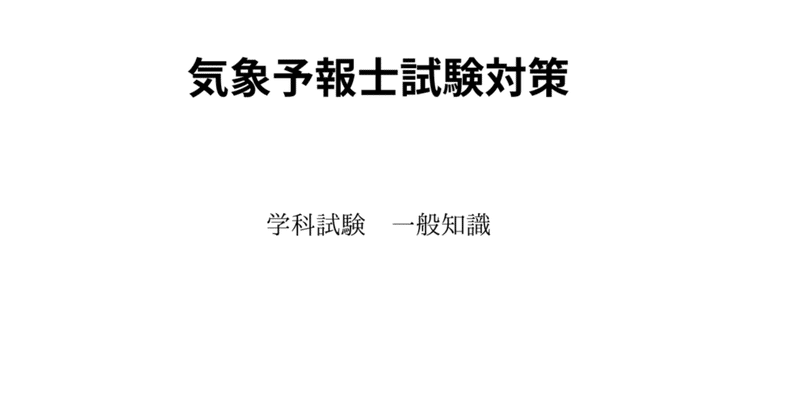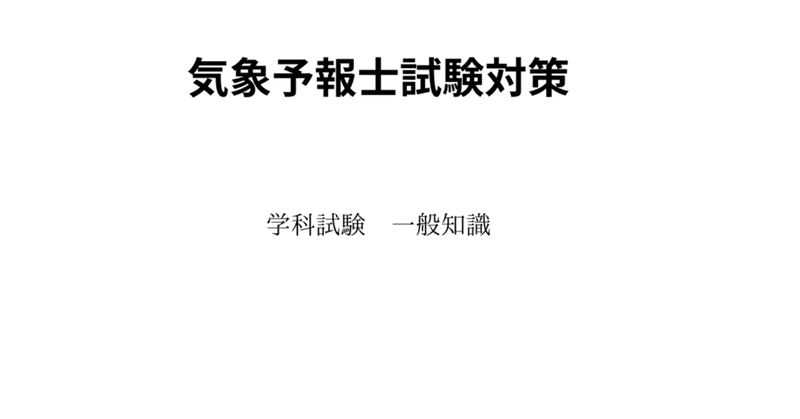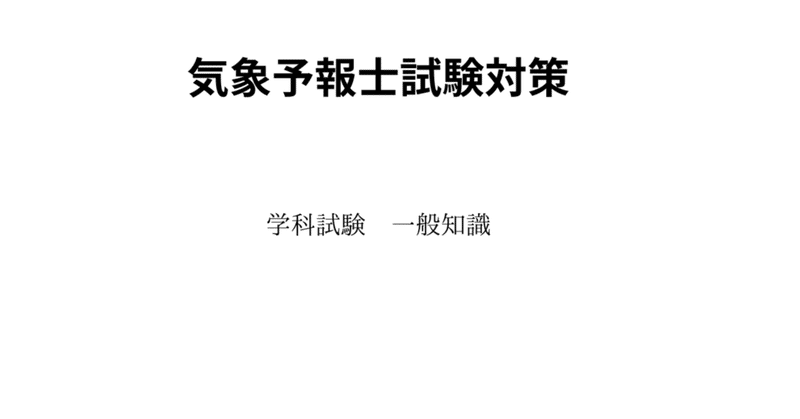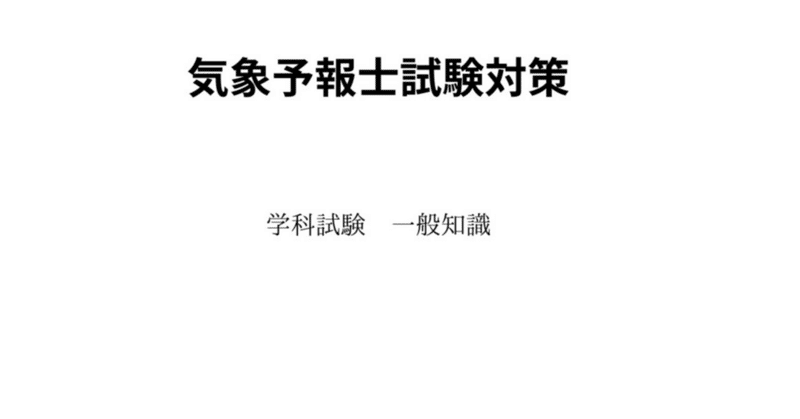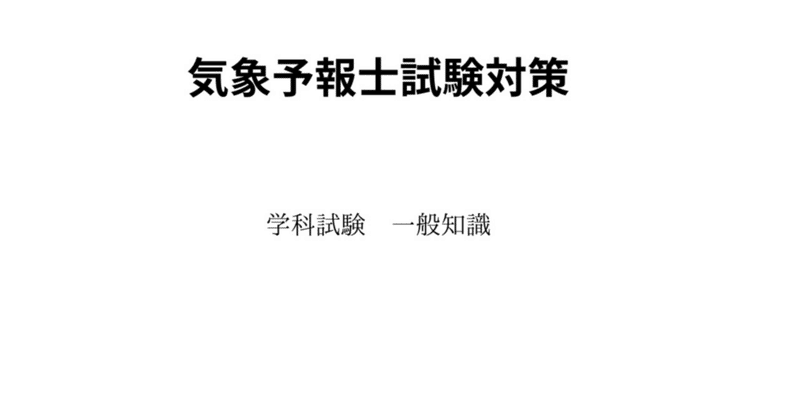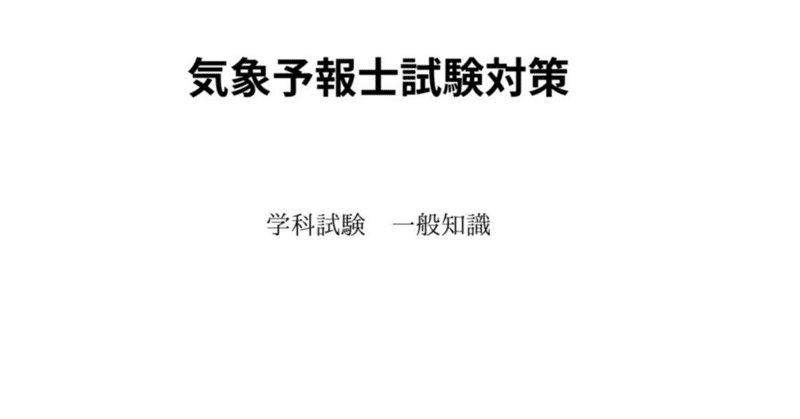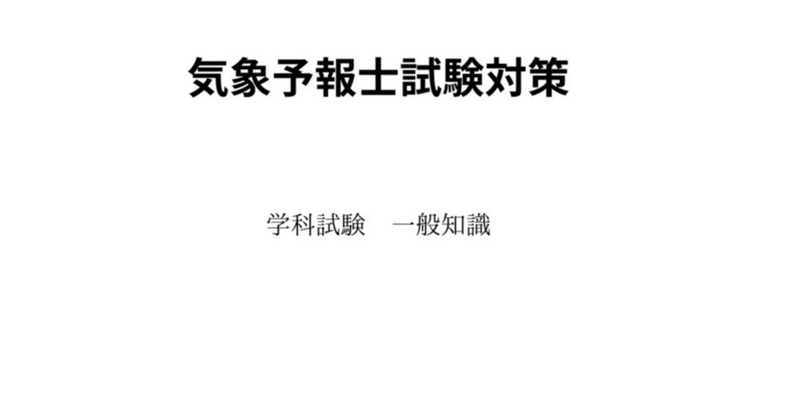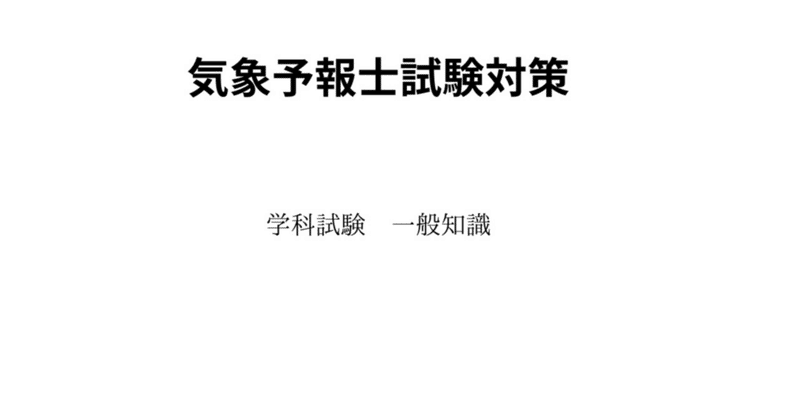2024年3月の記事一覧
気象予報士試験 学科 一般知識 大気の熱
空気の熱力学などを学んだ後は、地球の大気を温める熱源と熱の伝搬について学びます。大気の熱源の大部分は太陽からのエネルギーです。
気象学などの教科書では、「黒体放射」とかプランクの法則、シュテファン・ボルツマンの法則などの説明があり、難しいなぁと感じる人もいるかもしれません。
山を張るわけではありませんが、どうしても理解が困難な場合は捨て問にしてその他で確実に得点するという戦略もあります。実技試
気象予報士試験 学科 一般知識 大気の安定度
よく天気予報を聞いていると特に梅雨期や夏季に「上空に寒気が入って大気が不安定になり・・・・」というフレーズを耳にすることが多いと思います。
大気が不安定になると天気が荒れます。荒天になるとはどういうことでしょうか?「荒天」と同じ読み方で「好天」があります。全く正反対です。
荒天(severe weather)。確定した定義はありません。しかし、好天と正反対で雨や風がつよく、雷が鳴ったり落雷があった
気象予報士試験 学科 一般知識 熱力学
高等学校の物理の教科書をお持ちの方は、そちらをご参照ください。
理科系の知識が必要な部門です。
PV=nRT でお馴染みの式。n:物質量(mol)
密度ρは空気の重さnを体積Vで割ったものなので、上式は
P=ρRTと書けます。 P:圧力、ρ:密度、R:気体定数、T:絶対温度
↑この式を使って解答する問題が出題されています。
🔵ボイルの法則
PV=nRTを見てみましょう。気体の温度を一定として