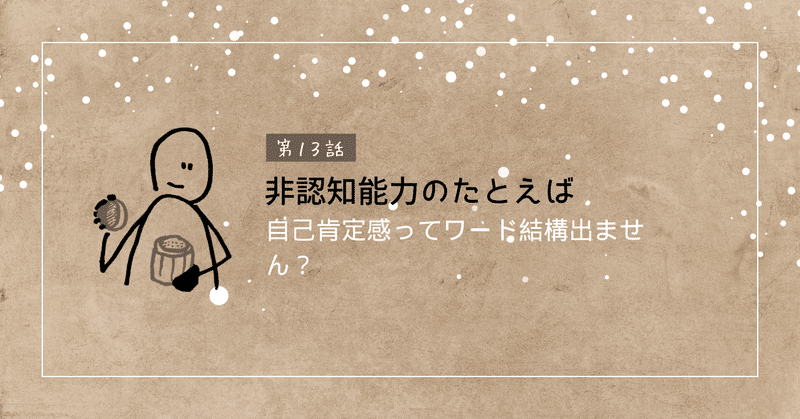
スウェーデンと日本初!非認知能力を伸ばす実践アイデアブック! 著 中山芳一 田中麻衣 德留宏紀
今回ご紹介したいのはこちら。
認知能力と非認知能力は「コインの裏表」
認知能力か非認知能力かという話ではなく,お互い背中合わせでつながっているんですね。
中山さんはそれはスペクトラムのようにつながっているともたとえています。
そんな非認知能力は,認知能力に重きを置いてきた国々で見直す動きが盛んに見えてきているそうです。
片方に流れれば,反動に逆に流れていくということもあるのかもしれませんね。それがいいか悪いかは置いておくとして,非認知能力が一過性のものではなく,これからも大事なものとして扱われていくのはうれしいことです。
とはいえ,非認知能力という言葉こそあまり耳にしませんが,そういった力をこれまでも日本では大事に教育してきました。
ただ,数値化できなかったり目に見えにくかったりして共通認識が持ちにくかったことも相まって,うまく扱いそこねているのもまた事実です。
例えば…
授業の主体性どう見とってます?
粘り強さと自己調整の側面から見とるわけですが,授業のどんなタイミングで見とっていますか?
これって勘違いの見れちゃったつもりで授業を進めちゃったり,そもそも自己調整が働かないような授業計画にしちゃったりしているケースって結構ありませんか?
若干雑な言い方になりますが,トライ&エラーを授業内に仕組んであげないと粘り強さも自己調整も働かないはずです。
がちがちに固めた授業ではその余裕はなさそうですよね。
非認知能力を計画的に見とりにくいのもうまく扱いにくい理由の一つです。
自己肯定感って言葉をよく聞きませんか?
誤解があるまま言葉が使われがちなのも扱いにくい理由の一つだと感じています。
例えば「自己肯定感を高めて…うんぬんかんぬん」って結構耳にしませんか?
自己肯定感という言葉の中にも,ありのままの自分を受容できる「自己受容感」,何かができて認められることで生まれる「自信」,人のために役立つことで得られる「自己有用感」など,いろんな考え方がごっちゃになって使われている場面ありませんか?
そのせいで議論にずれが生じちゃったり,明後日の方向に向かって対策を練っちゃったりするんですね。
正しい理解がないままに話を進めてもだめだってことです。
今回はあまり本の内容に触れることができなかったので,もうすこし詳しく書きたいのですが,この扱いにくい非認知能力を知ることで,これまでしていた活動の解像度がさらに高くなるはずです。
私もこれから皆さんと一緒に解像度を高めていきたいと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
誰かの「よりどころ」になりますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
