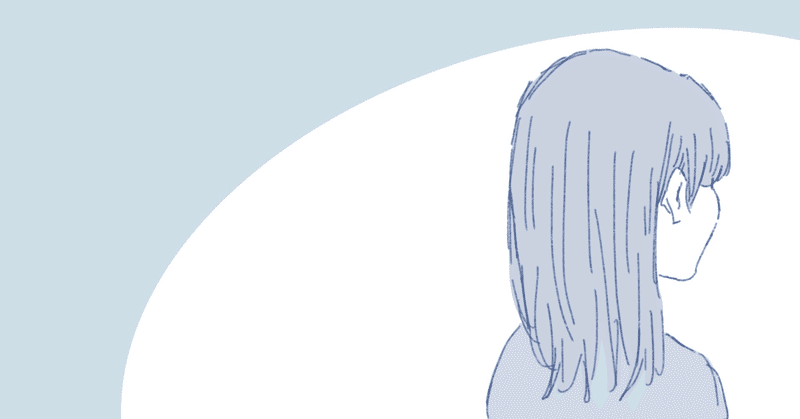
【極超短編小説】美しい妻
「女の子は顔じゃないよ。何より中身が大事だよ。性格が良くなきゃダメだ」
大学のキャンパスを歩きながら、僕はいつもの仲間に言った。
僕たち男4人は気が合っていて仲が良く、いつも一緒にいた。そして年頃の男の話題といえば当然女の子のことが多かった。
「お前はイケメンだからそんなこと言うんだ」
友人の一人が異を唱えた。
「はー?僕がイケメンだって?普通だろ。こんな顔」
今度は僕が反論した。
「お前、本気で言ってるの?そうだとしたら嫌味だぜ」
と言った別の友人は苦笑した。
「お前たち、からかってんのか?腹立つな」
僕は言い返した。
秋の空は澄み渡り、遠くの鉄塔もくっきりと見えた。広いキャンパスの芝生はよく手入れされて、緑が目に気持ちよかった。
僕たちは女の子の話題で持論を披露し合いながら、キャンパスを歩いていると、正面からやはり4、5人の女の子のグループがにこやかに喋りながらこちらに歩いてきた。
「おい、あのグループ見ろよ。学内で一番綺麗だっていう噂のミスキャンパスがいるぜ」
友人の一人がその女の子のグループをちらりと見て言った。
一目惚れとはこういうことなんだ、と僕は初めて分かった。目を奪われた。一瞬息が止まった。
と同時に友人たちには、それが知られないように何食わぬ顔をした。「女の子は顔じゃないよ。何より中身が大事だよ。性格が良くなきゃダメだ」とついさっき言った手前、一目惚れしたことを知られるわけにはいかなかったからだ。
その日から、僕の頭の中はその女の子のことでいっぱいになった。性格も中身もなんにも知らないのに。日が経つごとに好きな気持が強くなって、自分の想いを伝えずにはいられなくなった。胸が張り裂けそうとは、こういうことなのだろう。
美人のその女の子、彼女のことを誰にも気づかれないように調べた。学部、学年、名前、行動パターン。僕は彼女と二人きりになれるチャンスを探した。告白するためだ。そして、ついにその時が訪れた。学内の裏庭にあったベンチで、彼女は一人で本を読んでいた。
「座っていいですか?」
僕は彼女に声をかけた。心臓はこれ以上ないくらいにドキドキしていた。
「は、はい。ど、どうぞ」
彼女は顔を赤くした。
「僕のこと……知らないですよね?」
「校内で見かけたことがあります。3年生ですよね?」
僕のことを初めて見るわけではなさそうだった。とりあえず、全く知らない不審者の扱いではなくて少しホッとした。
「突然、こんなこと言うの迷惑かもしれないけど……この前、キャンパスで君を初めて見て、すごく綺麗だな、可愛いな、美人だなって思って、好きになりました。一目惚れしました。忘れられません」
昨夜考えたセリフをそのまま言った。思っていること以上のことは言えないし、他にうまいセリフも思いつかなかった。
「からかわないでください!」
「えっ!そんな……からかってなんかいない!本当にひと目見た瞬間から……」
「嘘!あなたみたいな素敵な人が、私なんかに一目惚れしたなんて……」
彼女はうつむいて肩を震わせた。
「嘘じゃないよ、本当に好きになったんだ!信じてよ!」
僕は懇願するように彼女に言った。
「ごめんなさい、私、講義があるから」
そう言うと彼女は俯いたまま立ち上がり、校舎に向かって歩いていった。
ベンチに一人残された僕は考えた。振られたというわけじゃない。嫌われたというわけでもない。ただ僕の想いを信じてくれないだけだ。それなら、彼女が僕の言っていることを信じてくれれば、振り向いてくれるかもしれないし、もしかしたら付き合ってくれるかもしれない。
そう考えた僕は翌日から彼女の後をつけて、彼女が一人になる機会を待った。そして彼女が一人になるたびに、僕は必死に想いを伝えた。何度も何度も。もちろん、いつもの仲間にバレないようにだ。
数週間後、彼女はようやく僕の想いを信じてくれて、付き合い始めた。実際付き合ってみると、彼女の中身に惹かれた。優しいところ、気の強いところ、冷静なところ、頭の良いところ、何より僕を大切にしてくれるところ。 彼女の容姿に一目惚れしたのに、僕の中で容姿のことは些細なことになった。そして、大学を卒業し、しばらくして僕と彼女は結婚した。
「君は今日も可愛くて、綺麗で美人だね」
僕は毎朝、彼女、妻を見るたびにそう言わずにはいられなかった。結婚して数十年経った今でもなお、僕の気持ちは変わっていなかった。
「あなたやっぱり変わってるわね。私、ブスよ」
妻はキッチンで朝食を作りながら応えた。
「いや、君は綺麗だよ」
「あなた、私をあなたの友達に紹介した時のこと覚えてる?」
「ああ、覚えているよ。みんな驚いていたな」
「どうして驚いていたか分かってる?」
妻は食事を作る手を止めて、振り向いた。
「女の子は顔じゃない。性格だ」なんてことを言ってた僕が、可愛くて綺麗な君を連れてきたからだろ」
「はあ〜、あのね、あなたの友達は私じゃなくて、ミスキャンパスだった美人の子を連れてくると思ってたの。私はあのグループの中で一番ブスで、そのブスの私を連れてきたことに驚いたの」
「ミスキャンパス?気づかなかったな。あのグループの中で君が一番美人で、僕は一目惚れしたんだ」
「あのね、私は小さい頃からブスって言われてて、世間一般的にもブスよ。それが普通の感覚なの。私も自分で自分のことブスだなぁて思うもの」
「……君ってブスなの?」
僕は目から鱗が落ちる思いだった。
「そうよ。あなたのお母さんが初めて私を見た時、なんて言ったか覚えてる?」
「いや、覚えてない」
「あなたが好きそうな娘だって言ったの。そしてお父さんと同じだって」
「何それ?」
「私もお母さんもブスってこと。私とお母さんが仲がいいのも、そういうことかもね。でも、あなたは本当にイケメンよ」
妻はそう言ってカラカラ笑いながら、再び朝食を作り始めた。
「いや、いや納得行かないなあ。僕は、君は可愛くて綺麗で美人だと思うけどなあ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
