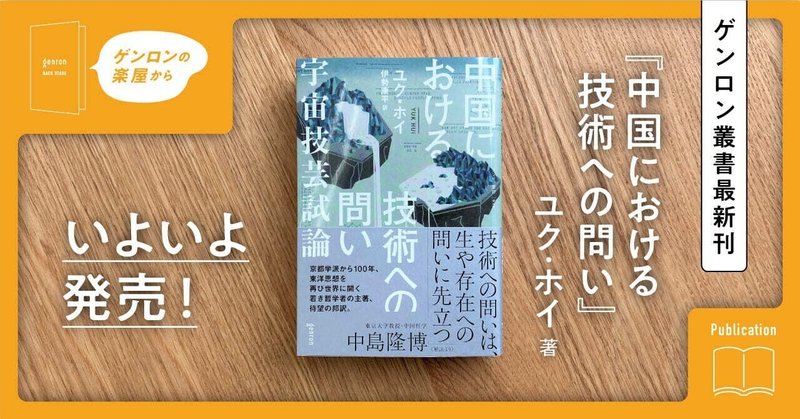
来週発売!『中国における技術への問い』ってどんな本??
いよいよ8月30日に発売となる『中国における技術への問い』。世界的な注目を集める若き哲学者、ユク・ホイ氏の主著ともいえる本書の問題意識はどこにあり、彼は何を解き明かそうとしているのか。孔子や荀子、荘子ら諸子百家から、西田幾多郎、さらにリオタール、スティグレールから人新世まで。壮大なスケールで展開される本書はいったいどんな本なのか。訳者である伊勢康平さんに聞いてみました。
ユク・ホイの『中国における技術への問い——宇宙技芸試論』は、一言でいえば、技術の多様性について哲学的に考えようとする本です。
哲学に関心のある方はお気づきかと思いますが、この本のタイトルは、ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーの「技術への問い」という講演をもとにしています。ハイデガーによると、近代的なテクノロジーの本質は、プラトン以来の西洋の形而上学のものの見方とつながっています。つまりテクノロジーのなかでは形而上学が具現化されており、その意味で、テクノロジーが世界中に普及している現状は「形而上学の完成」と呼べるだろう——ハイデガーはこのように考えました。
この議論がもつ意味はとても深刻です。というのも、もしハイデガーの考えが正しいのなら、たとえ文化やアイデンティティなどの多様性を人々が強調し、認めていったとしても、だれもがおなじ原理をもつテクノロジーを使いつづける限り、私たちは根本的なところで西洋の形而上学に支配され、たえず均質化されていくことになるからです。
では、私たちはどうすればよいのでしょうか? ハイデガーは、プラトン以降に失われた「本来的」なものを求めて、ソクラテス以前のギリシア哲学にさかのぼりました。これに対してホイは、西洋のものとはちがったテクノロジーを構想するべきだと言います。これが技術多様性を構成するのです。
ホイの言う「ちがい」は、外見や機能の相違のことではありません。ハイデガーの技術論に対抗するのなら、あくまで哲学的に異なるテクノロジーについて考える必要があります。そこでホイは、かつて非西洋のさまざまな地域では、技術がそれぞれの自然観や宇宙論とのかかわりのなかで多様な理解をされていたことに着目します(ちなみにホイは、近代に西洋で誕生した「テクノロジー」と、時代や地域を問わず技術的なもの一般を意味する「技術」を区別しています)。
このように、技術を宇宙論との組み合わせのなかで捉えるべく、ホイは「宇宙技芸 cosmotechnics」という概念を提示します。ホイによると、これはなにか特定の技術をあらわしているのではなく、すべての技術がほんらいもつ性質なのです。
異なる文化のさまざまな技術は、それらの文化がもつ宇宙論の理解に影響され、ある特定の宇宙論的背景のなかでのみ自律性をもつ──技術はつねに宇宙技芸である。
宇宙技芸という概念の利点は、なによりまず、宇宙論の差異をつうじて技術の多様性を考えられるようになる点にあります。本書では、中国哲学における宇宙論と技術、そしてそれを用いる人間との関係が、プラトンやアリストテレス、あるいはストア派などと比較されつつ論じられます。とりわけホイは、それを道(宇宙と道徳の原理)と器(道具、技術的対象)の関係として描きました。
道家も儒家も私の言う「道徳的宇宙技芸」を体現している。これは宇宙と人間をめぐる関係的思考であり、そこでは両者の関係が技術的存在者によってつながれるのだ[…]儒家と道家を並行させるこの読解のなかでは、中国哲学における道は存在者の至高の秩序を意味しており、技術はその最高の境地へ達するために道と合致していなければならない。したがって、この最高の境地は道器合一と表現される。
ですが、このような道と器の関係は、こんにちでもそのまま利用できるほど有効なものではありません。それは歴史上何度も変化を繰り返し、中国が近代化してゆくなかで根底から解体されてしまったからです。そのためホイは、グローバル化する近代テクノロジーと向き合うためには、伝統的なものをあらたに捉えなおす必要があると語ります。
もっとも、これはさほど新しい問題ではありません。19世紀や20世紀から、世界の各地でこの問題が検討されてきました。ハイデガーはその一例です。またアジアに目を向ければ、日本の京都学派や中華圏の新儒家は、西洋の哲学やテクノロジーとの関連のなかで、仏教思想や儒家思想、道家思想の再解釈を試みました。そのほか、『ポストモダンの条件』で知られるジャン゠フランソワ・リオタールもまた、日本の禅僧・道元の思想を独自に解釈して、あらたなテクノロジーのありかたを構想しました。
ホイはこうした「近代の問い」や「テクノロジーの問い」の試みに一定の評価を与えてはいるものの、結果としてそのすべては失敗に終わったと言います。なぜホイはそう考えたのでしょうか? 宇宙技芸というプロジェクトは、どのようにしてそれらの失敗を乗り越えるのでしょうか?
かれの結論は、私たちのすべてにさらなる思考をうながすことでしょう。けれども、いまここでそれを明かすのは控えておこうと思います。詳細はぜひ、本書を手に取って確かめてください。
(伊勢康平)
---
いよいよ8月30日より書店発売開始!
諸子百家と人新世を結ぶ、まったく新たな技術哲学の誕生!
なぜ「技術」は西洋の伝統のうえでのみ定義され、論じられてきたのか?ハイデガーの「技術への問い」を乗り越え、破局へと暴走するテクノロジーに対抗するために、香港の若き俊英は文化的多様性に開かれた「宇宙技芸」の再発明に挑む。京都学派から100年。「近代の超克」を反省し、東洋思想を再び世界へと開くために必要な、「道」と「器」の再縫合はどうなされるべきなのか。諸子百家と人新世を結ぶ、まったく新たな技術哲学の誕生!
特設サイトはこちら!
Amazonなどでも予約受付中です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
