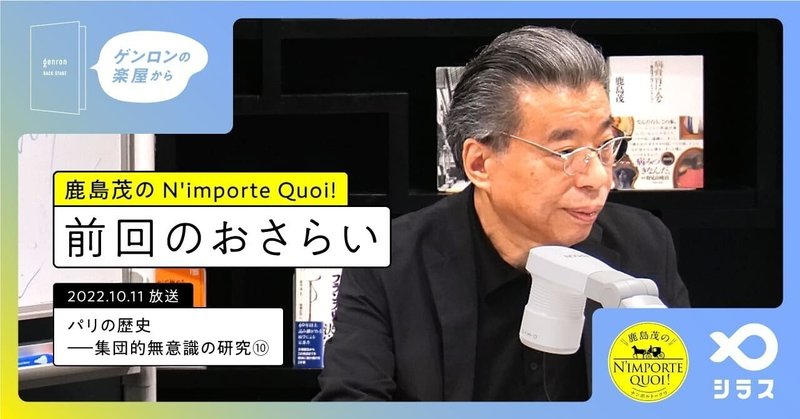
盛り場に集う人々の研究はいかに行いうるか――鹿島茂のN'importe Quoi!「前回のおさらい」
フランス文学者・鹿島茂さんによる講義チャンネル「鹿島茂のN'importe Quoi!」。「パリの歴史――集団的無意識無意識の研究」と題された講義では、パリという都市の成り立ちや、そこに集う人々、そして暮らす人々をさまざまな史料をもとに読み解いてきました。
10月に行われた「モンマルトルの名店と人々」と題した第10回目の講義では、あらためて講義名につけられた「集団的無意識」にフォーカスをします。見ていくのはおもに19世紀パリ、カフェやブラスリーと呼ばれる店に集まる人たちですが、現代でもどこかで見かけたような光景のような気もして……?さっそくおさらいしてみましょう!

1.カフェと集団的無意識
さて、今回見ていく「カフェ」や「ブラスリー」と呼ばれるようなお店ですが、集団的無意識が形成されるような「不特定多数の人が集まってくる場所」になったのはフランス革命後でした。何が違うかと言えば、「基本的には誰でも入れるようになった」ということ。革命以前にもカフェは存在していましたが、無階級的に、誰もが訪れることができる場所……ではなかったのです。
それ以前に集団的無意識を形成していたものに「サロン」があります。しばしばサロン・リテレール(文学サロン salon littéraire)、あるいはサロン・フィロソフィック(哲学サロン salon philosophic )と言われるような場がルイ14世の頃から設けられてきました。こうしたサロンを形成した人物としてはスタール夫人やレガミエ夫人といった人々が有名ですが、貴族だけではなく、文学者、芸術家、政治家、ときには革命家などさまざまな人々が集まり、さまざまなジャンルで一種の「党派性」を持つようになります。
こうしたサロンは革命後、社交の場としての性質を強め、かわりに不特定多数の人が集まってくる場所としてカフェが台頭してきます。ところで、こうした「カフェ」にいつ、どんな人々が集っていたかを調べるにはどうすればいいのでしょうか……?先述の「サロン」であれば、〇月〇日に開催したときにはこの人が来た!というような記録も残っていそうなものですが、連日・不特定多数の来客があるカフェ。なかなかそういった記録は期待できませんし、公文書として残っているタイプの情報でもありません。まして、彼らは集まる店も変えていきます。
そこに取り組んだのが鹿島先生の『モンマルトル風俗事典』。その店に出入りしていた人の日記や店主らの回想録などをもとに取り組まれたこの一冊。放送を通じてそのエッセンスも伝われば……!と思いますが、機会があればぜひ読んでみてくださいね。
2.カフェ文化を形成した3つの世代
さて、本題となる19世紀パリのカフェについてみていきましょう。鹿島先生はそこに1800年前後生まれ、1820年前後生まれ、1840年前後生まれの3つの世代を中心としたグループがある、と言います。そしてこうしたグループで実際に集団的無意識となるようなカフェ文化を形成していったのは、世代を代表する有名人……ではなく、その取り巻きとなる少し下の世代でした。
例えば、1800年前後に生まれた世代を中心としたグループとしてはバルザック(1799)、ユゴー(1802)、デュマ(1802)らが挙げられます。ロマン派第一世代とも呼ばれる彼らは、サロン文化も経験がある世代です。その取り巻きとなっていたのはロマン派第二世代とも呼ばれる1805~10年頃に生まれたゴーティエやネルヴァルという人たち。さらにその周りにいた、後世の私たちからは名前も知ることもできない「プチ・ロマンティック」と呼ばれた人たちが、実際の生活としてのロマン主義の担い手になったというのです。
第一世代の代表的な例として挙げられるのは、ユゴーを中心とするロマン派と、否定する古典派が対立した「エルナニの戦い」。詳細はぜひ番組中の鹿島先生の解説を聞いていただくとして、当時のフランス古典派演劇のルールを壊そうとした若き才人たちと、彼らにあこがれる青年たち。実際に目立つ行動をして名を挙げたり、なんらか作品を残した人もいれば、それにあこがれる取り巻きの人たちもいる……そしてその取り巻きの彼らこそが日々カフェに集い、喧々諤々の批評をしている……といった図式は、どことなく、現代にも通じるものがあるような気がします。

悪く言えばいまだ名声も地位もお金も得ていないワナビーが集い、あーだこーだと文学や演劇、芸術に対して議論を交わしている。そんな様子を聞いていると、なんだがひと頃のゴールデン街ってそんなところだと聞いたような……と思い浮かべてしまうのでした。あるいは文化系の大学サークルとか……(どうしてでしょう、耳が痛い)。
何はともあれ、あるムーブメントにはそのスタイルを生み出した、中心となる人々がいる。しかしその人たちだけではなく、彼らにあこがれて集まってくる人々がいることでそのスタイルがムーブメントになり、流行になり、人々の集団的無意識になっていく……ある種の「観客」「観光客」とも言えるような彼らの存在もまた、集団的無意識の研究に欠かせない要素です。
3.カフェからブラスリーへ
さて、1820年前後に生まれたグループにはボードレール(1821)、フロベール(1821)、ナダール(1820)らが挙げられます。
彼らが拠点としたのが当時パリに現れ始めたブラスリーでした。以前の講義でもあったように、ヌヴェル・アテネ(新アテネ)など、モンマルトル地区の開発が進み(チヴォリという遊園地→宅地化→忌み嫌われる、物件の最初の住人として娼婦や若き芸術家たちが移住をして……という流れ)、新たなな客層としてカフェから岸を変えてやってきました。ここでいうブラスリーは今のビアホールのようなイメージでしょうか。ワインが主流だったパリの街では、ビールは新しい飲み物でもあったのです。
彼らが集ったお店の代表例がブラスリ・デ・マルティール(Brasserie des Martyrs)。この店でボードレールがどんな振る舞いをしていたかの記録なども多数残っているほか、ここにもやはり名を成す前の若者たちが集い、さまざまな文学談義、芸術談義が行われていたようです。
彼らはまた、当時の新聞(今も残るフィガロ(Le Figaro)が誕生したのもこの頃でした)の書き手として、出版の文化を支えた人たちでもありました。とはいえ、十分に賃金を得て暮らしていたわけではなく、その肩書と引き換えにほとんどタダ同然で記事を書いていたようですが……今も昔も変わらぬ物書き稼業の難しさについては、講義の前半、第一世代の解説の中でも鹿島先生の実体験を踏まえてお話いただいております。こちらも必聴ですよ!

4.次回の講義は明日11月8日!
さて、駆け足で振り返ってきた前回のおさらいですが、ここで紹介した以外にもさまざまなお話がありました。例えば第一世代と第二世代の生まれ育ち・バックグラウンドの違いや、その関係性。あるいは、ときにカフェがつぶれるきっかけにもなってしまった「ツケ」の問題と、それを活かそうとした店主たちの試み。驚きの理由で店の名前が変わってしまった「ラ・モール(La Ratmort=死んだネズミ)」というカフェ、そしてマネやドガがこの店で女性をモデルにした絵をたくさん残しているのですが、そもそもなぜこの店に女性客が多かったのか、ゾラの小説『ナナ』からも読み取れるその理由などなど……ぜひまだ番組をご覧になっていない方は、放送でお楽しみください。

照らし合わせながら解説いただきました。
さて、次回の鹿島茂のN'importe Quoi!の放送は11月8日。19時からを予定しています。ぜひ放送でお会いしましょう。
さらには11月20日にはゲンロンのイベントとして、荒俣宏さん、東浩紀との鼎談も予定しています!こちら会場観覧は満席となっておりますが、配信でもご覧いただけます。
7月に千代田図書館で行われた荒俣さんと鹿島先生の対談の続編ともなるこちらも、ぜひよろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
