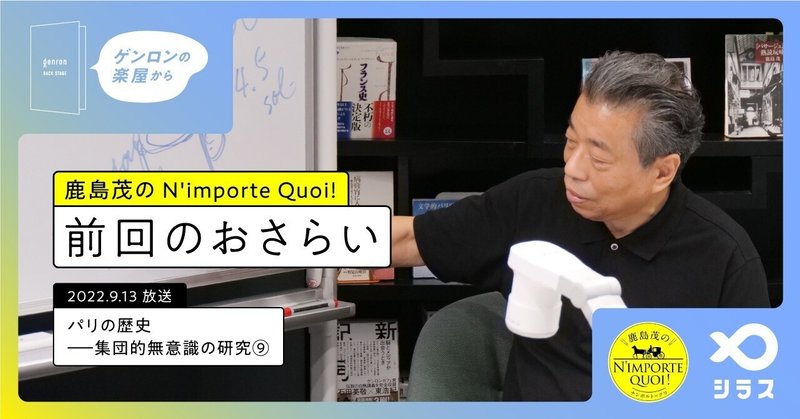
モンマルトルとパリ──鹿島茂のN'improte Quoi!「前回のおさらい」
前回のおさらいの冒頭、海外旅行の話をマクラにしましたが、9月から条件付きで帰国時の検査が簡易化されていたんですね。全然知らなかった……。フランスは渡航後の行動制限もあまりないようで、時間(とお金)さえあれば行けちゃうのだな、いや「時間(とお金)」こそ一番難しいところではないか、と悶々としております、鹿島茂のN'improte Quoi!担当の野口です。
そんなときは鹿島先生のお話を聞きながら妄想フランス旅行するにかぎりますね。ということで、シャンゼリゼとモンマルトルについて解説いただいた、9月13日放送の「モンマルトルとパリ【パリの歴史──集団的無意識の研究・第9講】」をおさらいしましょう!

1.シャンゼリゼとモンマルトルの共通点
前回最後にたどり着いた盛り場・シャンゼリゼ。そして今回のテーマであるモンマルトル。シャンゼリゼはどちらかというとブランドショップなどが並ぶ高級な通り、モンマルトルは「ムーランルージュ」に代表されるような歓楽街……とイメージすると、栄えているには違いないけれど、それぞれまったく違う経緯で成立したスポットのように思えます。
しかし鹿島さん曰く、この2つの盛り場、発祥にはある共通点があるといいます。

その共通点とは城壁。この講義でも何度か出てきている「徴税請負人の壁」。その外にできた3つの建物や施設が現代のパリの成り立ちにもつながっていきます。
それは
1.税金を取られる前に腹に入れちゃえ!と大衆が集った免税酒場
2.徴税請負人たちの屋敷であるところの「フォリー」
3.18世紀半ば以降にイギリスからもたらされた郊外型の遊園地(いわゆるVoxhall)
の3つ。
いずれも過去の講義で出てきたこともありますが、この日の講義ではVoxhallのお話を深掘りしていただきました。あえて1つにポイントを絞るならば、Voxhall名物である、花火でしょうか。もともと住宅密集地だったパリ東側で花火をあげるのは難しい……ということで、施設自体は徐々に西側に増えていきます。これも盛り場の西漸につながった理由の1つでした。
現代の様子からは少し信じがたいですが、シャンゼリゼがある現代のパリ8区、16区のあたりも、もともと片田舎、民家も少ないようなエリアだったので、新たに施設をつくりやすい条件が整っていました。
2.オスマンの大改造によってできた街
このバックグラウンドに加えてシャンゼリゼやモンマルトルの発展につながったのが、1860年から始まるオスマンによるパリの大改造です。ニューヨークや京都のような碁盤の目の都市ではなく、従来からフランスにあった放射型の街づくりは、東西にそれぞれ中心となるスポットがありました。エトワール広場とバスチーユ広場、ブローニュの森とヴァンセンヌの森、モンソー公園とモンスリー公園……といったように。コンセプトの背景には、当時発達してきた解剖学の影響があったそうです。広場は心臓、森と公園は肺として空気や血液を循環させる。サン・シモン主義の影響もあったのかもしれません。
さて、そのシャンゼリゼ。あらためてどんな通りかと言えばコンコルド広場からナポレオンの凱旋門があるエトワール広場までをつなぐ大通りなのですが、このエトワール広場の凱旋門、最初はここに建てられる予定ではなかったのだとか。もともとは太陽が昇る方角である東側に建てるのがスタンダードな考え方で、ナポレオンも当初はバスチーユ広場への建造を予定していたそうです。それが臣下からの提言を受け、今まで通りと同じじゃダメだ!ということで西側のエトワール広場への建造が決まりました(結局ナポレオンが権勢をほこっていた時期には完成しなかったのですが)。
代わりに、というわけではありませんが、バスチーユ広場も革命のシンボリックな場所でもありますので、何かモニュメントを……ということで計画されたのが、「象」。ナポレオンのアフリカ遠征を記念して、超大型の青銅製の象が作られようとしていたのです!模型(マケット)まで作られたものの、ナポレオンの失脚に伴い最終的に完成にいたらなかったのですが、当時の図版や、『レ・ミゼラブル』にこの象に住み着く登場人物がいるなど、その影を見ることができます。

『19世紀パリ時間旅行-失われた街を求めて‐』(鹿島茂、新潮社 P158)
マルシアルの銅版画第170番「サン=マルタン運河」より

『19世紀パリ時間旅行-失われた街を求めて‐』(鹿島茂、新潮社 P155)より
さて、オスマンに話を戻しましょう。彼の辣腕は特にエトワール広場からブローニュの森に至る「L'Avenue de Impératice(皇妃大通り)」など、特にパリの西側で発揮されました。この通りは当時世界最大の規模(幅140メートル!)で、以前の講義にも出てきた「ロンシャン詣で」でもここを通ったといいます。
この時代の雰囲気はプルーストの『失われた時を求めて』でも描かれているのですが、なかなか読むのはハードルが高い……そんな(ぼくのような)人には最近祥伝社さんから出版されたコミック版もおすすめです!フランスでも大人気のバンドデシネの翻訳版で、そのイラストの精緻さや中条省平さんの翻訳とも鹿島さんも一押しとのことです!
シャンゼリゼはその後プジョーやシトロエンなどの車の販売店、その後は航空会社の店舗が並ぶなど20世紀にかけて高級な盛り場として人気を集めます。その背景には前述のとおりもともと片田舎、民家の少ない田園地帯で整備されていなかったがゆえに大規模な整備が実施できた、という事情も見て取れるのです。
3.モンマルトルの成立
さて、講義の後半はモンマルトルへ。おもに9区の北部と18区にまたがるこのエリア。18区がパリ市内に編入されたのもオスマンの大改造の時期でした。シンボルともいえるモンマルトルのサクレ・クール寺院も1870年の普仏戦争とパリ・コミューンの犠牲者への慰霊を目的としていましたが、完成したのは20世紀に入ってから。これまで見てきたエリアに比べると、シャンゼリゼ同様、比較的新しい部類といえるでしょう。
エリアの目印となるのはイタリア大通りよりも少し北に位置するノートルダム・ドゥ・ロレット教会とトリニテ教会。ここから斜めに北西に登っていくとモンマルトルの丘となります。クリシー広場、ブランシュ広場、ピガール広場という3つの広場もそれぞれの特色を持ったポイントです。

真ん中下部の十字架がノートルダム・ドゥ・ロレット教会。
さて、冒頭で徴税請負人の壁の外にできた3つの重要な施設に上がっていた免税酒場で有名なものに、ジャン・ランポノーという人がオープンさせた「Le Tambour-Royal(タンブール・ロワイヤール)」というお店があります。レペブリュック広場のあたりにあったこのお店では、当時1杯4.5ソル(sol、通貨の単位。1ソル=1スー=1/20フランorリーブルだそうです!)が相場だったワイン1杯を3.5ソルで販売し、人気を集めたそう。その後日々大騒ぎ・乱痴気騒ぎが繰り広げられるようになります。
どのくらいのものだったかというと、居酒屋で飲むこと、少し飲み過ぎることを指す「ランポネ(ramponner)」という新語ができたぐらい。「ランポネ」はもちろん店主のランポノーさんの名前(ramponneau)にちなんだもので、今でも辞書で引くと、名前のramponneauのほうは「殴打、金槌、小刀」を指し、語源にはランポノー氏に由来すると記載があるのだとか。

この日々大騒ぎが繰り広げられる人気店は、やや手狭なこともあり、ほかにもいろいろ面倒事があったようで、ランポノー氏はモンマルトルのほうへ店舗を移転。Porcheron(ポルシュロン)という巨艦店をオープンさせ、そちらでも人気を集めました。
他にも人気の施設となったのは大衆向けのダンスホール。来場者が中央に設けられた柵のなかで踊るスタイルで、お針子などの仕事をしている女性だけではなく、娼婦もやってくるようになります。
スカートがめくれ上がるほどに高く足を上げる「カンカン踊り」が主流だった当時。中にはダンスクイーン的な存在になる人もいたそうで、娼婦の人たちは仕事も兼ねての来場でした。特に現在もイベントスペースとして営業を続ける「Elysée Monmartel(エリゼ・モンマルトル)」や「Boule-Noire(ブール・ノワール)」といったお店では、こうしたセミプロの女性が客を取るためにやってくることが多かったのだとか。逆にこれらのお店から少し離れた「Reine Blanche(レーヌ・ブランシュ)」というお店は、娼婦たちがプライベートで遊びに行くところとして人気を集めたそうです。こういった盛り場のエリア分け、使い分けは日本でも共通性が見られる、例えば銀座と赤坂・六本木の関係を見てみると……という解説もあります!
さて、モンマルトルにあったのはそんなセミプロ・プロたち向けのお店ばかりではありません。もう少し庶民的なお店もありました。例えばルノワールの絵画で有名な「Moulin de la Galette(ムーラン・ド・ラ・ギャレット)」もその1つ。もともと「ムーラン」……風車小屋だったというこの店がどんな経由で「ギャレット」……ガレットを出すようになったのか、その発祥の伝説も、アーカイブをぜひご覧ください。
4.モンマルトルと画家たち
ルノワールといえば、ここモンマルトルはたくさんの画家たちが住んでいたエリアでもあります。そんな画家が住んでいた共同住宅をベースにしたのが現在営業中のモンマルトル美術館。当時このあたりは土地が安かっただけではなく、斜面に合わせた家を作ることで採光のいい家が作られていました。これらはセーヌ川に浮かぶそれらと見た目がそっくりだということで、Bateau Lavoir=洗濯船と呼んだのだとか。
ちなみにこのモンマルトル美術館の外に見えるブドウ畑で生産されるワインがあるそうです。いまでこそフランスのワインと言えばボルドー地方やラングドック地方などが有名ですが、パリがあるイル・ド・フランス地方もかつては一大ワイン生産地でもあり、モンマルトルでも古くからブドウ畑が広がり、ワインが生産されていたそう。
その後、モンマルトルの発展とともにブドウ畑は一度なくなってしまうのですが、それを復活させよう!という動きがあって、作られたのがこのブドウ畑。ここで作られたワインは、毎年10月に収穫祭が行われるそうなのですが、召し上がったことのある鹿島先生曰く、あまりおいしいとはいえないワインなのだとか。しかし、先ほどのランポノー氏のお店のような当時の大衆が飲んでいたワインもこんな感じだったのかな、と思いを馳せながら飲むと、それはそれで味がありますよね!

さて、画家たちが集うようになると、モンマルトルはさらにアトリエ村的に発展をしていきます。当時の雰囲気を知るのにおすすめ、として紹介をしてもらったのが福音館書店さんから出版されている『オリヴィエ少年の物語』のシリーズ。庶民の街、下町としてもにぎわっていくこの街には、さまざまな地域や国からパリにやってきた画家たちが集い、彼らが通うようなお店もできていくのですが、その雰囲気も少しずつ変化が訪れます。
きっかけとなったのは1889年の「Moulin Rouge(ムーランルージュ)」のオープン。さきほどご紹介した「レーヌブランシュ」を取り壊して作られたこの店は、人々が「踊りに来る」場ではなく、最初からダンサーの「踊りを見に行く」場として運営が始まります。現代のアイドル戦略にもつながる様々な仕組みも導入しながら作られたムーランルージュの誕生をきっかけに、モンマルトルは歓楽街としての発展に舵を切るのです。
そんなモンマルトルですが、最近はまた少し雰囲気が変わってきている、というのがモンマルトルの本を書くために取材に行かれた際の鹿島先生の見立て。かつて油絵の画家たちが集ったこのエリアには、現代の油絵画家ともいえるマンガ家やアニメーター、CGクリエイターたちが増えてきているのだとか。
そんなことを思うと、地霊=ゲニウス・ロキってやっぱりあるんだなぁなんて考えてしまうよね……といったお話のあたりでこの日の放送は時間切れ。いつかまたパリに行くときは、そんな時代ごとの移り変わりに思いを馳せながら、しかし似顔絵の押し売りをしてくる人たちには気をつけながら、たくさん散歩してみたいと思うのでした。
さて、次回の放送は本日です!ここでは語り切れなかったモンマルトルの話、もう少し続きます。こちらもぜひご覧ください。
■次回放送予定
日時:2022年10月11日 19時~
モンマルトルの名店と人々──パリの歴史・集団的無意識の研究⑨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
