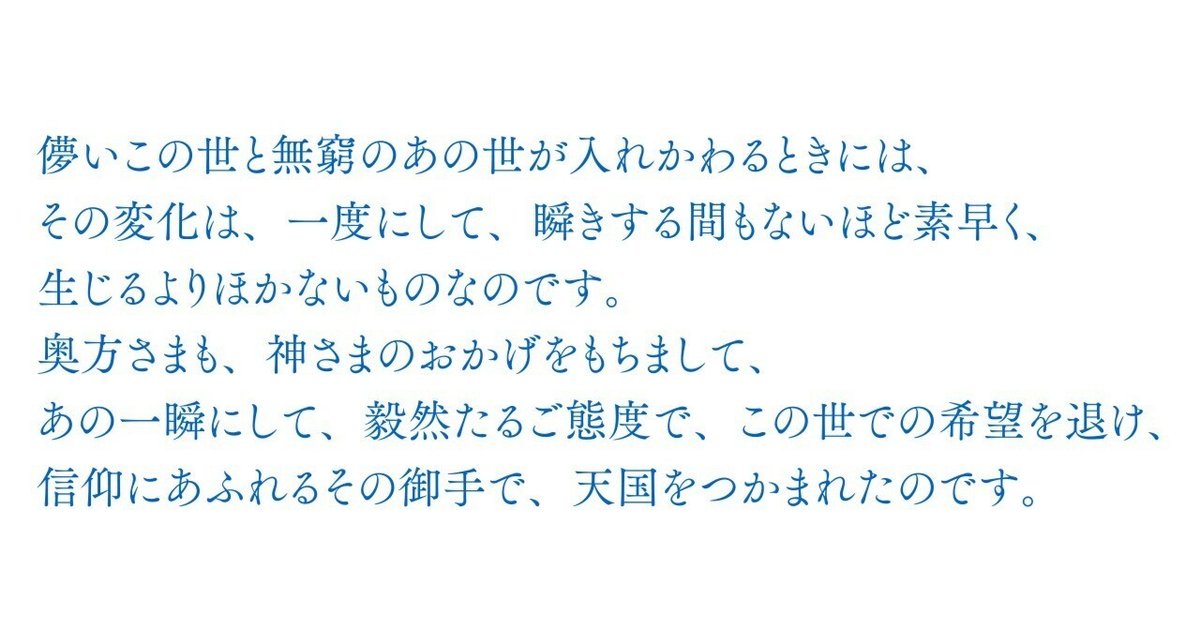
フリードリヒ・シラー『シラー戯曲傑作選 メアリー・ステュアート』訳者解題(text by 津﨑正行)
2023年8月29日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第33回配本として、フリードリヒ・シラー『シラー戯曲傑作選 メアリー・ステュアート』を刊行いたします(『シラー戯曲傑作選 ドン・カルロス スペインの王子』と同時刊行です)。フリードリヒ・シラー(Friedrich Schiller 1759–1805)はドイツの劇作家、詩人。雑誌編集者、歴史学者、美学研究者としても活躍した文人。1781年、戯曲『群盗』が成功を収め、一躍有名になりました。
本作品『メアリー・ステュアート』は、『マリア・ストゥアルダ』の題名で知る人が多いかもしれません。イタリアの作曲家ガエターノ・ドニゼッティ
(1797-1848)のオペラ《マリア・ストゥアルダ》は、シラーの本作をもとに書かれた名作として知られますが、ナポリのサンカルロ劇場での初演直前に公演禁止になるなど、上演地域によっては、宗教上の観点から賛否両論など物議を醸す作品だったようです。
以下に公開するのは、訳者・津﨑正行さんによる「訳者解題」の一節です。

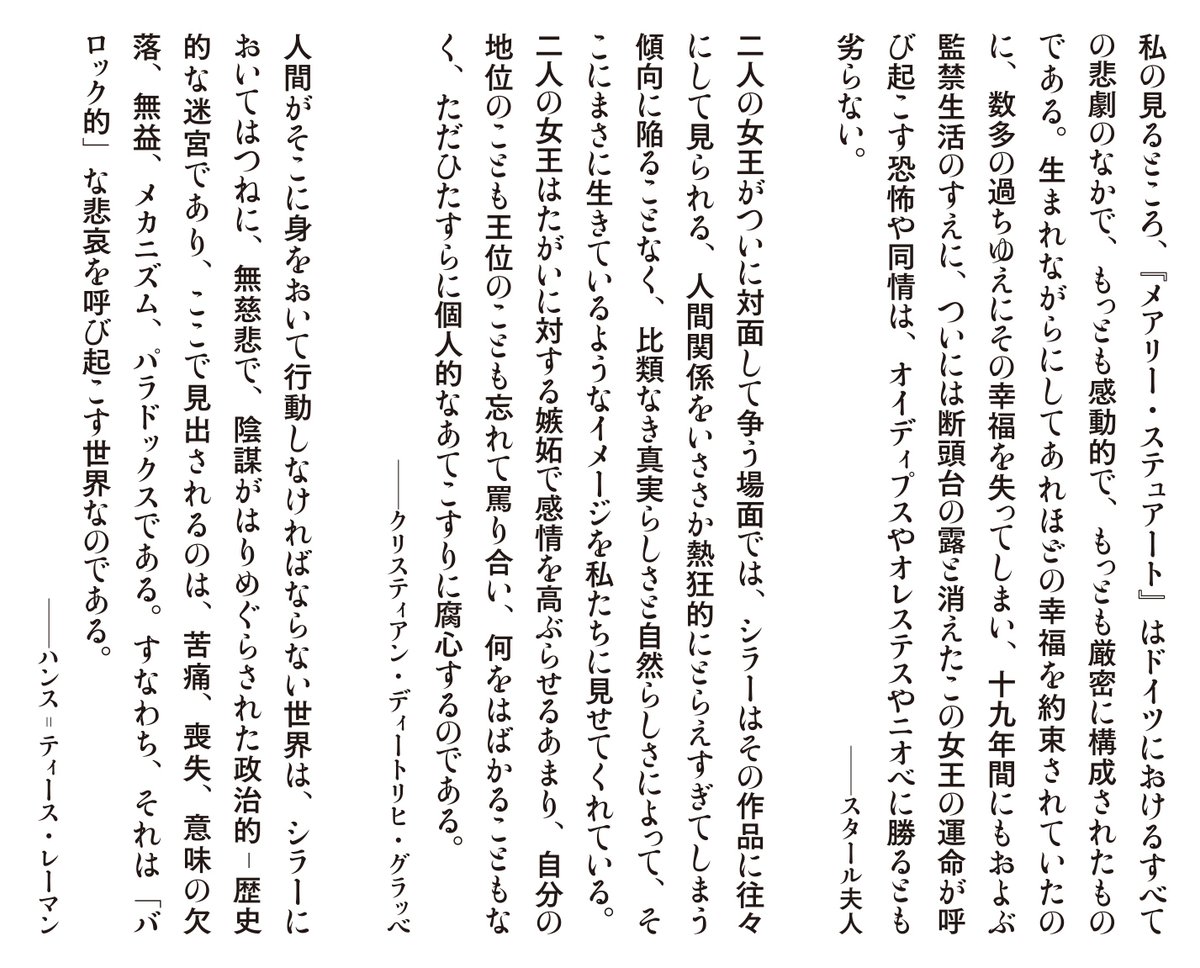
『メアリー・ステュアート』の成立と初演
シラーはかねてより、十六世紀に実在したスコットランド女王メアリーをめぐる歴史に興味を示していたが、それに取材した作品との取り組みを開始したのは、『ヴァレンシュタイン』三部作が完成し、その初演が行なわれる前後の時期、1799年4月ごろのことである。前作の場合と同様に、作品の執筆は、最初から順調に進んだわけではない。「『メアリー・ステュアート』につきましては、おいでいただくころには、まだひとつの幕しか完成していないでしょう。この幕を書くために多くの時間を要しているのですが、完成するまでには、まだ一週間ほどかかりそうなのです。それはなぜかと申しますに、この幕において、私は歴史的な素材を詩によって克服しなければならなかったからなのです。そしてまた、想像力に歴史を超越する自由を与えながらも、それと同時に、歴史がそなえている有用なものを我がものとしようとするのに、ひどく苦労したからなのです。それ以降の幕は、もうすこし順調に書き進めることができるだろうと期待しておりますし、この幕と比べると、かなり短いものになるでしょう。」(1799年7月19日、ゲーテへの書簡)[NA 30, 73]
作品の文体についても、ここで簡単に触れておくと、シラーが前作『ヴァレンシュタイン』を執筆したときには、ヴィルヘルム・フォン・フンボルトの助言もあって、当初は散文で書くことも検討していたが、最終的には、一部の箇所をのぞいて、基本的にはブランクヴァースで書いている。これ以降の劇作品はすべて、最初からブランクヴァースで書かれている。『メアリー・ステュアート』で採用された文体もまた、その舞台となっているエリザベス朝のイングランドにおいて、シェイクスピアをはじめとする劇作家たちが用いたのと同じブランクヴァースである。すなわち、弱拍と強拍からなる脚が五つ重ねられて一行をなし、行末で韻を踏まない文体である。ただし、これはあくまでも原則であって、シラーの原文では、四行以下の短詩行や六行以上の長詩行が挿入されている箇所もすくなからず見られ、それによって単調に陥ることをまぬがれている。独白や各場の最後などの箇所で、ブランクヴァースと同じ弱強格五脚の詩行を用いながら、押韻をほどこし、それ
を無韻の詩行のなかに溶けこませたり、行末で同じ語句を繰り返したりすることによって、その台詞を印象づけるという工夫もなされている。さらに付け加えるならば、第三幕第一場においてメアリーに、幽囚の身から解放される可能性がにわかに示されたかに思われた箇所では、ブランクヴァース以外の押韻をともなう詩行を用いて、彼女の心のうちが語られているのだが、それに対する乳母のケネディーの返答は無韻の詩行で語られており、押韻をほどこした詩行と押韻をほどこさない詩行で対話がなされるという、特異な形式が見られる。このような文体上の工夫について、シラーは次のように述べている。「私は『メアリー・ステュアート』で、しかるべきときには、韻律におけるより大きな自由を用いはじめています。あるいは、自由というよりはむしろ、多様性といったほうがよいかもしれません。韻律にこうした変化をつけることは、ギリシアの劇作品にも見られたことであり、観客には、あらゆることに慣れてもらわなければならないのですから。」(1799年9月
3日、ゲーテへの書簡)[NA 30, 95]
歴史的な素材の扱い方にも、新しい文体にも苦労しながら、執筆開始からおよそ一年をかけて、シラーは五幕の悲劇『メアリー・ステュアート』を書き上げる。1800年6月9日に完成したこの作品は、6月14日には初演を迎える。初演は成功を収め、シラーも自信を深める。その二日後には、次のように書いている。「先週、私はこちらに戻ってきて、劇場での稽古も監督したのですが、一昨日、この作品が上演されて、これ以上は望めないくらいの成功を収めました。ようやくのことで、ドラマというものに対する感覚を我がものとし、自分の生業を理解できるようになってきたのです。」(1800年6月16日、ケルナーへの書簡)[NA 30, 162]
初演の翌年、1801年には『メアリー・ステュアート』の初版が出版されている。この作品に対しては、それを高く評価する声がある一方で、批判の声もあった。批判的な立場をとる評者がとくに問題視したのは、聖体拝領の場面である。第五幕第七場における聖体拝領の儀式は、とりわけカトリック側の地域において拒絶反応を引き起こし、そのために、上演の試みが頓挫することもあった。この場面は、ヴァイマルにおける初演の際には削除されていた。カトリックの儀式を舞台に載せることに、大公から懸念が示されたためである。大公の意向を、ゲーテは初演の数日前に書かれた書簡で、次のように伝えている。「聖体拝領を舞台に載せようという大胆なお考えは、すでに物議を醸しておりまして、私のほうからあなたに、そのようなことは避けていただきたいと、お願いするように申しつかっているのです。あえて申し上げますと、私自身も、あまりよい気持ちはしません。まだ上演する前だというのに、今からもう、それに抗議する声が上がっていますので、どちらの点からしても、あまり賢明なこととはいえますまい。」(1800年6月12日、シラーへの書簡)[NA38I, 269]
以上の場面に加えて、両女王が対面する場面(第三幕第四場)に対しても批判があり、とある匿名の評者はそれを「魚売りの女の喧嘩」になぞらえている。また、それに続くモルティマーによる告白の場面(第三幕第六場)についても、その「野獣のような肉欲」ゆえに眉をひそめる者はすくなくなかった。こうした批判はあったものの、総じていえば、シラーの『メアリー・ステュアート』は19世紀のドイツにおいて、きわめて大きな成功を収めた舞台作品であったとみなすことができる。古典主義的な規範に厳密にしたがって構成された作品の典型とみなされるこの悲劇は、統計的に見ても、通俗的な作品にはおよばないまでも、古典的な劇作品の枠内にかぎれば、もっとも上演回数の多い作品のひとつであった。
【目次】
メアリー・ステュアート
第一幕
第二幕
第三幕
第四幕
第五幕
フリードリヒ・シラー[1759–1805]年譜
訳者解題
【訳者略歴】
津﨑正行(つざき・まさゆき)
1973年、東京生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。慶應義塾大学、東京理科大学、東京藝術大学非常勤講師。近代ドイツ演劇を専攻。訳書にベルトルト・ブレヒト『ファッツァー』、エルフリーデ・イェリネク『スポーツ劇』、ヨッヘン・へーリッシュ『メディアの歴史』(共訳)など。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『シラー戯曲傑作選 メアリー・ステュアート』をご覧ください。
