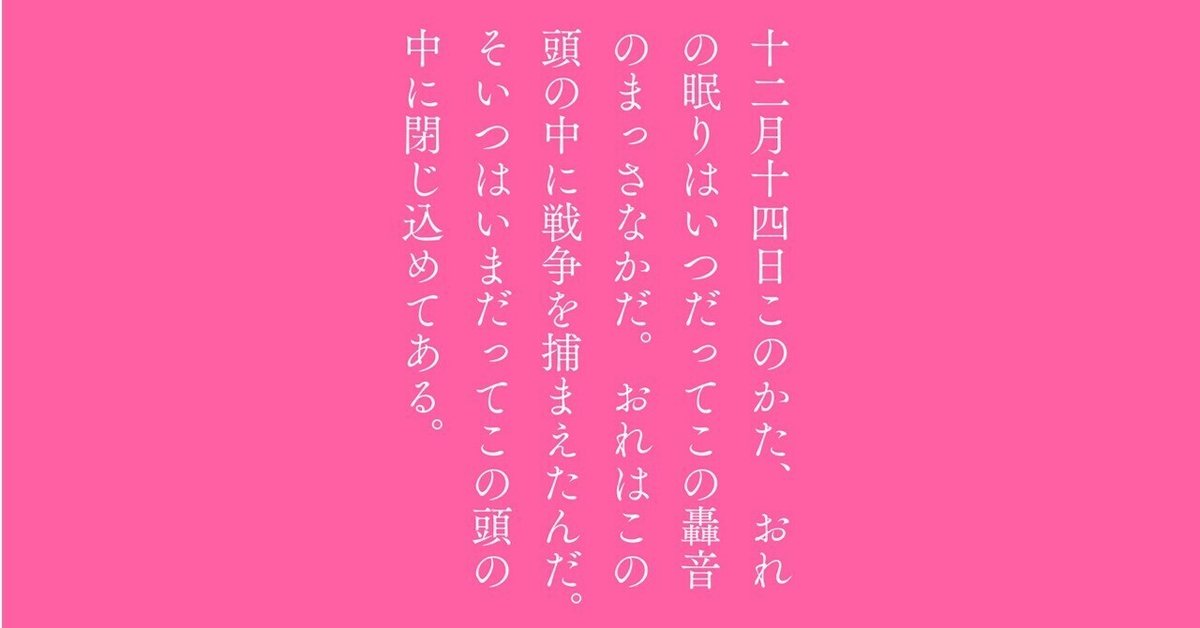
ルイ゠フェルディナン・セリーヌ『戦争』訳者解題(text by 森澤友一朗)
2023年11月27日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第36回配本として、ルリユール叢書50冊目となる、ルイ゠フェルディナン・セリーヌ『戦争』を刊行いたしました。ルイ゠フェルディナン・セリーヌ(Louis-Ferdinand Céline 1894–1961)はフランスの作家・医師。パリ郊外で医業に携わるなか、俗語・卑語を駆使したデビュー作『夜の果てへの旅』で圧倒的反響を巻き起こしました。第二次世界大戦にあたっては、激越な反ユダヤ主義パンフレットを書き連ねたため、終戦間際にデンマークへ亡命、現地にて逮捕、収監されました。大赦を得ての帰国後、パリ郊外ムードンに居を構え、亡命行を主題とした三部作などでフランス語の構文を破砕する言語実験を推し進めました。死後も現在に至るまで、その文学的達成と反ユダヤ主義言説との関係が国内外で度々スキャンダラスな議論を巻き起こし続けている作家として知られます。
本書は、セリーヌの死後60年の時を経て発見され、「21世紀の文学史的事件」と国内外で話題を呼んだ幻の草稿群のひとつで、昨年2022年に、編者の校訂を経て原書が刊行されたばかりの作品の本邦初訳です。『夜の果てへの旅』に続いて執筆された未発表作品であり、セリーヌの自伝的戦争小説となっています。
以下に公開するのは、訳者・森澤友一朗さんによる「訳者解題」の一節です。


戦争万歳──セリーヌ概観
なにはさておき、戦争万歳、である。大摑みな類型の分類にかかれば一括りに反戦文学と目されかねぬ、しかも本人も1930年代の来るべき戦争を前にしての焦燥感のなかで筆を握ったこの草稿の末尾に書きつけられる文言がよりにもよって、戦争万歳、である。これは決して呑気なアイロニーの類ではなく、事実、本作以後、彼は爆撃をはじめとした戦争の暴威を前に、逆にそれらと一体化してゆくことで、唯一無二の文体を作り上げてゆくだろう。この反転性、反発していた対象への生成変化をもたらすような捻(ねじ)れのエクリチュールこそが、セリーヌという作家の本領であり、こうした点こそが、アンリ・バルビュス(Henri Barbusse 1873‐1935)をはじめとする第一次大戦を描いた反戦作家たちとセリーヌを分かち、むしろ戦線のあちら側で塹壕の中の悲惨と栄光を綴り続けたドイツの軍人作家エルンスト・ユンガー(Ernst Jünger 1895‐1998)の方へと連ならせてゆくのではなかろうか──とはいえ、二度の邂逅(かいこう)の機会にめぐまれた当人どうしは、その後お互いに相手を歯牙にもかけぬ態度を見せつけるのだが。いずれにせよ、セリーヌの著作を丹念に紐(ひも)解いてゆくなかで如実に現れてくるのは、ユンガーに親炙する本邦のイデオローグ千坂恭二のロジックを借りて言えば、戦争に抵抗しようとするのではなく、むしろ戦争をその内部でまるごとに肯定し、そうして戦争を凌駕(りょうが)してゆかんとする姿勢だといえよう。
いや戦争だけではない。いまやセリーヌの枕詞と化し、彼とは切っても切れぬものとなっている「反ユダヤ主義」にしてからが、単純な善悪の審級で裁かれるがままに任せてはくれず、たとえば彼の反ユダヤ主義著作『虐殺のためのバガテル Bagatelles pour un massacre』(1937)では反ユダヤ主義の雄を自認するセリーヌが憎悪の言葉の奔流を吐き出し呑み込まれしてゆくうちに、いつしか終盤、自身が反対にユダヤ人そのものと化してゆくような一節が書き込まれていなかっただろうか。この書物に付された「塹壕で大笑いするために(Pour bien rire dans les tranchées)」という秀逸な宣伝文句は、この特異なポテンシャルの一端を過たず捉えている。物分かりのよい単線的理解を常に撥ねつけるこの捻れた肯定性のエクリチュールこそ、その死後およそ60年が経過した2017年においてなお、フランスで彼の反ユダヤ主義著作の再刊をめぐって賛成派と反対派が国論を二分し、結果、再刊見送りへと至るといった騒動を巻き起こす密かな淵源でもあろう。
忘れちゃならんが、インスピレーションってやつは、死からやって来るんだ。作業台の上に自分の肌身晒さなかったら、なにひとつだって手に入りゃしない。自分で支払う必要があるんだ! タダで作り出されたものなんてのはきまって失敗、いやもっとひどい。ほら、タダでやってる作家連中がいるだろ。いまじゃ、みんなタダでやってる作家ばかりじゃないか。タダのものからはタダの臭いが臭ってくるのさ。
自身の身体と情動を身ぐるみ言語の俎上に提供して、新たな文体を追求していったセリーヌは、先にも述べたとおり、まずなにより1930年代の作家であった。ナチス党の政権獲得の前年、『夜の果てへの旅 Voyage au bout de la nuit』(1932)によって鮮烈なデビューを飾った彼だったが、しかしこの第一作目では彼は「戦争」の経験を正面から扱うには至らなかった。次回作の構想を膨らますなかで、彼は友人と出版元のドノエル書店に宛てて「幼年期、戦争、ロンドン(Enfance—La guerre—Londres)」の三部仕立てを予定していると打ち明けている。結局、一つ目の「幼年期」のみが拡大してゆき、第二作『なしくずしの死 Mort à crédit』(1936)へと結実するのだが、後に挙げられた二つこそ、今回発見された草稿のなかの、本書『戦争 Guerre』、続編の『ロンドン Londres』として行李の奥に死蔵されてゆくことになったのだと考えうる。
一貫して『夜の果てへの旅』の文体には不満であった彼は、第二作の試行錯誤の過程でフランス語の構文を裁断してゆく新たな文体を獲得し、これを満を持して刊行した。しかし反響は著者の期待に大きく反し、そのあまりに赤裸な表現が当時は圧倒的な不評を被ることとなった。この第二作の受難が彼をして前記の構想を放棄させ、自身の書き物に「いまだ不足する憎悪」を求めて、反ユダヤ主義パンフレットの三部作『虐殺のためのバガテル』、『死体の学校 L’École des cadavres』(1938)、『苦境 Les Beaux Draps』(1941)へと向かわせた。この反ユダヤ主義陣営へのアンガジュマンは彼の生前のみならず死後にまで高くつく選択となるわけだが、やがて第二次大戦中、連合軍がパリに迫ってくるに及んで亡命を決意、ドイツを経由して、デンマークはコペンハーゲンを目的地に定める。このときの連合軍爆撃下の第三帝国亡命行は、後の戦後の三部作『城から城 D’un château l’autre』(1957)、『北 Nord』(1960)、『リゴドン Rigodon』(1969・死後出版)の素材となってゆくだろう。亡命先のデンマークにおいては、フランス政府からの「国家反逆罪」の罪状によるデンマーク政府への依頼に基づき、逮捕、収監。フランス外務省の理不尽な引き渡し要求を突っぱねたデンマーク司法のおかげもあってなんとか死を免れることのできた彼は、第一次大戦の軍功により大赦を獲得し、1951年帰国、以後はパリ近郊ムードンで動物たちと踊り子たちに囲まれながら、「年代記作家」を自称しつつ、二度の戦争の新たな証言の書を記し続け、1961年、その生涯を終えた。
ところで、この作家の日本での受容は、日本で教鞭もとるセリーヌ研究者であり小説家のミカエル・フェリエ(Michaël Ferrier)も本国のインタビューに答えて述べているとおり、残念ながらきわめて偏りのあるものであった。日本こそ彼の反ユダヤ主義著作が翻訳され正式に流通している唯一の国(フランスではいまだきわめて高価な戦前の古書やネット上の海賊版が幅を利かせている)であり、生田耕作、高坂和彦両氏を中心とした訳業、さらには70年代以後の国書刊行会による作品集〈セリーヌの作品〉全15巻の刊行が作家の紹介に大きな寄与を果たしてきたことは確かでありながら、一方でそれらがアンダーグラウンドな作家のイメージを醸成してもおり、文庫本としてはわずかに『夜の果てへの旅』、『なしくずしの死』がそれぞれ一冊ずつ刊行されているにすぎない。さらに研究・批評といった領域では、なおのこと大きな欠落が存在し続け、折りに触れ在野の領域でかろうじてその欠が補われてきた(たとえば吉林勲三の奇書『セリーヌ式電気餅搗機』[1983])。まだ70年代から90年代には、フランスでの再評価のあおりも受けて、多少はセリーヌについて書く研究者も存在していたものの、今世紀に入ってからは彼らも一人また一人と鬼籍に入るか足を洗うかしてゆき、いまや国内のセリーヌ研究者を数え上げるのに片手どころか指一本二本あればといった窮状である。同世代のファシスト、ドリュ・ラ・ロシェル(Drieu la Rochelle 1893‐1945)の研究者は存在しても、セリーヌの研究者は絶無に近いという現状──それゆえ一介の演劇パフォーマーである自分などが本書を訳してもいるわけだが──、このことはおそらく、なぜ本国においてこの反ユダヤ主義作家がマルセル・プルースト(Marcel Proust 1871‐1922)と並ぶ20世紀フランス文学の巨塔としての扱いを受け、死後も定期的に大騒動を喚起し続けるのかという問いに関わって、いわばフランスの「国体」とでもいったものを隠微に証し立てるこの作家の反ユダヤ主義以上の危険性が根にあるのではないかと思われてならない。なお、一方で実作の領域においては、先日亡くなった大江健三郎がセリーヌに愛着を寄せており、連作小説『静かな生活』(一九九〇)内の「小説の悲しみ」においてはこの作家を中心的題材として扱っていたことも言い添えておきたい。
「世紀の文学史的事件」
その知らせは、2021年8月6日、飛び込んできた。「セリーヌの失われていた未発表の原稿群が、執筆からおよそ80年の時を隔てて、このたび発見された」──ルモンド紙の一面を飾ったこのセンセーショナルな第一報はSNSを通じて世界中を駆け巡り、自分もその興奮の渦に思わず呑み込まれたのを鮮明に記憶している。当時、訳者は、コロナ禍のなか延期となっていた、セリーヌの反ユダヤ主義パンフレット『死体の学校』を主題とした演劇作品の上演を終え、長期間にわたって継続してきたセリーヌ連作にひとまずの終止符を打ったことで、セリーヌの憑き物ともやや間遠なつきあいとなりかけていたところであり、そこへ降って湧いた思いもかけぬ知らせには、死んだばかりの亡友がにわかに蘇ってきたのを目の当たりにするような奇妙な驚愕(きょうがく)の念を覚えさせられたものである。ルモンド紙は、発見された原稿の写真を付しながら、詳細をおおむね以下のように伝えていた──今回発見された「財宝」は、セリーヌが生前レジスタンスに盗まれたと主張していた『クロゴルド王の意志』、『死地』、その他の草稿であり、その量は計数千枚にも及ぶ。20世紀を代表する作家の原稿がこれだけの時を経て大量に発見されるというのは、その経緯からしても、まことに世紀の文学史的事件と呼んでさしつかえない出来事である。保管していたのはジャーナリストのジャン゠ピエール・ティボダ(Jean-Pierre Thibaudat)という人物であり、氏は前年2020年、弁護士のエマニュエル・ピエラ(Emmanuel Pierrat)と連絡を取り、長年にわたって保管してきた原稿をセリーヌの権利相続者二名に返還した。なお、その原稿がどういう経路を経て彼の手元にたどり着いたのかについては、氏は黙秘を貫いており、依然詳細は明らかではない──
セリーヌの書き物に憑かれたセリーニアンたちにとって、前述の「レジスタンスによる盗み」はセリーヌ伝説を構成する有名なエピソードのひとつであった。ナチスドイツによる占領期、反ユダヤ陣営の大立者として鳴らした彼は、ヴィシー・フランスの敗戦濃厚となるに及んで、他の多くの対独協力者らの顰みに倣い、1944年、先に述べた亡命の途につくことになるのだが、彼はこうして後にした自身のアパルトマンに関して、戦後、そこに保管されてあった大量の貴重な原稿群が、パリ解放に伴う「粛清」騒ぎの最中、レジスタンスの人間たちによって窃盗にあったと主張し続けていたのである。彼は、戦後の小説作品・インタビュー等でことあるごとにそのことに触れ、レジスタンスをいつもながらの罵詈雑言でこき下ろしている。
[レジスタンスの連中はこう叫んでいた]汚らわしいセリーヌ! 信じがたいほど夢にも見がたいほどのウンコまみれのクソドイツ野郎! その証拠に連中、アルレット〔セリーヌの妻リュセットのこと〕とわたしが、5月22日、ひとたび出発するや、粛清のための大いなる大盗賊団を結成しやがった! うちの目の見えない母を引きずり出し、あらいざらい掻っ払っていきやがった、17の原稿を焼き払い、シーツなんかは蚤(のみ)の市に売り払い、『ギニョルズ・バンド』に関しちゃどうしていいのかわからない… 『クロゴルド王』だってどうしたものか… 『死地』にしたって… それで倉庫に突っ込んどいたが倉庫代払う金がないってんでこっそり競売屋ドルオに競りに出したのさ。ああ! そういう陰謀はこっちには筒抜けなんだ…
そう、たしかにセリーヌは何度も繰り返しこう主張していた。だが、一を百に膨らまし、現(うつつ)を夢にねじ曲げるセリーヌのことである。たとえいくぶんかの真実がそこに含まれていたにせよ、決して彼が言うような「レジスタンスの盗み」が事実そっくりそのままあったとは世界中のセリーニアンたちもなかば信じられずにいたはずである。ところが、今回、『クロゴルド王の意志』や『死地』、さらには誰も存在を知らなかった草稿までが、まさに彼が告げていたとおり、それも80年の長きにわたって、レジスタンスによって保管されていたというのであるから、その衝撃は決して小さなものではありえなかった。
だが、である。20世紀のスキャンダルたるセリーヌ、発見あいなり大団円とは事態は運ばない。その後、保管されていた原稿の中身が明らかになり、その辿ってきた来歴が表に出てくるに及び、どうも彼が主張していたとおりとは言いがたい成り行きが判明してきたのだ。
さて、ここで遺稿発見の顛末を紹介する前に、先ほどから言及している書名含め、発見された「財宝」の主な中身について説明しておこう。
──『クロゴルド王の意志 La Volonté du roi Krogold』未完草稿、およびその前身と考えられる「ルネ王」を主人公とする伝説物語のタイプ原稿。この作品については、本書の第一・第二シークエンスでも度々引用されているが、小説第二作『なしくずしの死 Mort à crédit』(1936)において主人公゠語り手にとって愛着のある特権的な物語として繰り返し語られているのが有名である。中世の伝説に材を取った、セリーヌとしては異色の作品であり、ガリマール社より、2023年4月に出版された。
──『死地 Casse-pipe』の未発表部分の未完草稿。なお、やや複雑な経緯についてここで断りが必要かと思われるが、ここまで『死地』と記してきた作品は、日本において「発見」以前のこれまでは『戦争』と訳されてきた未完の作品であり、その一部が国書刊行会の作品集の第14巻に収録されている。casse-pipeという単語は字義通りには「パイプを壊す」という意であり、麻酔のなかった昔、軍医が負傷兵に切断手術を行う際、兵隊が叫ばないよう歯に挟ませていたパイプであり、手術が失敗すると死に至り、パイプも口から転げ落ちて壊れる光景から転じて、「危険のつきまとう戦場」を意味するようになった特殊なニュアンスの俗語であり、『戦争』と訳して問題があるわけではないのだが、次項のGuerre(そのままずばり「戦争」としか訳しようのない)が刊行された以上、混乱を避けるべくcasse-pipeのニュアンスをできるだけ汲み取って『死地』という訳語を代わりに提案する次第である(あるいは俗語として語の重量を汲んだもう少し軽い訳語があればなおぴたりとはまるのだが)。第一次大戦開戦以前の兵営における訓練の日々が描かれた作品であり、本作についてもガリマール社より出版の予定があるようである。
──『戦争 Guerre』というタイトルで出版されることとなる、全六シークエンスの未発表草稿。これが本訳書の原書であるが、研究者の誰ひとりその存在を知らなかった草稿であり、最大の驚きをもって迎えられた。なお、本書前付の編者注記でも述べられているが(「編集についての注記―パスカル・フーシェによる」参照)、シークエンスの最初の頁には番号がそれぞれ、10、1、2、2'、3、4、と振られており、おそらく前半の9までが失われた、後半のみの草稿であることが推測される。
──『ロンドン Londres』と題された、全三部にわたる大部の未発表草稿。『戦争』の続編に位置し、ロンドン逃避行を物語る小説であり、発見された草稿のなかでは唯一、始まりから終わりまで完結した姿で発見された。ガリマール社より2022年10月出版された。
──その他、『なしくずしの死』など既発表作品の草稿やタイプ原稿、書簡、写真、領収証など。加えて、そのなかには反ユダヤ主義文書も含まれていることも言い落としてはなるまい。
【目次】
編集についての注記──パスカル・フーシェによる
戦争
註
ルイ゠フェルディナン・セリーヌ[1894–1961]年譜
訳者解題
【訳者略歴】
森澤友一朗(もりさわ・ゆういちろう)
1984年、岡山県生まれ。翻訳者。劇団解体社所属、パフォーマー・文芸・制作。東京大学文学部フランス語学フランス文学専修課程卒。劇団では過去に「セリーヌの世紀」と題して、訳し下ろしたセリーヌのパンフレや小説を題材とした連作を国際プロジェクトとして展開。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ルイ゠フェルディナン・セリーヌ『戦争』をご覧ください。
