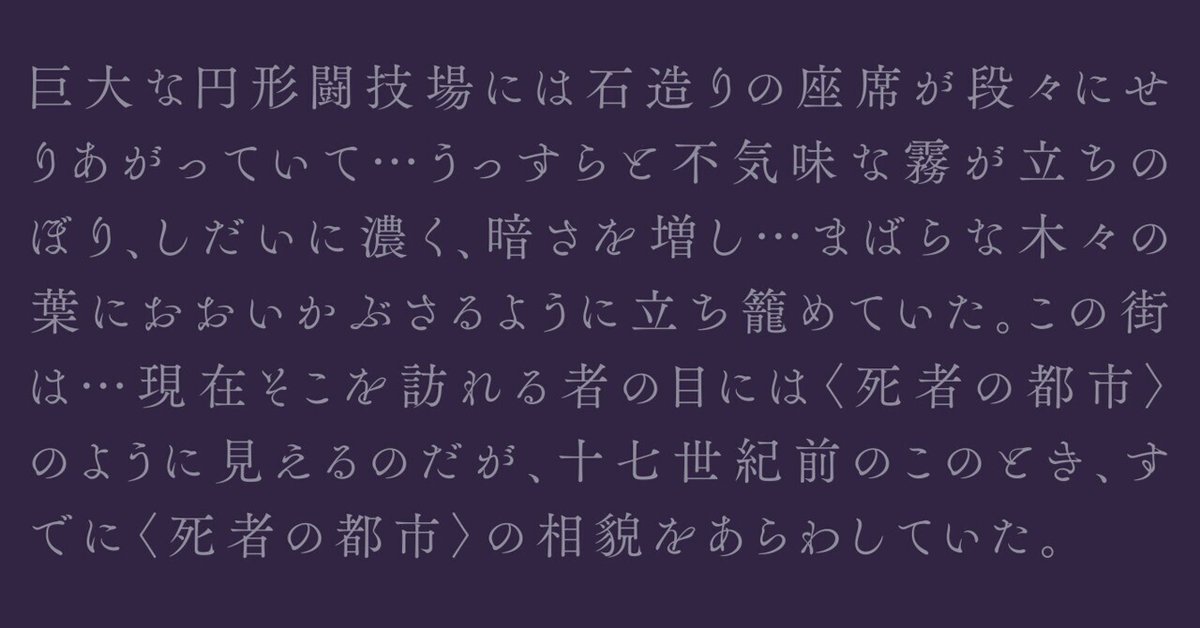
エドワード・ブルワー゠リットン『ポンペイ最後の日』〈上・下〉訳者解説(text by 田中千惠子)
2024年6月下旬と7月下旬にわたり、幻戯書房は海外文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第40・41回配本として、エドワード・ブルワー゠リットン『ポンペイ最後の日』〈上・下〉を刊行いたしました。エドワード・ブルワー゠リットン(Edward Bulwer-Lytton 1803–73)はイギリスの小説家、詩人、劇作家、政治家で、社交界小説や犯罪小説、歴史小説、オカルティズム小説など、多彩な作風の作品で成功を収めました。彼の作品はエドガー・アラン・ポーに多大な影響を与え、ブルワー゠リットンは探偵小説・スリラー小説・ファンタジー・SFの父と呼ばれています。代表作は『ぺラム』、『ポンペイ最後の日』、ほかに犯罪小説『ポール・クリフォード』『ユージン・アラム』、歴史小説『リエンツィ』、オカルティズム恐怖小説『ザノーニ』『不思議な物語』『幽霊屋敷』などがあります。
『ポンペイ最後の日』は、ヴェスヴィオ山爆発で壊滅したポンペイを舞台に、ギリシア人美女をめぐる青年貴族とエジプト人魔術師の対決を軸として、古代魔術、殺人、剣闘士の戦い、キリスト教の芽生えなどを描く波乱万丈の歴史小説です。古代遺跡の発掘調査に基づき、当時のローマ文化と風俗、退廃的な文化と生活を再現しています。『ポンペイ最後の日』は数々の映画化で世界的に有名な小説ですが、日本ではこれまで完訳がありませんでした。本書が初めての完訳となります。ヴィクトリア時代にゴシック小説を復活させたブルワー゠リットンの、一大恐怖絵巻がくり広げられる不朽の名作――娯楽作品でありながら、人間の諸問題をあつかう大作『ポンペイ最後の日』が初めて、その全貌をここにあらわします。
以下に公開するのは、エドワード・ブルワー゠リットン『ポンペイ最後の日』〈上・下〉の翻訳者・田中千惠子さんによる解説「E・ブルワー゠リットンと『ポンペイ最後の日』」の一節です。




『ポンペイ最後の日』をめぐって
『ポンペイ最後の日』はイギリス・ヴィクトリア朝の作家・詩人・政治家エドワード・ブルワー゠リットンの歴史小説である。紀元79年のヴェスヴィオ山の噴火によるポンペイの壊滅を背景に、才色兼備のギリシア人美女をめぐる若きギリシア人貴族とエジプト人魔術師の争い、魔術師のたくらみ、魔術、妖術、占星術、残虐な殺人などを描いて、キリスト教と異教の相克、円形闘技場での血みどろの戦い、魔女や媚薬などを駆使しながら、ヴェスヴィオ山の大噴火へといたる波乱万丈の運命を描きだす。本作品は数々の映画化により、世界的に有名な小説となった。だが、ヘンリー・ミラーが『ポンペイ最後の日』を「最も大きな影響を受けた100冊の本」(ミラー『わが読書』)の一冊に選んでいることからもわかるように、本作は単なる娯楽作品にとどまらず、人間の情熱、生と死、信仰、人生哲学など、深甚な人間の諸問題をあつかう畢生の大作となっている。
ポンペイは、イタリア南部のナポリ湾に臨む古都である。当時はローマの治下にあり、カンパーニアでも有数の華やかな都市であった。ローマの富裕者が別荘をつくり、劇場、神殿、浴場、公共広場(フォルム)、柱廊、商店が建てられ、ギリシアやアレクサンドリアなどとの通交も続けられた。エジプトの女神イシスの崇拝も盛んで、多くの祭司が仕えていた。文化は爛熟し、富裕な市民は逸楽にみちた生活を楽しみ、饗宴をもよおし、豪奢な生活がくり広げられた。ポンペイの人びとは贅を凝(こ)らした浴場で快楽にひたり、賭博や飲酒などに憂さを忘れた。また、円形闘技場で剣闘士や猛獣を戦わせて血みどろの闘いに歓声をあげたが、この見世物は市民の最高の娯楽だった。
それが79年のヴェスヴィオ山の大噴火によって、近郊のヘルクラネウム(エルコラーノ)とともに灰に埋もれ、1748年にポンペイの本格的な発掘が開始されて日の光を浴びるまで眠りつづけることになった。その発掘により古代の生活が明らかにされ、その豪華で淫靡な様相に人びとは目をみはった。その遺跡にはヴィンケルマン、ゲーテ、モーツァルト、スタンダール、マーク・トウェインらが訪れている。
ブルワー゠リットンは、1832年『ユージン・アラム』、33年『ゴドルフィン』などを刊行したのち、健康上の理由からイタリアへ旅行し、ポンペイ遺跡を見て着想を得、『ポンペイ最後の日』を執筆、1834年に出版する。本書は出版されるやいなや、ウォルター・スコットの『ウェイヴァリー』以来の大成功をおさめ、当時、ヴェスヴィオ山の大噴火が起こったこともあって、たいへんな評判を呼んだ。
保守党政治家・小説家であったベンジャミン・ディズレーリの父、文人アイザック・ディズレーリは「これほどみごとでおもしろいフィクションは、これまでなかった」と絶賛し[★01]、「エグザミナー」誌(1834年10月26日)はつぎのような書評を掲載した。
『ポンペイ最後の日』はひとつの芸術作品としてみごとに構成され、全体が調和している。それは苦悩と安らぎにみち〔…〕近年まれに見る傑作である。この作品に匹敵するような作品がこれまで書かれたことがあるだろうか。レンブラントの筆でさえ、光と影を使って、これほどまでに真に迫る破滅的な効果をうみだすことはなかった[★02]。
これは非常に好意的な書評であるが、手厳しい批評家たちはその偉大な才能を認めながらも、辛辣さをにじませることも忘れなかった。
創造的な芸術家として、ブルワーが偉大な芸術家であるのは議論の余地がない。この点において、彼の作品は同時代の作家、あるいはほとんど〔あらゆる時代の〕作家の作品を凌駕している。〔・・・〕写実性、知恵、ユーモア、上品さ、詩情、そしてある種の高尚さにおいては、フィールディングのほうがはるかにまさっている。しかし、たくみな構成、複雑にからみあった事件をあやつる手腕にかけては、当代一流の散文フィクションの作家を超えるとはいわないまでも、匹敵するといってよいだろう。彼は実にみごとなまでに作品の構想を自家薬籠中のものとし、登場人物と事件を生き生きと描きながら、からみあったプロットをいともやすやすと巧みに発展させる。彼はあらゆる素材をうまく使い〔・・・〕みずからの力をひとつの結末に集中させるのである[★03]。
ブルワー゠リットン自身は『ポンペイ最後の日』の大成功に大喜びであったが、そうしたときに彼がいつも見せるように、他人には謙遜してみせた。彼は友人のディズレーリに「イギリスでは、この作品が私の作品のなかで一番すぐれているという評判だ。それが本当かどうかはわからないが、私は女性が読んでもおもしろくないのではないかと心配している。女性というのは、こみいったプロットや技巧に富んだ構成を評価しないからね」と書き送っている[★04]。
『ポンペイ最後の日』は念入りな調査にもとづいて執筆されており、著者はポンペイで実際に発掘された「ディオメデスの屋敷」や「悲劇詩人の家」(グラウコスの邸宅)などを登場させている。本書を読んで、実際にポンペイ遺跡を見たならば、読者はそこに登場人物のすがたをありありと思いえがくであろうし、ディオメデスの屋敷の地下室で発見された固まった溶岩のなかに、若い女性の胸の跡が残されているのを見れば、作中のはすっぱなユーリアの最期について思いを馳せるかもしれない。S・J・フラワーによれば、19世紀初期に発掘されたアルバケースとイシスの神官カレヌスの頭蓋骨が1859年ブルワー゠リットンに寄贈され[★05]、彼はこれをたいそう自慢していたといわれる。
『ポンペイ最後の日』の執筆については、ブルワー゠リットンがイギリスの考古学者サー・ウィリアム・ゲルと出会ったことも重要である。ゲルは当時ポンペイの発掘調査において考古学者のあいだでも一目置かれていたが、イギリスからの旅行者を案内してまわる役目も引き受けていた。その旅行者のひとりがウォルター・スコットであり、スコットは本作品にも書かれているように、ポンペイの町を見て、「死者の都市だ!」としきりに叫んでいたといわれる。ブルワー゠リットンもゲルの指導のもと、ポンペイの歴史や地誌を研究し、本作の執筆に際してゲルの著作やスケッチを参照し、多大な恩恵をこうむったことから、本作品はゲルに捧げられている[★06]。
[★01]Michael Sadleir, Bulwer and His Wife: A Panorama 1803-1836 (London: Constable, 1933) 366-67.
[★02]Edwin M. Eigner, The Metaphysical Novel in England and America: Dickens, Bulwer, Melville, and Hawthorne (Berkeley: U of California P, 1978) 168.
[★03]Eigner, 168.
[★04]Sadleir, 368-69.
[★05]Sibylla Jane Flower, Bulwer-Lytton: An Illustrated Life of the First Baron Lytton 1803-1873 (n.p.: Shire, n.d.)18.
[★06]Angus Easson, “‘At Home’ with the Romans: Domestic Archaeology in The Last Days of Pompeii,” The Subverting Vision of Bulwer Lytton: Bicentenary Reflections (Newark: U of Delaware P, 2004) 102.
【上巻・目次】
第一部
第一章 ポンペイの二人の紳士
第二章 盲目の花売り娘と上流階級の美女——アテナイ人の告白——エジプト人アルバケースの登場
第三章 グラウコスの素性——ポンペイの家の造り——古代の饗宴
第四章 イシスの神殿と神官——アルバケースの性格がわかってくる
第五章 花売り娘のその後——恋の進展
第六章 鳥師は逃げた鳥を再びとらえて、新しい獲物を求めて網をはる
第七章 ポンペイののらくら者の享楽生活。ポンペイの浴場
第八章 アルバケースは快楽といういかさまで細工して、まんまと成功する
第二部
第一章 ポンペイの「ならず者の巣窟」——古代の闘技場の勇士
第二章 ふたりのお偉(えら)方
第三章 グラウコスが買い物をするが、それはあとで高くつく
第四章 グラウコスの恋がたきが先手をとる
第五章 哀れな亀——ニディアの変化
第六章 幸福な美女と盲目の奴隷
第七章 イオネー、罠(わな)にはまる——ネズミは網を嚙(か)み切ろうとするが
第八章 アルバケースの孤独な人生と独り言——彼の性格の分析
第九章 アルバケースの屋敷に着いたイオネーはどうなったか——恐るべき敵の受けた天罰の最初のしるし
第三部
第一章 ポンペイの公共広場(フォルム)——世界の新紀元を画したキリスト教の黎明
第二章 カンパーニアの海の真昼の舟遊び
第三章 集会
第四章 恋のゆくえ——いったい、どこへ?
第五章 ニディア、ユーリアに会う——異教徒の妹と改宗した兄の会話——グラウコスのキリスト教観
第六章 門番——娘——そして剣闘士
第七章 ポンペイの美女の化粧室——ユーリアとニディアの重大な会話
第八章 ユーリアがアルバケースに会う——その結果
第九章 南国のあらし——魔女の洞窟
第十章 《炎の帯の王》と家来——運命の神は赤文字で預言をしるすが、それを読むのは誰なのか?
第十一章 事態は進行する——筋書きは錯綜する——陰謀はめぐらされたが、役者が変わる
註
【下巻・目次】
第四部
第一章 初期キリスト教徒の熱情について——ふたりの男が危険な決意をする——壁に耳あり——ひときわ神聖な壁!
第二章 古代の饗宴の主人、料理人、台所——アポエキデスがイオネーを訪れる——ふたりの会話
第三章 ポンペイの上流社会の饗宴と当世風の晩餐(ばんさん)
第四章 あるエピソード
第五章 媚薬——その効果
第六章 さまざまな役者が再会する——ばらばらに見えた流れがひとつの深みになだれこむ
第七章 その後のグラウコスのようす——友情が試される——憎しみもやわらぐ——愛は変わりなく——恋する乙女は盲目なのだから!
第八章 古代の葬儀
第九章 イオネーにせまる危険
第十章 アルバケースの屋敷でニディアはどうなったか——アルバケースがグラウコスに同情する——同情も罪を犯した者にとっては無用
第十一章 ニディア、魔術師のふりをする
第十二章 飛んで火に入る夏の虫
第十三章 奴隷がお告げを聞く——ニディア、ソーシアをだます——一夜でふたりの囚人
第十四章 ニディアがカレヌスに話しかける
第十五章 アルバケースとイオネー——ニディア、庭に着く——果たして彼女は脱出して、グラウコスを救えるか?
第十六章 グラウコスの仲間の嘆き——牢獄と囚人
第十七章 グラウコスに九死に一生のチャンス
第五部
第一章 アルバケースの夢——あらわれた訪問客と警告
第二章 円形闘技場
第三章 サルスティウスとニディアの手紙
第四章 再び円形闘技場
第五章 囚人の監房と死体置き場——悲しむ者は恐れない
第六章 カレヌスとブルボ——ディオメデスとクローディウス——円形闘技場の娘とユーリア
第七章 破滅の経過
第八章 アルバケースがグラウコスとイオネーに再会する
第九章 恋人たちの絶望——民衆のようす
第十章 つぎの朝——ニディアの最期
最終章 すべてが終わる。グラウコスからサルスティウスへの手紙——ポンペイ崩壊の十年後
註
エドワード・ブルワー゠リットン[1803–73]年譜
訳者解説 E・ブルワー゠リットンと『ポンペイ最後の日』
【訳者略歴】
田中千惠子(たなか・ちえこ)
1957年、兵庫県生まれ。首都大学東京大学院(現東京都立大学大学院)人文科学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。英文学・表象文化論。大阪大学大学院文学研究科非常勤講師などを務めた。著書に『「フランケンシュタイン」とヘルメス思想——自然魔術・崇高・ゴシック』(水声社)、『イギリス・ロマンティシズムの光と影』(共著、音羽書房鶴見書店)、訳書に『神智学とアジア——西から来た〈東洋〉』(共著、青弓社)などがある。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、エドワード・ブルワー゠リットン『ポンペイ最後の日』〈上・下〉をご覧ください。
