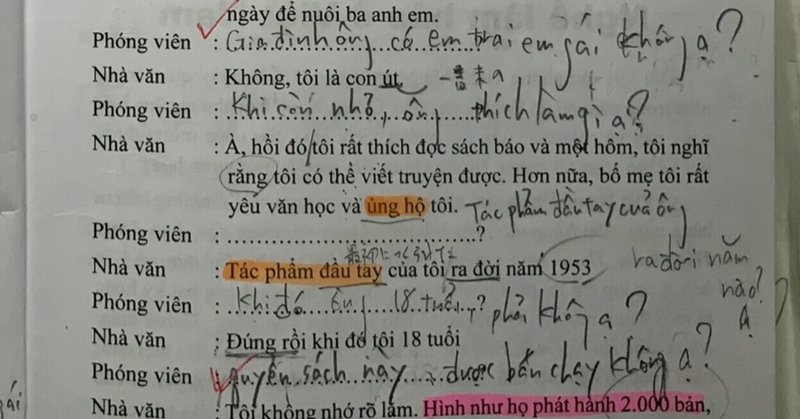
30代からの語学4 無理のない勉強法
娘が幼稚園に行くようになった頃から平日よりも休日の方がずっと忙しく感じるようになった。在宅勤務が中心なので幼稚園に行っている平日はある程度自分のペースで仕事をしたり食事を取ったりできるのだが、幼稚園のない休日は娘のペースで家族全体が動く。来週の小テストを作っている途中で「遊んで〜!」とせがまれ、業務メールを書いていたらPCのキーボードをめちゃくちゃに叩かれる...
しかも今は8月、つまり幼稚園は夏休み。娘は毎日が週末状態。コロナ禍で思うように外出できないので家で過ごす時間が自然と長くなった分、仕事のスケジュールに少し余裕を持たせないと回らなくなってきている。
30代にもなると、学生の頃みたいな「勉強だけに静かに集中できる日々」なんて遠い昔の記憶になってしまう。当然ながら学生時代の勉強法も全く合わない。今回は30代からの語学のための無理のない勉強法を考えてみよう。
30代からの語学勉強法 何が目的か?
大半の方にとって学生時代の勉強は「知識+α」を得る必要があったはずだ。「+α」の部分は大学の単位や学位であったり、就職に必要な資格が入る。自分の学生時代を振り返ってみても、比較的自由に勉強していたと思っている時でも「単位や学位とは全く関係のないこと」を勉強した経験はとても少ない。
30代から新しい語学を勉強しようと思い立った時、学生時代と同じ意識で勉強することはもはや不可能なことに気づく。大学の単位も就職のためのSPIもとっくに昔の話だ。何のために勉強するのかをもう一度考え直してみないといけない。
語学を勉強する上で注意しないといけないのは、語学自体にはゴールがないことである。もちろん語学の検定試験には最上級(例えば、英検一級やHSK6級)があって、そこを目指して頑張っている人たちもたくさんいる。私も中国語では最上級の検定試験の一つをクリアしているが、だからといって中国語をマスターしたという感触を得たことはこれまでに一度もない。よくよく考えてみると、母語である日本語ですら全てのことを知っているわけではないので、母語ではない中国語を完全にマスターしたと思う日は一生かかっても来ないのだと思う。
学生時代のように単位に追われることもなく語学自体にはゴールもない...思わず「何のために勉強すればいいのか?」と問いたくなる。この問いに対しては「続けるために勉強している」と私は答える。
新しい知識を得ることは基本的に楽しい。また、まとまった量の勉強をやり切った時には達成感も得られる。でも実際は忙しい日々の中で心身ともに疲労しているし、勉強すること自体がしんどい日もある。そのしんどさ自体はどうやっても否定できないので、それをあえて受け入れた上で「それでも勉強を続けていく」ことを目標にしている。「続けていれば楽しいこともあるし、いつか達成感を得られる日が来るさ」と軽く考えておく。
「続けるため」の勉強に必要なこと
「続けていくこと」を目標にするならば、勉強の仕方は根本的に変わってくる。一番避けなければいけないのは「諦めてしまうこと」なので、あまりにもストイックでしんどい勉強スタイルは向いていない(ただし、第3回で紹介した最初に軌道に乗せるための一週間のスタートダッシュは必要)。
最初の一週間のスタートダッシュが過ぎたら、テキストを毎日開くことは目標にせず、せいぜい一週間に二、三回のペースで進めるくらいの計画を立てるのがちょうどいい。例えば、一週間に二回ならば週末に一回頑張ってしまえばあとは平日一回だけ時間を確保できればクリアできる。大抵の入門のテキストは二回やれば一課分進めることができるのでキリもいい。一週間に三回進める場合は、三回目にその課の復習をすれば内容の理解度も定着度も向上するのでさらに良い。
このペースで一ヶ月続ければ四課分進めることができる。入門レベルのテキストは通常二十課くらいの構成なので、このペースを五ヶ月キープできれば大抵のテキストは終わらせることができる。
テキストを開かない日を支える秘密兵器
机に向かってテキストを開くのが一週間に二、三回でいいとして、残りの日は語学をすっかり忘れてしまっていいのだろうか?
そうは言いつつも実際は仕事や家事育児に追われており、せいぜい通勤や子どものお昼寝などの「細切れな数十分」くらいしか時間が確保できない。
この細切れ時間を語学のために有効に使いたい人にピッタリな教材がある。それは白水社の『言葉のしくみシリーズ』である。
このシリーズを一言で表現するなら「読む語学入門テキスト」。どの外国語でも見開き1ページで話がひと段落つくので、通勤時の一駅間でも読めるし子どもがいつ昼寝から起きても安心だ。私もベトナム語、ドイツ語、フランス語を買って読んでいたが、白水社さんは本当にものすごいシリーズを開発したと思う。
ただ個人的な経験にもとづくと、このシリーズは「細切れ時間をうまく埋めてくれる補助教材」として使うのがベストで、メインのテキストは別に用意したほうがいい。私も中国語を教える時には色々と工夫をするけれど、どうしても本を読むだけではうまくならない。一週間に最低二回は耳と口を動かさないとなかなか進歩を実感できないから、そこは少しだけ頑張ってみよう。
