
理性の神話
最近、メディアにあふれる論理性の無さに絶望する機会が多かった。論理性や合理性といったものは物騒な兵器のように思われており、大きな影響力を持つ人の言葉ほど共感や同調をベースとし、結果として立場の違う者同士の議論がまるで成り立っていない。論理性の持つ真の力、すなわち、普遍性を大切にすることで共感ができない人にも理解を促すという力が活かされず、そのような言説はほとんど塵のようにしか扱われない。
世界がなぜこんなに論理を蔑ろにするのか、と嘆いていた昨今。
書籍「啓蒙思想2.0」との出会い
私自身はさっぱり読書に縁遠い人生を送ってきたのだが、幸いにして読書家の友人がいる。彼から「あなたは今これを読むと良いと思う」とオススメされたことがきっかけで少しずつ本を読み始め、「ファクトフルネス」やら「サピエンス全史」やらを楽しみ、それまでスッカラカンだった自分は素晴らしい読書体験を知ることができた。
なので、その友人から「あなたは今これを」と紹介される書籍のことはかなりの精度で信頼しているのだが、この前会った時にすごい丁寧にオススメされたのがこちらの書籍、「啓蒙思想2.0」だった。
【啓蒙思想2.0〔新版〕 政治・経済・生活を正気に戻すために (ハヤカワ文庫NF)/ジョセフ ヒース】「やっぱ個人の理性に期待するよりナッジとか行動デザインですよ!」みたいな話に落ち着くのはそれ… → https://t.co/DT0dATj6hd #bookmeter
— 水原由紀/Yuki Mizuhara (@mizuharayuki) April 17, 2022
タイトルを見て私は少しならず怖気づいた。
啓蒙思想。およそ理数系の道を歩んできた人間からは縁遠い存在に思えた。三角関数と指数関数のことはわかっても、啓蒙のことと思想のことはさっぱりわかる気がしない。正直、タイトルからはなかなか自分が楽しめそうな要素を想像できなかった。
しかし、彼がわざわざオススメするということは、これは何か絶対に自分に必要なものが書かれているはずだ、との思いで読み始めてみた。そして20ページも読んだところでそれが完全に正しかったことを確信した。
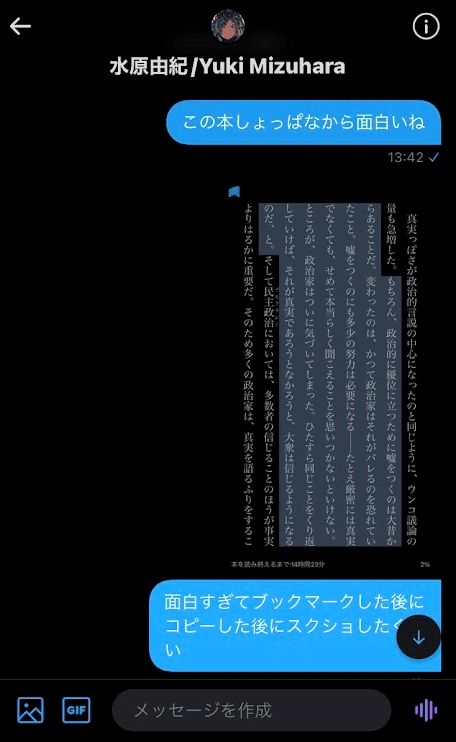
気がつけば読み進めるほどに多くの文章をブックマークしてコピーしてスクショしまくっていた。その数222個。
理性に期待する人間の絶望
本書はトランプ大統領が誕生するより以前の2014年に原著が出ているわけだが、「ポスト真実」はその頃既に始まっており、「政治家はかつて嘘がバレるのを恐れていたが、ついに気がついてしまった。同じことをひたすら繰り返すだけで、大衆はそれを信じるようになるのだ」と呆れながらに記している。本国でも同様のことを味わって呆れ果てていた私は、それが世界共通で避けがたい傾向なんだと知ることができて、大変気が楽になった。
理性的な人が社会に感じている不満に本書はどんどん切り込んでいくので、理性的な人にとっての読書体験は爽快だ。しかし、そうした不満を「これだから非合理的な奴は」で済ませずに、むしろ、人間の理性に期待しすぎていたのは啓蒙思想1.0と呼ぶべき過去の失敗であり、これからは啓蒙思想2.0として人間の理性が働きやすい環境をどうやって作るのか?という建設的な提案にシームレスにつながるのが面白いところだ。
私はこの本を読んでいる途中からタイトルを
「理性の神話」
に変えるべきではないか、と感じはじめた。
というのも、著者であるJoseph Heathの前著に「反逆の神話」なるものがあり、こちらは(友人によると)「お前らカウンターカルチャーって言ってるけどそれ資本主義の上で差異化のゲームで踊ってるだけじゃねえか!!」ってずっとキレてる本、らしいが、こちらに倣ったタイトルのほうが内容の想像もしやすくウケも良い、気がする。
そんなわけで啓蒙思想2.0、あらため「理性の神話」について、かいつまんで内容を紹介しつつ(より精緻な話は本を買って読んでほしい)、私なりの、すなわち、ゲーム製作者という、社会にそんな影響を与えるとはあまり思えない立場からの、ささやかなアイデアについて考えてみようと思う。
なぜ世界は非合理に溢れているのか
具体的な問題に言及するとこのnoteが政治的になってしまうので、抽象的な話になるが、このような構造を各自で想像してみてほしい。
あなたはある問題に関して、合理的と思われる仮説を持っている。
一方で、あなたが到底賛成できないような、完全な非合理を叫びながら支持されている有力者がいる。
有力者は何度もその嘘や非合理を指摘されているにも関わらず、そんな事には耳も貸さない民衆からの支持が途絶えることはない。
それどころか、メディアはそうした非合理の一番過激な部分だけを切り出して拡散し、それを訂正したり注釈したりする情報はあったとしてもまったく広がらず、結果として合理的な議論がすべて飲み込まれる。
あなたはそうした世間に嫌気がさし、そもそも問題に関わること自体が人生にとって非合理であると考え、非合理な過激派だけが議論に残り続ける。
あるいは、合理的な専門家が微力ながらも民衆に訴えかけ、こう締めくくるのである。「皆さん一人一人が、この問題に関してもっと良く考える必要があります」と。
こうした形式は世間の至る所に見られる。
なぜ自分ごときが少し考えたらわかるようなことが、世間では微塵も通じないのだろうか。エリートがこぞって大いなる陰謀に加担しているからだろうか?それとも、自分は思っていたより数少ない優秀な人間で、世の中の99%の人間は自分のように文章をちゃんと読んで考えるなんてことはできない、ただの無能なんだと、そう考えるしか説明がつかないではないか?
と、諦念を抱えている人にこそ読んでいただきたい。ここから始まるのは、人の理性の限界と可能性の話だ。
理性という「能力」がある、という幻想
実は私自身、「皆さんが一人ひとりよく考えて」という提案を目にした時に、少なからず違和感を抱くことがある。
それは、「なぜ私が考えなくてはならないのか?」あるいは、「その問題に関心がある人がちゃんと考えてくれれば、私が考えなくても良いじゃないか、そんなことを、全部考えている暇はないんだ」ということだ。
これは問題を主体的に考えて行動している人にとっては、ひどく残酷な話に思える。時間をかけて考えて呼びかけたのに、もっと多くの人が声を挙げないと世の中は変わらない。しかしながら、その切実な問題に対して、誰も同じレベルで考えてはくれない。
同じように、「もっと良く考えろ」「もっと声を挙げろ」と言われた私や多くの人は感じる。一体どれについて真剣に考えれば良いのか。日々押し寄せる情報から、1つの問題に関して深掘りすることだけでも精一杯なのに、一体どこに「あなたの問題」や「知らない人の問題」を考える暇があるのか。ましてや、それが仕事である政治家ならまだしも、私達には仕事も子育ても趣味もあるんだ、それだけで1日24時間ですら足りないというのに。

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
まずは、「考える」ということが、有限のリソースを消費する行為、すなわち、資源であると捉えることが必要に思われる。
そうすると、「皆で同じことを一人ずつ考える」なんてことは、「各ご家庭でお弁当を作って持ってきてください」とか「皆がそれぞれ車輪の再発明をして同じプログラムを作ってください」みたいな、非合理性の極みのような提案に近い。
「考える」ということは、料理をしたり、プログラムを書いたりすることと比べたら、誰にでもできる、むしろ人間ならできて当たり前で、やらない奴は獣と同義である、とすら思われがちだ。しかしながら、近年の認知科学ではむしろ人間がいかに非合理なままの直感を使ってほとんどのタスクを処理しているかが明らかになっている。
理性は可能なかぎりケチりたいリソース
私たちは思考を一つの統合された意識だと感じているが、そこには直感と理性という、本質的に極めて違う2つのシステムが搭載されている。
いや、実は理性なんていうものはシステムとして存在しているかどうかすら怪しい。どちらかというとそれは、理性があるかのように見せかけている、エミュレートしている、と言ったほうが正しいようだ。本書では解明される意識 | ダニエル・C. デネットという書籍からの引用として、「並列型のハードウェアに実装された、直列型のバーチャルマシン」と表現している。

既にご存知の方も多いかもしれないので、ここではいくつかの引用をしつつ簡単にまとめておきたい。
私達の思考には2種類の過程があり、まったく違った特性がある。
システム1:
直感、ヒューリスティックな判断
無意識で、自動的に、並列に、迅速に働く
常識的な答えを高速に導くだけで、間違うことがある
低労力
システム2:
理性、分析的な判断
意識的で、直列に、低速にしか働かない
ワーキングメモリを消費する
常識的な連想を超えて、抽象的・仮説的な思考が可能
高労力
詳しくは「二重過程理論」とか「ファスト&スロー」が参考になるはずだ。
私たちは「物心がついた時」から、もっぱら理性的に考えることができている、かのような錯覚に陥りがちだ。しかしこのような発達した認知能力は子供が言語を習得した後でようやく芽生えてくるらしい。人類もまた、文法という直列かつ汎用的な表現方法を発達させる過程でこのような理性的思考を獲得した。
その証拠に、チンパンジーなど遺伝的に近い生物でも言語をもたない人間以外のものは、「数を数える」という初歩的な汎用性も会得することができないという。

私達は自然に数を数えたり文章を作ったり明日の献立を考えたり、ましてや、行政からの見慣れない重要そうな書簡を開けて中身を理解しようとするわけではない。
それらは極めて不自然な形で脳を使うことで成し遂げており、毎日それなりに使うから当たり前だと思っているかもしれないが、実際それをした後はひどく疲れており(MP切れとか、決断疲れなどと呼ばれる)、脳は一刻も早くこの鈍重な理性エミュレーターを終了させてCPUを解放してくれという思い、あるいは物質でいっぱいになる。
補題:ゲームは理性の限界を学ぶ最良のツールかもしれない
香川県の悪名高いゲーム規制条例が出た際に「(任意の)ゲームをやるとドーパミンが(いくらでも)出る」かのような衝撃的なエアプ認識のまま審議が進められたことは記憶に新しい。
参考:
ゲーマーの皆さんはご存知のとおり、むしろそんなに簡単に気持ちよくなれたらどれだけ神ゲーか、世のゲーマーや開発者がどれだけ血と汗をにじませながらゲームに向き合っているか何もわかっていないんだな、と思うわけだが、実際のゲームはそれどころかむしろ我々に高いレベルの断続的なセルフコントロール、すなわち理性の働きを求めるものだ。
この認識に到るまでにはそれなりのプレイ時間、真剣に向き合うことが必要にはなるものの、むしろフィードバックが早い分、他の活動では人生を通して会得するような境地にゲームという環境は高速に収束していく。
気持ちよくなりたいと思ってプレイしている人間同士が対戦した場合、最終的に気持ちよくなる(=勝つ)のは、一番最後まで気持ちよくなるのを我慢(=セルフコントロール)して、より安全でより確実でよりチームのためになる行動をした方だ、ということが体感できる。
参考:
理性的に考えればあの時こうプレイするべきだった、という事はわかるはずなのに(だから「次なら勝てる!」と思ってしまうのに)、それを「頑張って敵を倒した直後」とか「頑張ってピンチを切り抜けた直後」とかの、脳が休みたがるタイミングでも冷静に実行することは非常に難しい。

理性を要求される場面が数秒ごとに何度も訪れる環境だからこそ、こうした理性を持続させるのは難しい、ということを嫌でも認識させられる。
翻って、我々は仕事で頭を使って疲れたと思った直後は何も考えずに高カロリーなものを食べてしまったり、何も考えずにTwitterを見てしまったり、後で考えればそうしないほうが将来のためであることは明らかである事をついやってしまう。もちろんそこで理性的になれるに越したことはないのだが、脳にそうしたリソースが残っていない時は、そんな簡単な警告すらも自分に届けることができない。これが理性の限界なのだ。
非合理性を利用する商業主義
人間にとって理性を働かせるのは、有限のリソースを消費することだ。
では、どこにその貴重な判断力を使うべきなのか?それを何らか社会に役立つ仕事や、正しい投票先を選ぶことに振り向けられるのならまだ良い。現実はもっと悲惨だ。
商業主義が、我々の利便性を究極まで押し上げ、客にとって将来的に毒になろうと借金になろうと知ったことではない誘惑の数々を生み出すことにすべての人類を駆り立てる。そうした人間敵対的な環境を分析して正しい選択をすることだけでも(つまり、普通に生きることだけでも)私達の判断力は歴史上かつて無いほど酷使されている。
人が理性を使わずに生きてきた時代
人類がまだ狩猟採集生活を送っていた時代、私達は直感を使ってうまく生き残ることができた。
大きな獲物を見つけたら、逃げられたり奪われたりする前に獲り尽くしてしまうのが重要だ。
脂質や糖質は貴重なリソースであり、これを摂取しない者は飢えて死んだ。
毎日顔を合わせる部落の民は大事な仲間であり、敵と瞬時に区別できることは重要な意味があった。
しかし現代社会はどうか。

肥満があらゆるリスクに繋がる事が明らかであっても、バターたっぷりのクロワッサンにクリームを乗せたものを我慢することは直感に反する。
今すぐに現金が手に入るなら、将来それがどんな借金になるのか気にするのは臆病者のすることだ。
毎日何億人のスマートフォンに何兆件と流れ込む広告イメージは、よく目にするものだから親しみやすく疑うべきではないと直感が教えてくれる。
本書は他にも様々な点でより深く商業主義の問題を取り上げているが、中でも衝撃的だったのは、ほんの150年ほど前の広告がいかに人間の理性に訴えかけようとする良心的なものだったかということだ。
およそこの小さい文字の広告全文を読む気になる人が現代社会に残されているとは思えないが、

この広告は、人間が誰しも理性的に商品を選ぶはずであるという、あるいはそうした信頼の構築がブランドにとって大切であるという素朴な期待が生んだ遺物である。
現代の広告はそんなまどろっこしい真似はしない。
もっと直感に訴える”良い”方法を編み出した。そのことを考えるたびにこの映画『素晴らしきかな、人生』のことを思い出す。ウィル・スミスが広告代理店のカリスマ経営者を演じる中で、映画のテーマとなる「愛、時間、死」について演説する。
本作は別に商業主義を皮肉ったりするわけでもなく良い映画なのだが、この3つのテーマには普遍的な価値がある。「愛、時間、死」。人はそれを手に入れること、あるいは失うことに対して冷静ではいられない。そこに意図的に付け込む広告こそが、人々の心を、すなわち直感を動かし、購買行動を起こす。
問題は、現代の広告産業や商業主義が、何らかの悪意や陰謀をもってこれを生み出しているわけではない、ということだ。ウィル・スミスの演じる広告マンのように、まったくの善意、あるいは情熱から、人々の直感により訴えかけやすい広告を作るクリエイターがいて、彼らに資金をつぎ込んでいくことが商業的に生き残ることの条件である、というだけだ。
この条件はもっぱら人間の理性の限界、直感の誤謬に起因しており、条件が変わらない限りそれがもたらす結果は同じものだ。
すなわち、より洗練された手段で人々にものを無駄に買わせることに成功するものだけが残り、あとは淘汰される。それを繰り返すだけで、1866年のフェル社のコーヒー広告のような消費者の理性に期待した広告は自動的に絶滅する運命だった。
かくして、我々の理性は、元から足りないのみならず、今や普通に生活をするだけで街中やSNSに紛れる何千件という広告の全面攻撃を浴び、その中からまともそうな物や信頼できそうなインフルエンサー判断するだけでも使い果たしてしまう状況にある。
しかもこれは誰かの悪意ではなく人間の性質から自然と導かれる状況だというから始末に負えないばかりか、今後さらに洗練された攻撃方法が編み出されていくことによって、私達の理性はより一層貴重なものとなり、大切なことに向けられない状況になる可能性がある。
共有地の悲劇
理性が足りなくても、直感に従っていれば楽しく気楽に生きられるじゃないか、という期待は間違っている。それをしかも、論理的に示すことができてしまう。
それが「共有地の悲劇」というものだ。経済学の用語として有名なので、これだけでわかる人もいらっしゃるだろう。
最も単純な例で言うと、漁獲量の問題がある。海、というのは共有地だ。漁をすると魚をたくさん獲ることができるが、海という共有地のリソースは無限ではない。全員が乱獲を行えば翌年に捕れる量はどんどん減ってしまうだろう。そのため、全員がそれぞれ自分の取り分を少なく保つことに納得しなければ、結果的に全員が取り分を減らしてしまうことになる。
ここに共有地の悲劇が起こる。
ほとんどの理性的で協調性のある人が、魚資源を守るため、漁獲量を少なく保ったとする。すると、海にはまだ充分な、少なくとも一人がこっそり取り分を多くするには問題のない範囲の、魚が残っているではないか。ではその恩恵に預からないことは損ではないか?たしかに全員が乱獲をすれば全員が損をするが、最も理想的なのは自分以外の全員が我慢をした上で、自分だけが得をする、という状況ではないか?そうすれば、漁獲量が毎年減ることもなく、自分が利益を逃すこともない。こうした考えのもとに全員の努力で生み出した資源をかすめ取る存在のことを「フリーライダー」と呼ぶ。
だが当然のこととしてこれは文明的な秩序の崩壊を招く。フリーライダーがたった一人では問題とならないかもしれないが、「あいつ」がやっているなら「おれたち」がやって悪い理由などあろうか。「あいつ」に利益を独占されるために「おれたち」は漁獲量を守っているわけではない。「あいつ」がやめないなら、「おれたち」だって協調的な行動は取らない。そうやってフリーライダーに溢れた海では、魚資源がすっかり失われる場合もある。
これは実に本質的な問題だ。我々が集団としての利益ではなく個々人の利益に縛られているが故に、誰にとってもフリーライダーになるインセンティブがあり、全員が最適な行動をするからこそ、共有地の悲劇に陥るのである。
様々な「共有地」の悲劇
こうした「個々人が最適解を選ぼうとした結果、全員がフリーライダーになるインセンティブが生じて、全員が損をする」という構造は、他にいくらでもある。
本書で取り上げられている中でわかりやすいのは銃社会の問題だ。

アメリカでは平和へのフリーライダーが増えすぎた結果、毎日のように銃乱射の事件を耳にするような平和とは程遠い世界が実現された。

Photo by Yasin Arıbuğa on Unsplash
このコロナ禍で嫌というほど目にした反ワクチンや反マスクといった存在も、このフリーライダーの構造に当てはまる。
彼らが本当に全員がワクチンやマスクをしなくても(=医療資源のフリーライダーになっても)問題ないと思っているのか、あるいは自分以外の全員が対策をしていれば自分は大丈夫だというフリーライダーの自覚があるのかはわからないが、実際そのような不合理な存在を生かしているのはまさに、ワクチンを打って感染防護および免疫によって医療資源を守り、またマスクをして感染を広げないようにしている真っ当な感覚の市民たちだ。もちろん、こうした市民が皆諦めてフリーライダーになると、最も多くの死者を招いたであろうことは想像に難くない。
もう一つ、多くの医療関係者の努力や市民の自粛によって守られた「感染者数の少ない社会」という共有資源を、オリンピック選手と関係者に独占させる=フリーライドさせる形で行われたのが前回の東京2020オリンピックだったことも忘れられない。
参考:
驚くべきことに、本来はフリーライダーを規制して社会に秩序をもたらす機能を担う政府が自ら、共有の資源を分配するでもなく特定の集団に使わせることを是としたわけだ。
たしかに、自分だけ乱獲をする漁師のように、「他の人が我慢しているからこそ」問題なく社会が回ってしまう、という事は起こる。
しかしながら、「お前がフリーライドするなら、なぜ私が一方的に損をしなければならないのか」という集団としての理性の崩壊を招きかねない所業を、反社会的な個人ではなくむしろ国家が行ったということに、私は少なからぬ絶望と衝撃を覚えた。
しかしそれは、この本を読んだ後になれば、むしろ当然の帰結であったと思わされる。なにしろ、政治家や政党というものも、まさに我々の非合理な直感を満足させるように淘汰されてきたものなのだから。
非合理性に最適化した民主主義
我々は民主主義というツールによって国家を横暴な独裁者から取り戻す力を得ているが、今ここには商業主義と同じ種類の淘汰圧がかけられている。
フェイクそのもののスローガンやイメージが商業メディアによって何万回と再生されるうちに、その検証や批判について知る機会は(多くの人が気持ち良いと思ったことを否定する内容であるために)自然に最小化される。
本書では、とくにアメリカ合衆国第40代大統領ロナルド・レーガンについて、俳優上がりの親しみやすさを持ちながら、嘘や非合理を指摘されることに何らやましい気持ちを抱かずに堂々と同じ嘘や非合理を繰り返せる、という能力について、興味深い考察が載っている。

本国で同じようなことを味わって呆れ果てていた頃のnoteがある。しかしながら、私もこんなことを指摘していると党派的だと思われてしまい(党なんて関係ないのだが)、友人を失ったりした苦い経験となっているので、こうした非合理性への指摘はまったくもって身のためではない。
しかし集団の中にそのような指摘をする人がいなくなり過激化すると痛い目を見ることになる。つい最近もそのような集団が幾度となく対立し、問題の解決のためではなくお互いのコミュニティ=部落集団の維持のために敵を敵のままにしようとする姿を目撃した。
参考:
↑の記事で書きたかったことは「合理性は相手を攻撃する道具ではなく、合意形成して味方を増やすための道具のはずだ」ということだ。数学者たちがフェルマーの最終定理がほとんど正しそうだ、ということが直感でわかってもなお300年も証明を諦めなかったのは、普遍性がなければ信じる人・信じない人の溝が永遠に埋まらないからだ(ということを↑の記事で書いた)。
しかしながら、こうした合理的な妥協の提案は両方のコミュニティから弱腰であると捉えられたり、「味方ではないならば、敵だ」という扱いを受け、どちらからも採用されることは無い。そうした態度そのものがコミュニティを過激化させ、集団の規模を狭め、結果として目的からさらに遠ざかっているとしても、だ。

本書ではこうした「直感を満足させるための主張」をする集団が、理性というツールを手放したがために、かえってその集団の目的から遠ざかっていく過程をいくつも例示している。
ポルノグラフィを敵視するフェミニズムにとどまらず、犯罪被害を低く抑えるために司法制度を厳罰化すべきと考えがちな私達の直感の間違いや、消費税が不要であるといった願望に付け入る主張や、国際貿易が失業者を生み出すといった直感などなど、「被害者の声」に耳を傾けるという非難しにくい体裁を維持することで、支持者は減りにくい一方で被害者を増やしている、といった状況が至る所に現れる。
専門家は声ではなく事実に目を向ける
「客観的になること」は「人をモノ扱いすること」だととられやすいし、感情の排除は人間の苦しみへの無関心になりかねない、と本書は綴っている。公衆衛生の改善などまさに典型だ。病に苦しむ人々に一人ずつ対処するよりも、どこでどんな条件で病が広がっているかを観察し、環境そのものを改善しなければならない時はある。目の前の患者一人を脇において研究を行う医者は、後に表彰されるかもしれないがその場では悪魔と見做されるだろう。
しかしながら、人間の苦しみへの共感的な対応が、多くの人間を新たな苦しみに誘うことになると認めるには、大いなる自制が必要だ。
かくして、人は自らを本当に助けてくれる可能性の高い主張ではなく、自らの(直感に従った結果として悪い結果を招く)主張を守ってくれる人を選んでしまう。合理的な手段を提供する専門家は、人の気持ちを理解しないという点で犯罪者と同類であるように扱われ、利権があるからそのような事を押し付けるのだという陰謀論に堕されてしまう。
知能とは間違いを認める能力
さて、こういう話をすると「だからあいつら(敵)は気持ちよくなりたいだけで助かりたくなんてないんだ」と斜に構えたくなる。その気持ちは私もあるが、「自分は嘘や非合理を見抜いているが、敵対集団こそが嘘や非合理に騙され続けている」という認識こそが最も危険な確証バイアスと呼ばれるものだ。
本書によれば、認知バイアスを受ける度合いは知能によらない事が広範な研究で示されている。しかしながら、ひとたび答えが認知バイアスによる間違いだと指摘された際に、間違った箇所を見つけて答えを正す能力は知能指数に関係しているという。
知能とはまさに、間違わない能力ではなく、自らが間違っていたと認識する能力のことなのだ。
一貫性は、私からすると、最も論理性からかけ離れた性質ですけどね。それはむしろ「妄信」という性質に非常に近い。
— じーくどらむす/岩本翔 (@geekdrums) May 29, 2022
論理的であるっていうのは、前提が変われば結論が変わりますっていう状態のことなんですよ。
— じーくどらむす/岩本翔 (@geekdrums) May 29, 2022
そして、純粋数学と違って私達は誰も社会の前提をすべて知ってはいない。
私自身は間違いをあっさりと認めることが美徳であると考えている。しかしながら、こうした考えは世間で受け入れられないどころか、「論破」された人として晒し上げられたり、「一貫性のない」人として信用すべきではないと思われる事が多い。
そうした人間の心理を知った上で、政治家は自分の言うことが間違っていても一貫性を優先し、または、具体的な事には一切言及しないままに一貫して言える当たり障りのない内容を繰り返すことに腐心するわけだ。

こうした非合理に関して政治家を非難することは、気に入らないCMに出演する芸能人を非難することと同じくらい虚しい。そこには「より多くの直感を満たした方が選ばれる」というシステムによって淘汰された姿があるだけなのだ。
さて、ここまで、人間の理性には期待できない、直感を満たすものが勝つ、ような話をまとめてきたが、それでもなお文明社会が存続するには理性が欠かせない。では、そのような文明を作り上げる理性は、誰がどうやって働かせているのか。
理性を自動化するための国家と制度
これだけ扇動政治が蔓延りながらも民主主義が生きながらえているのには、理由がある。それはまさに、政治判断を直接の民主的コントロールから分離しておくための多岐にわたる「制度」によるものだ、と本書は説いている。
もちろん民主主義自体も、権力者の理性をある程度保つための1つの制度だろう。しかしながら、民衆によって本当にすべてが決められたのであれば、世はもっと混沌としてしまうはずだ。
近代の民主主義には、三権分立をはじめとして、中央銀行の独立性や、上院・下院の存在によって判断をゆっくりにすることなど、おおよそ民衆が直接素早く決めてしまうとおぞましい結果をもたらすものへの防御策としての制度が至る所に実装されている。
制度は、さながら自動化された理性である。
人間個人にはそのような理性が期待できずとも、いったん制度化して教育も行き渡って社会に根付き、常識と化してしまえばいとも簡単に高度な概念を操ることができる。
例えば、私達は今日当たり前のように「民主主義」や「人権」という概念を操る。さもそれが、「直感的に正しい」と感じることができている。しかしながら、これは完全に国家による制度と文化、そして教育の賜物だと考えられる。これは、そうした常識が無かった時代の人間が残してきた数々の歴史的な教訓からも明らかだ。

世界には既にこうした自動化された理性が数多く動いている。著者によれば、制度によって自動化できる理性のアイデアはまだまだ残されている。
例えば、イギリスの議会制で首相が庶民院に登場して政府の方針の正当性を主張し、他の議員から異議を突きつけられる制度や、欧州議会で採択されているような虚偽報道や捏造報道に対して有効な決議や、あるいは、短いアピールポイントを繰り返したりミスリードな切り抜きができないように放送局に1分未満のシーンの再生を禁じる制限を加える、などなど。
こうした提案は、我々一人一人が理性を働かせよう、などと呼びかけるよりもずっと効果的で、現実的だ。ちょうど、食べたいものを理性で我慢するよりも、小さい食器を揃える方がよほど効果的で現実的であるように。
しかし結局は制度を決める政治そのものがメディアによって扇動政治に最適化されており、「「「理性的な議論」を取り戻すための制度」を制定するための理性的な議論」を望むことが難しい。
そうして最後に著者は、メディアの速度に毒された政治を解放するために「スロー・ポリティクス」というスローガンを掲げて、それには「多くの献身的な支持者が必要である」と結んでいる。
念のために記しておくが、これだけ多く引用してもまだこの本の重要な部分の1%も紹介しきれたとは思えない。興味を持った人は、是非「啓蒙思想2.0」を読破いただきたい。現代社会に抱いているモヤモヤに対して、目を覚まされるような思いを何度もするはずだ。
著者のジョセフ・ヒースについて。
1967年カナダ生まれ。哲学者。ユルゲン・ハーバーマスとチャールズ・テイラーに学ぶ。現在、トロント大学教授(哲学・公共政策・ガバナンス)。著書に「反逆の神話 「反体制」はカネになる」「資本主義が嫌いな人のための経済学」など。
文中では、自らの理性の足りなさを証言する際に「夜も更けてきたのに次のセーブポイントまで進みたく成ったり、次のマップチェンジまでサーバーにとどまっていたくなるものだ」などと、ゲーマーの一面も見せていた。
理性を守るための文化と技術
ここまでは著者の主張を引用しつつ紹介してきたが、制度設計への提案を主とする著者の主張と違い、文化産業に従事する私の展望はもう少し明るいものだ。
これまで「理性」と「直感」はまるで相容れない2つの別物のように扱ってきたが、制度などによって「自動化された理性」は、ほとんど直感と区別がつかない。すなわち、理性と直感は連続的に変換可能なのだ。
この事は、ゲームの習熟過程を考えてもよくわかる。楽器演奏やスポーツなどの文化活動も同様だと思われる。最初は1つ1つ考えなければできなかった複雑な行動が、練習を重ねることで流れるように無駄なく繰り出すことができるようになり、多くの熟慮が自動化されて圧縮されていく。
より厳密に言うと、直感に変換されるのは、理性で考えた結果へのショートカットであって、前提が変わればもう一度理性で考え直す必要がある。練習でついてしまった悪い癖などはその典型で、理性的にそれを否定しなければ新たな高みにたどり着くことができない。
理性をショートカットする方法は練習だけではない。文化産業では多くの場合「直感的」で「ユーザーフレンドリー」であることが求められる。個々人に説明書を読んだりするような理性を求めているとユーザーは離れてしまう。そんな無駄なことをしなくても、触りながらで操作がわかるようなデザインがされていれば、多くの人が不必要に理性を消費せずに済む。
もちろんそれは制度ほど強力に影響するものではないけれど、文化に携わる者がそうした価値観を共有することに意味がある。だから本を読んでなおこんな記事をわざわざ書いている。この記事自体も、本を読んでいない人にそうしたアイデアを簡便に届けるためのショートカットだ。
ショートカット、つまり、橋である。
今世界に必要とされているのは、悪を討ち滅ぼすヒーローではなく、異なる世界を繋げていくブリッジズなのだ。私も、そして誰もが、その架け橋の1つとなりえるはずだ。

橋がないところでは、遠回りをするしかない。理性を使って何かを考えることはまさにそんな遠大な作業だ。
しかし、橋をかけることで、そうした作業を短縮できるばかりか、多くの人がその恩恵に預かり、誰も遠回りをしなくて済むようになる。直感で正しい選択に近づくことができる。
いきなり皆が理性的になることはなくても、「理性がより働かせやすいようなショートカットが張り巡らされた社会」なら、橋を1つずつ作っていくことで着実に目指すことができる。
だからこそ、
ゲーム制作の技術は、人の理性を守るために必要なものだ。
ゲームを作ることは、人を楽しませるという意味だけではなく、社会に役に立つという意味でも無駄ではないと思う。
ゲームクリエイターがここまで貪欲にゲームを作っていなければUnityのようなツールは生まれず、手軽にインタラクティブなUIを生み出して何億のデバイスで共通して動かせるような基盤は整っていなかっただろう。
ゲームデザイン、インターフェースデザイン、サウンドデザイン、あらゆるデザインのクリエイティブが今後より多く求められていく。それを誰もが扱えるようにするエンジンやライブラリやミドルウェアや、それらのチュートリアルや、それをさらに噛み砕いてわかりやすくするような動画配信者なども人類の理性を直感でショートカットさせる事に貢献している。

Photo by Balázs Kétyi on Unsplash
この本の著者も、最終章の手前でこのように期待を綴っている。

この世界が扱える理性の総量を増やすには、「一人ひとりがよく考える」などという鈍重な作戦ではなく、「人の理性を無駄に消費しないデザイン」のような環境に働きかける作戦が重要ではないだろうか。
まとめ
人間の思考は、直感と理性、システム1とシステム2の2種類があり、理性的な思考のためのワーキングメモリは、常に不足している。
人間の理性に限界があることを前提として、商業主義はユーザーが気づかないうちに過剰に消費するように世界を仕向けるし、民主主義は政治家を合理的な言説よりもただ同じことを繰り返す言説に仕向ける。
私達は共有地に生きているので、悲劇を免れるためには理性を持って協調しなくてはならない。
国家と制度は理性を自動的に働かせるための工夫に満ちあふれている。
制度的な工夫だけではなく、文化的な発展も人々が無駄に理性を消費しないような社会に役に立つはずだ。
より直感的に過ごしやすい社会のために、橋を作ること。
橋を作りやすくするような技術や知識を積み重ねること。
そして最終的に重要なのは結局、そうして生まれた理性の余裕を「本当に大事なこと」に各人が振り向けることだ。
それは自らの直感に反する思考を真剣に行うことでもある。
自分の常識は、他者の非常識であることを想像できるか?
自分一人ならズルをしても良いという感情を抑えて、共有地の悲劇を乗り越えられるか?
自らの直感に従って敵を裁けば、よりいっそう敵が増えるという事を理解できるか?
自分の信じていることが正しいというバイアスを抑えて、「どのような反証であれば受け入れるのか」を真剣に検討することができるか?
自らが下した決断が間違っていた時に、それを認めることができるか?そしてさらに、間違いを認めた相手を、許すことはできるか。
そのような事にこそ理性を振り向けるべきだということを、多くの人に伝えることはできるだろうか。
少なくとも私はそのための献身的な支持者の一人となろう。
↓その他のnote記事(この記事のアカウントは今回みたいな読書ログとか一般的な話向けで、普段はゲームとか音楽のデザイン的な話を書いてます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
