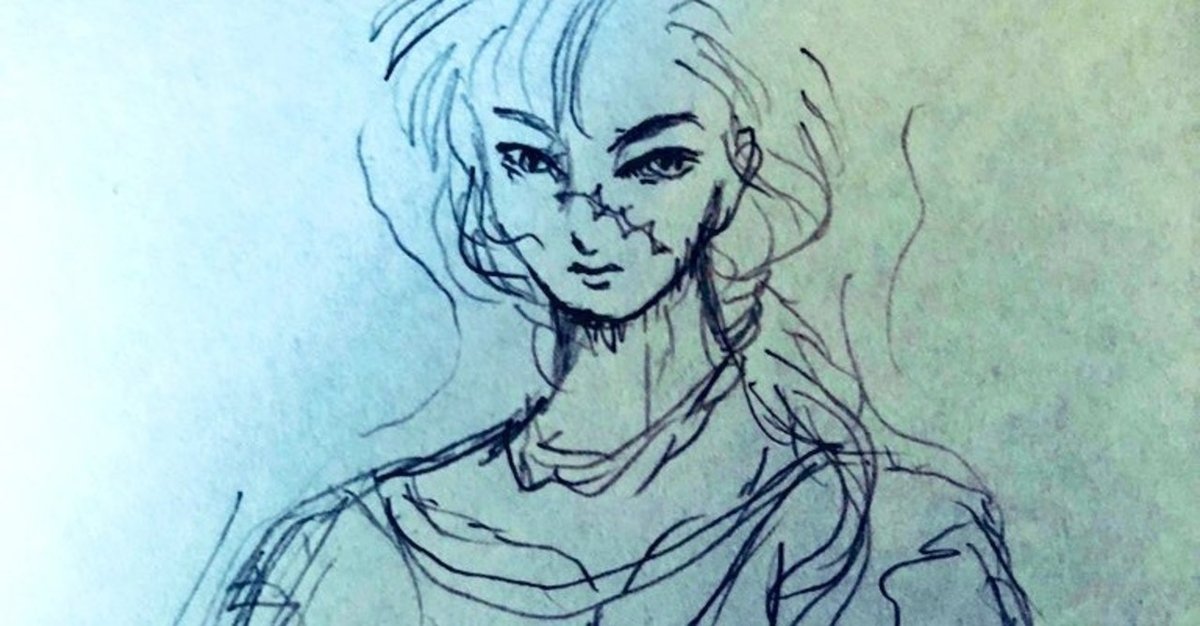
ルーイシュアンの宝石~8
15 満ちゆく月
ジーとリュウはボーボーラの家で、心づくしのもてなしを受けた。
素晴らしい勢いでごちそうを平らげているジーの横で、リュウは静かに酒を飲んでいた。
「美味しいわよ。少し食べてみたら?」
ジーは頬張りながら、リュウに言う。
「残念だが、俺は食べ物には興味はない。」
「酒には興味あるのにね。」
「これは薬だ。」
リュウはニヤリと笑う。
「やはり聖獣だの。」
ボーボーラは皴だらけの顔を震わせて笑った。
「そうなの?聖獣になるのちょっと考えちゃうわ。食べる楽しみがなくなっちゃうなんて…」
ジーは残念そうに言った。
リュウは本気で顔をしかめて残念がるジーの様子に、思わず飲みかけた酒を噴き出しかけた。
二人は寝床を用意してもらい、早々に眠りにつくことにした。
深夜、気配を感じたリュウは目を覚ました。
暗闇の中でも見ることができるリュウの瞳は、ジーの寝床が空であることを見て取った。
リュウは起き上がり、そっと鼻を動かした。そして外に出た。
真っ暗な夜空に、満月に程近い月が浮かび、辺りを柔らかな光で照らしていた。サラサラと遠く砂の流れる音の他は、何一つ聞こえないほど静かだった。
リュウは泉の畔で一人腰を下ろすジーの姿を見つけると、ゆっくりと近づいた。
「ごめん、起こさないように出てきたつもりだったんだけど…」
ジーは振り向きもせずに言った。
「どうした…眠れないのか?」
リュウは穏やかに言うと、隣に同じように腰を下ろした。
ジーは黙って泉の水面を見つめていた。
「怖いのよ…」
ジーはぽつりと言った。
「怖いものなんて何もないと思っていたこの私が、今とても恐怖を感じているの。」
「ジー…」
「私の一族全てを滅ぼしたモルバブジは、倒すべき仇でもある。でも、あいつの底知れぬ闇の力の前に、私の力がどの程度通用するのか、私には分からない。もちろん、全力でぶつかるわ。でも、あいつの闇の臭いを嗅ぐだけで、自分の無力さが私の心を苛む。闇に堕ちていくような恐怖を覚えるの…」
ジーは唇を噛みしめた。
「心の隙間を、邪は見逃さないぜ。」
リュウは呟いた。
「俺は昔、聖獣になりたての頃、虚栄心という心の隙間ができた。その隙間に狡賢く入り込んだ邪の影に、俺はいいように操られてしまったんだ。」
ジーは顔を上げ、リュウの横顔を見つめた。
「俺は、重心の時より遥かに性能が良い素晴らしい、聖獣になることにより得られた力に酔いしれた。天狗になってしまったんだ。
そんな時、聖獣が行くべき”本当の世界”に行かず、この世界に留まり、己の力をこの世界のために役立てようとしているという、聖獣チャントの噂を聞いた。チャントが持つ”セアナの雫”を飲むと、天と地の力を得られるという話もな。
俺はどうしてもその”セアナの雫”を飲みたくて、必死にチャントを探した。そしてようやくチャントを探し当てた俺は、すぐに”セアナの雫”を要求した。が、軽く流されてしまった。俺は頭に血が上り、俺の聖獣の力を見せつけてやろうと、チャントに襲い掛かった。こんな甘ちゃん、俺の一撃で仕留めてやると…
だが、チャントの聖なる境地の前に、俺の見せかけの力は砕け散った。いくら襲い掛かろうとしてもことごとく弾き飛ばされた。
チャントの手から発せられた光が俺の横顔を切り裂いた。そして、彼の剣が俺に振りかざされ、恐ろしいほどの光と衝撃が俺を貫いた。
俺は生まれて初めて感じる、本当の死の恐怖を味わった。そして、一瞬で自分の中の弱さ、驕りを悟った。その瞬間、俺の心を支配していた邪の影が消え去っていくのを感じた。
チャントは、俺の中に憑依する邪の影を見抜き、祓ってくれたんだ。俺が気づかないのに、チャントは分かっていた。
俺は泣いて詫びた。恥ずかしさのあまり、そのまま消えてしまいたかった。
チャントは俺を許してくれた。いや、許すというよりも、最初から俺の魂を信じていてくれてたんだ。
彼は俺の身体のあちこちにできた傷を癒してくれた。顔の裂傷も直そうとしてくれたが、俺は断った。俺は、この時の驕りを悟った気持ちを忘れぬよう、彼の浄化の光が作った顔の傷をわざと残してくれと頼んだ。
俺はそのあと暫くチャントと共に過ごした。その時”この世の闇を祓う聖なる風”のことを知った。良くわからないが、聖なる風を起こす古の遺品のようなものらしい。その風とチャントの力で、この星の穢れを祓い平和を守る力になるということらしい。」
「それが、シュアの風というものなのね。」
「そうだ。俺はチャントに報いたい、感謝の気持ちを表すために、なんとしてもシュアの風を手に入れたかった。
で、今はそれを探す旅を続けているところに、あんたたちと出会ったということだ。
俺に驕りという恥をかかせた邪の影、その司祭のモルバブジ、やつらにはお礼をたっぷりするつもりだ。
リュウはジーの瞳を見た。
「暗闇は光が当たっていないから暗いだけなんだ。恐れることはない。恐れにとらわれ、飲み込まれるこそ、邪の影の思うつぼだぜ。自分の弱さを受け入れられる、そのジーの素直な心があれば、必ず闇に光を当てられる。モルバブジはそれを一番恐れるだろう。」
「でも…」
「鍵がお前を選んだんだから大丈夫だ。それにイシュを護れるのはお前だけだ。イシュはお前を信頼し、お前とここまでやって来た。鍵とイシュにどういうつながりがあるのかは分からないが、イシュも鍵もお前を信頼し、頼りにしている。」
リュウは励ますように言った。
ジーは無言で泉を見つめていた。
「私もイシュが好きよ。」
ジーは何か思い出すように呟いた。
「あの子を見ていると、こう、不思議な感情が湧いてくるの。ただガムシャラに生きてきた私が、初めて感じる、母性というか保護欲というか、人に対する愛情というか…」
ジーは唇をかんだ。
「私を頼り切って、必死についてきた小さなイシュ。何度も怖い思いをさせて、挙句守ってあげられなかった。
私は今あの子がどんなに恐ろしい思いをしているのかと思うと、悔しいし、怖いし、自分が情けないし、私…」
ジーの瞳から、ポロリと涙が落ちる。
リュウは、そっとジーの肩に手をかけた。
ジーの瞳から、また一つ涙がこぼれる。
二人の間を、時が静かに流れていった。
「私、犬系は嫌な奴ばかりだと思っていたけど、考えを改めるわ。」
ジーは鼻をすすりながら言った。
「俺も猫系はいけ好かないやつが多いと思っていたけど、考え直すよ。」
リュウもボソッと言った。
ジーは、自然にリュウの厚い肩に頭を乗せた。
満ちて行く月の明かりが、静かに二人を包み込んでいった。
16 砂の中の少女
翌朝、ジーとリュウはボーボーラに別れを告げるとリョッカを後にした。
獣身に変化した二人は、リュウの聖獣の輝きの輪に守られながら、砂漠を駆け抜けた。
ボーボーラの話によると砂漠の遥か北東、その先西方に進むと、その辺りにスギライ・ロー神殿があるということだった。
二人は、神殿目指してひたすら走り続けた。
軽快に走っていたリュウが突然立ち止まった。ジーも慌てて急ブレーキをかける。
「どうしたのさ?」
ジーは訝し気にリュウの横顔に目を向ける。
「この先から人のような匂いがする…」
リュウは首を傾げながら答えた。
「人?」
ジーは目を丸くした。
「ああ。不思議だな。用心しながら行こう。」
リュウは、耳を動かしながら言った。
しばらく進むと、砂の中に黒い影が見えた。
二人は少し離れたところで立ち止まり、その黒い影の様子を伺った。
ジーは耳をそばだてた。
「何か、救いを求めているようだわ…」
ジーは驚いたようにひげを動かした。
「おい、待てよ。危ないぞ!」
リュウが止める間もなく、ジーは黒い影に向かい走り出していた。
黒い人影は、近づくにつれ、少女の姿と見ることができた。
ジーは、砂の中に半ば埋もれかかっていた幼い幼女を咥えだした。
淡い茶色の柔らかな髪が、蒼ざめた顔にかかっている。小さな口からは、小さな声で救いを乞う言葉を呟き続けていた。
ジーは、人間の姿をとると、その少女を抱え起こした。細い体を包む麻色の服は、ボロボロで、その身体の重さは軽く、頼り無げだった。
「ちょっと、しっかりしなさい。」
ジーは、少女の和やらかな頬を、軽く叩いた。
少女の長い睫毛が震え、ゆっくりと瞼を開き、灰色の瞳がジー見つめた。
「助けて…」
「あんた、どうしてこんなところに…」
「盗まれたものを探しに…」
少女はか細い声で答える。
「それがないと困るの。長の命を受けたの。だから見つけない限りは戻れないの…」
少女はシクシク泣き出した。
「地図を頼りに旅してきたの。地図を無くし迷ってたの。」
「いいから、泣くのは止めな。」
ジーは、少女の涙を自分の指で拭った。
その時、ようやくリュウが追いついた。
「おい、ジー!」
「何か良くわからないんだけどさ。この子一人でここまで旅をしてきたらしいのよ。」
「ええ?こんな子供が一人で砂漠をか?」
リュウは訝し気に金色の瞳で少女を見つめた。
少女は、ジーの腕のでその細い身を震わせた。
「この狼は怖くないから。」
ジーはなだめるように少女の髪をなでた。
「怪しいじゃないか。こんな子供がたった一人で砂漠を旅するなんてあり得ない。しかも、獣身の姿さえとっていないなんておかしいだろう。」
リュウは厳しい視線を少女に送る。
「お前、連れはいないのか?」
「前に死んだの。」
「お前の名前は?部族は?村の名前は?獣身は何だ?」
リュウは鋭く言葉を投げかける。
少女はまたシクシク泣き出した。
「ちょっと、相手は子供なんだから、手かげんしなさいよ。」
ジーは苦笑した。
「怪しいと思わないのか?」
「あんたがさっき言っていた、人のような匂いって、この子の匂いなんでしょ?」
「うーん。そうとも言えない。どこかいつも嗅ぐ人の匂いとどこか違う気がするんだ。」
「どう違うのよ?」
「うーん…」
リュウは苦笑した。
「でも確かに不思議といえば不思議ね。」
ジーは小首を傾げると、少女を見つめた。
「あんた、名前は?」
少女は不安げに瞬きをした。
「私はミアっていうの。」
「じゃあ、住んでいた村の名前は?」
「……」
「獣身は何?」
「獣身…」
ミアは押し黙る。
「この子もイシュと同じで記憶を失っているのかしら…」
ジーの呟きに、ミアは顔を上げた。
「イシュおにいちゃん…」
ジーは思わず聞き返した。
「あんた、イシュを知っているの?」
ミアは俯くとシクシク泣き出した。
「お兄ちゃんが…」
「お兄ちゃん?あんた、イシュの妹かなんかなの?」
ミアは否定するように首を横に振った。
「お兄ちゃんが盗んだの…」
「はぁ?イシュが盗み?」
ジーは目を丸くした。
「お兄ちゃんは宝石を盗んだの…」
「宝石って…」
「宝石は大事な鍵なの…」
「ちょっと、ミア。」
ジーは厳しい瞳で腕の中の小さな顔を見た。
「お兄ちゃんのせいで、私の仲間みんな困っているの…」
ミアは、灰色の瞳で、ジーのとび色の瞳を見返した。
「ジー、そいつは人間じゃない!離れろ。」
リュウが大声で怒鳴った。
ジーははっとしたようにミアを見た。
ミアの影はなかった。
「お姉ちゃん。返してちょうだい鍵。邪様のために…」
ミアはジーの腕の中でニヤリと笑った。
ジーはミアを放り出そうとしたが、ミアの細い腕がジーの手首をしっかりつかんでいた。不思議なことに、その小さな手を振りほどこうともがいても、振りほどくことはできなかった。
「ほうら、変化してごらん…」
ミアはぞっとするようなしわがれ声で行った。
ジーは必死で獣身の姿をとろうとしたが、変化することはできなかった。
「モルバブジ様から変化封印の魔術を教わったのさ。変化できるものならしてごらんな。
クックッック…人間の姿では虫けら同然だからねえ。」
ミアの表情は激しく変化し、今は全く別のものになっていた。
骨ばったざらざらのうろこ模様の顔半分に、嘲るように開いた口の中に、紫色の歯茎が見える。澄んだ灰色の瞳は、白濁した灰色に。
「お前は邪の欠片だね!」
ジーは鋭く睨みつける。
「鍵をよこせば、命だけはとらないでやってもいいんだよ…」
「死んでもお前なんかに渡すもんか。」
ジーは叫ぶと、ミアの邪悪な顔に唾を吐きかけた。
「じゃあ、死んでもらおうかねえ…」
ミアは、顔にかかった唾を拭きもせず、ニヤニヤしていた。
リュウは即座に光狼の発光を強めると、ミア目掛けて光を放った。ミアはジーを盾にすると、可笑しそうに笑い狂った。光はジーを避けて四方に散った。
「リュウ!私に構わずこいつを攻撃して!」
ジーは叫んだ。
「聖なる獣様に仲間を殺すことができるかねえ…」
ミアは黒ずんだ下細い舌を突き出し、嘲笑った。
「お前、何で人の匂いがしたんだ。」
リュウは厳しく問いかけた。
邪の欠片のミアは、ニヤニヤした。
「これの匂いだろうねぇ…」
ミアは何かの塊をリュウに投げつけた。
一枚の肌色の皮だった。
「内部からその心に憑依してやった人間の皮だえ。面白いように欲に振り回された最期は、そりゃあ面白い見ものだったねえ。
獣身に変わられると面倒だから、変わる前に内部で遊んでやった方が、なかなか面白いんだえ。こいつが私の影に振り回され、欲望に潰されて自死した記念に、その皮をいただいたのさえ。」
ミアは、紫色の歯茎を剥きだした。
「てめぇ…」
「あんたって…」
リュウとジーは同時に叫んだ。
ジーは目を怒らせ、必死で体をよじり、ミアに向かって蹴りを放った。
「危ないねえ…」
際どいタイミングでミアは避けると、ジーの手首をさらに強くつかんだ。
苦痛に顔を歪めるジー。
「さあ、鍵を寄越しな…」
「お前を許さない!」
ジーは叫んだ。
「さて、黒豹が大人しくなるまでに、目障りな聖獣様を片付けるかねえ。そのあと、お前を八つ裂きにして、ゆっくり鍵を頂くことにするよ。ついでにお前らの毛皮を剥いでモルバブジ様に献上したら、さぞかしお喜びになるだろうねえ。楽しみだねえ…」
ミアはそう言うと含み笑いをした。
ミアは口をすぼめ、甲高い口笛を吹いた。
ジーとリュウの足元に、突如激しい振動が起きる。
砂を巻き上げて、何か巨大なものが轟音と共に現れ出でた。
自分の力を試したいと 試行錯誤しています もし 少しでも良いなと思って頂けたのなら 本当に嬉しいです 励みになります🍀 サポートして頂いたご縁に感謝 幸運のお裾分けが届くように…
