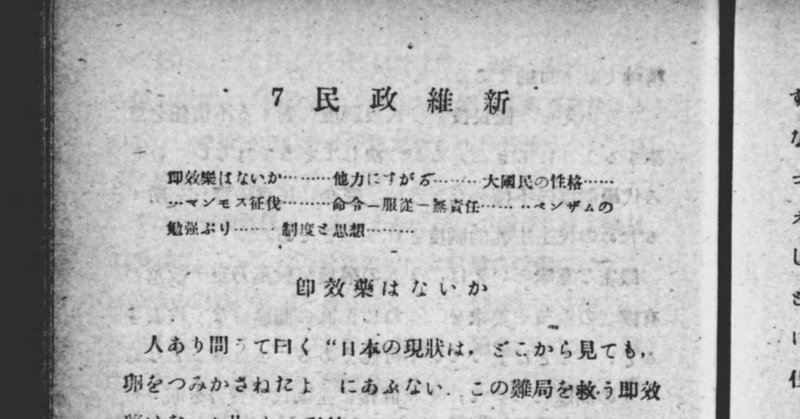
§7.7 制度と思想/ 尾崎行雄『民主政治読本』
制度と思想
民政維新にもっとも必要なものは批判的精神である.上からの命令や指令をうのみにして盲動するような国民では,とても民政維新を成就することはできない.行動する前に先ず批判せよ.それが誰からの命令・指令であろうとも,一度自分の良心のふるいにかけて,しかる後に行動する.そして,その行動に対しては,どこまでも責任をとる覚悟をもった人々によってのみ,民政維新の大事業はなしとげられるのである.
王政維新は形式的維新であった.頭の上のチョンマゲは切ったが,心の中のチョンマゲは切れなかった.立憲制度は輸入したが,これを運用する精神は輸入しなかった.近代文明の皮相は学んだが,これを生むにいたった根本の精神を学ばなかった.この制度と思想のくいちがいが,王政維新のはなばなしい進行をつまずかせて,僅か6~70年で行き詰ってしまったのである.
民政維新は,王政維新のごとき単なる外形の上のサルの人まねに止まらず,進んで精神革命にまで徹底しなければならぬ.民主憲法はできたが民主思想は消化しきれなかったではすぐに行き詰ってしまう.百年はおろか千年万年たっても制度と思想のくい違いから,国家の進運を行きづまらせることのないように,必死の努力をかたむけねばならぬ.
――――◆◇◆――――
鍬かせったか――大正年間の選挙の1風景(関東地方で実際にあったというはなし).選挙が始まると,村村に投票の仲買人ができる.これが有権者をつかまえて,“今度の選挙には誰それに入れてくれ”と頼む.有権者が“入れてやってもいいが,今度は鍬かせったか,きせるか”ときく.仲買が“そりゃあ鍬さ”といえばいいが“すまんがせったにしてくれ”となると,少々事が面倒になる.有権者が“せったならだめだ”とこだわる.仲買がこの候補者はせったでも決して間違いはないから,“せったにしてくれ”としつこくたのむ.すると有権者も“間違いがなければ,せったでもいいが,鍬なら3両,せったなら5両だが承知か”と念を押すのだそうだ.これだけでは何が何やらわからぬが,鍬は先に金がついておるから先金で投票の前に金を渡すことで,せったはあとに金がついておるから後金すなわち投票の後で金を渡すこと.きせるというのは,投票の前に半金渡して,これががん首,投票の後に半金渡して,これが吸口になって1本のきせるができるという陰語だそうだ.全くあきれてものがいえない.
次:§8.1 米英の婦選運動 →
底本
尾崎行雄『民主政治讀本』(日本評論社、1947年)(国立国会図書館デジタルコレクション:https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1438958, 2020年12月24日閲覧)
本文中には「おし」「つんぼ」「文盲」など、今日の人権意識に照らして不適切と思われる語句や表現がありますが、そのままの形で公開します。
2021年3月12日公開
誤植にお気づきの方は、ご連絡いただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
