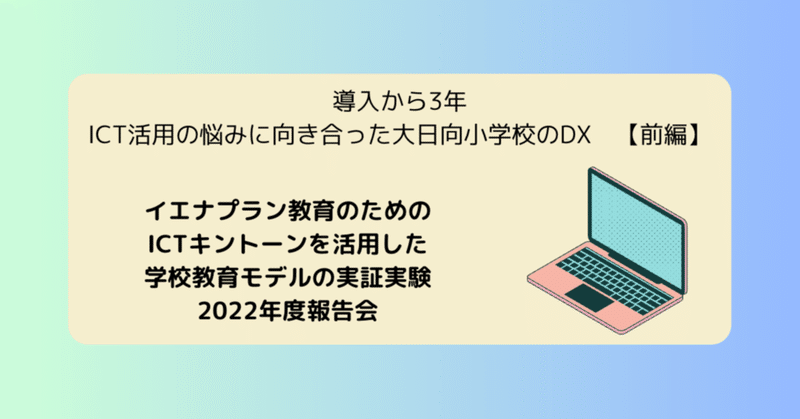
【開催リポート(前編)】導入から3年!ICTツール活用の悩みに向き合った大日向小学校のDX
2023年2月25日、大日向小学校とサイボウズの実証実験報告会「導入から3年!ICTツール活用の悩みに向き合った大日向小学校のDX」を開催しました。
今回の報告会は3回目で、前回の報告会リポートはこちらから見ることができます。

イベント概要
サイボウズは、大日向小学校・中学校の建学の精神である「誰もが豊かに、そして幸せに生きることのできる世界をつくる」ため、ICTツールを活用した学校教育モデルの実証実験を2020年4月に開始。
児童の学び方の多様性や教員の働き方改革に伴う課題解決に、ICTツールがどのように寄与できるか試行錯誤を重ねてきましたが、導入から3年が過ぎた今、新たに浮き彫りになった課題もありました。
それをどのように乗り越えてきたか、その軌跡についてもお話しいただきました。
全体の進行はサイボウズ株式会社 社長室長 中村龍太(なかむら・りゅうた)が務めました。

実証実験の背景 -サイボウズ中村龍太より
私たちサイボウズは「チームワークあふれる社会を創る」という目標を掲げ活動をしています。
その目標を達成するために、サイボウズの製品であるグループウェアを開発・販売しています。

社長室のミッションとしては、社会問題を解決するための実証実験プロジェクトをしています。
教育分野においても、「自立分散型の”ひと”を創る」ために活動をしており、その1つが今日の大日向小学校の活動になります。

大日向小学校の実証実験の目的を、2020年4月に覚書として定めております。今日の報告会は、覚書の第一条に則り、私たちの経験した内容を広く発信、普及することで、他の方に上手に活用してもらうことを目的としています。

ここ2年の活動おさらい
■ 2020年はキントーンの活用領域はどこか?それを探った1年
コロナ禍の中、「何に活用する?」と模索しながら進めていただきました。
まずはいろんな書類の整理に活用していました。
「下学年」をクリックすると、下学年で使ういろんな資料がスレッド形式で表示され、そこに情報をまとめるということをしていました。

また、児童・生徒情報として基本情報をまとめ、それに関係する情報を紐づけるという活用もしていました。
「児童・生徒情報」アプリという大元となる基本情報があり、その情報に紐づけて、生徒の観察記録や面談記録などを管理していました。

■ 2021年はキントーンのチームでの利用を試行
校外学習の申請をキントーンで実施していました。
管理職の承認をもらうというワークフローを回すということをキントーンで行っていました。(これが紙申請の時には、外出がちな管理職の印鑑をもらうのが大変だった、というお話もありました。)

導入から3年を振り返る ー大日向小・中学校 秋山さん・稲井さん・安井さんより
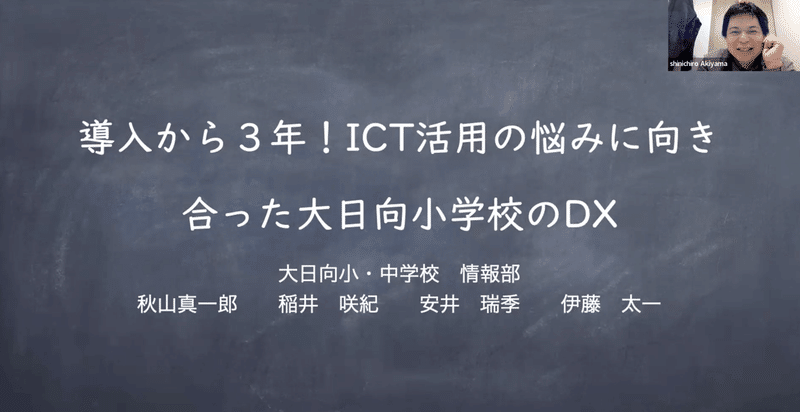

■大日向小・中学校の紹介
さきちゃんが紹介してくれました。
2019年に小学校が開校、2022年に中学校が開校しました。
中学校は今年度に開校なのでまだ20名と小規模です。


大日向小学校は、異学年で構成したグループで学びを進めています。
活動は「対話」「遊び」「仕事」「催し」という4つの活動から成ります。
「仕事」にあたるブロックアワーという時間では、1週間でやるべき課題があり、それを子供たち自身が計画して、主体的に進めます。上学年(4・5・6年生)になると、PCを使うようになり、PC上で自分のスケジュールを決めたり、振り返り(ポートフォリオ)を作って振り返れるようにしています。


下記の写真がスタッフルーム、いわゆる職員室で、フリーアドレス制です。
また職員間の連絡にICTを活用しているので紙がありません。
(実はこれは少し古い写真で、今はキャビネがない、机も変えたとのことです。いずれにしても、いわゆる普通の学校の職員室とはだいぶイメージが違いますね。)

■大日向におけるICT活用
引き続きさきちゃんが紹介してくれました。
大日向では、キントーン以外にもICTツールを活用しています。どんなツールをどんな用途で利用しているのかを紹介していただきました。
まずはMeta社のWorkplaceとWorkplaceチャット。
Workplaceは学校行事や連絡についてシェアしていて、掲示板のような使い方をしています。
Workplaceチャットは、個人やグループで連絡を取り合う時に使います。

Googleのアプリも活用しています。
ドキュメントは、職員会議の議事録などに利用します。
スプレッドシートは、学校で管理しないといけない出席簿を作っていたり、アンケートのまとめに使います。
インストラクションは、発表資料や子どもへの短い授業(インストラクション)で使います。
Jamboardは、付箋のようなものを貼って皆の意見を見える化したり、整理したり、また席替えに使ったりします。
これらは大人も子ども使うアプリです。
みっきーさんが、こんなことを付け加えてくれました。
「スプレッドシートは、職員の打合せ用に、議題を整理するアプリとしても活用しています。これがなかったときは、論点が整理されぬまま2時間くらい話していた、ということがありましたね。
また、GoogleはWindowsやMacなどOSの違いを吸収してくれるので、共有や共同編集ができて便利です。子どもとの共同活動にも使います。」

Zoomは休校中のオンライン授業や保護者との対話の会で使います。
Slackは、保護者の方に学校の様子を共有する際に使います。˚˚˚

情報の即時性、情報の性質(流れる情報flow・蓄積する情報stock)で分けて整理した図です。

キントーンの特徴とその用途についてはこんな風に整理しました。
・アカウントを持っている人とのみ共有できる安心感・セキュリティの高さ
・情報を溜められる、そして分類できる、検索しやすい

・外に漏れてはいけない、児童の情報・面談記録を溜めている
・情報の紐付けができるので、子どもを中心として様々な活動や成長をわかりやすく整理できる

■「大日向に赴任して、ツールの多さにパニクりました」
1年前に大日向にジョインしたみっきーさん。
「初めて使うツールがあったのと、情報の種類によっていろんなツールを使い分けているので、最初は「どのツールを使えばいいんだ?」と混乱しました。
今は慣れましたが、今後新しく入ってくる人のためにも、情報とツールが整理されるといいなと思っていたので、このように整理できてスッキリしました。」
■大人のICTの悩み
ここからは大人がICTに向き合う中で、考えてきたことについて、あっきーさんがお話ししてくれました。

「スキル」ということを考える際に、どこまで分かっているのか、どんなことができるのか、を適切に理解することが大切だなと感じています。

今はICTに関するスキルを考えたときに、いろんな「できる」いろんな「できない」があると考えています。
スライドを作れるけど、音楽の操作ができなかったり。
また、スライドを作る、ということに関しても、キーボードで打ち込むこともあれば、ペンで電子的に書くこともあったり。
とても多様になったと思います。

「知っている」という状態についても多様性があると感じています。
例えば、コンピュータに関する幾つかの用語、知っているでしょうか?読めるでしょうか?

それぞれ多様である、というところから始める。
その前提で、その人に合った使い方をしてもらえるようにコーディネートする「情報部」が作られました。

後半は、”その人に合った使い方をしてもらえるように支援する情報部”として、
これまでのICT活用の歴史と、情報部としての展望をご紹介していただきます。

次の記事もお楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
