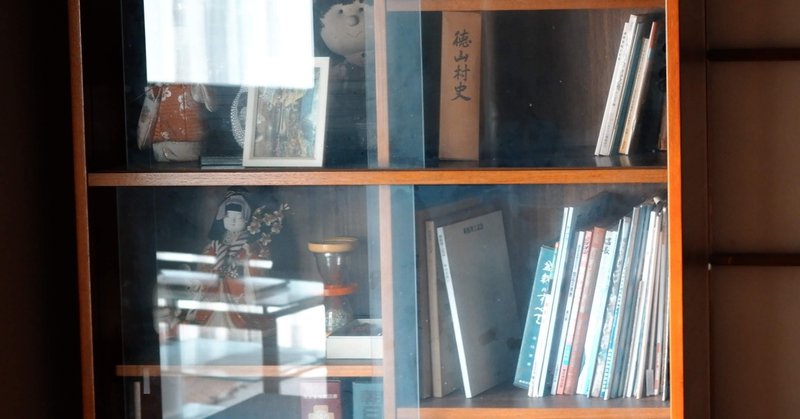
5月に読み終えた本
5月も外出自粛で、やることはあまり変わらない。その中でも読書と運動は妙に捗っていて、自粛体制が終わってしまったら揺り戻しが起きそうな気がしている。
そして本の量も揺り戻しがきていて、10万円がぶら下げられているからか、はたまた「経済を回す」という大義名分からか、ひさびさにそこそこの本を買った気がする(つまり定かではない)。それも物理的にでかいやつ。あの苦しみを忘れてしまったのか。三つ子の魂百までというやつかもしれない。いや、馬鹿は死ななきゃ治らない、か。
東浩紀『新対話篇』(ゲンロン)
対談集かと思って読んでみると、新規に対談されたもの以外はほぼ読んでいた。別にそれが残念という話ではなくて、意外とちゃんと読んでるんだなと自分で驚いたという話である。
あらためて読んでみると、東浩紀がゲンロンを作って、そこでカフェやイベントをリアルスペースで行ってきたことの意味が彼自身にすごい影響を与えているのだなということが印象に残った。その先行事例(?)として鈴木忠志の対談と利賀村のプロジェクトの話が出てくるけど、物理的な空間や身体を通じて「やっていく」(ネットスラングっぽい言い回しだけど、そういうのがしっくりくる)ことの重要性は増していくばかりだと思う。外出自粛体制によってそんなわけにもいかなくなっている現状だけれども。
國分功一郎との対談で出てくるリアルの「効率の悪さ」の話にしても、リモート隆盛の現在の状況下では顧みられることも難しいけれども(そして自分もその楽ちんさを享受しているが)、そのリアルの「めんどくささ」が生み出すおもしろさにも希望を持っていたいなと思う。パンデミックはよ終われ。
東浩紀『哲学の誤配』(ゲンロン)
続いても東浩紀の本。この2冊はゲンロンの10周年を記念して同時出版された。
韓国向けのインタビューと講演で構成されていて、読みやすい。テン年代の前半と後半に行われたものなので、この10年間に東とゲンロンのやってきたことの話がわかりやすく語られていると思う。『新対話篇』を先に読んでたのも一因だと思う。
最後のインタビュアー・訳者(別の韓国人批評家による解説もあるのでその訳)である安天氏のあとがきというか解説というか、この文章がなかなかよい。韓国の現代史と思想史がコンパクトにまとまっていて、韓国が日本とは全く違った形で民主化していったことは恥ずかしながらまったく知らなかった。それと、氏の東との出会いが妙に爽やかで、それも素敵だなと思った。まえがきにあるとおり、まさに誤配という感じ。
クリスチャン・メルラン『オーケストラ――知りたかったことのすべて』(みすず書房)
オーケストラについて、縦横無尽に語った本。
かなり厚い本で、600ページぐらいある。それなりのお値段なので買うか迷っていたのだが、外出自粛だし、書評を読む限りおもしろそうなので買ってちまちまと読んだ。ちなみに外出自粛だから読めるというのは時間の問題というよりも、重さの問題である。
縦横無尽といったが、欧米を中心に古今東西のオーケストラについて、本当にあらゆることに触れている。第一部ではオーケストラがどんな集団なのか、どうやって入団するのか、序列は、楽器による出身階層は、リタイア後は…、といったことが実際の団員の話を交えながら書かれる。第二部では各パート(楽器)の紹介と役割、活躍するのはどんな曲で、有名な(オーケストラでの)奏者はどんな人がいるのかが事細かに書かれる。第三部は指揮者とオーケストラの関係についてで、ここもこれでもかというぐらいにいろんな例が出てくる。
要するにオーケストラオタクが持ちうる限りの知識を総動員して書いた本で、そりゃ厚くなるわという感じなのである。しかしこれがとても読みやすいし、おもしろい。一口にオーケストラといっても、国ごとでも楽団ごとでもまったく違っていて、それを知れるのも楽しい。若干偏りはあるとは思うけれども、しかし、さすが本場(著者はフランス人)のオタクやな、という感慨もあったりする。第二部なんて個人名がバンバン出てくるのだが全然わからず、しかしすごいいい奏者なのだろうなというのが伝わってきて良い。第三部を読むと指揮者は知っているなあと思うので、裏を返せば、ちょっと管弦楽を、と思っても、指揮者+楽団が何を演奏するか、ということまでしかなかなか興味がいかないということでもあるのだろう。
チェロもやって(最近レッスンが休講でまったくできてないが)、引っ越しもして、演奏会に行ってみようと思っていた矢先でこのご時世なので、この本を読んで、明けたら絶対行くぞという気持ちになった。クラシックやオーケストラに興味があればぜひおすすめしたい本だった。
中沢新一『人類最古の哲学 カイエ・ソバージュ(1) 』(講談社選書メチエ)
『新対話篇』に、中沢新一との対談が掲載されている(これ自体は『ゲンロン』本誌でも読んだ)。中沢新一の本なり対談を読むといつも、「カイエ・ソバージュ、読まなきゃ…」という気持ちなっていた。名著と誉高い講義録、とはいえ5巻本だし、紙だと新品はなさそうだと思っていたところ、タイミングよくKindleのセールで50%ポイント還元をしているのを発見しついに買ってしまった。ちなみに買ったのは分冊版で、合本版もある(ちょっと安い)。
この巻は神話学とは何かということを主にシンデレラの神話を題材にして説明している。ベースになっているのはレヴィ=ストロースの『神話論理』かなと思うが、講義録というのもあるし、シンデレラというよく知ったお話を扱ってるのもあってとてもわかりやすい(『神話論理』はめっちゃ厚いのが5巻(邦訳版)でたぶん超むずい)。
この本(シリーズ通してかもしれない)がもっとも強調しているのは、神話は徹頭徹尾「具体性の世界」に結び付けられていて、極めて論理的な構造を持っている、ということだ(だからこそレヴィ=ストロースは「構造主義」の人とされる)。一方、例えば宗教にその様式だけが取り込まれた場合、具体性を失ってしまうことがある。神話も宗教(の話)もある意味では荒唐無稽な話で、ときにファンタジー的な感想を持ってしまうことがあるわけだが、神話はその構造や論理が一番重要な点で、そのことを示すために様々なシンデレラのバージョンが語られるわけである。シンデレラの灰かぶりという名称や片足だけ脱げる靴といった話にどういう意味や構造があるのかが、様々なバージョン(中国にも異文があり、それを南方熊楠が指摘したという話もすごい)をとおして説明されていくのはとてもおもしろい。刊行からだいぶ経ったが、それでも読みはじめて良かったなと思う。このまま続きも読んでいきたいところだ。
『世界哲学史5――中世III バロックの哲学』(ちくま新書)
ついに折り返し。
ようやくという感じで、知った名前が出てくる。デカルト、ホッブス、ライプニッツ、スピノザ、荻生徂徠、伊藤仁斎、山崎闇斎…。前回も書いたが、江戸の文化史出てくる儒学者の名前が懐かしくて、しかも今回はそれぞれがどんな人か、どんな思想だったかもうっすら覚えていて良かった。まあこれは最後の章だけだが。
おもしろかったのは朝鮮の思想についての章で、たしかに朝鮮の思想ってほとんど聞いたことがなかった。ただ、ちょうど↑に書いたように『哲学の誤配』でも韓国の現代思想の話が出てきていたので偶然だなと思った。その特徴として「人間の本質的善性に対する強い信仰があり、その道徳的能力への痛ましいほどの帰依がある」(P224)と書かれているが、その信仰心の強さが、『誤配』でも書かれている韓国の民主化につながっていったのだろうと思うと、単純にすごいなと思う(理解がちゃんと合ってるかは自信がない)。
中沢新一『熊から王へ カイエ・ソバージュ(2) 』(講談社選書メチエ)
2巻。この巻では「対称性」という考えが大きくクローズアップされる。このシリーズの最終巻は『対称性人類学』というタイトルなので、メインテーマがやっと登場といったところだろうか。
神話や、神話が語られた社会では人間と動物、人間と人間の関係は「対称的」なものとして語られる。たとえば狩猟においては、捕らえた獲物を丁重に扱い、解体も手順が決められており、食べたあとも骨は綺麗に飾って自然に返す、というような儀礼でもって応える。そのように獲物を必要以上に獲りすぎず、敬意を持って接するのは、外部から(現代から)見れば次のシーズンにも獲れるようにするための配慮でしかないのだが、それを神話として伝えていくことで、「文化」を維持していく知恵となるわけである。
そのような対照的な関係が、人間が文明を得て自然の力を必要以上に得ようとし、国家を持つようになると、非対称な関係になってしまう。この「文明」と「野蛮」という視線が、現代的な問題(ちょうどこの講義の頃に狂牛病問題や9.11が起きている)にまでつながっているというのがこの本の大きな流れで、かなり射程の長い話になっている。
ほんとにいろいろな話が出てくるので、こまけぇこたぁいいんだよ!!(よくない)という感じになっちゃうこともあるのだが、対称性の思考から国家の発生、あるいはその知恵を内包した仏教のあり方まで、神話に則して縦横無尽語られるのがやっぱりおもしろい。このシリーズは場所と場所、時代と時代、神話と神話、思想と思想がどんどん連結してくおもしろさがあって、それは多分講義録で、即興性も備えているからなのだと思う。いまこの講義を実際に聞いてみたいものである。
