
お江戸食肉事情
食欲の秋!
いまだに真夏日が続くなかではありますが、暦の上での季節を優先させていただきます。
江戸末期の黒船来航を機に鎖国をとりやめた日本は、そこからアメリカをはじめとした諸国との外交を開始し、様々な西洋文化を輸入、そこには肉食も含まれており、明治初期には牛鍋が大ブームを巻き起こして食生活が一変した。
というのが教科書的な説明で、一般的にも広く浸透している考え方だと思われます。
仏教伝来以来、肉を食べる習慣を日本人は放棄していたが、外国からの影響で千年ぶりに口にするようになったというものですね。
けれども、ここに歌川広重「名所江戸百景 びくにはし雪中」(1858)という浮世絵があります。

雲に圧される夜空の下でしんしんと雪の降りゆく様を描いた、冬の静謐と陰影を活写する傑作ですが、ここで注目したいのは画面左端に大きく描かれる「山くじら」の看板です。
山で獲れる鯨、かつての俗語で獣肉を表しました。
つまり獣の肉を出す店が江戸の町では普通に大きくアピールして営業していたということを示しています。
さらに、1830年代から30年にわたって書き続けられた喜田川守貞による随筆『守貞謾稿』後集巻一には「三都ともに獣肉売店には異名して山鯨と記すこと専らなり。又猪を牡丹鹿を紅葉と異名す。虎肉あらば竹と云わんか」とあり、江戸だけでなく京都大阪でもほぼ同様に獣肉が食されていたことや、猪の肉を「牡丹」、鹿肉を「紅葉」と呼んでいたこともわかります。
この牡丹と紅葉につきましては、安永7(1778)年刊『一事千金』にも「秋はもみじにぼたんの吸物」という記述があり、かなり古くから呼びならわされ、それだけ肉食の馴染みが深かったと思われます。
こうした猪肉や鹿肉など山くじらを出す店は「ももんじや」や「ももんじい」と呼ばれていました。文化8(1811)年刊行の式亭三馬『浮世風呂』三編 巻之上では、
例所へ行て、ももんじいで四文二合半ときめべい
という一節があり、「ももんじい」という言葉には「猪鹿の料理屋」という注が原書から振られています。「四文二合半」は居酒屋でちょっと一杯ひっかける際の決まり文句だったそうです。
「例のももんじやで肉をつまみに一杯やろう」というお誘いですね。
気軽な調子からも肉食をそこまで特別視していないことがうかがえます。
この『浮世風呂』から約半世紀後の1860年、江戸時代の末期も末期に鎖国の解かれた日本を訪れたイギリスの植物学者ロバート・フォーチュンは、著書『幕末日本探訪記』で、ももんじやを西洋人の目から見た記録を残しています。
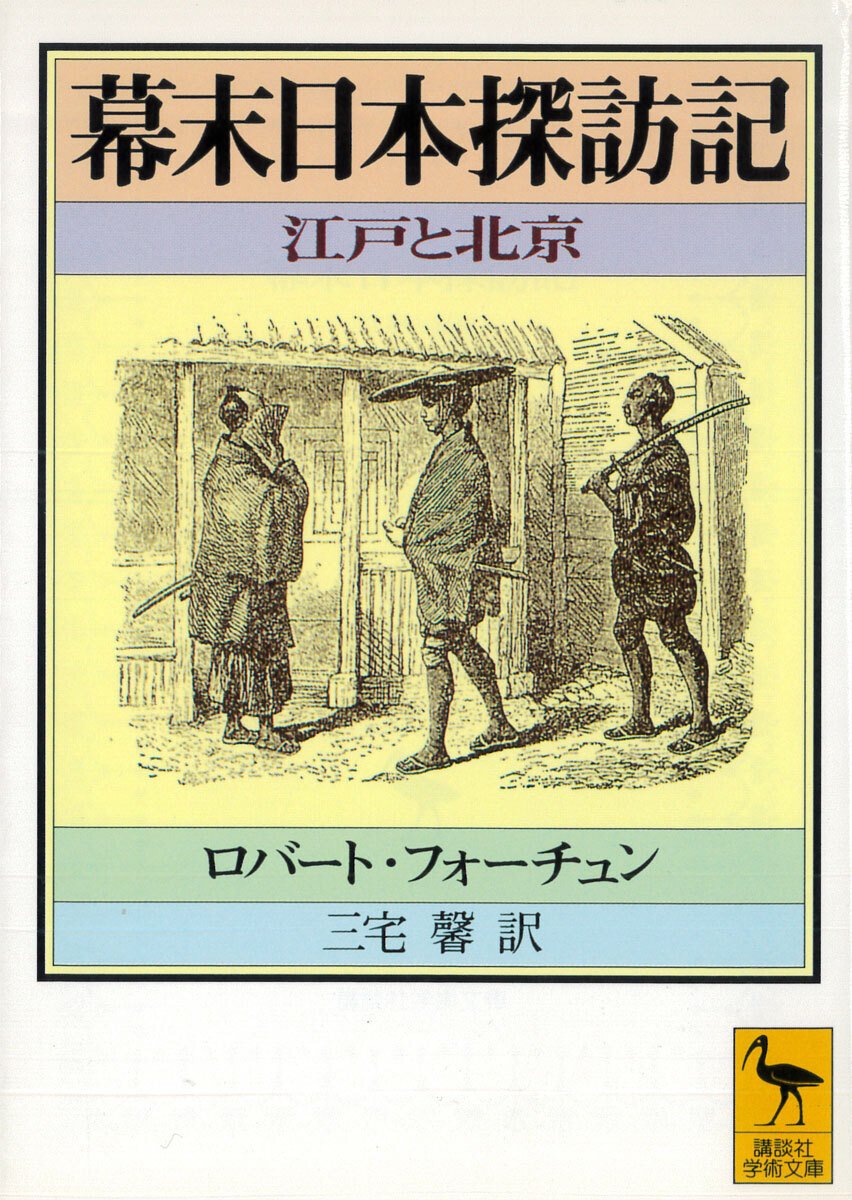
通りすがりに肉屋も目にとまった。これは日本人が野菜や魚だけを常食にしていないことを表している。しかし実際には日本人は、われわれがするように、牡牛を殺したり食べたりしないから、それらの店では牛肉は目に入らなかった。それに日本では羊を見かけなかったから、もちろん羊肉も見ることはできなかった。だが、鹿の肉はどこにもあった。
やはり鹿肉が言及されています。鹿肉のなじみは日本人にとってかなり古く、例えば国立歴史民俗博物館に収蔵されている江戸初期17世紀に制作されたとされる「江戸図屏風」でも鹿狩りとそこで捕らえられた鹿が解体される様子が描かれています。

フォーチュンの記述に戻りますと、鹿肉だけでなくさらに別の商品についても言及しています。
ある店では猿が目についた。猿が肉屋の店先に吊り下げられているのを見たときに、刻みつけられた印象を忘れることはできない。猿は皮を剥ぎ取られていたが、人間の種族に類似しているだけに、非常に気持がわるかった。おそらく日本人は、猿の肉をうまいと思っているのだろう。もっとも、その気持がわるいという感情と、食欲とは関係がない。実は私も以前ひどく空腹の時に、この人間に似た猿を食ったことを白状しなければならない。
猿の肉が、それもほとんど全身剥き身で軒先につるして売られていたという、現在の私たちからしてもかなりショッキングな光景です。
しかし、どうもももんじやで売られていたのは猿にとどまらなかった可能性が高いです。
明治になってから書かれたものですが、慶応3(1867)年生まれの明治と同い年の数多い著名人(夏目漱石、正岡子規、幸田露伴、南方熊楠、宮武外骨、尾崎紅葉などなど)の一人、文筆家斎藤緑雨は随筆「おぼえ帳」で、
〇赤犬黒猫ということあり、犬は赤きが、猫は黒きが、味わいの美なればなりと。
と、犬や猫が食用にされていたことを記しています。
畜産が盛んではなかった日本において牛や羊が食べられることはなかったのは事実ですが、そのかわりに鹿や猪、犬や猫まで食用に、さほど特殊なこととも思われずに、されていたらしいことがわかってきます。
これは現在の私たちの江戸以前の食のイメージとは大きくかけ離れてきます。このあたりのギャップについては、おそらく柳田国男が次のように指摘していることが実情に近いのでしょう。
われわれは決してある歴史家の想像したように、宍を忘れてしまった人民ではなかった。牛だけははなはだ意外であったかもしらぬが、山の獣は引き続いて冬ごとに食っていたのである。家猪も土地によっては食用に飼っていた。都市にはこの香気を穢れと感ずる風が、しだいに普及していったのも事実であるが、一方にはいわゆる薬喰の趣味は、追い追いに新たな信徒を加えていたので、ただ多数の者は一生の間、これを食わずとも生きられる方法を知っていたというに過ぎぬ。だから初めて新時代に教えられたのは、多く食うべしという一事であったとも言える。
文中の「宍」とは「肉」のことです。
ざっくり要約しますと、江戸以前と明治以降での肉食についての差はその食べる量だ、と実にみもふたもありません。
ただし柳田は「食わずとも生きられる方法を知っていた」と書いていますが、当時の庶民の摂取カロリーが都心部においても1日1500カロリー未満と推定されるという話もありますので(立川昭二『江戸病草紙』によります)、平均2500カロリー前後を1日で摂取する現代の私たちが食を選択するのと同様に考えるのは危険ではあります。
仏教の影響により殺生や肉食は忌避されていたものの、それはそれとして慢性の栄養不足は如何とも仕様がなく、そこで「薬喰」、滋養強壮のための薬事という建前で肉食が行われてもいました。
この例としましては、明治中頃の記憶ではありますが内田百閒がそのものずばり「薬喰」というタイトルのエッセイに残しています。
岡山の造り酒屋だった百閒の生家では、酒蔵が穢れるという理由から食卓に四つ足の獣がのぼることがありませんでした。けれども百閒は幼い頃体が弱くそれを補うために、親戚の家で大変な警戒のもと牛肉を食べさせてもらうことになった、その経験を描いたものです。
短い文章ながら、当時の肉食の穢れのイメージと、それが必ずしも共同体全体で守られなければならないものではなかった(周囲の友達は普通に肉を食べていたと書いています)ことがよくわかる一編です。
江戸期の薬喰については俳人の与謝蕪村(1716-1784)の句があります。
しづしづと五徳すえけり薬喰
くすり喰人に語るな鹿ケ谷
客僧の狸寝入りやくすり喰
妻や子の寝顔も見えつ薬喰
薬喰隣の亭主箸持参
「しづしづと」や「人に語るな」あたりからは人目を忍ぶタブー的な雰囲気もありますが、けれども「人に語るな鹿ケ谷」と鹿ケ谷の地名と鹿肉を掛けていたり、また同室となった僧があえて見て見ぬふりをしてくれている狸寝入りも食材としての狸を想像させたりと、むしろ公然の秘密をからかうようなユーモアが先に立って感じられます。
そう読みますと、静々と料理の支度をしているのも、いそいそと気の逸る様子を抑えているようでもありますし、妻子の寝顔を想像するのも、衰えた体を養うために敢えてタブーを犯して申し訳ないと思う気持ちとともに、申し訳ないけど大変にうまいとまったく別の表情を浮かべている様子も想像されます。
「隣の亭主箸持参」は一見穢れを慮っているようでもありますが、考えてみましたら、それだと自宅の箸を持ってこずにその家の箸を借りるべきでしょうから、どちらかといいますと肉を食べようと準備していたら隣人が「いやあ、いい匂いさせてるじゃないですか。すいませんねえ、本当に、どうもどうも」などと相好を崩しながら箸を持って御馳走におよばれしようとやって来る図々しい姿の方がしっくりとくるように感じます。
という具合で、少ない例ではありますが明治以前の日本人の肉食を見てきましたが、全般として殺生の禁止という道徳的な習慣を念頭におきつつも、生きるため差し迫った必要性もあり、同時にしたたかにそれをしっかり楽しんでもいたという雰囲気が伝わってきます。
秋とはいえまだまだ暑い日々が続きますから、このしたたかさの伝統を教訓に、私たちも食べるものを食べてこの時期を乗り切りたいものですね。
いいなと思ったら応援しよう!

