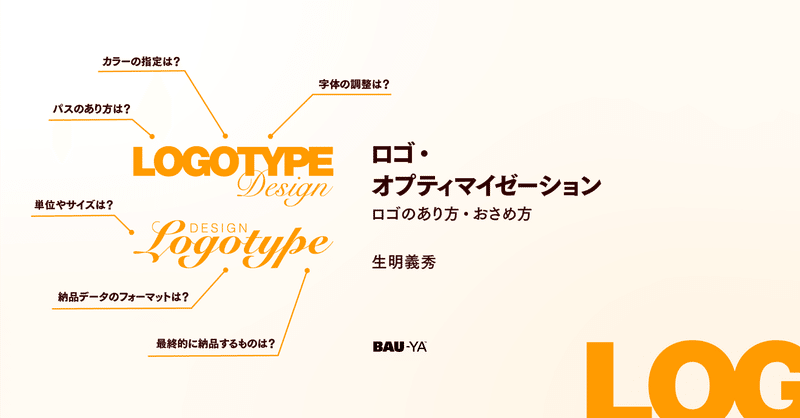
『ロゴ・オプティマイゼーション — ロゴのあり方・おさめ方』フォローアップ
先日登壇した『ロゴ・オプティマイゼーション — ロゴのあり方・おさめ方』の参加者の方々へ配信した、フォローアップです。
『ロゴ・オプティマイゼーション — ロゴのあり方・おさめ方』へご参加くださり、誠にありがとうございました。
また、昨年末は12月28日に催されましたDTP Transit主催の「朝までイラレ」へもご参加くださった皆様には、重ねてお礼を申し上げます。
振り返れば、私はグラフィックデザインおよびウェブデザインの両界に、Bau-ya®の前身は「生明塾」(私の私的ブランドでした)の頃から、さまざまな提案や問題提起を示してきました。
私自身も日々のクライアントワークの中から、常に最適な方法論を模索し続けてきました。
劇的な進化と変貌をし続けているデジタル文化やIT技術の中にあって、我々のデジタルクリエーションの「あり方」も、それに伴って多かれ少なかれ変化してきたはずです。
DTP黎明期の時代では、原始的で必要最小限の機能しか有していなかったPhotoshopやIllustrator。
やれInternet Explorerだ、やれNetscape Navigaterだと盛り上がりながらも、ノンCSSで張りぼてだらけなウェブデザインの暗黒時代。
それから四半世紀以上も経っていれば、現代のデザインの創造性や制作技法は当時とは大きく違っていて然るべきです。
しかし私は、EPSファイルでの入稿、テキストオブジェクトを重ねた袋文字、テーブルレイアウト、ボタンや見出しのすべてが画像のページなどを、目撃したことがあるのです… 今からわずか数年前に。
世間知らずや時代遅れであっても、それがプライベートやライフスタイルについての事柄であれば、他人からとやかく言われる筋合いはないでしょう。
しかし、プロの仕事人と、その仕事や納品物についてならば話は別です。
そのようなクリエーターに関係する業者の人たちに及ぶ悪影響や負担は、決して軽いものではありません。
それが個人規模ではなく会社などの団体が、丸ごとそのような集団的セオリーで成り立っていたら目もあてられません。
さらに最悪なことは、そのようなクリエーターが講師職に就くことです。
そうすると、若いのに現代的常識を知らないというクリエーターが、業界に向けて大量に輩出されることになるのです。
クライアントは何も知らないからこそ、自分がオファーするクリエーターが現代的で適正な仕事と納品をしてくれるものと信じて、それにお金を払います。
対して制作者は、果たして「ベストを尽くしているのか」という根源的問題を孕んだ講座でした。
この講座で提示した方法論は、私がさまざまな制作物を観て、それらを参考にし、日々研究をしてきたものです。
もちろん、クリエーター各々によってさまざまな考え方もあるでしょう。
ついては、先の「朝までイラレ」での私のセッションでも、当初はあくまでも問題提起のみにとどめ、私の模範解答のようなものは一切提示するつもりはありませんでした。
しかし、DTP Transitの主宰者である鷹野氏から「せっかくだから、生明の考えや方法を示した方がいい」という助言をもらい、簡単なものでしたがリストなどにして添えました。
ならば、その提示した解答の理由や根拠、考え方や実例などを紹介する機会があってもいいのではないかと思い、Bau-ya®ブランドで用意したのが当講座です。
制作に着いてまわる諸々の方法や問題は、本来であればプロフェッショナルである皆様が、自らで気づき、自らで考えるべきことであります。
それは、これまでのやり方や常識を疑うことであり、今とこれからの最善策を考えることであります。
皆様のそのような助けになることを願って、2023年の今年、Bau-ya®は再始動する次第です。
今後も皆様が、Bau-ya®で問題意識とヒントを得て、ご自身のお仕事で役立てていただけたら幸甚の至りです。
Bau-ya® 主宰 生明義秀
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
