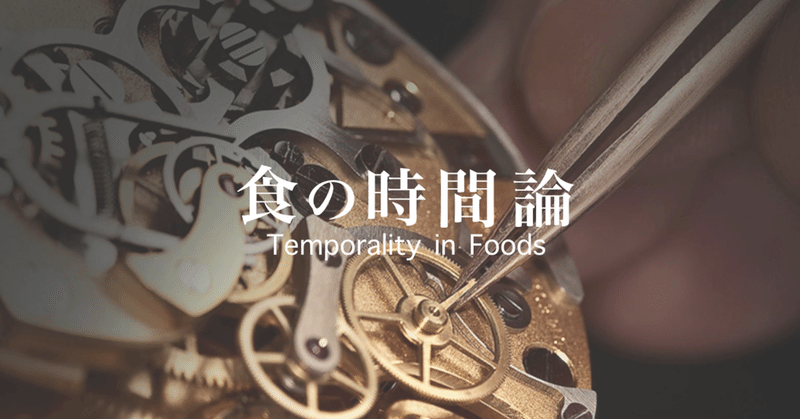
食鑑賞の時間論①時間の類型(加藤周一『日本文化における時間と空間』)
「料理は科学」「日本酒は科学」がもう当たり前になる時代だからこそ,料理や日本酒を味わう上での「人文科学」が求められるのです.
口に入れてから飲み込むまでの可測的な時間ではなく,現象の時間・心の時間にアプローチしましょう.フレンチのコース料理と,日本の本膳料理,インド料理には異なる時間が流れている.このことが理解できるだけで,料理人であれば自分の料理がどういう体験をもたらし,食べる人であれば眼の前の食事にどう向き合えばよいかがわかるはずです.
加藤周一『日本文化における時間と空間』
「食鑑賞の時間論」,今回は,
加藤周一『日本文化における時間と空間』
第一部 時間 第一章 時間の類型 のまとめ.
日本文化における時間を説く導入としての,世界の文化における「時間の類型」をまとめた章として秀逸なのでまとめておきたい.
本書のどのあたりがありがたいかというと,過度に東洋のアイデンティティを主張し,西洋の行き詰まりを批判するスタイルに偏ることなく,割とフラットに論じてくれているところ.
例えば名著,九鬼周造の『時間論』では東洋の意識の特徴が反復的なものであることが指摘されるが,そこでは本書で指摘されるようなギリシャ,ヘレニズムの循環的な時間論については言及されていない.
九鬼が「反復する時間」を東洋に固有の概念として論じるために意図的に古代ギリシャの話をしなかったのか,単にその考えが九鬼に無かったのか(あるいは本書の加藤の説が間違っているか)は定かではないが,テンポよくユダヤ,ヘレニズム,古代中国,仏教,古事記,日本文化の時間観をまとめてくれる第一部第一章は,それだけでもこの本をよむ価値につながると思う.
ユダヤ教的時間
『出エジプト記』に代表される時間観であり,「始めと終りがある時間」「両端の閉じた有限の直線(線分)として表現されるような歴史的時間の表象」とする.
ユダヤ・キリスト教的世界の時間類型の特徴
1.絶えず目標に向って前進する直線的な有限の時間の概念
2.人間が作る歴史という概念,または歴史的人間中心主義
ここでは時間は直線上を初めから終りに強い方向性をもって向かい,流れる.逆戻りはなく,すべての出来事は一回限りである.
この時間観は次に挙げるヘレニズム(古代ギリシャ)の時間とは対照的である.
古代ギリシャの時間
ユダヤが「始めと終りがある」時間を指向したのに対して,古代ギリシャの時間観は「始めも終りもない無限の時間の表現」である.
無限の時間には,①無限の過去から未来という直線上を未来に向って流れるという時間,②円周上を無限に循環する時間,という2つの種類がある.ヘレニズムの時間概念は,②の循環的時間である.
古代ギリシャの時間観
天体の運行をモデルとした古代ギリシャのの時間観においては,ピュタゴラス派,ストア学派,プラトン派において「宇宙の持続は反復であり,永劫回帰」であり,ヘレニズムは「時間を周期的なもの,あるいは循環するものとして知解する」.
ヨーロッパの歴史意識を決定したのはユダヤ・キリスト教の直線的時間であって,ヘレニズムの循環する時間ではなかった. (p.21)
--memo---------------------------
○循環的な時間,回帰的な時間は,アジアや仏教に特有のものとして考えられがちであるが,ここに示されているように古代ギリシャの時間観も循環的なものであったことに注目したい.ただしギリシャの特徴は天体の運行をモデルにしたものであることが,次の古代中国の時間観との決定的な差異であるというのが,加藤の主張である.
-------------------------------------
古代中国の時間
循環史観(歴史的事件の周期的な反復)は,古代ギリシャだけではなく,古代中国にもみられる.
中国の循環史観がヘレニズム(古代ギリシャ)の永劫回帰と異なるのは,それが歴史的時間に限定されていて,天体の運動には係わらないという点である.
古代中国の時間観
無限の直線上を一定の方法(原文ママ,方向?)へ流れる時間の概念は,しばしば無限に円周上を循環する時間の概念と,同じ文化のなかで共存する.
古代中国の一方には循環史観があり,他方には(中略)直線的な時間の意識があった.
仏教における時間
加藤は仏教における時間を,輪廻思想,ミロク信仰,末法思想の3つに分類する.
加藤は輪廻思想を業(ごう)とその結果の因果関係であるとして,因→果の前後関係と捉える.加藤の考えではその前後関係は円周上を循環する関係ではなく,直線上を前進する,半ば循環的,半ば直線的時間とする.
ミロクは本書では一種の終末論とされ,時間は無限の過去から有限の未来に向かうものとして措定される.
一方,加藤は,末法思想は「始めがあって終わりがない」歴史的時間として,ミロク終末論とは対称的であると主張する.
最後に4つめの時間として,時空間を「空なるもの」として捉える考え方を指摘する.
--memo----------------------
この「現在・過去・未来は永遠の今であり,永遠の今は過去・現在・未来である」という考え方はたった4行で説明されているが,井筒俊彦の『コスモスとアンチコスモス』を読むとかなり詳しく理解できると思う.
現在,過去,未来が等距離に,一挙に生起するという考え方は,味覚ではかなり重要になる.コース料理(直線時間)に対して,本膳料理あるいは幕の内弁当のような形式では一挙に世界が陳開される.時間の捉え方を理解しておくことは,料理の鑑賞の最も基本的な事項である.
------------------------------
『古事記』の時間
古事記の時間には始めがない.時間の終わりや終末論を示唆するものもない.
古代の日本文化が意識した歴史的時間は,始めなく終りない時間直線である.
その後日本に影響を与える仏教や儒教も,この古代の日本の世界観に大きな変更を迫るものではなかった.江戸期にユダヤ・キリスト教的時間の概念が持ち込まれるが,日本文化に浸透することは,文化的にも政治的にも不可能であった.
日本文化の三つの時間
本章の最後は,日本文化の三つの時間として,以下を結論としている.
始めなく終りない直線=歴史的時間
始めなく終りない円周上の循環=日常的時間
初めがあり終りがある人生の普遍的時間
まとめ
ということで,以上のような内容から本書は始まり,時間の文学的表現,行動様式に論が展開される.
第二部では同様に空間について,まず類型が示され,空間の様々な表現と行動様式を論じ,第三部,「今=ここ」の文化へとつながっていく.
この本一冊で時間論,空間論を語ることはできないが,冒頭にも書いたようにフラットに西洋も東洋も論じられているし,この本から色々な文献をリファーするというのにはうってつけで,必読と言って良い本だと思う.なにしろ,読みやすい.大学入試でよく使われるのも納得である.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
