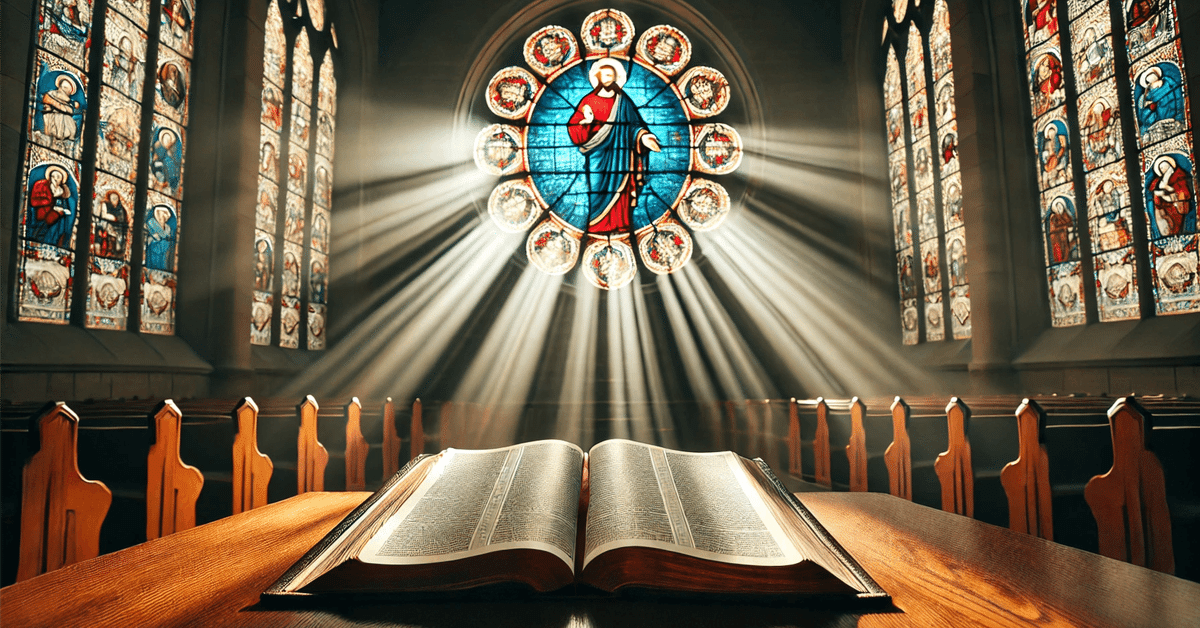
《聖書・キリスト教の研究-01》受講ノート#129
キリスト教の歴史を哲学的に考察すると、信者が「思考を外部に依存しすぎる」現象が目に付く。つまり、プロテスタントでもカトリックでも、多くの人が牧師や神父の言葉を無批判に受け入れる傾向が強い。これはある意味自然なことだ。なぜなら、宗教は多くの人々にとって信仰の支柱であり、精神的な安定の源だからだ。が、それが「思考の停止」を招きやすい点も無視できない。
例えば、学校の先生が教科書に忠実であることと似た現象だ。先生は教科書をよく知っていても、日本史の全貌を理解しているわけではない。それでも、教室では教科書の内容が絶対的な真実として伝えられる。同様に、教会で語られる教義も多くの場合、長い伝統に基づくものだ。しかし、この「伝統」がいつも「真実」であるとは限らない。人間は、自分にとって都合のよい物語を信じる傾向がある。それは歴史でも宗教でも同じだ。
興味深い例として「死海文書」が挙げられる。20世紀半ばに発見されたこの文書は、聖書の起源や初期のキリスト教に関する新たな視点を提供したが、当初はローマカトリック教会によってその内容が秘匿された。この隠蔽は、文書の中にカトリック教義と矛盾する可能性のある情報が含まれていたからだと推測される。
教会にとって不都合な事実が広まれば、信者の信仰基盤が揺らぐ危険がある。とはいえ、インターネットの時代になり、死海文書は無償で公開され、誰でもアクセスできるようになった。これによって、かつての教義に対する再考が進み、カトリック教会の過去の教えが覆される可能性が一層高まった。
このような歴史的経緯は、信者にとって「目覚め」をもたらすこともある。自分で調べ、考えることで、盲目的な信仰から抜け出す瞬間が訪れる。だが、その「目覚め」は決して簡単ではない。信じてきたものが覆される衝撃は大きい。たとえて言うなら、まるでハンマーで頭を殴られるような感覚だろう。特に長年深く信仰していた者にとっては、その心理的衝撃は計り知れない。時にはパニックやヒステリーを引き起こすほどだ。しかし、真実に近づくためには、このプロセスを避けることはできない。
宗教や歴史のように、真実が隠されることは珍しくない。だが、だからこそ、自分で調べ、学ぶ姿勢が重要だ。教義や伝統に疑問を持ち、それを掘り下げることで、見えてくる真実がある。これは宗教に限らず、すべての学問に通じることだろう。
興味深い問題提起だ。この議論は、何世紀にもわたって宗教の歴史と力学に興味を持つ者たちにとって、常に熱いテーマであり続けている。宗教が虚構であり、特に権力者に都合よく操作されてきたという考えは、多くの歴史学者や哲学者によって論じられてきたし、その一方で信仰の側からは強く反論されてきた。つまり、宗教そのものが「真実」か「虚構」かという問いには明確な答えがなく、むしろそれが人間社会の複雑な力学を映し出す鏡のような役割を果たしているという見方もできる。
まず、死海文書やナグ・ハマディ文書の発見は、キリスト教の成立以前に存在した様々な思想や信仰が現代の私たちが持つ宗教観とは大きく異なっていたことを示している。これらの文書は、単なる歴史的資料以上のものであり、カトリック教会が確立される以前に多様な宗教観が存在していた証拠となっている。これらの信仰が後に「異端」とされたことは、宗教が歴史的にどのように整理され、権力のために利用されてきたかを物語っている。
宗教に対する懐疑的な視点から見ると、あらゆる信仰体系が「虚構」であるという立場も理解できる。宗教はしばしば、個人の精神的慰めだけでなく、社会秩序を維持するための道具として機能してきた。例えば、古代エジプトにおいてはファラオが神として崇められ、その神性が社会を統治する正当性を与えたように、キリスト教や他の宗教もまた、権力を持つ者たちによって形作られてきた。
しかし、宗教が全て虚構だという見解は、いわば冷静な分析を基にしていると言える一方、数多くの人々にとって宗教がいかに重要なものであるかを見落としている可能性もある。宗教は、多くの人々にとって人生の意義を見出し、苦難を乗り越えるための指針を与えてきた。ローマ・カトリックが虚構の頂点にあるという主張も、その背後にある複雑な歴史や哲学的な問いを無視することなく、慎重に議論する必要があるだろう。
また、聖書の改ざんや翻訳の歪みについての指摘も重要だ。確かに、聖書は何度も翻訳され、その過程で意図的、あるいは無意図的に意味が変わってしまった部分があるのは否定できない。例えば、ラテン語訳の「ウルガタ版」や、後に英語版として広まった「キング・ジェームズ聖書」も、それぞれの時代や宗教的背景に影響を受けたことが知られている。
宗教に懐疑的な立場から見るならば、こうした事実は、信仰を盲目的に受け入れることの危険性を浮き彫りにする。一方で、それでも信じる者たちにとっては、その信仰自体が生きる意味や道徳的指針を提供していることも事実だ。結局のところ、宗教を虚構とみなすか、それとも何らかの真理を含んでいるとみなすかは、個人の視点によって変わってくるものなのだ。
旧約聖書の構成
創世記の天地創造から始まり、アダムとイヴ、カインとアベル、大洪水とノア、バベルの塔といった話は、シュメールの伝承を編集したものだとされている。これらは神話のレベルにあり、実際の証拠がほとんどない薄弱なものだ。しかし、天地創造の部分を話に組み込まないと、アブラハムから突然始まることになり、物語の権威付けに問題が生じる。そのため、後で加えられた部分が大洪水やバベルの塔の話で、これらは完全にシュメールの神話から取られてきたものである。この辺りは彼らの民族の物語として伝わっていた話だろう。アブラハム、イサク、ヤコブたちの祖先に関する話であり、おそらくは民族の間で口承されていたと考えられる。
モーセの出エジプトも同様に、口伝えで伝わっていたものだろう。文章として成文化されていなくても、口頭で伝わっていたと考えられる。そのため、実質的には旧約聖書の物語はアブラハムから始まると見なすべきだ。アブラハム以前の部分は、後から取ってつけたようなものだ。
ヤコブがイスラエルという名前を与えられ、その子孫がイスラエル民族と呼ばれることになる。そして、ヤコブの子供たち、特に末のヨセフが重要な役割を果たす。ヨセフは兄弟たちの嫉妬を買い、奴隷として売られ、エジプトへ渡る。だが彼は夢解きの能力を持っていたため、エジプトで出世し、最終的にはエジプトの宰相にまで上り詰める。この時代はちょうどエジプトがヒクソスの支配下にあった時期であり、ヒクソスはカナン地方の遊牧民族で、イスラエル人と関係が深い。ヨセフがエジプトで宰相になれたのは、ちょうどその時期だったと考えられている。
ヒクソスの支配が終わると、エジプトの元の王朝が権力を取り戻し、イスラエル人はエジプトから追放されることになる。聖書ではこの部分が削除され、エジプト人がイスラエル人を一方的に虐待したかのように描かれているが、実際にはイスラエル人がエジプトで卑劣な行為をしたため追い出されたのだ。その後、彼らは奴隷として扱われたというのが真実である。
旧約聖書はイスラエル民族の歴史を描いているが、都合の悪い部分は省略されており、都合の良い解釈がなされている。神の命令として行われたことが正当化され、他の民族への虐殺さえも神聖な行為として描かれている。現在のイスラエルとパレスチナの問題も、このような信仰に基づいて正当化されており、パレスチナ人の苦難は続いている。
狂信的なユダヤ教徒や、ユダヤ教に加担する一部のキリスト教徒の中には、イスラエル建国を正当化し、パレスチナ人の追放を肯定する者たちがいる。彼らは、イスラエル国家が神の命令であり、その建国が神の国の到来を意味すると信じている。このような考え方を持つ人々にとって、旧約聖書は絶対的な正当化の道具となっている。しかし、そうした信仰は人間の良識を破壊してしまう。
一方、パレスチナの人々の苦難に対しては、世界の大多数が同情し、彼らの受けている扱いに対して非難の声を上げている。イスラエルとパレスチナの対立において、どちらを支持するかと問われれば、現代の多くの人々はパレスチナの側に立つだろう。イスラエルの側に味方する者は、少数派である。にもかかわらず、狂信的な宗教的信念に基づく行動が、パレスチナ人を絶えず苦しめ、彼らの存在を脅かしている現状が続いている。
こうした信仰に基づく行動は、第三次世界大戦を引き起こそうとする危険性も孕んでいる。彼らはイスラエル建国を神の国の到来と見なしており、そのためにいかなる犠牲も厭わないという極端な考え方に取り憑かれている。だが、このような宗教的狂信は、人間の良識や道徳に反していると言えるだろう。信仰は尊重されるべきだが、それが他者を傷つけ、殺害することを正当化するものであってはならない。
現代におけるイスラエルとパレスチナの問題を見ても、パレスチナ人の苦難は続いており、世界中の人々がその状況に対して懸念を抱いている。しかし、宗教的な狂信者たちは、イスラエルの行為を神の意志として正当化し続けている。だが、現代の価値観からすれば、こうした行為は到底受け入れられるものではなく、パレスチナ人の権利や人間性を尊重すべきだという声がますます高まっている。
信仰というものが存在しているとき、それが一瞬で吹っ飛んでしまう瞬間がある。例えば、神が出現した瞬間に「どうしてそんな卑劣なことができるのか」と感じるかもしれない。しかし、それを「神の命令だ」と考えれば、アブラハムに「この地はお前の子孫に与える」と神が言ったように、それが正当化されることがある。そういった卑劣な行為が本当に可能なのかという疑問に対しては、可能であり、それが現実であると実感することがある。
そういった行動はまるで「悪魔に魂を売っている」のではないかと思うが、彼らは神の命令に従っていると信じている。これがユダヤ教徒やキリスト教徒、またはイスラエルの建国を強く支持するシオニストや、彼らを支援するキリスト教の一派に見られる世界観である。一方で、イスラム教徒やアラブ、パレスチナの人々を支援する勢力も存在している。双方が「自分たちは神に従っており、選ばれた民族だ」と主張している。このような対立が続く限り、事態が解決することはないだろう。
そのため、宗教というものを客観的に捉え、本当のところを理解することが重要だと言える。信仰から少し距離を置き、冷静に見つめ直すことが必要だと感じる。
そういう意味で、学者の中には非常に良心的な人がいて、物事を非常に冷静に分析している。聖書を研究する学者の多くは、実際には聖書を信じていない。おそらく99%は信じていないだろう。彼らは聖書を調べれば調べるほど、それが虚構であることに気づく。しかし、彼らが信仰心を持っていないわけではなく、無神論者でもない。ただし、オーソドックスなキリスト教やユダヤ教を信じているわけではない、というだけのことである。
ヨセフがエジプトに売られ、宰相となった後、イスラエルの一家がエジプトに住むようになるところで物語は終わる。そして次に「出エジプト」として、彼らの子孫がエジプトから追い出される展開になる。エジプトに残った者もおり、奴隷階級に落とされた人々もいた。そんな中で、イスラエル民族を導く指導者として登場するのがモーセである。モーセはイスラエル12部族の中に生まれ、彼の召命(神からの使命)から始まり、エジプトからの脱出が物語の主軸となる。さらに、数々の天災や、脱出後の奇跡、シナイ山で神と結ばれた契約などが描かれる。
シナイ山での神との契約については、実際にあった出来事だろうと考える。ただし、モーセの生まれに関する話は、シュメールの神話、特にサルゴン王の神話とほぼ同じであり、これを拝借したものではないかと思われる。したがって、モーセの出自については非常に曖昧で、どのような家系でどのように生まれたのかは不明である。
エジプトからの脱出自体は事実であろうが、その人数については疑わしい。ナチスによるホロコーストで600万人が殺されたとされているが、研究者たちはその人数に疑問を呈しており、実際にはそんなに多くの人が犠牲になったわけではないという説がある。同様に、出エジプトの人数も膨らまされており、当時のエジプトの人口の4分の1が消えるほどの規模であれば、エジプト側の記録に残るはずだが、そうした記録は全くない。エジプト人は何でも細かに記録していたため、この点からも脱出者の数は少人数だったと推測される。
彼らの思想や物の考え方は、現代に至るまで変わらず、事実を大いに誇張する傾向がある。実際には少数の脱出者であったのが、数十万人、数百万人にまで膨らまされて伝えられている。ナチスのホロコーストに関する話も同様で、600万人という数字が膨らまされ、人々に信じ込まれている。これは彼らの情報操作の手腕によるものであり、彼らは情報を操作する天才であるということが分かる。現代のアメリカがメディアを使って行っている情報操作にも通じるところがあり、彼らの民族的特質といえるだろう。
シナイ山での神との契約については本当だろう。幕屋の作り方や金の子牛事件が出てくるが、これらはミトラ教と深い関係がある。金の子牛はミトラ教の象徴である。この事件によりモーセは十戒を授かる。また、レビ記では出エジプト記の最後の部分に記された祭司に関する規定が詳述されており、祭儀全般に関わる律法が細かに記されている。
レビ族の祭祀と日本神道
出エジプトに関するレビ族の祭祀規定が、日本の神道に反映されているという主張がある。この共通点から推測されるのは、古代ユダヤ民族の一部が日本に辿り着いた可能性が高いということだ。バビロン捕囚によりイスラエルの失われた十支族が世界中に散らばった際、その一部が日本へ渡来し、彼らの文化や宗教が神道の中に取り込まれたという説である。レビ族が持つ高度な技術や建築の知識も、日本の神道に影響を与えた可能性が考えられる。
神道において、ユダヤ民族の祭祀規定が守られていることからも、ユダヤ人と日本人が共存してきた歴史が見えてくる。この共存の背景には、日本が多神教の文化を持ち、他宗教を受け入れる寛容さがあったことが挙げられる。特に一神教を持たなかった当時のユダヤ人たちは、キリスト教に改宗しながらも、自身の宗教的アイデンティティを保ち続けたと考えられる。
こうした背景により、日本の神道は多様な信仰を受け入れながら発展し、共存共栄の文化を築いた。日本人は宗教的な無節操さともいえる特性を持っており、これは他民族との共存を可能にした重要な要素だと考えられる。このような共存の姿勢こそ、日本人が世界に誇るべき点であると主張している。
しかし、こうした寛容な態度を拒む民族も存在する。自分たちの宗教や民族性に固執し、それ以外を排除しようとする排他性を持つ民族がいる。その究極の例として、一神教を崇拝するユダヤ人が挙げられている。特に、強い信仰心を持つユダヤ人の中には、他の宗教や信仰を認めない姿勢を持つ者もいる。一方で、日本に同化したユダヤ人たちは多神教を容認し、日本文化に適応してきた。このようなユダヤ人たちは、自分たちの宗教が優れているとは主張せず、むしろ共存の道を選んだのである。
その例として、超正統派ユダヤ教徒の「ナートーレー=カルター」というグループが挙げられている。彼らは、あらゆる民族が聖地で仲良く暮らすことこそが神の望む姿であると主張しており、平和的な共存を求めている。この立場は、日本人や神道が持つ価値観と共通しており、異なる宗教や文化が共に存在し、それぞれが相手を尊重し合う社会を理想としている。
一方で、世界を破壊しているのは、狂信的なキリスト教徒やユダヤ教徒、イスラム教徒だという指摘がなされている。これらの過激派は、自分たちの宗教だけが真実だと主張し、他を排除することで世界を混乱させているという批判である。
続いて、共産党員の中にも非常に善良で良心的な人々が存在するという話に移る。こうした人々を認めることができないのはなぜかという疑問が提起される。同様に、アボリジニやインディアンといった先住民にも優れた思想を持つ人々が多く存在しているにもかかわらず、差別されることが多い現状が不思議でならないという主張だ。
もちろん、先住民全員が優れているわけではなく、現代文明に巻き込まれて愚かに振る舞う者もいるが、そのような状況に嘆いているホピ族やアボリジニの人々も少なくない。どの民族にも優れた人と愚かな人が存在するという認識を持つことが重要だと説いている。
これらの考え方が広がることで、この講座を行う意味が多少なりともあると感じているという結論に至っている。そして、ユダヤ人に対しても、特別に批判的な意図はなく、立派な人々が多く存在することを強調している。
民数記
民数記(Numbers)は、確かに出エジプト記の続編とも言える部分が多く、イスラエルの民が約束の地カナンに向かう過程での人口調査や宿営の様子が描かれている。そして、彼らが信仰の弱さと不従順のために40年間荒野を彷徨うことになった経緯が中心に据えられている。つまり、エジプトを脱出して解放されたものの、すぐに約束の地に入ることができず、その理由をめぐって多くの神学的な解釈が存在する。
確かに、彼らは武力が不足していたというのも一つの現実的な側面だが、聖書が描くところでは、もっと大きな問題は彼らの「信仰の欠如」だった。神の指示に対して恐れや不安を抱き、敵対するカナンの民に対して不信を抱いた結果、神の怒りを招いたとされている。これが40年の放浪につながったというのは、単なる戦略的失敗というよりも、神との契約に対する信頼の欠如に焦点を当てているのだ。
さらに興味深いのは、カナンの地の先住民との関係について。聖書の物語の中では、イスラエルの民が単にカナンに同化し、穏やかに共存することができたのではないかという見解も浮かび上がるが、そこには一つの問題がある。彼らは自分たちの信仰、すなわち唯一神を崇める信仰を守るために、その地にいる異教徒たちと混ざることを避けようとした。それが、結果として「殲滅」という厳しい選択を迫られたことを正当化する要因となっている。
この物語の核心には、信仰とアイデンティティの保護という深刻なジレンマが横たわっている。同化することが許されない状況において、先住民の文化や宗教がイスラエルの民に影響を与えるリスクが大きくなる。それを防ぐためには、極端な手段が必要だったというのが聖書の記述の根底にある。これが旧約聖書の一つの問題提起だ。モラル的な視点から現代の読者には理解しがたい部分もあるが、古代の人々にとっては生存のための必然的な選択と捉えられていたのかもしれない。
この点については、現代の視点から異なる解釈も可能だろうが、旧約聖書が描く神とイスラエルの民との契約の厳格さは、単なる歴史的出来事ではなく、彼らの信仰の試練として記憶されている。
申命記以降
申命記というのは、神からの律法を再び命じられるという意味であり、モーセが約束の地カナンを目の前にして、エジプト脱出以来の出来事を振り返り、イスラエル12部族に律法の精神をもう一度教えた書物だ。この5つの書物がモーセ五書(創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記)とされ、非常に重要なものである。
旧約聖書は多くの書物から成り立っており、その中でヨシュア記はモーセの後継者であるヨシュアがイスラエルの民を率いてカナンの地を奪い取っていく戦闘の記録である。士師記にはサムソンとデリラのような有名な話があり、これはイスラエルの初代の王が現れる前、サムソンのような強力な英雄たちがイスラエルを導いていた時代の物語だ。
イスラエルの最初の王はサウルであり、その後を継いだのがダビデだが、サウルが選ばれる前の英雄たちの物語が士師記に描かれている。ルツ記はダビデ王の家系を証明するための書物であり、アブラハムから続く正当な血筋がダビデに至るまでしっかりと繋がっていることを示している。
サムエル記は、羊飼いだったダビデがサウル王に仕えるようになり、サウルが次第にダビデを危険視するようになる物語である。サウルは戦闘で死に、ダビデが新たな王に選ばれる。そして列王記に続き、ここではダビデの息子ソロモン王の治世が描かれている。ソロモン王の時代にイスラエル王国は絶頂を迎えるが、その後、南北に分裂し、北のイスラエル王国は多神教に傾いていき、最終的にバビロンによって滅ぼされ、民は離散することになる。
この失われた北イスラエルの10部族は、後にキリスト教と出会い、特に「罪の許し」という教えに感動し、東方キリスト教に改宗していったと考えられる。彼らが日本にたどり着き、もともと多神教だった日本の宗教と自然に同化していったというのは非常に自然な流れだと思う。現代の一神教であるイスラエルのラビたちから見ると、日本の神道は堕落したユダヤ教と見なされるが、どちらが堕落しているかは判断が難しい。
宗教というものは、どちらが正しいかを一概に決めることができない部分が多く存在する。ユダヤ教の一神教的な価値観やキリスト教、または多神教の考え方、それぞれの宗教が生まれてきた背景や文化が異なるため、どれが堕落しているという見方も相対的なものである。
一神教のユダヤ教を信じようが、多神教を信じようが、どちらでも構わない。それぞれの人が善良で良心を持っているならば、その信仰が何であれ、問題はない。宗教の違いは、社会や文化に対する影響力が強いため、時に対立を生むこともあるが、信仰心の根底にあるものは人間の精神的な成長や道徳的な向上であるべきだろう。
宗教が異なることによって、個々の価値観や考え方が違ってくるのは当然であり、その違いを尊重することこそが、真の意味での宗教的寛容さだ。
唯一絶対真の神
唯一真の神という考え方は馬鹿げた概念である。哲学的に成立しないため、正統派ユダヤ教徒たちが唯一絶対の神を信じていることには興味深いものがある。バビロン捕囚後、イスラエルの人々はエルサレムに帰還し、ソロモンの神殿を再建する話が続く。
エステル記では、ペルシャ帝国の王妃となった美しいエステルが民族を救った物語が描かれている。ヨブ記や詩篇、箴言なども含まれているが、雅歌は特に異教的な要素が強い。ソロモンがエジプトからの影響を受け、異教の神々を信じるようになったのは、彼の多くの妻たちの影響によるものであり、最終的にエジプトの女神を信奉するに至った。これがイスラエルの神の怒りを招き、王国が分裂する原因となったとされている。
実際には、エジプトの神々も存在していたが、イスラエル民族が選んだ神が唯一の神とされ、他の神々の信仰を許さなかった。イスラエルの神が歴史の中で大きな影響力を持ち、エジプトやギリシャの神々が駆逐されるに至った。今日ではギリシャやエジプトの神々を信仰する人々はおらず、旧約聖書を根本的な聖典とする宗教が世界を覆っている。
イスラエル南北に分裂後、多くの預言者たちの書物が残されている。哀歌はエルサレムの陥落と神殿の破壊を嘆く書であり、歴史的な出来事を描いている。中でもダニエル書は特異で、終末予言が描かれており、今でもハルマゲドンに関連する預言として重要視されている。
旧約聖書のモーセ五書は最初に位置付けられているが、実はこれが最後に書かれたものであり、その他の書物が先に作成されていた。
結局、エジプトやギリシャの神々は消え去り、唯一神を信じる宗教が支配的になった。その背景には、単に宗教的な信仰の違いだけでなく、歴史的、政治的な力が大きく関わっている。神々の存在は消えてはいないが、信じる人々がいなくなったことで、表舞台から姿を消したと言える。
このように旧約聖書は、単なる宗教的な教典というだけでなく、その背後にある歴史や文化、異教の影響などが複雑に絡み合ったものであり、それが現在の世界宗教に与えた影響は非常に大きい。
モーセ五書の創作背景
出エジプトの時期は紀元前1250年頃とされている。続いて、サウル王が登場し、ダビデやソロモンの時代、紀元前1000年頃になる。そして王国は紀元前926年に分裂した。この時期にバビロン捕囚が始まる。ユダヤ王国、南王国が紀元前587年に滅亡し、これがバビロンの第2回捕囚に繋がる。
この捕囚で、王や神官たちがバビロンに連れて行かれた。シュメールやバビロニアの神学・占星術がユダヤ教と融合することとなる。
それまでのユダヤ教は非常に原始的なもので、簡単に言えば日本の『古事記』や『日本書紀』のようなレベルに過ぎなかった。日本人が旧約聖書を見た時に、その歴史や宗教の深さにショックを受けるのは、この違いによるものだ。『古事記』や『日本書紀』しか知らない日本人にとって、旧約聖書は遥かに高度に感じられる。しかし、もしも日本のホツマツタヱを読んでいれば、聖書の価値観は吹き飛んでしまうほど優れたものだ。
捕囚される前のユダヤ人は、まるで『日本書紀』しか持たない日本人のようだった。だが、バビロンの捕囚により、シュメールから続く先進的な文化や強固な神学体系に触れたユダヤ人たちは、その影響を受けて自身の宗教を発展させたのだ。
その後、キュロス王の解放令により、ユダヤ人たちは帰還を許され、エルサレムの第二神殿を再建した。このあたりの出来事は『エズラ記』などに記録されている。
そして、この時期に「モーセ五書」が成立した。モーセ五書は、バビロン捕囚の際にバビロニアの神学体系に触れ、その影響を受けて作られたものである。ノアの大洪水やバベルの塔、サルゴン王の話など、バビロニア神話を取り込み、モーセの物語に変えた形で完成したのだ。
そのため、モーセ五書は一部に真実も含まれているが、虚構も多いことは明らかである。モーセが直接書いたものではなく、彼が生きていた時代のものではないのだから。
シュメールやバビロニアの神話に触れた彼らが、自らのアイデンティティを確立するために、都合の良い神話を作り上げたというのが真相だ。強固な神学体系が必要だったため、自分たちに合う形で神話を再構築したわけだ。
事実として、モーセ五書が成立することによって、ユダヤ教が形成された。このことからもわかるように、ユダヤ教はアブラハムの時代から存在していたわけではない。ダビデやソロモンがユダヤ教を信じていたとも思えない。特にソロモンに関しては、エジプトの神々を信仰していたため、ユダヤ教を信じていた可能性は低いと考えられる。
こうした背景を考えると、ユダヤ教は比較的新しい宗教であり、成立は紀元前500年頃とされる。つまり、ユダヤ教は古代から存在していたわけではなく、この時期に新たに誕生した宗教であることを理解すべきだ。
秘教
これに関連して、ブラヴァツキー夫人の秘教(シークレット・ドクトリン)も、この時期から出現したことがわかる。秘教は紀元前500年以前には遡らず、それ以前の時代に存在していたものではない。このため、秘教も実は歴史が浅く、古代エジプトのような非常に古い時代にまで遡るものではないことが明らかだ。
秘教が広まった背景として、エズラやネヘミヤによる宗教改革、さらにはアレキサンダー大王の征服が大きく関わっている。アレキサンダー大王はエジプトまでを支配し、その結果、エジプトがプトレマイオス朝となり、王が代わり、ギリシャ化が進んだ。エジプトの古代神々もギリシャ化し、神秘思想が発展していった。特に、古代エジプトで秘教とされていたものがギリシャ化していき、最終的には秘密の神秘思想として広まっていくことになった。
その神秘思想は、ギリシャからヘブライ民族へと流れ込み、イエスが登場する直前にはクムラン教団やエッセネ派という集団に影響を与えた。正確に言うと、エッセネ派は秘密結社であり、その内部において神秘思想が深く根付いていた。
フリーメイソン
ヨハネとイエスは、エジプトの宗教、特に神秘思想をヘブライ民族に伝えた人物である。そのため、聖書にはそのように記されているのだが、神父たちはその理解が乏しく、聖書を全く違うものにしてしまった。
本来、イエスが弟子たちに伝えた教えの一部が、現在に伝わっているのがフリーメイソンである。ただし、現代のフリーメイソンの儀礼や思想は、他の様々な要素が入り込み、かなり歪んでいるが、その中に一部、イエスがエジプトから持ち帰ったものが残っている。フリーメイソンの人々がキリスト教を憎んで滅ぼそうとしているという話には、ある程度の正当性があるという意見もある。
キリスト教徒に弾圧された異端派の人々は、実はイエスが伝えた本来の宗教を受け継いでいた。そして、その宗教がフリーメイソンに繋がっているため、映画『ダ・ヴィンチ・コード』では、ローマ・カトリック教会の過去の悪事が暴かれている。これもフリーメイソンの影響があるとされ、歴史的に正しい部分もある。
講師自身は、フリーメイソンやテンプル騎士団、シオン修道会、さらにはローマ・カトリックやヒンドゥー教、ユダヤ教といった宗教や組織とは全く関係がないと強調している。自分の立場はあくまで客観的に見ているものであり、特定の立場に偏るものではないという。
イエスが伝えたエジプトの秘教や神秘思想については、これらを馬鹿にしているという立場。それは重要視するに値しないものであり、現代のフリーメイソンが抱えている秘技や儀礼も同様に、無価値だと思っているという。
こういった詳細は、後ほど説明するとしているが、長くなるため、まずは旧約・新約の正統派の教えを一通り説明し、その後で「実際にはどうもこうだったようだ」ということを教える予定とのこと。
このような都市伝説めいた話をする理由は、最初に正統派の教えを教えると、人々はそれを盲信してしまうことが多いためである。そのため、正統派の見解を教える際には、どうも違うようだという視点も併せて教える必要があるとのこと。
ヘブライ語の聖典について
ヘブライ語の正典としてユダヤ人の間で正式に確立されたのは意外と遅く、西暦90年頃ローマ軍によるエルサレム神殿破壊後、ユダヤ人(パリサイ派)がサマリアのヤムニの宗教会議においてなされたと思われます。旧約聖書のギリシャ語翻訳についてはもっと古い時代、紀元前3世紀中頃にエジプトのアレキサンドリアで始めて編集され、徐々に改定されながら紀元前1世紀にほぼ完成されましたが、これは70人訳ギリシャ語旧約聖書(セプトゥアギンタ)と呼ばれるようになります。かなり以前から広く知られている事ですが、旧約聖書は歴史的順序では書かれておりません。最も重要な書と言われるモーセ五書は、バビロン捕囚からの帰還後かなり遅い時期に書かれ、しかも創世記1章「天地創造」は、モーセ五書編集の一番最後に書かれたとも言われています。
ここでは「旧約聖書」という言葉を使わずに「ヘブライ語の聖典」と表現されている。理由として、ユダヤ教徒は「旧約」という呼び方をしないからだ。キリスト教徒はヘブライ語の聖典を「旧約」と呼び、そこに新しい契約を加えて「新約聖書」としている。キリスト教徒にとって「旧約」は神との古い契約であり、古い契約が破棄され、新しい契約が成立したと考えている。しかし、ユダヤ教徒は新約を認めておらず、古い契約が破棄されたという考え方そのものが存在しない。そのため、彼らにとってヘブライ語の聖典は今でも続いている契約であり、「旧約」と呼ぶのは失礼にあたる。だから「ヘブライ語の聖典」と呼ばなければならない。
ヘブライ語の聖典が正式に確立したのは、意外にも遅い時期で、西暦90年頃である。この時期は、イエスが生まれた後90年ほど経過しており、ローマ軍によるエルサレム神殿の破壊があった後である。この時期にユダヤ人のパリサ派が集まり、ヤムニア宗教会議でヘブライ語の聖典が完全に確立した。したがって、それまではヘブライ語の聖典が正式にまとめられていなかったということになる。例えば、モーセ五書はこの時期までにはほぼ完成していたとされている。
アレクサンダー大王が大帝国を築き、エジプトまで支配を拡大した後、紀元前3世紀頃にエジプトのアレクサンドリアで初めてヘブライ語の聖典がギリシャ語に翻訳された。この翻訳が「七十人訳ギリシャ語旧約聖書」と呼ばれるものだ。ギリシャ語への翻訳が行われたことで、より広い地域でこの聖典が理解されるようになった。
その後、イエス・キリストの処刑後に西暦90年頃、ローマ軍によってエルサレム神殿が破壊された後、パリサ派が集まり、ユダヤ教が正式に確立した。この過程で、民族のアイデンティティを守るためにヘブライ語の聖典が重要な役割を果たし、西暦90年頃にヘブライ語の聖典として正式に確立された。
モーセ五書が完成したのは紀元前500年頃であり、その後にヘブライ語の聖典が確立したのは西暦90年頃ということで、比較的後の時代に確立されたものだ。また、旧約聖書の内容が歴史的な順序で書かれていないことも広く知られている。
モーセ五書は、バビロン捕囚からの帰還後、比較的早い時期に書かれたものだが、創世記の最初の章、天地創造の部分は一番最後に書かれたという事実が指摘されている。これは、天地創造の部分が付け足しのように作られたためだという。
モーセ五書の実際の作者がモーセでない事は、五書自ら教えているように思えます……モーセの物語はモーセを三人称で書いていますし(人々の中でもっとも柔和な人であった)、モーセが亡くなった様子や埋葬された場所など、誰も知らなかった記述(申命記34)などからも伺える気がします。
旧約聖書 申命記
34:5 こうして主のしもべモーセは主の言葉のとおりにモアブの地で死んだ。
34:6 主は彼をベテペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る人はない。
明らかにみんな知っていることがある。例えば、キリスト教の関係者で、モーセ五書をモーセ自身が書いたと信じている人がいるだろう。しかし、この聖句を読んだときに「モーセが書いたと信じる」と言うのは、少し理性的ではないと感じる。信仰が理性を超えると言われても、それは違う話だ。どうしようもないが、これは後世に書かれたものだと考えられる。
100歩譲って、仮にモーセが死んだ後、モーセの霊が霊導して書いたという可能性があるかもしれない。それならそうかもしれないが、それは証明できない領域だ。そこまで言うつもりはないが、少なくともモーセ自身が書いたものでないことは明らかだと思う。
この意味で、モーセ五書がモーセ自身が書いたことにされているが、実際には違うというのは明白だ。このことをよく知っている神父たちは言わないだけで、みんな理解している。言わないだけだ。説教の中ではその事実を伝えないが、NHKの「心の時代」といった番組では時々神父が出てきて、モーセ五書がモーセの手によるものではないと言っている。紀元前に書かれたものだとテレビで言う場面もある。それを聞くと、「この人はちゃんと知っているんだ」と思う。
さらに、イエスの誕生日が12月25日ではないことも、みんな知っていることだ。しかし、言わないだけで、神父たちはみんな知っている。12月25日はありえない日だが、信者たちはそれをイエスの誕生日だと思い込んでいる。それは異教の神々の誕生日なのに、信者たちは騙されている状態だと言える。
たとえば、「ただちに健康に影響はない」と言っている人たちも、みんなその意味を理解している。しかし、はっきり言わない。同じような状況が多く感じられる。
こういった意味で、神父や主祭たちは政治家のように感じる。都合の悪いことは決して言わないし、知っていても黙っているのだ。
最大の虚構
旧約聖書の最大の虚構は、「唯一絶対の神」という概念にある。この部分こそが旧約全体の柱となっているが、実際にはこの「唯一絶対の神」という考え方は虚構であり、崩壊するだろうと考えられる。これが非常に大きな問題だ。
旧約聖書の古代ヘブライ語原本によると、創世記第1章に登場する神は「エロヒム(Elohim、神々という複数形)」であり、第2章4節以降では「ヤハウェ(YHWH)」という名前で書かれている。後の文章でもエロヒムかヤハウェ、あるいは両方が使われている。これにより、異なる2つの原本が後にモーセ五書に組み込まれたのではないかと推定されている。現在では、ヤハウェに関連する資料を「J資料」、エロヒムに関連するものを「E資料」と呼んでいる。
「ヤハウェ」という読み方が正しいかどうかはわからない。この四文字(テトラグラマトン)は《YHWH》であり、母音を適当に補ったものが「ヤハウェ」となっているに過ぎない。実際の読み方はわからない。当時、正しい読み方を知っていたのは、大祭司以外にはほとんどいなかったと考えられる。この神の名前を知ることは、最大の秘密であった可能性が高い。
したがって、本来「ヤハウェ」とは読まれていなかったはずだ。別の名前であったはずだが、最近になって「ヤーウェ」と読むのが正しいと主張されるようになった。これはおそらくシオニズム以降のことだろう。学者が金で雇われ、御用学者として「ヤーウェ」と読むのが正当であると言い出した。古代ヘブライの人々は本当の名前を知らなかったが、記録によれば「ヤハー」や「ヤハ」というふうに呼んでいたという話が残っている。「ヤハを賛美せよ」といった表現も記録されている。
ところが最近になり、ヘブライ学者や御用学者たちが「ヤーウェ」が正しいと言い出し、現在の神父たちはみな「ヤーウェ」と呼ぶようになった。そして、旧約の神は「ヤーウェ」であり、新約の神も「ヤーウェ」であるとされている。こんなものを信じる方がどうかしている。
このテトラグラマトンが登場するのは、創世記第2章4節からである。それまでは「エロヒム(神々)」という単語が使われている。「エロヒム」は本来「神々」という意味だが、聖書では「神」と訳されている。一方、YHWHが登場すると「主なる神」と訳されている。
この翻訳が意味するところは、シュメール時代の多神教に由来している。シュメールは多神教の社会であり、旧約聖書はその古代の伝承をつなぎ合わせ、都合の良いところを「主なる神」に書き換えたものである。つまり、旧約聖書はシュメールやバビロニアの聖典から剽窃し、削除や改ざんを施し、自分たちのアイデンティティに合うように都合の良い文献に変換したものである。したがって、旧約聖書は「聖なる書」などではないということだ。
ヘブライ語原典における『神々の天地創造』の文法的解釈
エロヒム(Elohim)の複数形
ヘブライ語において「エロヒム」という語は、文法上複数形の形態を取っている。通常、ヘブライ語では「-im」という語尾が複数形を示す。そのため、直訳すれば「エロヒム」は「神々」を意味する。しかし、聖書における多くの文脈では「エロヒム」は単数の神を指す。これは、ヘブライ語特有の「威厳の複数形」と呼ばれる文法現象によるものであり、偉大さや権威を示すために複数形が使われることがある。このため、「エロヒム」は形式上複数形であっても、唯一の神を意味するものとして理解される。
創世記1章1節における用法
創世記1章1節のヘブライ語原文では、以下のように記されている。
「בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ」
(ベレーシート・バーラー・エロヒム・エート・ハッシャーマイム・ヴェエート・ハーアレツ)
日本語に訳すと、「初めに神(エロヒム)は天と地を創造された」となる。この文において注目すべき点は、動詞「バーラー」(創造する)が単数形で用いられていることである。これは、「エロヒム」が複数形の形をしていても、ここでは単数の神が天地を創造したと解釈されることを示している。もし「エロヒム」が実際に複数の神々を指していたならば、動詞も複数形となっていたはずである。
単数と複数の関係
旧約聖書の他の箇所でも、「エロヒム」は複数形の形態を持ちながら、文脈上は単数の神を指していることが一般的である。これはイスラエルの神が唯一神であることを強調するための表現であり、多神教的な意味で「神々」を指しているわけではない。また、ユダヤ教やキリスト教の伝統的な解釈でも「エロヒム」は唯一の神を指すものと理解されている。これは、神の権威や偉大さを示すための文法的な特徴であり、実際に複数の神々が天地創造に関わったという意味ではない。
歴史的背景と学術的解釈
歴史的および学術的な観点からは、古代近東の宗教文化には多神教的な要素が存在していたため、「エロヒム」が初期において「神々」を指していた可能性があるとする学説もある。しかし、ヘブライ語聖書が編纂された時点では、「エロヒム」は唯一神を意味する言葉として定着していた。この点において、現代のユダヤ教やキリスト教においても「エロヒム」は唯一の神を指すものと解釈されている。
結論
ヘブライ語原典における「エロヒム」は文法上複数形であるが、文脈上は唯一神を指す言葉として用いられている。したがって、創世記における天地創造は、複数の神々によるものではなく、唯一の神による創造であると解釈される。これは、動詞が単数形で用いられていることからも明らかであり、文法的には複数形であっても意味上は単数の神として理解される。
YHWHという神名を一貫して使用するヤハウィスト伝承(J資料)
五書の中にある特定の記事の冒頭に、ヤハウェという神名を貫して使用していることから名付けられた。
この資料の起源が、ソロモン王国時代の初期であると考えられているが、その理由として同じ時代に活動していたダビデの家族物語(ダビデ台頭史)の作者と文体に類似点がある事、ソロモンの死後の王国分裂を知らないと言う点、更にかつてダビデ王国に併合されたユダヤ民族とその祖先物語があるなど、総じて彼らが全てヤハウェの支配下にある事を示そうとした事にある。
エロヒスト伝承(E資料)〜神名として複数形のエロヒムが用いられ、ヤハウィスト伝承に対抗する形で作成された
神名として複数形普通名詞・エロヒムが出エジプト3章まで用いられているので、エロヒスト伝承と名付けられた。
成立時代として考えられるのは、記述内容から申命記以前であるとされ、また預言を重要視している事や、ホセヤ書の歴史神学と類似している点が見られる事から、南北分裂した王国の北イスラエルにおいてヤハウィスト伝承に対抗するような形で、数十年後の前8世紀前半頃に作成されたのではないかと推定されている。
神々の共同作業
王国が南北に分裂した際、北の方は多神教に傾倒していく。バビロンやシュメールも元々多神教であり、その古い資料が、彼らの思考に合うように変換され、南に対抗する伝承が形成されたと考えられる。この流れで、エロヒムという多神教の神々の伝承を取り入れたと見ていいだろう。
エロヒムは旧約聖書にも登場し、天地創造に関与しているとされる。「神は七日目に休まれた」とあるが、この「神」は実際には「神々」のことを指している。つまり、天地を創造したのは唯一の神ではなく、複数の神々によるものだという解釈ができる。
旧約聖書の冒頭から、神々が宇宙を創ったと記されており、唯一絶対の神という概念がどこから現れたのかが疑問視される。実際には、アブラハムを選んだ神々の一人が、唯一絶対の神に祭り上げられ、他の神々が存在しないことにされたのだと考えられる。
人々は自分たちが選ばれた神、あるいは契約を結んだ神を宇宙創造者に仕立て上げ、唯一の神とした。これが今日の宗教的信仰に繋がるが、このような考え方は滑稽であり、唯一絶対の神という概念は無意味であるとの主張がある。
スピノザの「神即自然」の概念の方が現実的だ。宇宙や自然はずっと存在しており、誰もその始まりを見たことがない。したがって、初めからあったと考える方が納得しやすい。誰もが何かを作り上げたり育てたりするが、元々の素材は自然に存在していたものを使っているだけである。宇宙も同じで、神々が元々存在していたものを変形させて作り上げたものであり、無から何かを作り出したわけではない。
東京タワーの建築例を挙げると、多くの人々が関与して素材を組み合わせて完成させたものであり、誰か一人が全てを作ったわけではない。宇宙も同じく、多くの神々が関与して作り上げられたものである。この考え方は分かりやすく、無から宇宙が生まれたという現代の宇宙論よりも理解しやすい。
宇宙は周期的に滅び、その後、また新しい世界が作られる。人々が眠りから目覚めると、新しい世界を作り出すのは再び神々である。唯一絶対の神が宇宙を無から作り出したという説は理解しにくく、スピノザのように宇宙を唯一絶対の神の体と捉える方が現実的である。体内の細胞や微生物も自分の一部であるが、自分だけがそれを作ったとは言えないように、宇宙も神々によって作り上げられたと考えるべきだ。
このように考えると、宇宙や自然を唯一絶対の神として扱うこともできるが、他の神々の存在を認めつつ、互いに共存しているという考え方の方が理にかなっている。
キリスト教研究一覧
#青樹謙慈のキリスト教研究 #キリスト教 #旧約聖書 #新約聖書 #聖書研究 #キリスト教研究 #聖書 #宗教 #カトリック #プロテスタント
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
