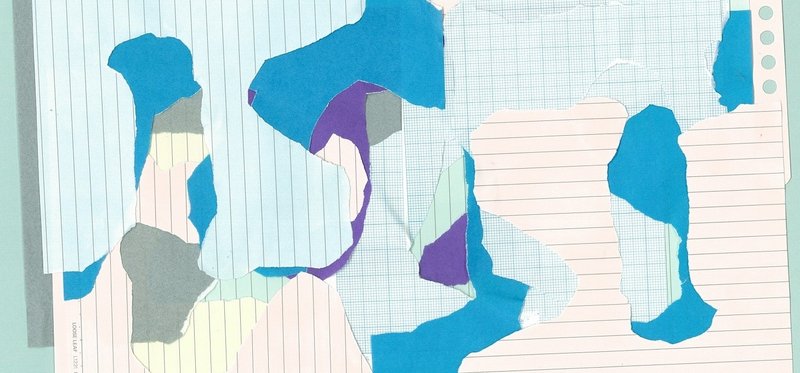記事一覧
書かれたものと書かせたもの / 青木淳悟論 (3)「ふるさと以外のことは知らない」
古谷利裕
4.「ふるさと以外のことは知らない」
4-1
「ふるさと以外のことは知らない」が、青木のそれ以前の小説と最もことなっているところは、そこでは物語上での「現在」がとうとうほぼ完全に消失してしまったという点であろう。 確かに、この作家においては、最初から「現在」は明確な位置を確定できない。この論考の冒頭でも触れた通り、「四十日と四十夜のメルヘン」にいきなり書きつけられる 《今日》が、
書かれたものと書かせたもの / 青木淳悟論 (2)「クレーターのほとりで」「いい子は家で」
古谷利裕
2 「クレーターのほとりで」
2-1
「クレーターのほとりで」の、森をさまよいつづける男たちは、数年もの間、日の光りを避けて生活しつづけること で、肌や髪の色を失うとともに、彼らが森に入る前の生活や、何故、森に入らなければならなかったのかという事情を、すっかり忘れてしまっているかのようだ。男たちだけ、十五人で群れをつくる彼らは、自分たちは木の洞から生まれたのだという神話をつくりだ
書かれたものと書かせたもの / 青木淳悟・論 (1)「四十日と四十夜のメルヘン」
古谷利裕
※「四十日と四十夜のメルヘン」は、新人賞受賞(「新潮」掲載)バージョン(=『匿名芸術家』所収バージョン)と、単行本バージョンと、文庫本バージョンと、それぞれの段階で大幅に改稿されていて、かなり違ってますが、ここで書いているのは単行本バージョンについてです。
1 「四十日と四十夜のメルヘン」
1.
「四十日と四十夜のメルヘン」の冒頭、主人公は、住んで いるアパートのポストを確認した
〔美術評〕だまし絵 Ⅱ 進化するだまし絵 /Bunkamura ザ・ミュージアム
古谷利裕
※以下は、2014年8月9日~10月5日まで、Bunkamura ザ・ミュージアムで行われた「だまし絵 Ⅱ 進化するだまし絵」展のレビューです。
https://www.museum.or.jp/report/517
本展に集められているのは、トリックを用いた作品であると同時にトリックを意識させる作品でもある。その意味で「手品」とは異なる。
まず不思議さに驚かされ、次に
〔映画評〕「十函」には内側も境界もないし、入り口も出口もない / 『にわのすなば GARDEN SANDBOX』(黒川幸則)
古谷利裕
https://www.youtube.com/watch?v=wdItUtRNVzQ&t=10s
地元とよそ者
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を楽しいコメディとは思えない。そこにあるのは、高校生時代の人間関係が大人になってもそのまま続き、さらにはその息子、「パート2」を含めると息子の息子に至るまで同様の関係が固定したまま継続している、閉ざされた地方都市のディストピアだ
〔美術評〕Re: play 1972/2015―「映像表現 '72」展、再演/東京国立近代美術館企画展ギャラリー
古谷利裕
※以下は、2015年10月6日~12月13日まで、東京国立近代美術館企画展ギャラリーで行われた「Re: play 1972/2015―「映像表現 '72」展、再演」のレビューです。
油絵の技法は15世紀にファン・アイクが完成したと言われる。その後、ヴェネチア派やチューブ入り絵具の登場などにより技法の革新は繰り返されるが絵具そのものは基本的には変わりない。今売られている油絵具でファン
〔小説批評〕歴史と固有性、そして記憶/橋本治『ふしぎとぼくらはなにをしたらよいかの殺人事件』をめぐって
古谷利裕
はじまり
橋本治の『ふしぎとぼくらはなにをしたらよいかの殺人事件』(一九八三年)は、この著者の最初の長編小説である。ぼくは、現在は橋本の熱心な読者とは言えないが(※このテキストは2008年に書かれた)、この小説の発売当時(高校の頃)はかなり読んでいた。特に「桃尻サーガ」の第三作目『帰ってきた桃尻娘』(一九八四年)は当時 のぼくにとってとても重要な小説だった。『ふしぎと』も同じ頃読ん
〔アニメ評〕反復という呪い、永遠という呪い、キャラクターという呪い/新・旧「エヴァ」について
※このテキストは、2009年「エヴァ破」公開時に、ある雑誌の「エヴァンゲリオン」特集のために書かれたのですが、事情により特集そのものがなくなってしまったため未発表となったものです。その後、ブログ「偽日記」にて、2009年10月01日から3日にかけて、三回に分けて掲載しました。
古谷利裕
キャラクターは歳を取らない
アニメのキャラクターは歳をとらない。のび太もカツオもまる子も、永遠に小学生だ
〔美術評〕フィリップス・コレクション展/三菱一号館美術館
古谷利裕
※以下は、2018年10月17日~2019年2月11日まで、三菱一号館美術館で行われた「フィリップス・コレクション展」のレビューです。
派手さはないが、質の高い作品が並ぶ。十九世紀から二十世紀半ばにかけ、ヨーロッパという土壌で育まれた近代美術のエッセンスが、作品それぞれが固有の花である小さな花壇の連なりによって体感できるようにしつらえられた庭のような展示だ。これらの作品のほとん
〔劇評〕パンとパン屑(全体を想定しない全体)について / 『うららかとルポルタージュ』(Dr. Holiday Laboratory)
古谷利裕
*以下は、2021年11月24日~28日に、東京のBUoYで行われた、Dr. Holiday Laboratory旗揚げ公演「うららかとルポルタージュ」のレビューです。
初出「うららかとルポルタージュ」記録集
はじまってすぐ、この上演が、たかだか一度きり上演に立ち会う一観客に全体像を把握できるはずないだろうという姿勢でつくられているとわかったので、「重要なところを見逃してはなら
〔書評〕子供たちの産まれる場所 / 『一一一一一』(福永信)
古谷利裕
「二」からはじまる。二人の人物がいる。《二つに分かれ》た道を前に《二の足を踏》む誰かに、別の誰かが声をかけた。《どちらか一方を選ぶ》ことが出来ず《一歩たりとも》前進できなくなっているのでは、と。つまり「二」の次に「一」がくる。その後しばらく、「二」は完全に姿を消すわけではないがやや後退し、「一」が圧倒的に前景化する。「刻一刻」「一時停止」「一期一会」等々。そして二〇頁まで進んではじめ
〔書評〕「わたし」たち/『星よりひそかに』(柴崎友香)
古谷利裕
1.「わたし」たち
「わたし」たち、について書かれた小説だと読める。「わたしたち」ではなく、「わたし」たち、である。「わたし」たちは、みんな「わたし」であり、それぞれ個別の「わたし」である。
小説の登場人物である「わたし」は読者である「わたし」とは違う。ではなぜ、わたしでない「わたし」を内側からわたしとして語る(生きる)一人称の小説を読者はすんなり受け入れられるのか。もしそれが
〔書評〕「そこ」にいる「わたし」/『わたしがいなかった街で』(柴崎友香)
古谷利裕
アメリカ大陸発見から数年後、スペイン人たちは原住民にも自分たちと同じ「魂」があるのかを調べるために調査団を送った。一方原住民たちは、スペイン人が自分たちと同じ「身体」をもつのかどうか調べるため、彼らを溺れさせて死体の腐敗を確かめた。西洋人にとって身体(物理、自然)の共通性は自明であり、一方、原住民にとって「魂」の共通性は自明であった。原住民たちは、人間たちも動物も精霊も、すべての存在
〔評論〕わたし・小説・フィクション/『ビリジアン』(柴崎友香)と、いくつかの「わたし」たち
古谷利裕
1.話者と登場人物
一人称の視点を用いて書かれたとしても、話者と登場人物との間にズレが生じることは、多少なりとも小説という形式に自覚的である人なら知っている。極めて常識的な一人称視点の小説において、語る「わたし」は、語られるわたしよりも時間的に後に位置することになるだろう。その時わたしは深い緑色の水面を見ていた、と語る「わたし」は、水面を見ているわたしより未来に位置していて、水面を