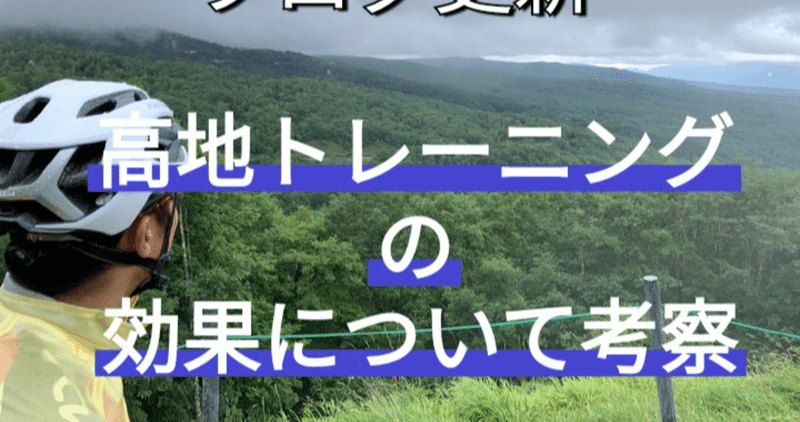
高地トレーニングの効果について考察
皆さんこんにちは!
今年の夏は3週間ほど山に籠っていた古山大です!
標高約1500m〜2000mでの長野合宿、来年もできるといいなぁ。
はい!というわけで。本日はちょっと頭捻って高地トレーニング(低酸素トレーニング)の効果や目的について、自分なりに考えをまとめてみようと思ったので、せっかくならという感じでブログにしてみました。今回は細かいところはざっくり割愛し、酸素に関してだけ考えてみました。あくまでも私個人の意見で、現時点での知識や情報から導き出した考えであるのでその辺は悪しからず…。
そもそもなんで突然今の時期に高地トレーニングについて考え出したの?!と思われるかもしれませんが、理由は簡単。先週月曜日に体験利用させていただいたAsics Sports Complex Gymでの感覚がかなり良かったのと、そこから「そもそも何で高地トレーニング(低酸素トレーニングし)があるんだっけ?」という疑問が出てきたからです。あ、一応今回は高地トレーニングと低酸素室を利用しての低酸素トレーニングは効果はほぼ同じであることを前提に考えます。念のため!
さて、昔からある「高地トレーニング」ですが、いろいろなトレーニング方法が生まれては消えていく入れ替わりの激しいスポーツ界でここまで長きにわたってメジャーなトレーニング方法として残っているものはなかなか無いんじゃ無いでしょうか。そんな高地トレーニングですが、そもそも何を目的にして行われるのか。トレーニングの5原則「意識性の原則」の観点からもここを明確にする事は大切ですね。
高地トレーニング目的は「酸素摂取関係の機能の強化」に尽きると思います。
標高の高いところに行くと、空気中の酸素量が少なくなります。いわゆる「空気が薄い」状態です。人間は呼吸によって肺から酸素を取り込み血管を通して全身に送り身体活動の動力としていますから、空気中の酸素が減ると取り込む酸素の量も減ります。人体にとって酸素の摂取量が減る事は大問題です。
で、じゃあ人間は酸素の薄いところに行くとそのまま動けなくなっちゃうの?というとそうでもありませんよね。酸素が地上の3分の1程度になってしまうエベレストにも人は登頂しています。それは、ざっくりいうと徐々に空気の薄い環境に体を慣らすようにして登っていくためです。人体の能力の一つ「順化」ですね。
つまり過酷な環境で生き抜けるように体の機能を慣れさせるのです。この場合は酸素の薄い場所でも生命活動維持に支障が出ないようにするため、血液内のヘモグロビンやらミオグロビンやらが増えたわけですね。
この順化の能力に目をつけたのが高地トレーニングなんだと思います。筋トレもジョギングもトレーニングと名のつくものは大体がこの順化を利用したものです。つまりは「40kgのダンベルを持てるようになれば10kgのダンベルは軽々持てるよね。じゃあ空気に関しても同じことやってみようか。」っていう発想ですね。簡単にいうと。
特に持久系種目においては、酸素を一度にどれだけ取り込めるかというのが1番重要になってくるので、高地トレーニングといえば長距離走、みたいなところありますね。
低酸素トレーニングはこの「酸素が薄い状況」を人工的に作り出すことによって、わざわざ遠くまで行かなくても近場で、さらには管理しやすい状況下で効率よく練習するためのものになりますね。カガクのチカラってすげー。
で、はい。メリットというか鍛えられる能力は以上のものになりますが、この世の中メリットしかない事なんてありゃしないですよね。メリットがあれば当然デメリットもある。世の真理です。じゃあデメリットはなんぞということで、これは完全に私が7月の合宿時に感じたものからピックアップします。
・すぐに息が上がる
・疲労が溜まりやすい、抜けにくい。
一つ目なんかは、いや、そのために行ったんじゃん!と突っ込まれそうですが、これが意外と厄介でした。というのも、我々持久系競技者にとって息が上がってしまうことは、限界値に達したということ。これが早めにきてしまうという事は、本来欲しいタイムでの練習ができなくなってしまうのです!例えば10kmのペース走をやる時に、平地と同じタイムで走れなくなります。そうなると、肺の活動的には平地と同じ負荷がかかるかもしれませんが、筋肉的には平地よりも軽い負荷しかかけられなくなります。走る速度が遅いですからね。目指すレースが低地でのレースだと、呼吸は強いけど速く走れないなんてことになりかねません。なので私が行った時は、色々調べて筋肉にもしっかり負荷がかかるように少し工夫してメニュー立てました。長くなるので割愛しますが。
二つ目は、何を持って疲労とするかという話は「同じパフォーマンスでの練習を続けられなくなる」事とします。疲労回復、練習で破壊した筋繊維の修復には酸素が必要不可欠です。その酸素が少ないわけですからまあ、当然といえば当然です。そこも含めた強化なのでしょうが。とにかく平地と同じ感覚で練習を組み立てられないので大変でした。具体的には強度の高い練習の量を積めなかった事ですね。あとはほんと油断するとオーバーワークで体調崩します。私も結構危なかったです。事前の綿密なスケジューリングと現地での柔軟な対応が必須です。
しかし、この二つのデメリットですが、裏を返せばこの部分を鍛えるために高地トレーニング(低酸素トレーニング)をやっているので、うまく回避しつつも時には真っ向からぶつかって体に負荷をかけていくことが必要になったりします。
というわけで、書きながら頭の中でまとめました。文章がとっ散らかってたらすいません。表面をサラッと書いただけのシンプルな内容でした。シンプルすぎてあまり中身ない気がしますが。兎にも角にも、高地トレーニング・低酸素トレーニングについての私の見解としては
非常に有効。しかしトレーニングプランは繊細に立てていく必要がある。
って感じですかね。疲労回復が遅い分、オーバーワークになりやすいので、諸刃の剣的な部分は大きいかもしれませんが、それに見合うだけのリターンはあるトレーニング方法だと思います。
そんなわけで今日はここまで!
それでは!
…なのですが、ここでお知らせがあります。
この度、「公式LINE」なるものを立ち上げました!!今のところは、ブログ更新のお知らせと、twitterで毎日更新している「#古山道場」というトレーニング豆知識の拡大版を週に2回配信予定です。ご興味のある方や、私のことを応援したい!と思っていただけた方は是非登録お願いいたします!この公式LINEを足場にして、今後色々なことをやっていけたらなと思ってます!
下記URLからご登録お願いします!
トライアスロンーーー!!!🏊♂️🚴♂️🏃♂️🥇
