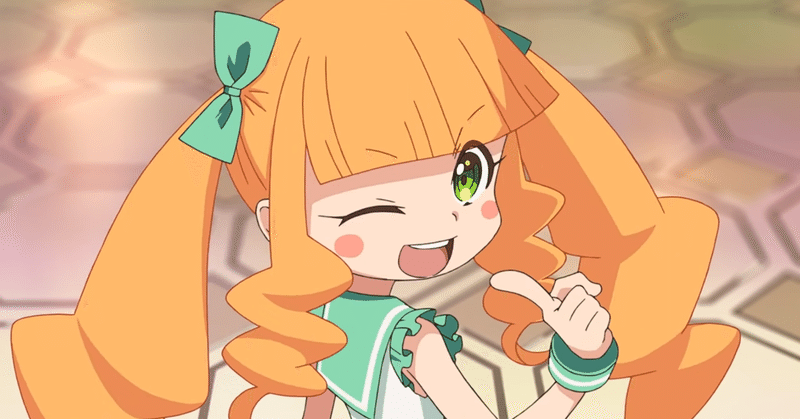
誰かの心を突き刺すために─「映画大好きポンポさん」感想─
幕を開ける
観客が映画という創作物に没入し、これは自分のための物語だと錯覚し、その感動を他者と共有したいと思うのは、必ずしもその映画の完成度が高いと感じたからではない。
それどころか全体としての完成度は高いとは言えない作品が観るものの心を打つこともある。
人の心に突き刺さるような鋭さは、物語全体の完成度とは別の要素によって研ぎ澄まされるものだからだ。
映画大好きポンポさんの視聴体験は、この種の創作に必要なたったひとつの大切なことを思い出させてくれた。
劇中劇「MEISTER」をつくるもの
この映画の主人公、ジーン・フィニは狂人だ。少なくとも映画製作という点に関して言えば。
青春時代のほぼ全てを映画に費やしてきた人間である彼を映画会社ペーターゼンフィルムのプロデューサーであるポンポさんが自身のアシスタントに採用したのは、「彼の眼が死んでいたから」である。
ポンポさんは言う。「幸福は創造の敵」であると。
「満たされた人間っていうのは満たされている故にモノの考え方が浅くなる」とクリエイターの才能を見極めることに長けている彼女は断言する。
念のために付言すれば、これは必ずしも真であるとは言えない。
満たされない生活をおくってきた人間に創作の才能があるとは限らないし、その逆に友人や恋人に囲まれて満たされていると感じてきた人間はつまらない作品しかつくれないというわけではない。
しかし、他の物事を切り捨ててある物事にのみ熱中してきた人間が長い時間をかけて涵養してきた技術や知識や熱量がその人間の自我を形成する土台になり、表現の世界で活かされることがあるということは事実だ。
他方で、この物語には「眼が死んでいる」わけではないのにも関わらず、映画という表現の世界に飛び込もうとするものもいる。
女優志望のナタリー・ウッドワードのことである。
物語序盤では田舎からでてきたアルバイトの少女にすぎなかった彼女の運命は、ペーターゼンフィルムのオーディションに参加したことがきっかけとなり、大きく変動することになる。
純真さの塊のような雰囲気を持つ彼女は、目の下にある大きな隈が暗い印象を与えるジーンとは真逆のキャラクターである。少なくともそうであるかのようにみえる。
しかし、将来に対して何の見通しもたっていない状況から意欲のみを武器に女優という表現の道を目指すことを選んだナタリーもまたジーンと同じように他の選択肢を切り捨てて茨の道を選んだものの一人だ。
実際、彼女はポンポさんに若手人気女優のミスティアの付き人になることを命じられるまで、週七回のアルバイトで生計を建てており、演技のレッスンも二週間に一回と少なく、夢の実現にはほど遠い状況にいた。
しかし、それでもなお「夢をすてるためにここにきたんじゃない。夢を叶えるためにここにきたんだ」という彼女からは、単純な憧れ以上の強い意志を感じることができる。
ジーンとナタリーは一見正反対の人間であるかのように見えるが、映画という媒体で表現する道を選ぶために他の選択肢を切り捨ててきたという点でお互いにとって鑑写しのような存在なのだ。

そしてこの二人とその手綱を握るポンポさん、有名俳優であるマーティン・ブラドックやミスティアの協力によって天才音楽家のダルベールを主人公にした「MEISTER」という映画を撮っていくというのが「映画大好きポンポさん」の大まかな流れである。
自己言及的な構造
映画を撮ることを題材にした映画にはその避けられない宿命として作品自体が自己言及的な構造を持つというものがある。
この作品も例に漏れない。
物語の最終盤、「MEISTER」でニャカデミー賞を取ったジーンがインタビュアーに映画の気に入っている点をきかれて「上映時間が90分ってところですかね」と答えるシーンは些か露骨(映画大好きポンポさんの上映時間は90分)だが、それ以外にもジーンとポンポさんが、試写室で映画をみているシーンが象徴的だ。
この場面でジーンたちがみているのは名作映画であるニュー・シネマ・パラダイスだ。
それにも関わらず、彼らがみているスクリーンには彼ら自身が出演している映画、「映画大好きポンポさん」のワンシーンが映し出されている。
この時、自分たちが映っているスクリーンを前に必死にメモをとるジーンと「名作の匂いってやつをかぎたい」と話すポンポさんの会話をきいた私たちは、ジーンやポンポさんが自分たちとは異なる世界の住人であることを思い出す。
自分たちが大写しになっているスクリーンをみても反応を示さずに名作映画を鑑賞しているかのような会話を続けるジーン達をみれば、登場人物と観客である自分たちとで劇中のスクリーンに映っているものが異なるということを意識せざるを得ないからだ。
スクリーンにジーンの回想を映すこのシ―ンは、この物語自体が製作陣のつくった映画であるということを観客に意識させる自己言及的な構造を持っている。
このような構造の構築は、終盤に向かうにつれて一層加速していく。
編集と選択
物語の後半、この映画のテーマが「選択」であることが明らかになる。
ナタリー達の協力もあって初監督作である「MEISTER」の映像素材を「ニャカデミー賞間違いなし」の質で撮ることに成功したジーンは、しかし、編集の段になって壁にぶつかる。
役者が全力で演じた素材を、切って除いて繋いでつくる編集作業において彼は何を選択し、そして何を選択しないことが、映画を成功させることに繋がるのかということに悩み、試行錯誤を繰り返す。
ところで、この「選択」の作業には既視感があるはずだ。
この作業は何もジーンのように創作をする人間の専売特許ではない。
「人生」を生きるすべての人間は、映画を編集するかのように自分の人生においても選択を繰り返している。
生まれ育った環境や個人の能力による違いはあるが、この国で生まれた多くの子供たちの前には一冊のカタログが置かれている。
そのカタログには、最初のうちは医師や弁護士、小説家や映画監督といった風に多くの職業が並んでいるが、その数は年齢を重ねるごとに減っていく。
カタログをじっと眺めているだけの日々は長くは続かずに成長するにつれて人は多くの選択を迫られるようになるからだ。
そして、ジーンが90分の映画にするための編集作業で何を残して何を削るかに悩んでいるのと同じように、人は自分の限りある人生において何が必要で、何が必要ないかということについて悩み、結論を出していく。
注意しておきたいことは、「選ぶ」ことに悩むとき、人は同時に「選ばない」ということにも悩んでいるということだ。
例えば、ある就活生が志望度の高い二つの企業から内定をもらい、どちらの企業に就職するか悩んでいるとする。
この時、その就活生は、身体が二つあればどちらも選んでみたいと思っている。
しかし、現実には就活生の身体は一つしかない。
従ってどちらかの企業を選ぶということはどちらかの企業を選ばないということになる。
この選択肢を潰すという折りになって人は悩む。
人生において、例えばいい大学に入ったり、いい資格をとったりということは選択肢を広げることとして推奨される。
しかし、その広げた選択肢の中から一つを選び残りを潰すこともまた難しいことだ。
こういう時、人は自分が何を大切にしているかという軸に立ちかえり、選択をすることになる。
ポンポさんに話を戻すと、結果としてジーンがポンポさんの祖父であるダヴィドヴィッチ・ペーターゼンと言葉を交わした上で映画の編集作業の軸に設定したのは、「映画のなかに自分がいるか」ということであった。
ポンポさんから与えられた納期を破ったうえ、新たなシ―ンを追加して一度解散させたスタッフを再結集させてまでジーンが表現しようとしたのは、ダルベールが妻と別れるシーンであった。
そのシーンで妻はダルベールに音楽と家族のどちらをとるのかということを迫り、答えのだせない彼に「二つはない。どちらかを選ぶしかない」というようなことを言う。
尚、このシーン自体も原作の「映画大好きポンポさん」にはない映画の「追加シーン」である。
この事もまたこの作品に自己言及的な姿勢があることを示している。
ジーンが「この映画のなかに自分がいるか」という点を編集作業の軸に据えたということは、「MEISTER」が自分がいなくても成立するようなものになっていないかということを検証して編集を行うということを意味する。
これはおそらくこの映画、「映画大好きポンポさん」の製作の軸にもそのまま当てはまる。
原作にはないオリジナルシーンの追加、原作には登場しない銀行員という「表現者ではない」職業についているアランというキャラクターとサブプロット、映画特有の技法や演出、これらがこの作品の本質にあたる。
ダルベールが一度は失敗したアリアの公演をもう一度やりたいというシーンとジーンがポンポさんに追加シーンをとりたいと懇願するシ―ンのシンクロナイズをみた瞬間、ぼくは不覚にも泣きそうになってしまった。
それは単にジーンの言動に感動したからではない。
製作側、作品、劇中劇、そして観客側の人生をシンクロさせるこのシ―ンで製作側の思いがはっきりと心に突き刺さったからである。
他の何もかもを切り捨ててでも追加シ―ンをとろうとするジーンの覚悟をみたとき、自分が人生でこれまでしてきた選択、あるいはしてこなかった選択を思い出して泣きそうになってしまった。
人が映画に感動するのは、必ずしも映画の完成度が高いと感じたからではない。
作中に自分自身を見いだした時、人はその映画に感動して物語に没入し、これは自分のための物語だと錯覚し、その感動を他者と共有したいと思う。
勿論、映画の製作陣はぼくのために作品をつくったのではない。
それにも関わらず、ぼくがこの映画に自分を見いだして感動したのは製作側が原作のなかに「自分」を見いだして作成したこの映画のなかに、ぼくもまた「自分」を見いだしたからだろう。
それが誤解であろうと幻想であろうと錯覚であろうと構わない。
ただし、あの瞬間、この作品がぼくの心に突き刺さったことだけは事実だ。
ポンポさんはその意味で間違いなく傑作である。
幕を閉じる
ただその一方で、この作品には問題もある。
例えば、作品全体で称揚されるクリエイターの「命をかける」、あるいは「命を燃やす」姿勢を一つのロマンとして肯定することに実害はないのかという視点だ。
ただでさえエンターテイメント業界は構造的に「やりがい搾取」になりやすい業界として知られている。
この点での批判はいくらでも可能だろう。
とかく「仕事」を題材にしたアニメはこの種の問題を孕みやすい。
仕事に追い詰められた作中のキャラクターが自己犠牲を払って仕事に打ち込むシ―ンは、「感動的」なシーンとしてつくりやすいからだ。
これは別にこの作品に限った話ではなく、「お仕事アニメとブラック労働」という視点でくくって考えてみる価値があるトピックかもしれない。
だが、今回はその点でこの映画を評するということはしない。
この映画をみた自分にとってまず心に残ったことはその点ではなかったからだ。
勿論、この作品が合わないと感じた観客の中には、作中のこのような製作思想が嫌で仕方が無いという人もいるだろう。
しかし、それでいいのだと思う。
切って除いて繋げてつくる。
そうして誰かの心に残るような作品をつくるために必要なたった一つの大切なこととは、すべての観客に受け入れられるように作品を丸くすることではなく、たとえ誰かを切り捨てたとしても別の誰かの心には深く突き刺さるような尖ったものをつくること、ただそれだけなのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
