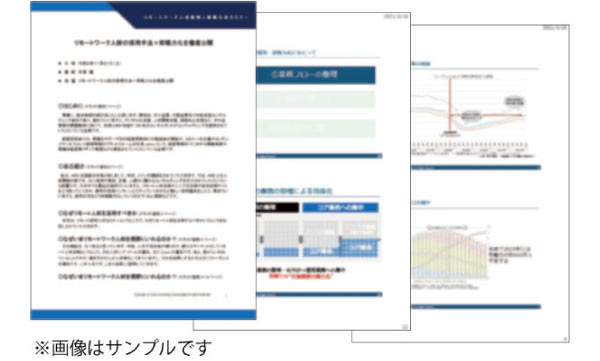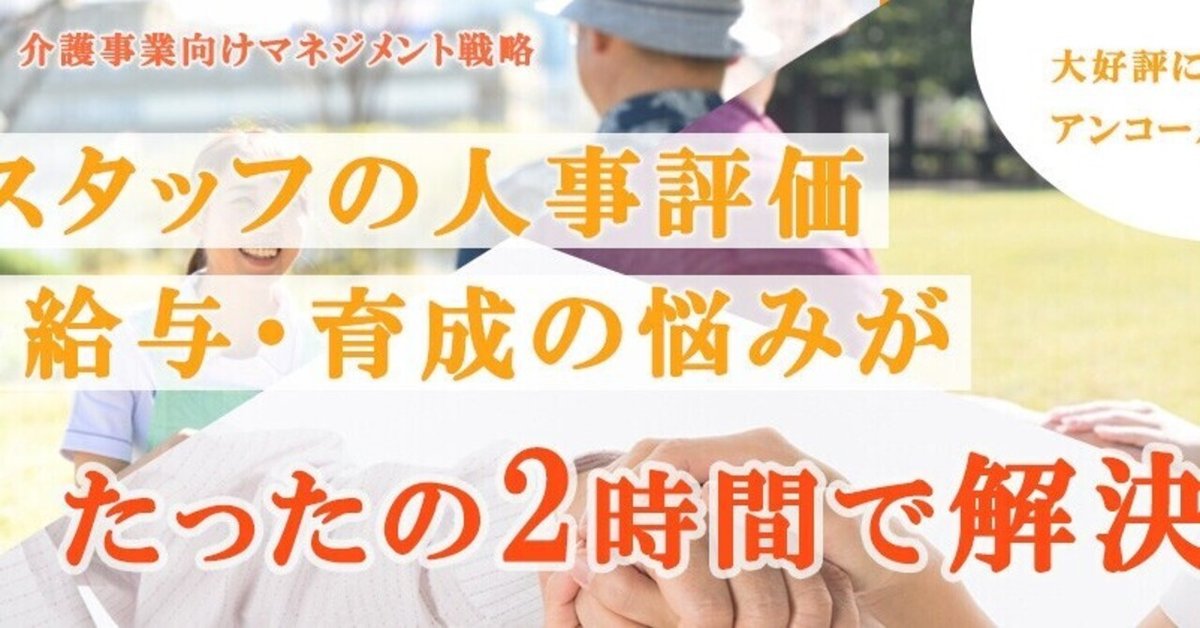
介護業界の評価・育成手法大公開!社員が定着し、育つノウハウとは?~セミナー特選講演録~
セミナーの講演内容と当日使用したテキストを無料でダウンロードいただけます。平均10,000文字を超えるボリュームの講演文字起こしとノウハウの詰まったテキストをご覧ください。
人事・評価・給与制度の3本柱でのメッセージ
今回お話をさせていただく前に、大事なメッセージを1枚にまとめました。ポイントは、見える化という点です。例えば、人事キャリアというところでスタッフの方々にどういうキャリアを歩んでもらいたいのかということです。マネジメントコースということで施設長などを目指すコースと、プロフェッショナルコースということで現場の最前線で頑張っていきたいという方の2種類のコースを設けていくことを、これまでは何となくだったものを、きちんと明確に表現することや評価の基準ということで会社の中で何を良しとするのかなどを明確にするということです。また、給与の昇給ということで、「どうやったら月給が上がる?」「どうやったらボーナス上がるの?」これをきちんと見えるようにしようと、これが第三講座の一番お伝えしたいテーマになります。
人事制度の作り方
まず、人事制度の作り方についてお話します。社員のキャリアアップについてですが、ベーシックコースとマネジメントコースということで社員やスタッフの方々のキャリアをしっかりと見える化しようというところが非常に重要になっていきます。これの意図として、「施設長になることだ」ということが絶対の正義のようになってしまうと、施設長になれない方やスキルはあるのだがマネジメント能力がやや低い方が居心地の悪い環境になってしまうというケースがあります。そのため、「両方とも認めますよ」というかたちで、きちんと会社の中で見られるようにするということが必要になっていきます。また、これを設けることによって、「じゃマネジメントコースを目指したい方にはこういう教育をしたほうがいいよね」や「ベーシックコースで現場の最前線に立つ人は、こういう研修したほうがいいよね」という教育の部分も見えるようになってきますので、ぜひ社内でこのようなキャリアコースというところをしっかり考えていただきたいと思います。
そして、そのためには役職基準をしっかり決めていく必要があります。つまり施設長に何を求めるのか、どこに責任を持たせるか、施設長の下級のマネージャーには何を求めるのか、これを決定していくことが人事制度で重要になります。「何となくこれまで施設長にはこの仕事を任せていた」ということや、他でいいますと、さまざまな役職が乱立をしすぎていて、名ばかりになっているということです。主任や係長や課長があって乱立しすぎていて全く意味をなしていないというケースがあります。したがって、組織が大きくなっていくと役職の肩書が増えていくということは健全とはいえないですので、最低限の数を設けていくという点が重要になっていきます。特に、マネージャーや施設長や管理職の方々には、個人の部分だけではなくて、全体の施設の中での数値や取り組みについての責任を持たせていくというところがポイントになっていきます。
昇格要件
名張育成会様の事例というところで昇格要件というのを載せています。この基準に達するためには、このようなことができないといけないということやこういう試験を受けないといけないということをまとめています。これがしっかりまとまっている会社様は、少ないのではないかと思います。私もお手伝いをしていて、ここまでまとまっているということは珍しく、スタッフからすると非常に安心感を覚えると思います。「自分は、あとこれとこれを身につけたら施設長なれるのか」「マネージャーなれるんだ」となりますと、スタッフの定着率というのも上がっていきますし、会社としても、これができていてほしいというレベルに達成している方も増えていきますので、より施設数を増やしていく、規模を拡大していくというところには必要な施策になっていきます。
キャリアパス
名張育成会様のキャリアパスの事例です。約何年でこの役職につけるということを見えるようにしています。年次に関しては、会社様によってさまざまかと思います。例えば、ベンチャー気質の若い組織でいいますと、さらに短いスパンで役職につくということもあるでしょうし、ベテランの方が在籍する昔からの会社様でいいますと、長くなるというところもあるので、一概にこの数字をお勧めするとはいえないですが、およそ何年でこの役職につける、そのときに年収はこれぐらいだというところが見えると、中途採用を行っている会社様でいいますと、応募者に対して見せることができます。年収400万が欲しい人に、うちだったらこのようなスキルがあってこれぐらい働くともらえるなど、これが表示できるできないで採用の質が一気に変わってきます。ぜひ、既存の社員だけではなく、未来の社員のことも見据えてキャリアパスの設計をしていただきたいと思います。
人事制度の作り方
ここまでのポイントということで、皆様の会社様に「3年後、5年後経過したときに幹部を任せたいと思える方はどれぐらいいますか?」そして、その方々に「こういうスキルができないと困る」ということや「こういうことはできてほしい」ということをしっかり明文化できているのかという点を今回のセミナーを通じてぜひ見直していただきたいと思います。
次に、人事評価制度です。まず、人事評価制度を作っていくフローということで5段階を載せています。一つ目、方向性の確定です。何を目的に人事評価を作っていくのかということです。よくありますのが、現場の生産性を上げていくや定着率を上げていくなど、どこにウェイトを置いていくのかを決めていく必要があります。また、育成方針の明確化ということで、面談は誰が面談するのかや評価項目をどのように測定していくのか、どのように教育していくのかということを決めていく必要があります。その後、それぞれに評価内容を作っていくのですが、評価シートを作る際には、職種の数かける役職の数で作っていただきたいです。つまり、一人一人に合ったシートを作っていくということです。ただ、個人別に作っていくとキリがなくなってしまいますので、最低限、職種の数と役職の数を掛け合わせた部分の評価シートを作っていただけたらと思います。そして、4番目、仮評価です。実際に作っていく中で仮評価をしていただき、基準が大丈夫かどうか、甘くないか辛くないかというところなど評価のオペレーションを確認していただきたいと思います。そして、最後5番目です。説明会ということで、どうして会社として評価制度を入れることになったのか、見直すことになったのか、あるいは評価制度を通じて皆さんにどのようなことを気をつけてもらいたいか、評価を付ける際にこのようなことを大事にしてほしい、そのようなことをしっかりと伝える場を設けてほしいと思います。なかなか難しいことだとは思いますが、理想は全社員が納得できるような評価制度を作ってもらえると良いかと思います。
ここからは、具体的な評価項目も一部お見せしながらお話をしていきます。考え方として、このピラミッドを覚えていただければと思います。コンセプトとして、業績が上がっていく、施設数を増やしていくというところがありますので、収益という点を視野に入れて作っていくことをお勧めします。その際に、5種類の項目があります。一つ目が数値評価です。施設の売上や稼働率の部分を昇華しようということです。これをスタッフまで求めるのか、逆に施設長以上には求めるのかという議論の余地がありますが、現場の業務だけではなくて数字の部分も意識させていくことが必要になります。次に重点施策です。売上げや数値評価を上げていくうえで、どこを押さえていかないといけないのか、これを決めていく必要があります。次に専門評価です。先ほどの重点施策を高めていくうえで、どのようなスキルが必要なのかということをこれに入れていく必要があります。そして、四つ目、組織行動です。全社員の共通の考え方です。よくありますのは、会社の中のクレドや行動指針でこの組織行動というかたちでこの項目に入れるケースがあります。最後、管理職の方に対しては管理職評価ということで、マネジメントができているのかや、施設の中の退職率を見ていくというような会社様もあります。
1個ずつ見ていきたいと思います。数値評価というところで、例えば売上や利益です。どうしても介護の業界や医療、また教育の会社様も今回ご参加いただいているかと思いますが、国の施策によって売上の計算式が変わってきているところもありますので、一概に安定的に増やしていくというのは難しいかもしれないですが、意識させていくというところは重要になりますので、ウェイトが小さくても項目として入れていくということをお勧めします。
次に、重点施策ということですが、私たちがお手伝いするときはこれを意識して作っていくことがあります。そのため、「見直し重要」と大きく書いています。つまり、スタッフの方に何をやっていただくのが一番結果につながるのか、コミットできるのかということです。例えば、スタッフベースでいいますと、ホスピタリティということで、日頃の業務のホスピタリティのレベル上げていくことです。また、利用者だけではなくて、利用者のご家族とかに向けた対応力を上げていこうということや、営業回数、営業補助ということで、新規獲得に向けて、やっていない会社様では行ってもらうために、このような項目を入れようということです。やはり重点施策の部分が、一番スタッフにやっていただきたいことをまとめているところになりますので、ぜひここの項目は都度、見直しをしていただけたらと思います。半期に1回や年に1回、項目を見直したり、基準を見直したりというのをお勧めします。
次に・・・
セミナーの講演内容と当日使用したテキストを無料でダウンロードいただけます。平均10,000文字を超えるボリュームの講演文字起こしとノウハウの詰まったテキストをご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?