
過去を捨てた女たち

プロローグ
銀座の路地裏の雑居ビルの一階の画廊店の奥の階段を降りていくと未来人Barと書かれている看板があり、その扉を開けると、まるでそこは異空間が広がる小さなバーがある。
そこに通い詰める客は、過去を抱えた女性達がほとんど。夜な夜な背負った過去を捨てにやってくる。
その女性達の相手をするバーテンダーは、少し初老の男性、まるで宇宙人のような雰囲気を醸し出している。
「いらっしゃいませ、どうぞこちらへ」
女性は、初めてらしく、戸惑いながら、カウンターに座った。
「何をお飲みになりますか?」
「何があるの?」
「何でもありますよ。お話する過去の思い出のお酒でも、新しいステージに、飲んだことがないお酒でも何でも」
「じゃあ、飲んだことないお酒を」「かしこまりました」バーテンダーは、様々なお酒を入れ、シェイカーに入れ、カクテルグラスに、ゆっくりと注いでいく。七色のようにも見え、透明にも見える、不思議なカクテルに見えた。
バーテンダーは、そのカクテルをその女性の前におき、
「未来人カクテルです」
その女性は、そのカクテルを少し口にすると、驚きの表情を見せた。
「美味しい!全く新しい味がする」
その女性は、その味に感動したのか、少し興奮ぎみに、過去の話しをし始めていく。
話しが終わると、カクテルを飲み切り、行きとは違う帰りの扉に案内され、帰っていく。
最初に来た時とは全く違う表情をみせ、その女性は去っていった。ここは、過去を話し、その過去を捨てにくる女性が通うバー。一つの過去を捨てる為には、その捨てたい過去をバーテンダーに話すと、一杯お酒が無料でサービスされる。お酒のセレクトは、自由である。もちろん、何度もくるお客様もいる。過去を捨てると、スッキリした表情になり、みんな未来人になっていくような感覚になっていく。
「いらっしゃいませ。今宵はどんな過去ですか?」
マスターが声をかけた女性は、白いワンピースに、真っ赤なハイヒールが一際目立った。
そして、肩まである黒い髪も印象的だ。
アジアンビューティーのような雰囲気があった。
さあ、彼女にはどんな過去があるのか。
聞き耳を立てようとしたら、バーテンダーに追い出されてしまった。ドアの外に追い出された黒猫は、仕方なく、階段の奥の隅に毛繕いをしながら、物語を想像しながら、眠りついていた。
1話 組織から自由になる

毎日同じ電車に乗り、1日のほとんどを会社で過ごす。それを何年してきたのだろうか。
雨の日も風の強い日も、けだるい暑さの日も。
休みたいと半ば思いながらも、休むこともせず、ひたすら我慢と根性で乗り越えていく。
辛い事があっても、泣きながら、悔しさを乗り超え、日常に戻っていく。
でも、それが当たり前だと思っていたのだ。
順子は、昔の自分も懐かしむように思い出していた。今乗っている電車は、都心に向かっているが、夕方の電車なので、がら空きだ。いまさらどこに向かうのだろうという目つきに攫われながら、ある場所に向かっていた。
白い無地のワンピースに、赤いハイヒールがよく目立つのか、通り様に振り返る人がいるくらいだ。女優にでもなったような気分で心地よかった。自由になるってなんて気持ち良いのだろうか。
有給もしっかりあったが、ここ最近なんか取りにくさを感じていた。何か理由がなくても、もっと有給を消化すればよかったのに。そんな事を、働いている時はぐるぐる頭の中で考えていた。コロナ禍になってからは、具合が悪くならない限り、そ有給の理由が見つからなく、引け目を感じて、ますます有給がとれなくなっていた。
でも、今は仕事を辞めてしまった。こんな時期にと思うかもしれないが、もう全てをリセットしたかったように思う。
久々の銀座を歩く。人通りもいない銀座の街を歩くのも気分がよい。
銀座の路地裏の道を入り、一階が画廊店のビルの地下に入っていく。そこにアンティーク調の木の扉があり、Barという文字が書かれている小さな看板がかかっており、順子は扉を開けていた。
バーカウンターしか無いところだ。順子は、そのバーカウンターの真ん中に座り、本日の赤ワインを注文した。そして、目の前にいるマスターに語りかけるように自分の思いを話していく。
組織の中に働いて、1番上の顔色を伺いながら、目立ないように生きていたが、それは自分にとって拷問に近いことだったのに気付いたからだ。
無難に働く。そつなく働く。
それは、みんながごく普通にしていること。
でも、生きている実感が感じられなかった。趣味を頑張ろうとか、プライベートを頑張ろうとか、そこに視点を変えればよいとは思い、舵を変えてみようとも思ったが、どうにもならなかった。鉛のような体は、行動を加速するエネルギーさえ、奪われていたのだ。
それでも、エネルギーがあがる場所や人もあり、そこで充電はされるものの、いつのまにか気力を失っていた。
いつも心の中で辞めたい気持ちが、顔をだす。
目標を失ってからの順子は、淡々に無難に仕事をこなす日々だった。それでも、わずかの望みをかけて、他の事をやり始めては、挫折し、結局今のお給料より稼ぐ事が無理な事に気づかされ、そもそも副業が無理なのに、おかしな話だと、ツッコミを自分に入れなながら、それは微かに都合の良い言い訳なのかもしれない。
でも、そんな日々を過ごしながらも、事態は決して悪い方向にいってはなかったような気がする。
コロナだ。世の中コロナで一変したのだ。確かに外回りが主な仕事は、ズームになり、在宅勤務も増えた。気晴らしができない環境に追い込まれたのだ。ある意味、人との距離感がとられ、人のエネルギーを受けずに済んだことは、自分の中で何かが変わるきっかけにはなっていく。
在宅勤務も最初のうちは、楽しめたが、だんだん憂鬱になっていく。結局、自分の中で、もう仕事が飽きているのだ。違うことをしたい欲望と、お金という餌を前に、しょうがなく我慢している家畜のように。
気晴らしは、映画やドラマなど、家にできるものに限られ、しだいにユウチューブの情報を楽しむようになり、さらに日本人として、日本女性として目覚めるきっかけの動画に出会うのだった。
私が得た感覚は間違っていない。この社会そのものが、世界を牛耳ってる社会の縮図で、一般市民は家畜だということに、だからこせ、そこから外れないといけないと。
それは、エサとしてのお金の価値観を根本から変えることに他ならない。お金は、エネルギーだとわかっていても、結局お金に支配されている自分に虚しさを感じていた。ただ、様々なユウチューブの動画をみて、いくつかの点が繋がっていく。
どこかで転職をしても、また別の組織に入るだけで根本は変わらないと思ったのは、そうゆうことなのか。他人からもたらされる、労働の対価。そのシステムこそが、ピラミッド社会であり、男ルールなのだから。
心の中で、組織から外れたい。この枠組みから卒業したい。今やっている仕事が嫌でもない。だからこそ、今まで人参というお金を前に、とりあえずその枠組みの中で働いてきたのだ。でも、魂の声の大きさは無視できなくなっていた。
確かにパラレルワールドはあるのかもしれない。
今いる異空間のような場所で、異星人のようなマスターに語っていた。
「自由になられたのですね」
「はい」
順子は、残っていたワインを飲み干し、
組織の中で鉛のようになってしまった原因の話は、また、この次かしらと言い、グラスを返すと、入る時に見かけた黒猫が自分の足元にいた。
ニャーと一鳴きすると、順子をエスコートするように、出口まで案内してくれていた。
順子は、扉を開けると、夜風が心地よく、ワインを飲んだせいか、ほろ酔い気分なせいか、自由になった鳥のように、軽く感じていた。
黒猫はまたニャーと鳴き、順子を見送った。黒猫も自由は最高さと言ってくれているように思えた。
順子は、不思議な感覚に襲われていた。
過去を捨てたせいなのか、出口が変わったせいなのか、見える景色が全く違って見えた。
パラレルワールドに移行したのかも。
もう自分が違う次元にいると思うと、この感覚も腑に落ちるような気がした。
そんな順子の後ろ姿を黒猫は見つめていた。

2話 パワハラのトラウマ

消耗という言葉が一番しっくりする。トップに逆らう事は、生命の消耗に近いぐらいエネルギーを消耗する事に近いからだ。そして、それは心の燻りとしてずっと燻り、スカッと解決できず、わだかまりが残る。
ドラマのように弱い立場の人間が、一発逆転のように行かず、さらに追い詰め廃人になる。廃人に友希はなりかけていたのだ。
友希の中に、従順でいなければと頭でわかっていても、心の奥底に、それが強い拒否反応があるからなのか、歯向かってしまう事があり、ただ圧力や権力に思い知らされ、結局萎縮してしまい、それ以上歯向かえなくなる。
想像の中ではできても、結局自分は損する役回り。倒す事はできない。倒せるヒーローをどこかに欲していたからなのか。いや、自分の正義を貫きたいのか、人の為に頑張りすぎてしまうだけなのか。つくづく損な性格だということを思い知らされる。
パワハラをするよういな人達は、自分の弱さを見限れないように、自分を守るために必死で、抵抗していく。こころの大きさや器などがあれば、怒りの感情は抑制できるはずだが、それができない人達が多い。自分の権威が脅かされるというほどに、お構いなしに怒鳴りつけてくる。
友希は、社長の怒った顔がフラッシュバックのように蘇ることがある。それは、目を大きくして、怒鳴り、またある時は、嫌味な言葉の数々で打ちのめす。それは、絶妙までに、かなり心が崩壊する。なんと言われて悔しかったのか、忘れてしまうぐらいに…
ただ、自分の頑張った分の悔しさも重なるから、余計に自分の心にトドメを刺すのだ。
この破壊力を、パワハラと言うのかもしれない。絶対的権力の前では、逆らわないが鉄則。頭の良い人達は、それをわかっており、逆らわない。周りをよく見て、器用に生きている。
不器用な人は、その匙加減を間違えてしまう。
そして、不器用までに生きにくくしてしまうのかもしれない。ただ、それは決して悪いことではなく、良い事なのだ。その環境に向いていない事がわなるのだから。
頑張ってきた自分が可哀想に思えてくるからなのかもしれない。気に入られるために頑張っているわけではないからだ。そうすると、そこに歯向かうエネルギーは途端に萎み、そこから逸脱しようと思えてくる。
トップの従順な犬になるように自分の魂を売るみたいな人は、男の人に多い。女性は、たまにいるかもしれないが、それは中身が男なのかもしれない。自分の魂を売れない人達は、もうこの恐怖から抜け出したいと思いのほうが強くなるから。
そこに歯向かう気力を失い、茫然自失のようになり、自分らしく生活するのにも時間がかかる。
ただ、後から見ればピラミッド構造から、抜け出すきっかけとなるのかもしれない。従順に生きることに違和感を持つ事で、全く別の扉が開くなのだから。
黙って聞いていたバーテンダーがボソッと聞いた。
「新しい扉は開いたのですか?」
「ええ」
そう友希は一通り話すと、マティーニを飲み干し、颯爽と出ていった。
パワハラのトラウマは、思いのほか時間がかる。
廃人のような鬱になりかけ、自分を取り戻す時間は結構な年月がいる。同じ会社にいるなら、PDSのような症状が出てくる。また、何が言われるのではないか、そんな恐怖に日々帯びえている。
そのうち対象が自分では無くなるのだが、他人に移っても、PDSの症状はなくならないのだ。
友希が職場を去れたのは、三年の年月が経ってからだ。すぐさま辞める選択もあったが、新しい所に行ける元気もなかったからだ。ようやく、自分を取り戻し、活力がでるまで、そのぐらいの年月が、友希の場合は必要だったに違いない。
もう、組織は懲り懲りだ。
新しい扉の先は、自分しかいない会社だ。個人事業主。いくらか蓄えはある。廃人のあいだ、お金を使うのも、面倒な時があったせいもあり、たまには無職の期間も良いだろう。
友希は、丸い月を眺めながら、初めて明日という日か憂鬱でない事に気づかされる。
明日が楽しみだと思ったのは、何年ぶりだろう
そう思うと、なんだかワクワクした気分になってきた。帰る足取りが、こんなに軽く感じれるのは、不思議な気分だ。心のしこりを捨てれたのは、大きい。もうパワハラのトラウマは卒業である。
オレンジ色のショールが月の明かりに反応して、金色に輝やいたたように見えた。元気よく歩いていく様は、きっと新しい世界には、怖い存在はいないのだろう。
黒猫をそんな事を思いながら、後ろ姿を見送った

3話 男女の価値観

再婚すれば幸せになる。それはやはり幻想に近いのかもしれない。
でも、不幸せではない。では、なんなのか。
互いの価値観の違いの認識なのかもしれない。
1回目の結婚は、自分の価値観を知る為のものだ。
2回目の結婚は、他人の価値観を理解することだ。価値観の違いは、決して悪い事ではないのだ。
聡美は改めてその事を認識した。それまでは、何で自分をわかってくれないのかばかりを相手に求めていたので、喧嘩が絶えなかった。2回目だからこそ、幸せにと思うからこそなのか。
夫の直樹もやはり2回目の結婚にどこかお互いの理想を重ねていたのかもしれない。
聡美は、人が変われば自分の価値観を理解してくれていると思っていた。
人が変わっても、自分が持っている価値観が大きく、固定化する。自分のワールドに、他人のワールドの許容が難しくなるのだ。
それは男も女も同じである。そして、好きだからこそ、自分のワールドに取り込みたくなる習性があり、衝突する。
全く違う世界で生きている。
そう理解して接したほうが、はるかに楽な事を、何回も喧嘩して傷ついた後に理解する。
別れるか別れないかは、相手のワールドを理解し、一つでも共有するワールドがあるかないか。いや無くても、理解できれば、それはそれなりに長く続くかもしれない。理解というより、認識にちかい。あくまでも妥協ではない。
どちらかがとりこもうとするとそれは支配になり、どちらかがその支配に従うと、それは共依存になる。それはお互い1回目の結婚で嫌というほど味わったからだ。
いわば、本来なら同志に近い。
なのに結婚をすると、お互いの理想の夫像や妻像があり、それをお互いに嵌め込もうとする。
でも、相手に合わせてそこを頑張ろとすると破綻するのは、1回目で学習している。
だから、2回目は、お互いの自己主張が強くなる。
私は私
俺は俺
その争いから、先に抜けだしたのは、聡美だった。理想の結婚や理想の夫は、もう諦めよう。
直樹は、直樹で、はるかに自分の理想とはかけ離れる。でも、再婚したのは、好きだから。
喧嘩しても嫌いにはなれなかった。
それが聡美が出した答えだった。
1回目の結婚は、そこのシンプルな所が若さ故に欠落をしていた。好きではないのに、結婚を継続してしまったからだ。だから、嫌いな理由がたくさん出てくる。
直樹の場合も、嫌いな所はたくさん出てきた。
好きな理由は、曖昧な理由が多い。
笑顔や安心感などぐらいしかででこない。
でも、別れの選択はない。
何故ならば、お互い一人の時間を、お互いに持つ事を意識し、結婚という固定概念を外したからだ。
今日は、聡美の一人の時間を満喫している。
オシャレをして、お酒を飲む。
それができるようになったのは、2回目の結婚も決して悪いものではない。
直樹ありがとね。
聡美はそう心の中で、夫に感謝しながら、
目の前にあるシャンパンを飲み干した。
そして、空になったバーテンダーに差し出し、おかわりを催促した。
グラスに注がれるシャンパンの液体を眺めながら、聡美は、第二の人生を楽しんでいることを
ようやく感じられてたのかもしれない。
シャンパンを飲みながら、聡美は改めて1人の楽しさを味わっていた。
黒猫は、毛繕いをしていた。
目の前を二匹の猫達が通りすぎていた。
一瞬自分が追いかけた雄猫に似た雰囲気の猫だったせいか、毛繕いをやめ、二匹の猫をそっと見つめていたが、黒猫は、ふとまた目をそらし、自分の毛繕いを始めた。
それはまるで、聡子がシャンパンを1人で味わう幸福と同じように、黒猫も毛繕いの幸福を味わっていた。

4話 子育ての呪縛

良い母親、愛情深い母親とはどんなものなんだろうか?子育てをし始めてずっと拭えない疑問。
てがかからなくなっても、そこはずっあった。
きっとそれは、自分の母親がその理想からかけ離れてたせいなのかもしれない。良妻賢母とはかけ離れた母親だが、虐待する母親ではなく、愛情もあるんだと思う。でも、母親としては何かがかけており、それが何なのか言葉には言えない。
そんな母親から育った自分は、まさにそんな母親像になっているのかもしれない。虐待やネグレクトまではいかない、愛情はある。でも、他のお母さんに比べてて愛情は薄いのかしらと首をかしげる事が多い。我が子なんだけど、我が子の感覚が人より他人事なのだ。
夏美は、そこの感覚をすごく不思議に思っていた。早く巣立って自立してほしい。シングルマザーになってもその感覚は強い。ずっと側にいてねという気持ちはさらさらないのだ。
夏美は目の前のバーテンダーに問いかけた。
「私は冷たいのだろうか?」
「そんなことありません。でも、ビールは冷えた方が美味しいから」
そう言うと、冷えたグラスにビールが注がれる。
「自慢のクラフトビールです」
夏美は、フルーティな味わいのクラフトビールを半分ほど飲み干した。
夏美は、再婚した夫に言われた事を思い出していた。私の子育ては甘いらしい。ただ、その事が愛情深い母親像との一致ではなく、子育て下手だからこそ、甘く感じるのかなと、最近ようやくわかったような気がする。
ただよくちまたのイメージの、
つい甘く育ててしまうのよね
息子は可愛いとか、
目に入れても痛くないほど可愛い
そんな感情はあまりない。
でも、なんか乾いた感じを抱きながら、子育てを続けてきた。もちろん真剣に怒ることも、お弁当を作ることも人並みに子育てしてきた。
もちろん、愛情がないわけではない。
愛し方が下手なのかもしれない。
それが子育てという呪縛となり、
自分を苦しめていたように思える。
もうすぐ息子は20歳になる。
このご時世、就職はまだ先になりそうだ。
でも、そのうちなんとかなるだろうと思っている。その感覚がそもそも他人事らしいのか、甘いらしい。
私はわたし、息子はむすこ
それ以下でも以上でもない。
ただそれだけ。
夏美は、そういつもいい聞かせている。
やはり変わりものなのかもしれない。
息子も夫もいないこの1人の時間は、夏美は好きてある。
そして、夕方のこの時間を好きなクラフトビール飲むひととき。
半分残っていたビールを飲み干した瞬間、ほんの少しだけ呪縛から解放されたように気がした。
それは、今までそれなりにしてきた子育てに対する労りのご褒美。そして、1人の時間を愛せるようになったご褒美でもあるのかもしれない。
さあ、私の時間を楽しもう。
バーの外では、やはり1人の時間を楽しむように、黒猫も夕日を浴びながらまどろんでいた。
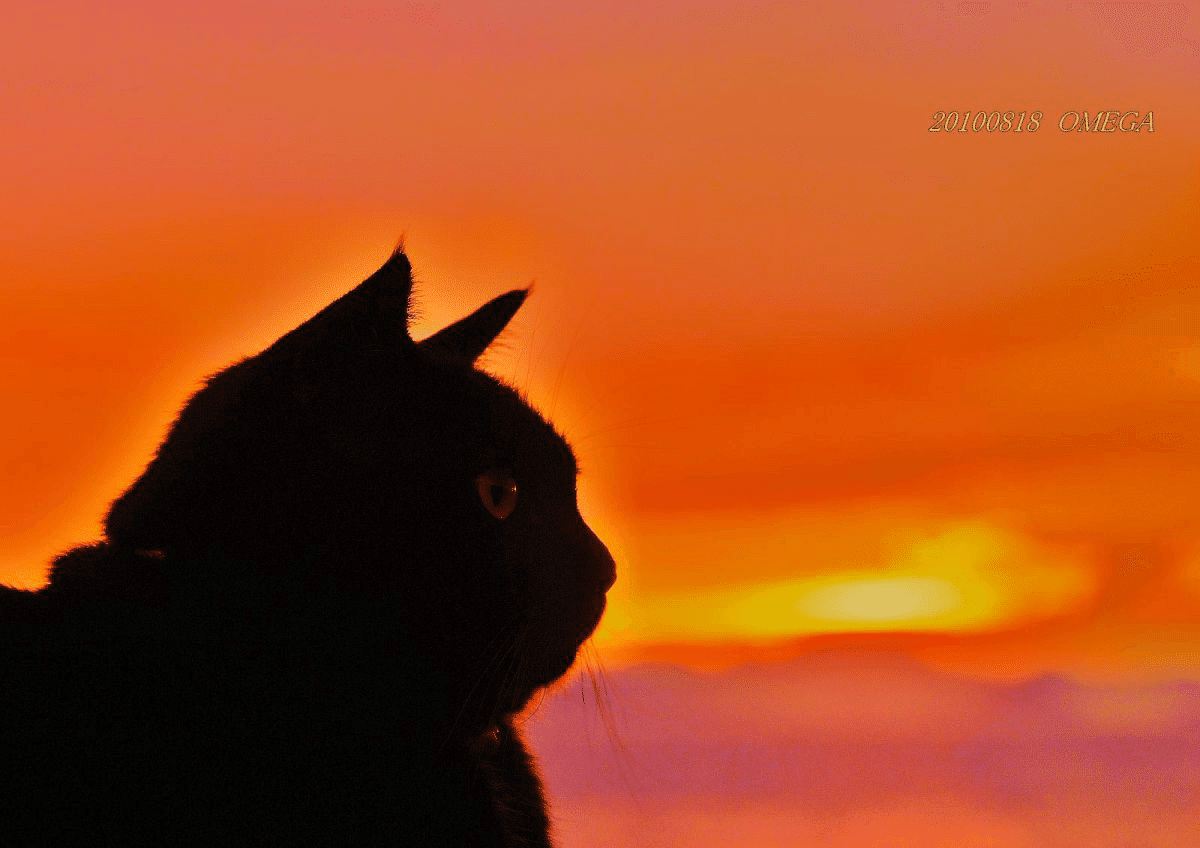
5話 不幸せの詰め合わせ

人生辛い時は、辛いことのてんこ盛りになるのは何故だろうか。
別居に、職場のいじめに、子供の発達障害発覚など、一個ずつとっても大変なのに、どうにかなるくら気が狂いそうになるが、今思えばよく耐えたなって思うが、なんかそんな時は、何故だか乗り切れる自分が嫌になる。だか、それさえも記憶が消してくれる。人間とは、よくできている。
幸子と書いて、幸せな子なのに、笑うしかない。
不幸を引き寄せていた?と言われればそうなのかもしれないが、この頃はそんな事を考えている暇などないのだ。
一つずつ解決しながら、生きていった。
そんな感じだ。
よく頭や心がおかしくならなかったのかなって。
でも、必死という言葉が一番似合う時代なのかもしれない。
モラハラな旦那と噛み合わない電話のやりとり、しょうもない介護デイサービスの陰険ないじめ、その頃癒されていたのは、そんな自分を暖かく見守ってきてくれていた老人達だった。
また療育の場でさえ、なぜか癒しの場になっていた。今思うと当時のママ達がなんと思うのだろうか聞いてみたいものだが、周りがどう思われるより必死に生きる術を模索してきたのだろう。
ただもう限界!、耐えらない、そう思ったら、不思議と一つずつ解決していく。いじめをしていた主犯の人達は、職場を離れていく。そしてその人達を涙でお別れを惜しんだ老人達は、涙も乾かないうちに、幸子の耳元でそっと、ささやく。
「あんたいじめられてただろう。居なくなってよかったね」
そして、思ったより、早く離婚も成立していく。
介護福祉士も受かった。
それでもやはり、悔しい思いを思い出す。デイサービスの風呂場で涙ながらに掃除して、床に涙が滲む場面を、とりとめのない電話攻撃におびえ、着信の音にビクビクしていた時を。
でも、それは継続はしない。
自分の中に、もう嫌だと、魂の叫びを、
それはちゃんと、届いているのだ。
だから、解決されていく。
ある人は、それを神様の仕業とか、
ある人は、波動が変わったとかいうが。
用は、嫌だという自分の思考が、宇宙に届いたのだ。
今あの当時の不幸の詰め合わせを感じていたならば、一瞬で即死かもしれない。
今では、ちょっとしたマイナスでさえ耐えられなくなっている。
もう、不幸の詰め合わせは懲り懲りだから。
ただ、今でも、記憶に残っているのは、老人の笑顔と、新しくなる新居の部屋に入った瞬間の喜び。
それは幸子をある意味強くされていたのかもしれない。
だか、今は強くなる必要もない。
無邪気な自分がいればそれでよいのだから。
バーテンダーが、そんな時期があったようには見えませんがといってくれ、よく冷えたシャブリの白ワインをだしてくれた。
サッパリした辛口の白ワイン。
それは、まるで、幸子の過去をバッサリと消してくれるような後味がした。
もう、過去はいらないのだから。
バーにいた黒猫は、幸子に向かって
ニャー
と鳴いてバーを立ち去った。
後ろ姿が凛としており。しっぽもピンと立っていた。まるで、僕も同じだよと言っているかのように、そんな過去は、人生の助走に過ぎないと言ってくれているような気がした。

6話 雨の日の決意

雨が激しく叩きつけるような中でも、息子にカッパを着せて自転車の荷台に乗せて、聡子はカッパきて雨の中を走りぬける。
保育士さんの言葉が頭の中にこだまする。
もっと旦那さんに頼っていいのよ
1人で頑張らないで。
頼れるなら、もうとっくに頼っている。
口では、何とでも言うが、何にもしてくれない。
いや、それをするとかなり面倒臭いのだ。
君が仕事を休めばすむことでは?
僕は毎日忙しいんだよ。
その言葉に抹殺される。
だから結局、頼らない。
いや、頼れない。
どんなに大変でも、なんとかして保育園に行かせる。病時保育園を利用する
たかが非常勤だが、されど非常勤。保育園に入れたのだ。仕事を辞めるわけにはいかない。
仕事はある決意の源になるからだ。
どんなに大変でも、辛くても、旦那に頼らないために。旦那と別れるために、必要不可欠だからだ。
雨の中、余計にその決意を胸に刻みながら、
保育園に向かう。時折、雨のしぶきが、
目に入る。それでも、自転車を漕ぐことはやめれない。
聡子は一通り話すと、注文してたジンライムを手にして、一口飲んだ。サッパリとして味が、口の中に広がる。
ふとバーテンダーは聡子に聞いた。
「雨は嫌いですか?」
「今は嫌いではないわ。むしろ好きよ」
聡子は、そう言うと残りのジンライムを飲み干した。
「不思議ね、ずっとその残像が残っていたんだけど、話したら本当に捨てたような感覚になったわ」
外にでると、まるであの時の雨の激しさになっていた。傘をさしても、雨が斜めに降っており、洋服を濡らす。
でも、あの時の悲壮感も、頑張りも今はない。
あるのは未来だけだから。
そう改めて感じながら、歩いていると、雨は次第に弱くなり、向こうの雲から晴れ間が出てきた。
黒猫は、雨の上がったのがわかっていたのか、バーの中にいたのにいつの間にか外に出てきた。
晴れ間の光が聡子を輝やかせているようにキラキラと眩しくみえ、黒猫はそんな聡子を見送りながら、またそっと目を閉じた。

7話 妊娠の憂鬱

理佐は、自分がこんなに妊娠をして、憂鬱になるとは思わなかった。離婚を回避したとき、確かに子供さえ生まれれば夫婦も関係が良くなるかもしれないと、微かな期待をしたのもあったが、それが現実となると、また違った感情が生まれたのだ。この子を愛せるのだろうか?ちゃんとした親になれるのだろうか?不安だげが大きくなる。
やはり、離婚をしておけばよかったのではないか。そもそも、何故結婚をしたのだろうか?そこから間違っているように思えてならない。
ただ、そこまで思うと生まれくる子は不憫である。自分が決めた事だ。全て自分が責任を負うしかない。結婚も妊娠も、母が祖父から言われた言葉を、理佐自身もなぜか頭にこびりついている。
まるでそれは呪いのように。
一度は結婚してみるものだ
一度は子供を産んでみるものだ。
結婚も子育ても、どこか自分には向いていなく、一生独身なのかもと、なんとなく思っていた理佐に、その言葉何となく引っかかっていた。
だから、本当に好きな人より、自分の事が凄く好きな人のほうが、幸せになれるのかと思っていた。
人並みの幸せを夢みながら、魂の奥では、本当は人並みを求めていない。それを見透かされた言葉だったからなのかもしれない。まずは、試してみないと、若いのだから。
それが教訓だと思っていたが、後から呪いの言葉になるとは…
妊婦は、幸せ感に満ちている。たぶん、それもどこからかの刷り込みでしかない。
妊娠の姿を見るたび、妊婦だった頃の憂鬱感をふと思い出した事がある。
ただ命を宿る神秘もまた尊いのも事実であり…。
唯一妊娠になって幸せを感じた時は、実家に里帰りした時だった。あ、これが私が求めていた家族の食卓。小さな時は得られなかった風景が、今目の前にある。繋ぎとめてくれたのは、このお腹の子のおかげである。
仕事や家事からも解放され、唯一ゆっくりとした時間が取れたのもこの時期で、もう憂鬱な妊婦ではなくなっていたからだ。
そんな妊娠の時の事を思い出したのは、生まれた子は自立し、巣立っていったせいなのか?それとも、
そう話した時に、バーテンダーの手が止まりかけたので、
慌てて、今は妊娠してないですよ。
それを聞いて、またバーテンダーは、シェイクをし、塩のついたグラスにシェイカーの中身を注ぐ。ソルティドックだ。
若い頃よく飲んだカクテル🍸だ。
もう、妊娠の憂鬱の懺悔は、今日でおしまいにしよう。あの時の心情が、お腹の子に影響したのかもと、子供の発達の遅れを感じた時に何度も罪悪感に襲われていた。でも、もうそれも卒業だ。
ちゃんと巣立ったのだから。
理佐はソルティドックを飲み干し、未来と書かれている扉を開けていた。
8話 悲壮感の花嫁

よく友達に、結婚式やハネームーンの写真を見せるとよく言われた言葉。
幸せの結婚式の写真は、悲壮感が漂っていると。
でも、それは友希にとっては、正しい表現のように思う。22歳という若さで結婚を決め、やり直しがきくとはいえ、本当にこの隣りの人と結婚をして良かったのかと。
マリッジブルーみたいな感覚は、結婚をしてもなお続いた。
結婚をする前に、別れのタイミングは何度もあった。しかし、その別れのタイミングに、別れという選択が出来なかったのは、友希が良い人であろうとした、良い人でないといけないという呪縛があったからだ。
別れを切り出すと荒れ果て、まるで友希自身が悪い人というような感覚に陥ったのだ。もしかしたら、それがモラハラの始まりだったのかもしれない。容易に被害者のように罪悪感を感じさせるのが上手で、ただ気持ちが離れてだだけなのに。それはもの凄い悪いことをしているような感覚になっていたのだ。廃人のようになってしまう恋人に、よりを戻す選択肢しかなかったのだ。
後から離婚になる結婚は目に見えていたはずなのに、わざわざ苦労する道を選択していた過去の自分をなんて愚かなのか。初めてモラルハラスメントという言葉や現象の文章を読んだときは、もう子供もいたが、限界に達していた。だから、このモラルハラスメントという現象や、モラハラ夫という言葉は、自分が悪いとか、罪悪感を感じていた友希にとって、救いのような言葉だったからだ。そして、二人目だけは身篭ってはいけないという、境界線が正しいかった事も、今思えばストッパーだったんだ。離婚を決意してからは、
弁護士をたて、離婚した。離婚さえも過去の自分になりつつある。
友希はバーテンダーに話しながら、最後にこう締めくくった。だからね、悲壮感ただよう花嫁写真を塗り替えたくなったのよね。
マスターは、カシスソーダを友希に手渡した。
懐かしい味が蘇る。
また結婚されるのですか?とマスターは素朴な質問してきた。
友希は苦笑いをしながら、結婚ではなく、花嫁写真を撮り直したいのよ。
最高の笑顔の写真で、旦那様は不在でよいの。
今流行りのソロ活よ。
これから、撮りに行くの。
友希は、カシスソーダを飲み干し、颯爽と出ていった。悲壮感というものは、今の友希には感じられなかった。
そんな姿を黒猫はバーの隅で佇みながら、見送った。

9話 いじめられた記憶

人は、いじめた記憶より、いじめられた記憶のほうが残像に残りやすい。
佐和子は、いじめられた記憶がたくさんあるが、一番小さい頃に受けた記憶が今でも鮮烈に覚えている。保育園にいたときに、蕎麦屋のゆみちゃんといういじめっ子がいた。
おままごとをすると、ペットか赤ちゃんの役しか与えてくれず、嫌な思いをしていた。それでも佐和子には、みっちゃんという一応助けてくれるヒーロー的な男の子がおり、いつもみっちゃん達と遊ぶ楽しい記憶もかすかに残っている。ゴレンジャーゴッコなど、ヒーロー戦隊ものにはからり出されていた。今良い風に記憶を改ざんすれば、きっと蕎麦屋のゆみちゃんは、自分に嫉妬していたのかもしれない。本当はピンクレンジャーになりたかったのかもしれない。
ただ小さい時の佐和子にとって、そんな事などは思いつかず、ゆみちゃんと遊ぶといじめられるという悪循環しかなかった。
そして、今だと大問題になる事件が勃発した。
佐和子は、ある日外の遊具のタイヤの中に閉じ込
められたのだ。ゆみちゃんだけではなく、きっと何人もこのタイヤ閉じ込め作戦に協力した子はいたのかもしれない。どんどんタイヤが高くなるに連れて、絶望と諦めをもうこの2.3歳で感じてしまったのかもしれない。怖くて泣いていたのか、どうしていたのかあまり記憶にないが、お散歩にいこうとした保育士さんが気づき、保育士さんに救いあげられた記憶は残っている。
一番最初の保育園ではなく、二番目の保育園で環境も全く違う環境の保育園だったからと、母は言っていた。生まれた頃の保育園では、我が強く、気が強い一面のほうが目立っていたらしい。
あまりにも環境が変わり、大人しく泣き虫な佐和子が出来上がったのは、二番目の保育園だった。
そんな小さな記憶を今でも持っている。
いや大人になってからも、いじめられる事があると、そのタイヤの中に閉じ込められた記憶が蘇る。でも、やはり我が強い面もあるから、大人になると巻き返しみたいな事や、相手を挑発する強さもあった。
もう、いじめられる事じたいなくなり、そんな世界にいた事さえ忘れてしまうが、そんな記憶も捨てたい過去の一つなのかもしれない。
バーテンダーが、梅酒のロックを佐和子に持ってきてくれた。小さい頃、この梅酒を食べて酔っ払った記憶がある。きっと幼心に忘れたい記憶もあったのかもしれない。
そう思うと、佐和子の中にあるインナーチャイルドがなんとなく癒されていくのがわかってきた。
小さな自分も、結構辛かったのねと。
梅酒の梅を一口かじり、そのアルコールに浸かった梅の味の余韻を静かに味わった。
梅酒の梅の種を空いたグラスいれ、佐和子は、なんだか満足した気分になり、未来へという扉を開けていた。
黒猫がそこにお出迎えしてくれていた。
10話 幸せな家族の幻想

一般的な家族とは?
核家族が当たり前な時代、それが幸せな象徴と言われ続けていたが、今、本当にそうなのか、ようやく疑問視されてきたが、美佐子の幼少時代は違った。
絵に描いたような核家族が当たり前の時代。
美佐子の家庭は、核家族ではなかった。
今でさえ、障害者のグループホームがたくさんある時代になったが、美佐子の時代は、そんな名前すらなかった。
我が家がグループホームになったのだ。
小学校一年生といえば、まだ両親の愛情をたくさんもらう時期だか、美佐子の場合は、その愛情は、見ず知らずの変わった人達にとって代わってしまった。
どんなに学校生活が灰色でもバラ色でも、両親にはさほど関係ない。
変わった人達の日常が常に関心ごとであった。
知力が美佐子と同等の時は、美佐子もその変わった人達に食ってかかったが、美佐子のほうが知力が上になると、そうゆうことも馬鹿らしく思え、距離を置いた。
周りの人達は、凄い事をしていると両親を褒め称える。頭で理解できる年頃になると、心は置いてけぼりなわけだから、このチグハグ感を埋めるには、両親に反抗するしかなく、そのうちに、このグループホームを家庭に持ち込んだ父親が自滅した。気づいた頃には家族は破壊した。
ただ、かりにグループホームをしていなかったら、家族は破壊しなかったのか…。
幸せな家族は崩壊しなかったかもしれない。
たらればの話しだ。
美佐子は、バーテンダーにそんな話をし、笑った。
「何を飲みますか?」
「にごり酒」
少しびっくりしたバーテンダーに、美佐子は付け加えた。
「初めて飲んだというか、味見したお酒は、にごり酒だったから、それも小学校の時にね笑」
白く濁っているが、光を当てると七色にも見えた。この過去があるから、今がある。
思春期の頃は、その環境を否定した。
そして、大人になり、その過去をも受け入れていた。
自分にも家族ができ、いびつなために、離婚をしたり、シングルになり、子育てや仕事に葛藤し、破壊と再生を繰り返しながら、息子は成長し、巣立っていった。
再婚した夫はいるが、新しい家族を再び構築するには、夫の家族の象徴もきっと違うんだなって、今ならわかる。
もう、家族の象徴という縛りから、卒業する時期なのかもしれない。
黒猫が美佐子を手招きしたようにみえた。
出口の扉が新しい扉のように見えた。
あるべき形の家族なんて幻想にすぎない。
幸せの形は人それぞれなのに、それを刷り込まれすぎたから、
生きづらかっただけなのだ。
愛情に飢えているという錯覚は、単に自分を愛する方法を知らなかったからだ。
今なら自分を愛し、自分の尊厳を大切にできるから。
美佐子は二杯目をバーテンダーに、オーダーした。
今度は、辛口の日本酒だ。
グラスに、透明な日本酒が注がれる。
さあ、人生はまたまだこれからだ。
もう人生のにごりはいらない。
透明な輝きを放つために、一歩前進していくのだ。
辛口の日本酒を飲み干した美佐子は、颯爽と出口を後にした。

エピローグ

バーテンダーは、ドアにクローズの看板を立てかけ、その場を後にした。
黒猫は店から出ると、満月の光に照らされ、
少し眩しそうな表情をした。
そんな黒猫の横を涙目の女性が横切った。
その女性にむけて言ったのか、
独り言なのか、黒猫は語りはじめた。
過去はたいてい良いように塗り替えられ、素敵な思い出として保管される。
あるいは、消し去りたいと思いなかったようにされ、自分の中で風化し、忘れてしまう。
肝心なその頃の感情までもが記憶から消し去っていくが、過去のネガティブな感情は、血や骨となり蓄積されていく。ある人は気づかず、脂肪として蓄え、人の念までも蓄えてしまうのだ。
だから、歳をとると行動も思考も鈍くなり、周りを羨み、歳をとることを不幸に思い、過去の栄光だけを美化して、過去に生きてしまう。
今を生きることを忘れてしまうのだ。
未来がくることさえわからなくなる
いらない過去、ネガティブな過去の思いは、正直に吐き出して、捨てるにかぎる。
過去を聞いてくれるバーテンダーも黒猫もいなくても、大丈夫。
他人に話す必要もない。
ノートと鉛筆さえあれば、過去の事実や感情を書いて破り捨てればよいのだから。
その後に自分の好きなお酒を用意しとけば、
そこは、あなただけの不思議なバーになる。
きっとあなたを新しい道へと手招きしてくれる
黒猫を見つける事ができるはずだから。
さあ、余分な過去=脂肪をすてないと、養豚の呪いにかかってしまいますから。
あ、それはまた別のお話でしたね。
満月の光に眩しそうにしていた黒猫は、一通り話すと、雑踏の街の中に消えていった。
涙目の女性は、黒猫の言葉が聞こえたようで、もう涙目にはなっていなく、満月の光をあびながら、大きく深呼吸をし、そして、毅然とした姿勢で歩きだしていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
