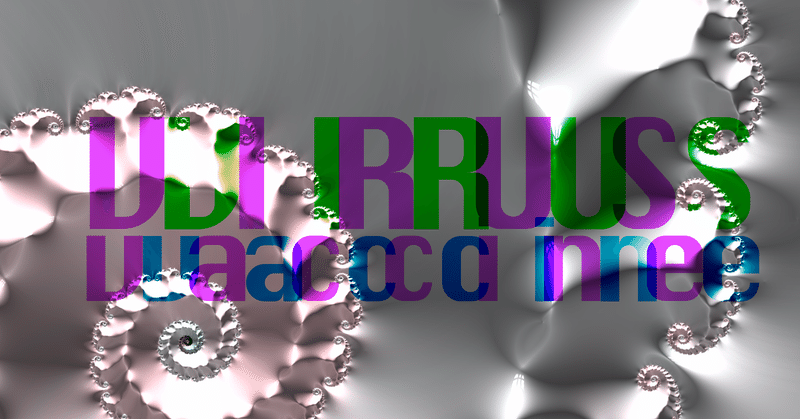
VIRUS/VACCINE
コロナに対抗するワクチンとして従来のBCGワクチンが有効であるという報告があったりすると、素人目には本当なの?という気持ちが強くあると思う(もちろん、専門家が高い有用性を証明してくれるならすがりたいのだが)。
アイザック・アシモフの著書「生物学の歴史」は有史以前から現代までの科学の発達を順を追って説明した、特に生物学に関係する事項をフォーカスして詳細に説明した名著である(ちなみに科学全般の歴史は「化学の歴史」という著作がある)。科学の歴史を詳しく知らなければ驚きだと思うが、1807年、19世記初頭にようやく「有機物」と「無機物」の区別が出来たぐらい、その開明は最近のことである。その後「細胞」と「染色体」が観測され、生物はすべからく「細胞」から出来ていてその分裂により「成長」することが判明した。そしてメンデルやダーウィンにより「進化論」が芽生え始めてもなお「生気論」(生物には「生命」の力で動いている的な)が生き残っていたが、今や常識であるが酸素と炭素により火が燃える現象と同じように生物の中でも炭水化物・脂質・たんぱく質が燃焼(火は出ないが)することによって同量のエネルギーとなることが確定し、無機物と有機物のエネルギーの取り出し方は同一であるという、エネルギー保存の法則が支持されたのは1894年であり、それによって生物に特別な力を想像する余地は無くなった。
第九章「病気との闘い」「種痘」に現在の本件に関する興味深い記録がある。「ワクチン」の誕生である。関係箇所をおよそそのまま引用する。
人類を苦しめた病気の中で最も悪いものの一つ「天然痘」がある。それは鬼火のように広がり、三人に一人の割合で殺しただけでなく、生き残った人々でさえ不幸にした。というのは、その人々の顔は他人が見るにしのびないほどあばたができ、傷跡が残りやすかったからである。
しかし、一度天然痘にかかると以後は免疫ができた。それゆえ、ほとんど跡が残らないくらいのごく軽い天然痘の場合は、全く羅病しないよりもはるかに良かった。前者の場合には、その人は永久に安心であり、後者の場合には常に脅威にさらされていた。トルコや中国のような国では、軽い天然痘にかかった人から病気をうつすことが試みられた。軽症の天然痘でできた水疱からとった物質を慎重に感染させることさえした。危険率は大変なものだった。なぜなら、時々、うつされた病気は新しい病人にとって全く軽症ではなかったからである。
十八世紀の初めに、そのような摂取をすることがイギリスに導入されたが、真に普及はしなかった。しかし、そのことはうわさで広まり、議論された。そして、イギリスの医師ジェンナーはその問題を考え始めた。彼の故郷グロスターシャに、牛痘(ある点で天然痘に似ている、ウシが普通にかかるおだやかな病気)にかかった人間はその後牛痘ばかりでなく天然痘に対しても免疫ができたという趣旨の老婦人の話があった。
ジェンナーは注意深い観察の後に、これをためしてみようと決心した。1796年5月14日、彼は牛痘にかかった乳搾りの女をみつけた。彼は彼女の腕の水疱から液体をとり、少年に注射した。もちろん、少年は牛痘にかかった。二ヶ月後、その少年に牛痘ではなく、天然痘をうえつけた。少年は天然痘にかからなかった。この実験を繰り返した後、1798年に彼はその知見を発表した。その技術を記すのに、彼は「種痘(”vaccination”)」という語を作った。これは牛痘という意味の”vaccinia”というラテン語に由来したもので、”vaccinia”というのはウシを意味するラテン語の”vacca”に由来している。
進歩が一度だけで歓迎され、何の疑いもなしで受け入れられたほど天然痘への恐怖は大きかった。種痘はヨーロッパ中にまたたく間に広がり、この病気は征服された――
「生物学の歴史」アイザック・アシモフ/太田次郎 訳
しがないフリーのクリエイーターですが、どうぞよろしくお願いしいたします。
