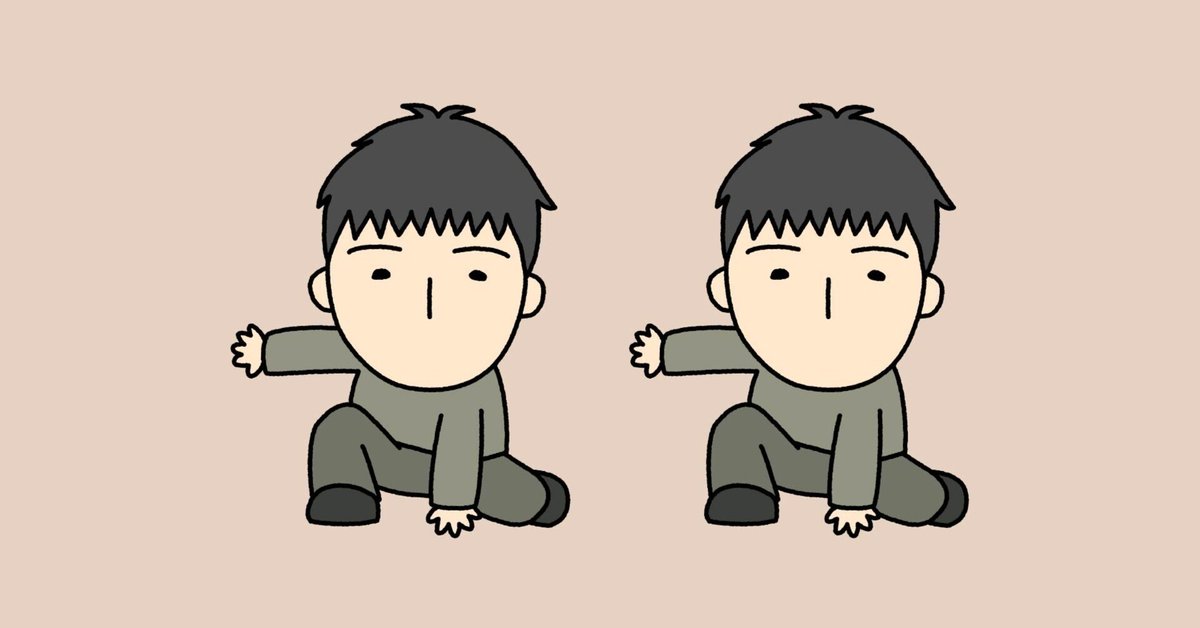
サンフランシスコに行ったことのないアメリカ人
何気ないエンジニアとの会話だった。そのエンジニアは生粋のアリゾナっ子で(白人のアメリカ人)、名をカーソンと言う。30歳前後の天才エンジニアだ。オフィスの中で一緒にランチをしながら「週末なにするの?」ということについてカジュアルに話していた。
ぼく「サンフランシスコに旅行に行ってくるんだよね」
カーソン「へーいいじゃん」
ぼく「やっぱりアメリカに住んでいるとサンフランシスコとかはよく行くもんなの?」
カーソン「いやーおれいったことないんだよね、サンフランシスコ」
ぼくは結構驚いた。「え、アメリカに生まれてこの方ずっと住んでるのにサンフランシスコみたいな大都市に行ったことがないんだ!」と。
ただ実はそんな会話をその後何度も他のアメリカ人ともした。その度におもしろいなーと思った。
日本で国内旅行に行かなかった自分
でもあることに気づいた。そういえばぼくも日本に住んでたときにほとんど自分が住んでいた県を出ることはなかったなと。思えば訪れたことがあるのは、北海道、大阪、京都、石川、福岡とかそのぐらいだったりする。逆に言えばほとんどの都道府県を訪れたことがないことになる。
この問題について(まあ問題と言うほどではないけれど)少し考えてみることにした。
日本に住んでいたときのことを振り返って思う。飛行機や新幹線を使えば簡単に国内旅行なんてできたんじゃないか?海外旅行に比べてずっと安いしお手軽に行けるわけだし。
翻ってアメリカに移住した後のぼくは暇を見つけてはアメリカのいろんな街に旅行しにいっている。もちろんお金はかかるけど日本に帰ったりヨーロッパに行ったりするよりも全然お手軽にいけちゃうからだ。なんなら「まあまあお金かかるなー」と思う時だってムリしてでもアメリカで国内旅行している自分もいたりする。不思議だ。
なんでアメリカにいる今はこんなにフットワーク軽くどこでも行くのに、日本に住んでいた時はどこにも行かなかったのだろうか?
「外国人」であることの効用
ここに一つの仮説が浮かび上がる。それはぼくがアメリカに住んでいる今「自分は外国人なのだ」という強い自覚があるからだということだ。
「ぼくはこの国についてなにも知らない」と思っているからこそ、この国の色々な場所に行って自分の目で確かめたくなるのだ。
逆に言うとぼくは日本にいるときは「日本のことは分かっている」という認識があったように思う。日本で生まれ育ったから仕方ないと言えば仕方ないかもしれないが。いずれにしろ「地方には地方の魅力があるだろうけれど、日本である限りはぼくは既に大枠を把握している」という気になっていたのだ。要は"知ったかぶり"というやつだ。
この感覚の違いは日本と海外で両方暮らしたことがある人なら頷いてくれるかもしれない。
「外国人」として学ぶことの大事さ
知らないということを強く自覚しているからこそ、知ろうとするんじゃないか。そしてこの態度というものは何においても大事じゃないか。そう最近思ったりした。
仕事においてもプライベートにおいても。ある程度経験を重ねると「はいはい、このパターンね」とか「こういうものですよね」という認識がどうしても作り上げられてしまう。でもそれは思い込みに過ぎなくて、いわゆる「井の中の蛙、大海を知らず」ってやつだったりする。例えばぼくが好きなジャズ一つとっても「大体こういうもんよねー」と思っていたら、調べてみると「こんな曲もあるんだ」とか「こんなアレンジをした人が過去にはいたのか」というのがいくらでも出てくる。その探究に終わりはない。
哲学の父ソクラテスは「無知の知」という言葉を残している。ソクラテスは「人間の本質は"なんでも知っている"というところにあるのではなく"なんでも知ろうとする"その知的態度にこそあるんだよ」というようなことを言いたかったのかもしれない。つまり「それを知っている」というよりも「それを知らない」と思っている人の方が学びを続けられるから強いみたいなことだと思う。
色んな分野で「外国人」として学ぶことって大事だなーと思う。そんな今日この頃です。

今日はそんなところですね。旅行で訪れたサンフランシスコにて。海の近くのカフェでコーヒーを飲みながら。
それではどうも。お疲れたまねぎでした!
サポートとても励みになります!またなにか刺さったらコメントや他メディア(Xなど)で引用いただけると更に喜びます。よろしくお願いします!
