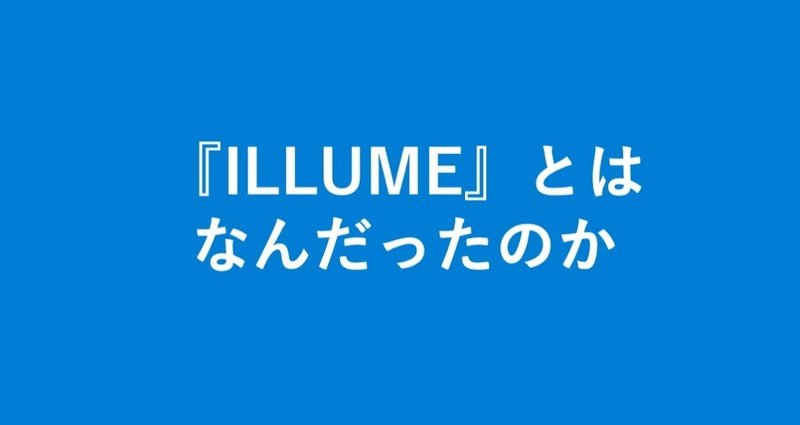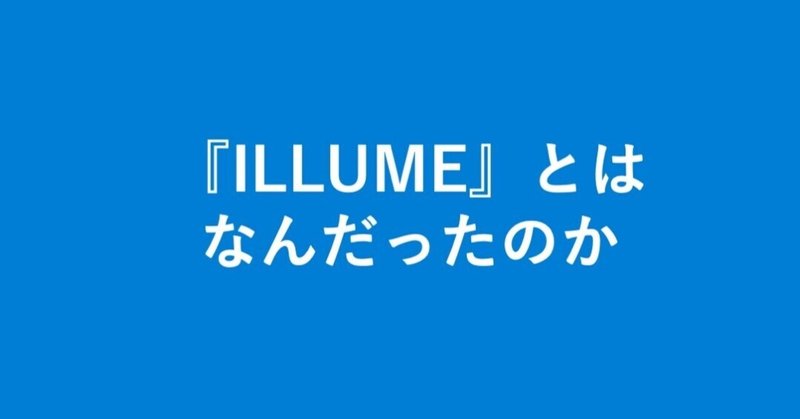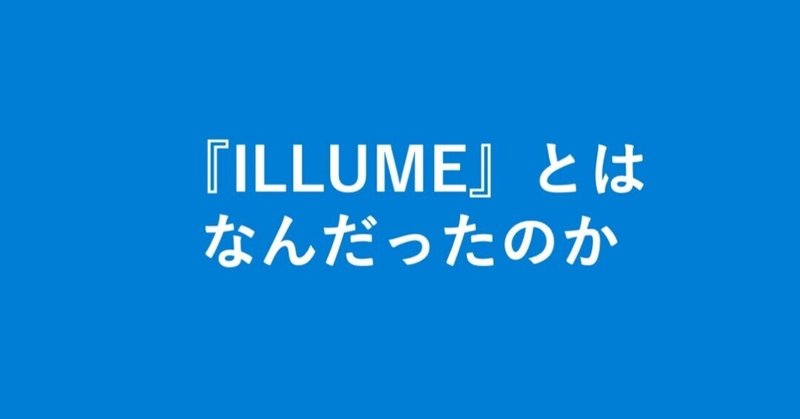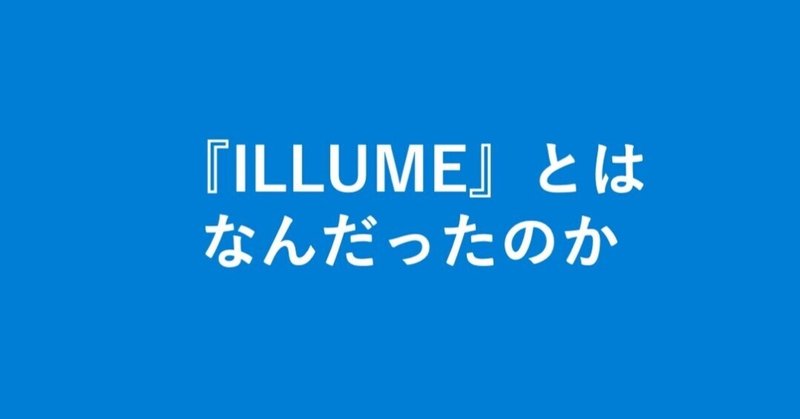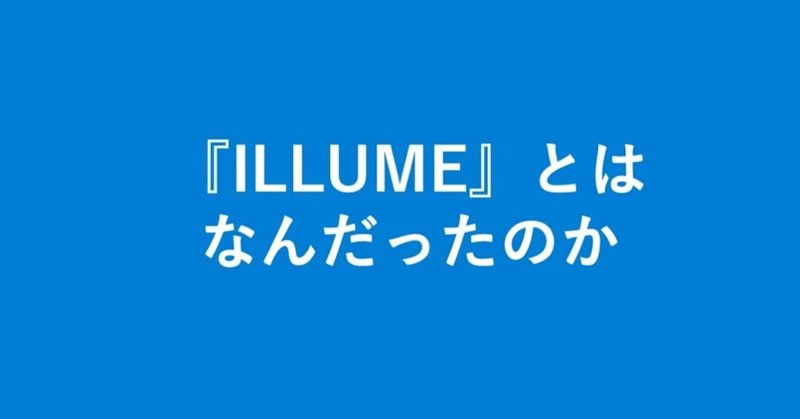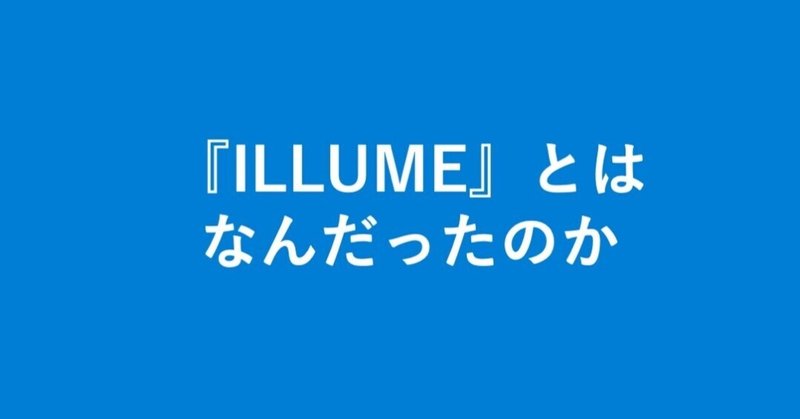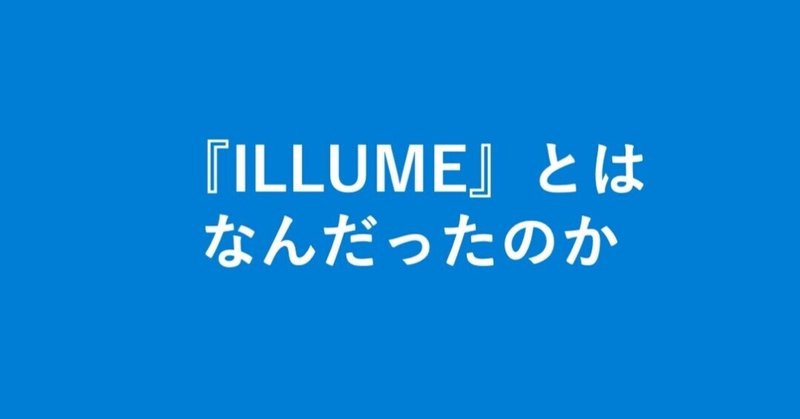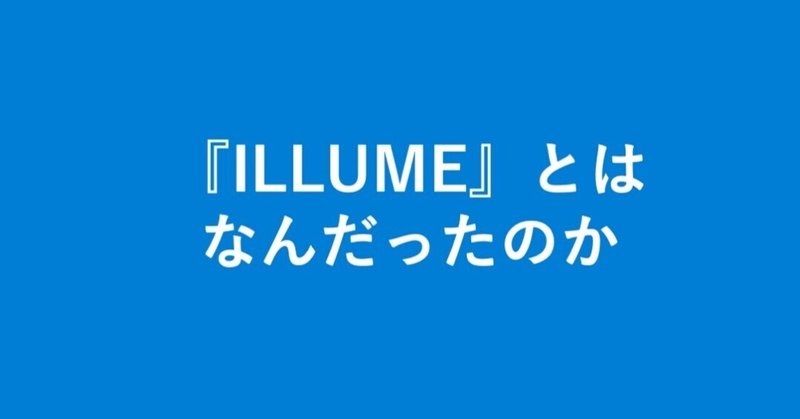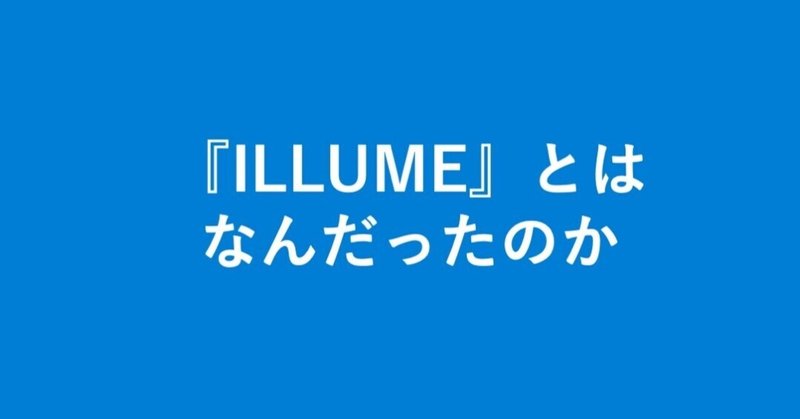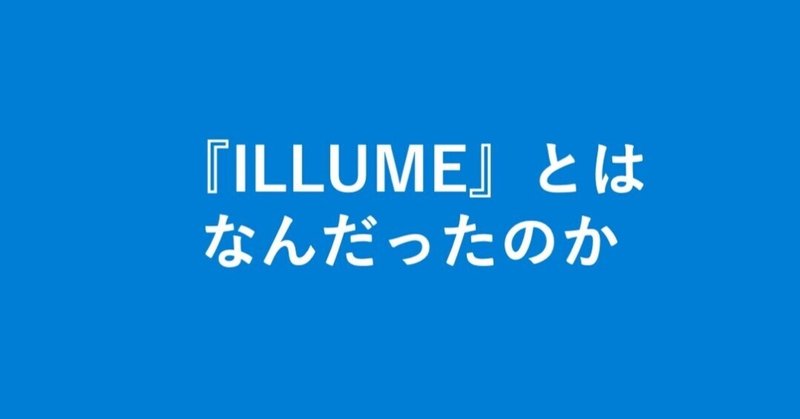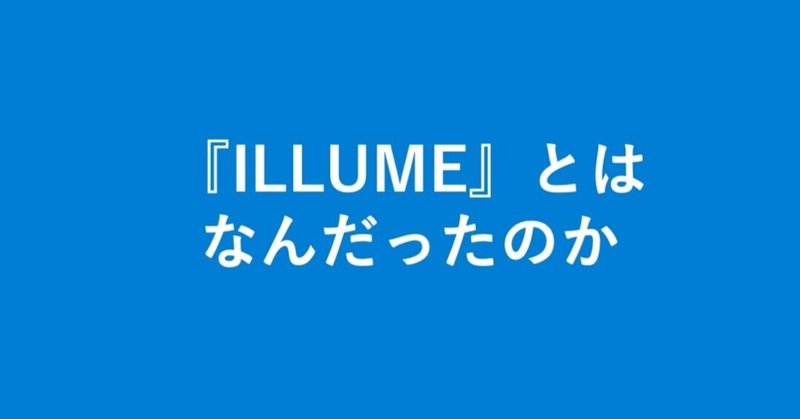#科学情報誌
『ILLUME』とはなんだったのか:第6回:創刊号と編集方針
長いね、それにしても。自分でも書いているうちにいろんなことを思い出すものだと呆れています。
4本柱を核として江崎玲於奈先生がインタビューに出てくださることが決まって、ついに1989年4月創刊に向けて、本格的に稼働したILLUMEですが、当然、インタビュー以外の企画も動いていました。
11月の編集会議で、山崎先生からダメ出しをくらった創刊企画は、練り直され、4本柱と2本のコラム、1本の連載という
『ILLUME』とはなんだったのか:第7回:社会貢献活動である意味
成立の流れを追っているとなかなか、他の話が書けないので、ちょっと外れて、この時の宿題を書いてみます。
この日本語と英語で言うと、社会貢献活動をphilanthropic programとしているところが重要なのですが、その説明は次回に。
こう書きながら、第3回ではオリエンとコンペの話をしてしまいました。
時代背景とオリエンの課題その中で、TEPCOの意図として「東京電力を代表する企業情報誌」
『ILLUME』とはなんだったのか:第8回:編集部の苦闘:サイエンスシリーズの作り方
前々回では創刊号で生まれた編集方針「素人のためにできるだけ理解しやすく、玄人に後ろ指を刺されることがなく」について触れました。
もう少し具体的に、どんなふうにイリュームを作っていたのかを思い出してみましょう。
最先端の事象を最先端の研究者にサイエンスシリーズは、ある分野の最先端の研究内容について、その専門研究者に執筆していただくという贅沢な考え方で企画されました。
科学雑誌のようにサイエンス
『ILLUME』とはなんだったのか:第9回:編集部の苦闘:印刷と構成の変容
サイエンスシリーズ以外の記事の作り方を書こうと思ったのですが、それに付随して、印刷とか構成が徐々に変化したことについて書いてみます。
読者が知っている言葉だけで、世の中はできているわけではないわけです。平易であるということは、専門用語が全くないということではありません。専門用語はわからないけど、そこに書いてある文意がわかるということが重要です。専門用語は調べれば良いし、本誌ならば脚注を見れば良い
『ILLUME』とはなんだったのか:番外編:私の場合
創刊からの流れと、構成やデザインの変遷などについて、徒然なるままに書いてきましたが、閑話休題。
また、制作方法もアナログからデジタルへのシフトが進んでいきます。原稿が手書きからワープロになり、ワードデータに変わっていきます。レイアウトも手書きの指定紙による入稿から、クォークエクスプレスさらにインデザインとレイアウトソフトを利用したものに変わっていきます。
ILLUMEへの参画全て知っているかの
『ILLUME』とはなんだったのか:第10回:M氏の場合
私の場合は、番外編で良いけど、この方の話は本編なので、第10回記念号です。
M氏とは、ILLUMEの創刊から休刊まで編集人のA氏を支え続けた、本誌のアートディレクターです。
サイエンスビジュアルについては、この回で少し書きました。
内容を捉えながらも、読者の興味を惹くように抽象化されたイメージビジュアルの創造は、毎回、デザイナーの知恵の絞りどころで、それに応えるイラストレーターたちの挑戦でも
『ILLUME』とはなんだったのか:第11回:ノーベル賞とILLUME
ILLUME38号の歴史の中では、ノーベル賞との関係も浅からぬものがありました。
さらに、毎号テーマが異なる本なので、過去の号を示す必要があると提案し、バックナンバー総目次一覧表を別刷で作成し、本誌に封入することにします。
バックナンバーに見るノーベル賞バックナンバー総目次を入れて置いたのは、読者に過去の号にも興味を持ってもらい、多くの方に読んでもらえるようにとの工夫だったのですが、今となって
『ILLUME』とはなんだったのか:第13回:科学・技術という表記
この回を読んだサイエンスシリーズ編集担当だったK氏からコメントをいただきました。今回はそれをもとに書いてみます。
論理が飛躍したり、思い込みで書かれている文章は直す必要がありますが、専門家が誠意を持って解説している文章は、編集部が手を入れる必要がなく、編集部の仕事は、それを補う工夫を考えることだというのも、ILLUME流編集術でした。
表記あるあるILLUMEでは、表記にも独自の工夫というかル