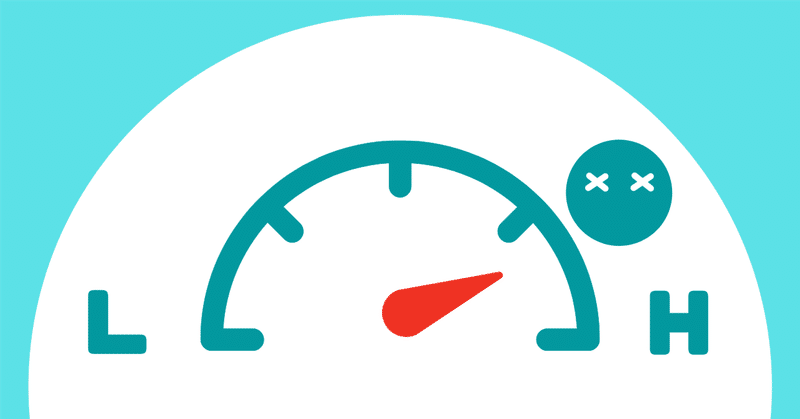
KPIの役割は「ちょっと未来の売上」を予測し、アクションを促すこと
フルスタックマーケティング株式会社の代表取締役CEO・清水優志(@fsm_shimizu)です。
企業のマーケティング活動を支援しています。
ITビジネスの世界にいる人なら、使わない人のほうが少ないくらいに普及した言葉である「KPI」。日常的に業務の中に現れて、我々を惑わす存在。
今日は、そんなKPIについての覚書です。
KPIの歴史を紐解くとわかる「なぜKPIは混乱の種になっているのか」
「KPI」という言葉の初出は、1992年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』に寄せられた論文 "The balanced scorecard: Measures that drive performance" だと言われています。
この論文はハーバード大学教授のロバート・S・キャプランと、コンサルティング会社社長のデビット・P・ノートンの共著で、 "The balanced scorecard" は経営戦略・業績評価に用いられるフレームワークでした。
つまり、KPIは当初は経営者だけが用いるツールだったのです。
"The balanced scorecard" において、KPIの基本概念は現在とほぼ変わらないかたちで示されており、同時に「KGI」「KSF(同論文内では "CSF" )」といった言葉も登場していました。
しかし2004年ごろから、エリック・T・ピーターソンというWeb解析のパイオニアが、『Web解析Hacks』や『Web解析のためのKPI大全』といった著書を通じて、KPIの概念をマーケティングの世界に持ち込みました。
エリックは同著の中で、KPIについて下記のように表現しています。
KPIについての考え方をひとことでいうならば、技術的データを収集し、それをビジネスに適した言葉で表現するということだ。
・KPIは、生データではなく、比率、パーセンテージ、平均で表現される。
・KPIは、円グラフや棒グラフではなく、タコメーター、温度計、赤信号(など何か意図を示すもの)
・KPIは、ただの表ではなく、その時々の状況や、変化を強調する。
・KPIは、ビジネス上の重要な行動につながる。
これを読めばわかるとおり、エリックが定義した「KPI」は "The balanced scorecard" における「KPI」とは少し異なり、今風に言えば「Web解析におけるメトリクス」のように見えます。
経営における「KPI」と、マーケティングの現場における「KPI」の感覚にややズレがあるのは、この2つの原典が存在するためかもしれませんね。
結果的に、現代のビジネスにおけるKPIは非常に曖昧な存在になってしまっています。
どちらのKPIでも「間違い」ではないが、「違い」を認識する必要はある
エリックがKPIの解釈をねじ曲げた、と見ることもできますが、Web解析の世界にKPIの概念を持ち込み、今日のWeb解析の考え方の基礎を築いた功績は非常に大きいとも言えます。
つまり「 "The balanced scorecard" における業績評価のためのKPI」と「エリック流のWeb解析におけるKPI」はいずれも間違いではありません。
しかし、それぞれの違いを正しく認識し、文脈に沿った使い方をする必要があります。
個人的には、エリックが定義した「KPI」は先述のとおり、現代では「Web解析におけるメトリクス」と表現したほうが誤解がないことが多いので、本noteでは「 "The balanced scorecard" における業績評価のためのKPI」に的を絞り、もう少しKPIについて深掘っていきたいと思います。
KPIは単体では機能しない
"The balanced scorecard" (いわゆる「バランス・スコアカード」)は、以下の図のように「財務視点」「顧客視点」「業務プロセス」「学習・成果」という4項目における「KGI」「KPI」「KSF(CSF)」をそれぞれ書き出していくフレームワークです。

現代では様々なシーンで用いられるようになったことで4項目の縛りがなくなり、「KGI」「KPI」「KSF(CSF)」が独立して利用されていますね。
いずれにしても、KPIに関して最も重要なのは「KPIはそれ単体では機能しない」という点です。

KPI(Key Performance Indicator)は日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。
"Indicator" とは「計器」のこと。飛行機のコックピットにあるメーターみたいなやつですね。
あなたが飛行機を操縦するとして、速度計やコンパスを確認せずに運転していたら、目的地には着けませんよね。ビジネスも同様で、自分たちの状況を定量的に把握できなければ、目的を達成することは難しいのです。
しかし、なんでもかんでも計測すればいいというわけでもありません。計器が増えれば見るべき場所が増え、故障も起こります。特に重要なものを必要なときに見るのがよいでしょう。
そして、その飛行機がどこに向けて飛んでいるのかを示すのが「KGI」(Key Goal Indicator: 重要目標達成指標)です。
また、その飛行機を正しく飛ばすための最重要プロセスが「KSF」(Key Success Factor: 重要成功要因)と呼ばれます。
これらの言葉は不可分な運命共同体で、1つでも欠ければ全体が成立しなくなってしまいます。
念仏のように「KGI・KPI・KSF」と唱えましょう…。
KPIの役割は「ちょっと未来の売上」を予測し、アクションを促すこと
では、ここまでの話を踏まえて「KPIの役割」について考えていきましょう。
KPIというのは、KGIを達成するための具体的な目標数値です。
KSFを実行することでKPIが達成され、それによってKGIが達成できる、という関係性になっています。
KPIを使うことには、3つのメリットがあります。
経営戦略や事業戦略に紐づく部門目標を設定できる
KGIを分解し、改善可能性の高い具体目標に落とし込める
「ちょっと未来の売上」を左右する中間目標を設定できる
部門目標なくしてチームは動かない
いくら経営戦略や事業戦略を立てたところで「では、うちのチームでは何をすればいいの?」と思考停止しては意味がありません。
多くのメンバークラスの社員は、経営や事業における数多の重要指標を理解できません。なぜなら経営者でも事業責任者でもなく、その指標に日常的に触れる機会がないからです。
KPIは、そんなチームに誰にでもわかる "Indicator" (計器)を授け、何を見ておけば正しく飛行機が飛ぶのかを教えてくれます。
これがチームが協力するための原動力になります。
具体目標なくしてアクションは起こらない
「売上必達!」というのは、昭和の営業マンだからこそできた目標管理です。現代のITビジネスにおいて、それは上手くいきません。
ITビジネスは複雑性が高く、戦術や手法も無数にあります。放っておくと「この方法は良くないのではないか」「もっといい方法があるのではないか」と、戦略の粗さがしを始める社員が出現します。
KPIは、そんなメンバーに具体的なアクションを求め、飛行機を目的地に届けるためにやるべきことを明確にしてくれます。
これが個人を動かす原動力になります。
中間目標なくして危機感はない
売上というのは遅行指標(アクション後、遅れて変化する指標)です。
例えば、BtoBビジネスはすぐに成果が出るものではありません。
リード獲得し、継続的に認知してもらい、必要になったときに声をかけられる・声をかけてもらえる関係性を構築しておき、商談し、受注する。これでやっと売上が立ちます。
ということは、売上だけを見ていると「ちょっと未来の売上」が悪化するシグナルを見逃してしまうのです。
「リード数が減っている」「商談数が減っている」というのは、未来の売上悪化のサインです。BtoBマーケティング担当者はこのことを直感的に知っています。
こういった中間目標とその意味を理解させ、チームや個人に危機感を与えてくれるのも、KPIの役割です。
正しい言葉遣いは、正しい言葉理解から
他人の言葉遣いを正そうとして「そんな言い方をするな!」と怒る人がいますが、理由もわからないのに怒られて納得する人はいませんよね。
正しい言葉遣いをしてもらおうと思うなら、あるいは自分が正しい言葉遣いをしたいと思うなら、まずは正しい「言葉理解」が必要です。
KPIという言葉も、おそらく多くの人が違和感を持って、しかしなんとなく惰性で使ってしまっているものだと思います。
このnoteを読んで、KPIについての認識をアップデートできたな〜と思っていただけたら嬉しいです!
===============
もし清水に興味を持ってくださった方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に以下のリンクより「ちょっと話してみたい」してください!案件の相談でも、キャリアの相談でも、コンテンツの書き方でも、なんでも大歓迎です!!
Twitterアカウントはこちら
https://twitter.com/fsm_shimizu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
