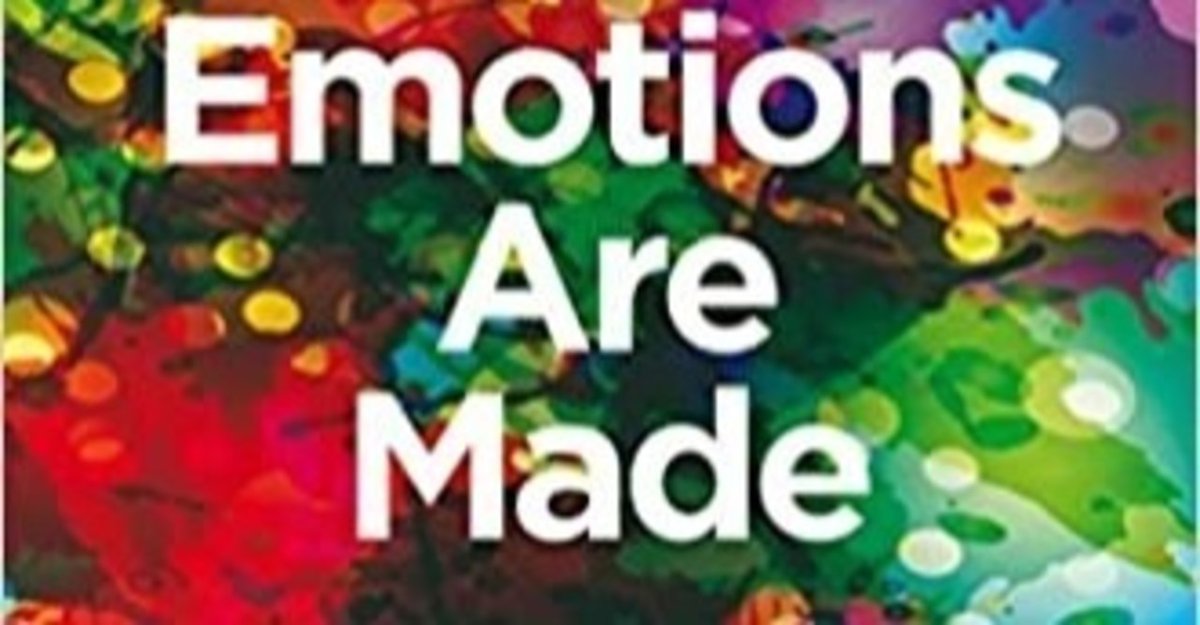
How emotions are madeを再読して(Lisa Feldman Barrett著)
Lisa Feldman Barretの"How emotions are made"を再読。
邦訳版「情動はこうしてつくられる」が日経の書評に取り上げられていて興味を持ち、Kindleで購入できないかチェックしたところ、原書の方がだいぶ安く手に入ることが分かったので、何とかなるかなと思い、ついつい手を出してしまったのが最初に読んだきっかけ。
この写真の通り恐らく脳を模したであろうカラフルな表紙と、冒頭から平易で親しみやすい文体で、専門外にも拘わらずどんどん読み進めることが出来る。怒りや悲しみといったEmotionは自然に感じられるものではなく、過去の経験に基づき人間の脳がつくり出すものだという説(Constructed Emotion Theory)にすっかり魅了され、素人ながら納得の読後感だった。
その後、Twitterで脳研究の専門家の方々より情報を頂く中、この説が新しく相当Radicalなものであることを知る。そこでこれが異端なのか、それとも主流となりつつあるのか、基本的なことを押さえておきたいと思い、脳研究の歴史が網羅的によく纏められたMatthew Cobb著のTHE IDEA OF THE BRIANを読むことにした。ここではBarretのことは一切触れらていなかったが、脳機能の全体像についてこの半世紀の間、新たに分かったことは殆ど無いということが分かり、ひょっとするとBarretの説はこの閉塞感を打ち破り、今後主流になり得るのではないかと思い、今回改めて読んでみることにした。
この本については既に多くの方がブログ等で要約を掲載しているので、ここでは彼女のConstructed Emotion Theoryのポイントを原書内容に触れながら振り返ってみたい。
先ず、彼女は脳研究の通説と言われている以下3点について間違っていると喝破する。
1. The classical view assumes that happiness, anger, and other emotion categories each have a distinctive bodily fingerprint.
2. The classical view proposes that we have a gift-wrapped animal brain- ancient emotion circuits passed down from ancestral animals, wrapped in uniquely human circuitry for rational thought- like icing on an already-baked cake. (often touted as "the" evolutionary theory of emotion)
3. The final major assumption of the classical view is that certain emotions are inborn and universal.
最初の点に就いては、幸福、怒りのような特定の情動の元となる特定の脳の部位(偏桃体など)があるはずだというものである。次の点に就いては、脳が反射脳・情動脳・理性脳の三つの脳より構成されるというものである。最後の点は特定の情動は生まれつきのものであり普遍的なものであるという点である。
Barretは過去20年の関連分野における研究をメタ分析し、これらの点は確認されなかったと述べると共に、アフリカ先住民地区含む様々な場所で特定の表情に対してどのような情動を読み取るかというテストを行い、感情というものに普遍性が見られないことを確認したという。
一方、これらの通説に対して彼女が提唱するConstructed Emotion Theoryというのは以下のようなものである。
Emotions are not reactions to the world. You are not a passive receiver of sensory input but an active constructor of your emotions. From sensory input and past experience, your brain constructs meaning and prescribes action.
即ち情動は外界への反応といった受動的なものではなく、能動的に作り出されるものであり、また感覚器からのインプットと過去の経験を基に、脳が意味をつくり行動を決めるものである、というものである。彼女は情動の形成に影響を与える3つの要素を以下の通り紹介している。
The theory of constructed emotion incorporates elements of all three flavors of construction. From social construction, it acknowledges the importance of culture and concepts. From psychological construction, it considers emotions to be constructed by core systems in the brain and body. And from neuroconstruction, it adopts the idea that experience wires the brain.
即ち、情動は、育った文化・社会からの影響、その時の脳や身体のコンディションからの影響、神経細胞レベルの影響(特定遺伝子のON/OFFなど)を受け、つくられるというものである。同書はこのような情動形成のメカニズムに就き詳しく解説してるが、それについては機会を改めて今度纏めてみたい(まとめると、内受容感覚(interoception)を起点に脳が特定の身体を動かすよう働きかけ(Body-budgeting)、その結果生じる感情(Affect-Arousal/Valence)と、過去の経験を基に、情動(Emotion)が形成されるというもの)。またこの理論を前提に、バレットは感情をいかにコントロールするか、メンタルな病気にどう対処するか、国家間の争いをどう考えればよいかなど、様々な応用事例を紹介しているが、面白い話も結構あるので、どこかで取り上げることが出来ればと思っている。
この理論によると、我々が見聞きしていることは、実のところ外界から入ってくる情報を基に、脳が自己都合でつくり上げたイメージに過ぎないものであり、我々が主体的に考え行動していると思っていることは、実のところ、それにイメージに基づき我々が自己の生存の為にプログラムされた通りに取っている最適反応に過ぎないということになる。即ち、人間は地球上で感情をもつ特別な存在ということは全く無く、脳は高度に発達しているものの、適者生存の原理の中で生き残ってきた動物の一種に過ぎないということになろう。バレットは本書の中でここまで言い切っている訳では無いが、彼女の理論はここ数百年の間、西洋文明を中心に人類が大切にしてきた価値観の根底を崩すパワーを秘めている面もあり、今後の動向に注目する必要があろう。
彼女の新著は"Seven and Half Lessons About the Brain"が今年11月に発売予定なので、楽しみである。
https://www.amazon.com/Seven-Half-Lessons-About-Brain/dp/0358157145
ちなみに最後に余談だが、脳科学研究者の誰もが目を通すという脳科学辞典の情動の項を見るとバレットのことには一切触れられていない。やはり現時点では異端なのだろうかと思ってしまう。
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E6%83%85%E5%8B%95
養老孟子さんは本書を好意的に取り上げたようだ。
https://mainichi.jp/articles/20191201/ddm/015/070/002000c
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
