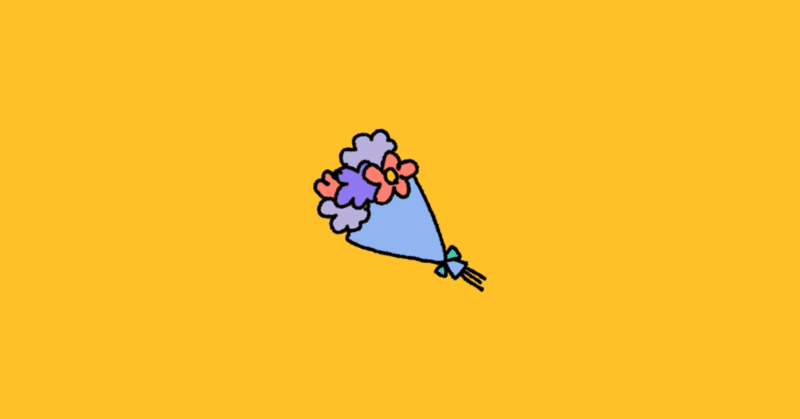
「結局これで良かった」と言いたい
知らないうちに、左耳が難聴になっていた。
知らないうちにとは言っても、予兆はあった。シャワーを浴びた後、耳の奥からハウリング音が流れることが1週間で2回あったのだ。せいぜい5秒くらいの耳鳴りだけれど、あの音量はもう、確実に僕の耳の中で全校集会が開かれていた。しかもちょうどその夜は、かの木曜ドラマ「silent」で、後に両耳を失聴する主人公・想の「耳鳴りみたいなのがずっとしてて、すごいうるさい」というシーンがバズった日。言語化してみて今更ながら思う。すぐ病院行けや!!!
耳鳴りがする病気といえば、僕の中では突発性難聴が検索ランキング第1位だ。学部時代は病気や障害について勉強していたし、芸能ニュースで時々聞く名前だから結構よく知っていた。でもその偏った知識が自分の症状と結びつかなくて、自分は違うと思った。別に聞こえにくくないから、違う。耳が塞がった感じはしないから、違う。耳鳴りも常にはしないから、違う。あんな大病がこんなもんで済むわけないから、違う。でも突発性難聴は2週間が治療開始のタイムリミットだって聞くし、そこまで続いたら病院行こうかな。さあ今日はもうねんねしましょうね〜。
で、本当に2週間経って、いざ受診してみたら突発性難聴だった。早よ病院行けや!!!
聴力検査の結果のグラフは、軽度とはいえ見事にどの音域にも難聴を示していた。主治医は「難聴自体は軽いから、このくらいだと自覚がない人も多いですよ」と、病院らしい小さな声で説明してくれる。一人暮らしの静かな自宅と騒がしい大学を往復するだけの生活だったから、小声の聞き取りにくさに初めて気づいて震えた。それと同時に、気のせいだと思いたかった聴覚過敏も病気のせいだったと分かった。もう「気にしすぎ」では飲み込めなくなってしまった今からの帰り道45分、というかこの先、我慢できる自信ないな。
◆
発病から4ヶ月。主治医の執念が功を奏して、聴力は完全に回復した。けれど、聴覚過敏が後遺症としてそのまま残ったがために、苦手なことが一気に増えた。マイクが使われるような大人数の授業だと、ざわつきとスピーカーの音で頭痛がする。グループワークは声が混ざって聞き分けられないから、ものすごく集中しないと上手くできない。飲食店で同期たちの声が聞き取れないのをしょっちゅう笑ってごまかしてしまうし、食器がぶつかる音を聞くと鼓膜が裂けたかと思うし、卵は肩で左耳を塞がないと溶けない、お菓子の袋がうるさくて開けられない、赤ちゃんや小さい子どもの声は聞いていられない……。
難聴という診断名でありながら、そしてそれはもう治ったはずなのに、いつまで経っても左半分の何もかもがうるさいのだ。今まで通り聞こえているのに、どうして。病気は過去の話なのに、どうして。普通に聞こえるからには諦めがつかない。「ノイズキャンセリングイヤホンさえあれば今まで通りなんだから」という気持ちと、それを「今まで通り」とは呼びたくない気持ちが混在している。この根源はきっと「誰かといる時にイヤホンを外さないだなんて、こんな無礼を誰が許してくれるんだろう」という内面化された差別だと分かっていたから、自分の差別心を認めるようで余計に葛藤が大きかった。
この葛藤がふと和らいだのが、今月のことだ。
今月から、僕は修士論文の調査でインタビューを始めた。たくさんの方々から、オンラインで長い時間をかけてお話を聴かせていただいている。お相手のプライバシーの保護を最大限考えたら、お話はICレコーダーで録音するのがベストだ。でもそのためにはパソコンのスピーカーをほぼ最大まで上げて、ICレコーダーに明瞭な音声が届くようにしなければならない。だからインタビュー当日は耳の調子が良いことをひたすら祈り、終わったら音による疲れで寝落ちするパターンを延々繰り返した。これでは到底身がもたないと思い始めたある日、インタビューに協力してくれた友人が言った。
「画面の録画じゃダメなの? こっちの顔出しは自由に止められるんだし、話せば相手は分かってくれると思うけど」
「インタビューの承諾の時点で、ICレコーダーに録ることを前提にOKもらってるんだよね。それをこっちの都合でやっぱ録画させろってのはわがままじゃない?」
「だってこれは持病じゃん。不可抗力でしょ。真琴って『持病の都合でこうさせてほしい』って言われたらキレるタイプ?」
言われてみれば確かにそうだ。翌日のインタビューは最初からイヤホンを着けて臨んだ。開始前の説明中、見ず知らずのお相手にこう尋ねた。
「耳の病気があって、イヤホンからでないと聞こえにくいんです。申し訳ないですが録画させていただけますか? 映像データはすぐ消して、音声だけを使いますので……」
お相手はにこやかな表情を崩さずに一言。
「はーい、了解です」
えっ? 了解してくれんの?
次のインタビューでも、またその次のインタビューでも、返事は満場一致で「はーい」だった。驚きとありがたさで同期たちにその話をしたら、彼らも驚いたように言った。
「何その謎の遠慮? てか俺らにもそれ早く言えよ。飯食っててイヤホンしてるぐらいが何?」
日常生活上でもイヤホンしっぱなしで了解してくれんの? 僕の葛藤は何だったわけ?
その日以来、僕は全てのインタビューで録画を許してもらえないか交渉しているし、誰とご飯を食べに行ってもイヤホンをするようになった。誰も嫌な顔をしないし、具体的な説明を求めてもこない。何なら、事情を知らない先輩が「右側から話した方がいいよね?」と声をかけてくれるほどだ。人間は優しい。この世は優しい。
この病気になったこと自体を貴重で素敵な経験だったとは思えない。後遺症だって残らないに越したことはなかったし、イヤホンが不可欠になった家事をする度にやるせなくなる。でも、持病や感覚過敏で生活に支障を来たす人たちが何を思いどう暮らしているのか、いかに世間は優しくまだまだ捨てたものではないか、それを身をもって知れたのなら、いつかは「結局これで良かった」と言いたい。
いただいたサポートは、大学院での学費として大切に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。
