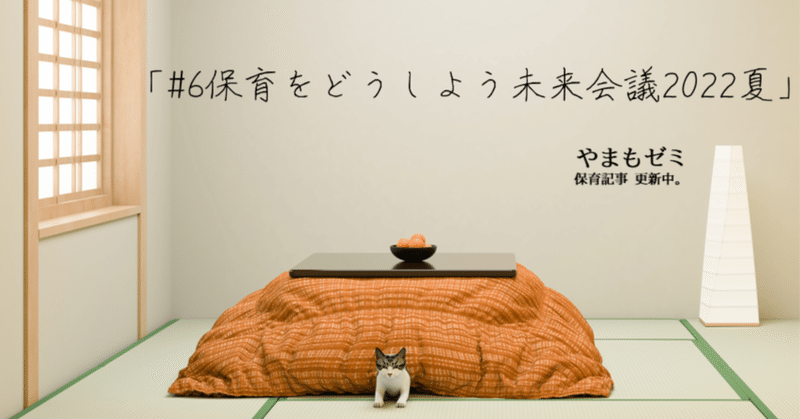
#6保育をどうしよう未来会議2022夏
どうも、保育主任やまもです。
このシリーズは、ユニファ株式会社主催のオンライン研修会のレビューです。研修の内容は「保育・子育て」です。
今年の夏も「保育をどうしよう未来会議」が行われましたね。いつもリアルタイムでの参加が難しく、アーカイブ視聴になっていますが参加させていただいています。
こんなに豊富で、しかも無料で見られる研修会はない!といつも思っています。
無料登録をすれば、みなさんも見られます。
登録はこちらから↓↓
園単位の申込みになっていますが、園を通さず個人で見たいという方もいると思います。その場合は、ご相談ください。
今回の未来会議のコンセプトは、
「子どもを真ん中においた保育・子育て社会の実現に向けて」です。
素敵なコンセプトですね。
視聴した動画
今回視聴した動画がこちらです。
社会福祉法人ルピナス
キッズ・キッズ折尾保育園 園長 山本 ユキコ先生
「保護者を園の味方にする Part2 ~気になる子どもの保護者対応~」
3行レビュー
前回の未来会議の続きのお話です。気になる子どもの対応、ではなく、その保護者との関係性や子どもの困り感を伝えていく実践の紹介でした。園への信頼度があるからこそ、園からの提案に前向きになる関係性ができます。
やまも的ポイント3選
ここからは、私の独断と偏見で研修動画のポイントを書いていきます。
動画を視聴して思いついたことでもあるので、動画の内容とズレることもあるかもしれませんが、ご了承ください。
園と保護者の関係性を保つネガポジ
どんな関係性にも、ネガポジのバランスは大切です。
ネガポジというのは、ネガティブとポジティブのことです。ここで言うネガポジは「ポジティブ=聞いた人が嬉しくなること」「ネガティブ=聞いた人が嫌な気持ちになること」と定義しています。
文字で読むと当たり前に見えますが、実際はなかなかそうはいかないものです。例えば自分と後輩のネガポジバランス。例えばクラスにいる気になる子とのネガポジバランス。どうでしょう、何:何の割合でしょうか。
先生の研究では、ポジティブ5:ネガティブ1だと良い関係が保たれるそうです。このバランスだとそりゃあ良い関係でしょうと思うわけです。
ですが、1:1でも関係は悪化はしないそうです。最低ラインというやつですね。1:1でも大丈夫。それよりバランスが悪くなることはあるのか?と思ってしまいますが…あるんでしょうね。
おそらくここで一つ気を付けないといけないことは、先ほどの定義です。「聞いた人が嬉しい/嫌な気持ちになる」と書きましたが、【聞いた人が】というのがとても重要です。伝える側(保育者)がポジティブだと思っても、受け取る側(保護者)がそう受け取らないことって実はけっこうあるんじゃないでしょうか。
「今日〇〇くんがこんなことがあって、すごい笑っちゃいました。」という保育者から見る微笑ましい(可愛く感じる)エピソードも、保護者にとっては「うちの子を馬鹿にしてる?」と感じるかもしれないということです。
先日、園長と事務の先生と広告の写真選びをしている時に学んだことがありました。その時に「保育者が選ぶ良い写真」と「保育に携わらない人が選ぶ良い写真」は違うことが分かりました。保育者が良いと思う写真は、実は一般受けしないんです。保育者の写真の選び方が良い意味で専門的、悪い意味で変態的なんですね。変態的=内輪と言ってもいいかもしれない。学祭で一部のグループだけゲラゲラ笑っているパフォーマンスと一緒です。分かる人にしか分からない状態です。
ということで、保育者のポジティブメッセージが保護者にとってのネガティブメッセージになり得ることを学びました。そうなるとポジネガバランスが1:1より悪くなることもあり得ますね。
心理士さんの活用
すでに活用されている園もあるかもしれませんが、心理士さんに定期的に園に来てもらえたら心強くないですか?保育者も質問できるし、保護者の方も面談できるようにすると、第三者でしかも専門の人が間に入る心強さがあります。良い!
保護者と保育者は子育ての面で協同していますが、障害については協同できていない部分があるように感じます。というか、保護者の方によっては「保育者は、そこは専門外だよね?」と思っている人がいるという意味です。実際に障害については対応に悩んでいる・困っている保育者が少なくないので、その言い分は正しいかもしれません。ただ、協同できないと協力的にはなりません。
そこで心理士さんです。
心理士さんは「障害の専門の人」というイメージが保護者の方にもあるでしょう。そうすると協同関係ができます。やっぱり良い!
園で心理士さんを探す時は、地域の心理士会に相談してみるといいみたいです。私もさっそく探してみます。
点を投げかけていく
こちらは山本先生のまとめの中で出てきた言葉です。
面談一発勝負や参観日や行事の様子一発で、保護者の方に子どもが困っている様子を伝えることは難しいです。無理と思ったほうが良い。そうなると大切なことは、ネガポジバランスを保ちながら気になる点を投げかけていくことに尽きる、ということです。
できていないところを見せることに抵抗感を感じるかもしれませんが、それを見せないのも不自然です。できている部分もその子、できていない部分もその子です。ここでもバランスをとって、それでも隠さずに見せるという意識に変わっていいのかもしれません。
でもバランスは大事。保護者にとって子どもは宝です。直接的に丁寧に関わるのはもちろんのこと、話題にあげる時も丁寧に、丁寧に。
まとめ
いかがでしたか。
気になる子どもに限らず、子どもの様子を保護者に伝える際には「保育者ノリ」になっていないか気を付けないと!と心に刻むやまもでした。
保育をどうしよう未来会議2022夏の視聴期間が残りわずかです。
見ようと思っている人は急いでくださいね。
私もまだ見ていない研修があります…まずい!
もう2022冬の申込みも始まっています。
そちらもぜひ。
やまもゼミ
最後にお知らせをさせてください。
”やまもゼミ”というメンバーシップを運営しています。
ゼミメンバー限定の記事を更新しています。
ぜひ読んでみませんか??
【ゼミ記事の内容】
保育について思うこと
息子の子育て
大学院での学び
園運営、後輩指導、同僚性
Twitterもやってます。
平日の朝は、音声配信をしています。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
ではでは。
追記
ゼミメンバーに追記です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
