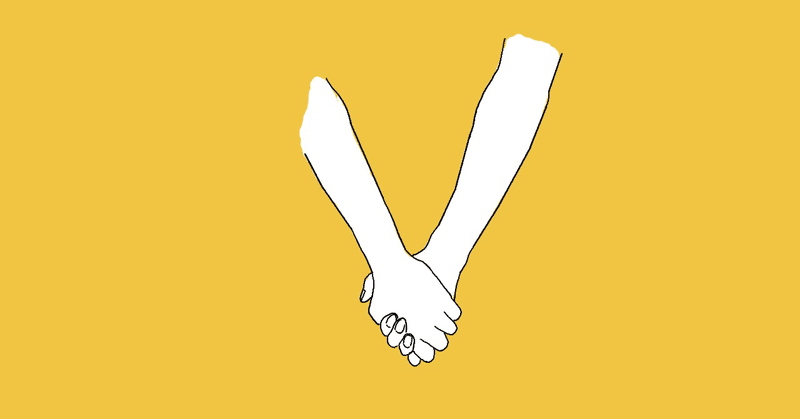
1月13日(土):ユニセフ・マンスリーサポートと「未来へつなぐ想い」
ユニセフのマンスリーサポーター向けに年4回発行されている広報誌「ユニセフニュース」では、新春特別企画として「わたしたちのストーリー 未来へつなぐ想い」と題した特集が掲載されていましたので、本日はこれに関連した話を少しばかり。
■ユニセフ・マンスリーサポート
こちらの特集はユニセフ・マンスリーサポート(毎月の定額寄付)を始めたきっかけやどんな想いでそれを続けているのかをサポーターに募り、そこに集まったものから抜粋された支援者たちの想いや言葉です。
私自身も20代の頃からマンスリーサポートを始めて、かれこれ15年以上も続けていますが、この特集を通じて支援をする他の方々の想いに触れることができたのは非常に良かったですね。
誌面から一部を転載させてもらいます。
「小学1年で父を亡くし、米軍の爆撃により家を失いました。奨学金を得て、中学から大学まで働きながら勉強しましたが、母や周囲の人々の援助のおかげで今日があると感謝を持ち続けて生きています。その感謝を、わずかですが社会にお返ししたいと思っています。」(90代男性)
「終戦後、小学校高学年の頃、お弁当も持参できない子が多くいました。ユニセフの脱脂粉乳の給食が始まり、ありがたく、みんな平等にお腹を満たすことができました。今、少額ながらサポートできるのは、そんな原風景によるところが大きいです。」(90代女性)
「自治体職員として30余年、児童相談所に勤務。日本の子どもたちも近年、貧困や虐待など厳しい現実にあることを実感した日々でしたが、世界にはもっと悲惨で、生後まもなく命を落とす子どもがいることを知り、少しでも役に立てばとサポートを始めました」(60代男性)
「子どもの不登校を親子で乗りこえた時、これから何をなすべきかを考え、小学校での読み聞かせとユニセフ募金を始めました。子どもを思う気持ちは、どの国も同じ。1人でも幸せな生活を送ってくれるなら、と。子どもたちも巣立ち、3年前からはマンスリーサポートをしています。金額は少しですが、続けていくつもりです。」(60代女性)
「母が施設に入る際に母の通帳からユニセフに定期的に寄付していることがわかり、今は話すこともできない母の気持ちを継いで自分も定期的に支援することにしました。」(50代男性)
「母子家庭で暮らしていた頃、いろいろな人に助けてもらいました。今は、私が困っている人の助けになりたいと思ったから、始めました。」(50代女性)
「寄付をしていることを唯一知っている夫からは『わが家を代表して取り組んでくれてありがたい』と言われました。私が寄付を始めてから、夫婦でチャリティーイベントに参加するなど、一緒に活動することが増えたように感じています。」(30代女性)
「きっかけは、高校の授業で観たドキュメンタリーに映ったアフリカの女の子です。『お金があったら何がほしい?』というインタビューに、きらきらした目で『学校に行きたい』と答えていました。なんとなく学校に通い、たまに授業をサボったりしていた当時の私にとって、予想だにしなかった答えでした。今の自分の生活はあたりまえのことじゃないんだ、生まれてくる場所によってこんなに不公平があるのは許されてはならないと、教室で涙が止まらなかったのを覚えています。社会人になってからずっと支援を続けていますが、私の心の中には、今でもあの女の子が住んでいます。」(30代女性)
このように、それぞれの方にとっての想いやストーリーがあるんですね。
私の場合は強烈な原体験などがあってマンスリーサポートを始めたわけではありませんでした。
ただ、世界を見渡したときに今の自分に与えられている環境や仕事、五体満足な身体があるのは感謝すべきことで、そうやって自分が与えられているもの、受け取っているものを自覚した時に、何かを社会へ返していくことが必要だろうなと思ったことがきっかけです。
また当時は20代で独身だったので、誰かのために何かを頑張っているというよりは、自分のためだけに仕事をして、時間をつかっている状況だったので、自分の頑張りが誰かの役に立てばという想いに立つ意味合いもあったと記憶しています。
ユニセフのマンスリーサポートの良さは身の丈にあった形で長く支援が続けられることだと思っています。
1ヶ月あたりの支援額はたいしたものではありませんが、それでもそれを毎月のように重ねて15年という期間になれば、それなりのまとまった額にはなるものです。
私には資産家や著名人のように、何か有事の際に何百万円や何千万円といった多額の寄付はできませんが、「細く長く」であれば続けようがあります。
またユニセフのような機関にとっては一過性の支援よりも、活動を維持するための安定した長い支援を求めている面もあると思いますしね。
何や役立てることがあれば、とは考えながらも、だからといって自分が現地に行って何らかの活動をするのは現実的に難しいので、自分にできるのはこうした小口の寄付によって、その思いを誰かに託すぐらいしかありません。
何事も継続が大事ですから、この先も20年、30年とそれを続けていくだけです。
宜しければサポートお願い致します!
