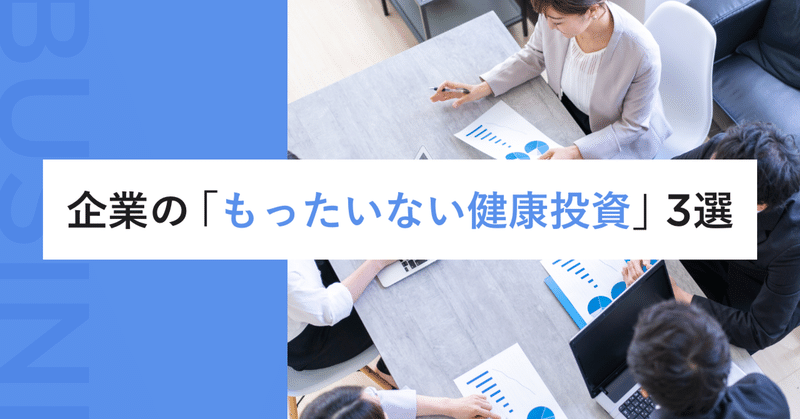
企業の「もったいない健康投資」3選
労働人口の減少や、人的資本経営の推進から
「人材への投資」「人件費の位置づけの変化」など、企業の従業員に対する考え方が変化し、人材への投資が積極的にすすめられるようになってきました。
報道で目にするものは、「リスキリング教育」や「賃上げ」がメインですが、従業員がパフォーマンスを最大化し企業の成長に寄与するためには、土台となる健康が重要になってきます。

『未来を気付く、健康経営-深化版: これからの健康経営の考え方について-』
(2021)イラストから一部改変
健康経営の取組みの中でも、従業員への健康投資を積極的に実施されている企業も増えてきていますが、企業の健康投資で、もったいないなと思う施策3選を独断と偏見でご紹介します。
健康経営の施策を検討されている方は是非ご覧ください。
ちなみに、健康経営優良法人の顕彰制度では、
評価・改善や効果検証に重きが置かれ、
より、従業員への投資に対する改善、効果検証が求められるようになってきています。
1.そもそも健康投資とは何か
「健康投資」とは、文字通り従業員の健康を維持または向上するために企業が従業員の健康目的に投資を行うことを指します。
具体的には、
・健康的な食事の提供
・適度な運動の機会や環境の提供
・ストレスの軽減を促すためのリラクゼーション施設の提供
などが含まれます。
2.企業が健康投資をする意義とは
企業が従業員の健康投資を行うことには、大きな価値があり、まず、健康な従業員は生産性が高いと言われています。
体調不良やストレスによる業務への集中力低下が防がれ、結果的に業績アップにつながる可能性があります。
また、定期的な健診や気軽に相談できる健康管理の機会を設けることで、疾病の早期発見・早期治療へのつながりなど、従業員の長期化する休職を防ぐことも期待できます。
企業に勤務する正社員・正職員10,000人を対象とした、経済産業省の調査データでも、所属企業の健康投資レベルが高いと感じている人の方が、健康状態や仕事のパフォーマンスが良好であることが分かっています。

3.もったいない健康投資3選
それでは、企業のもったいない健康投資3つご紹介します。
①IoT機器の配布
健康経営の一環として、健康に関するIoT機器
・スマートウォッチ(Apple WatchやFitbit等)
・体組成計
・活動量計
を従業員へ配布。
健康意識の向上や、健康の維持・増進につなげてもらうべく配布をされています。
(配布事例としては、Apple WatchやFitbitが多くあります)
取組みとしては、すばらしく、何が「もったいない」の?
と思われている方も多いと思います。
もったいないポイントとしては、
IoT機器を配布したのみで、企業がIoT機器で取得できる従業員データを活用できていないところです。
配付をしたことで、従業員の企業に対するエンゲージメントの向上等はあったかもしれませんが、普段の生活習慣での行動量やデータ、施策実施での変化・効果検証まで使えるとより効果的な健康投資になると考えています。
(IoT機器での取得データをアプリを介し、収集している企業もある為、配布のみを行った場合をこの記事では指しています)
②従業員のニーズにマッチしない施策
自社の従業員の健康課題や、ニーズが分からないものの、
・他社でも良く実施されている施策だから
・健康経営度調査票で求められているから
・イベント的に試しにやってみよう
健康に対して、従業員に興味関心を持ってもらい
少しでも行動につなげてもらいたい。
という意図で、各種施策を走らせる企業も多くあります。
ただ、実際にやってみると、参加者を募るも集まらない。
思っていた成果がでない。
と担当者を悩ませる結果になることも多いようです。
現状、自社の従業員はどんな健康課題や生活習慣の傾向があるのか
どんな施策なら興味関心を持ってもらえるのか。
自社の課題・ニーズを把握し、課題に合った、施策展開を実施することをおすすめします。
ここ数年、「女性特有の健康課題への対策」が、注視されていますが、経産省の資料では、ニーズのミスマッチが生じているというデータも出されています。

③やりっぱなしの施策
健康投資として、各種施策を展開するものの、振返り・効果検証が行えておらず、やりっぱなしになっている場合も多いです。
一例として、
健康セミナーは、イベントとして単発で実施しやすいですが
担当者は、セミナー参加者数のKPIに追われてしまい、
事後アンケートの結果はまとめますが、従来の目的であった、
健康知識が定着したのか。
それによる健診数値の改善につながったのか。
など、追えている企業はまだまだ少ないです。
健康経営推進担当者は参加者数というKPIに追われ、必死に参加を促すものの
参加メンバーはいつも同じ健康意識の高いメンバー
なんてことはよくお聞きします。
「情報を提供するだけ」
「施策展開後はフォローできない」
ということが無いように、効果検証や施策展開後のフォローも含め施策を実施することをお勧めします。
4.まとめ
従業員への健康投資が積極的に進められている中、
健康経営では取組みに対する、評価・改善や効果検証が求められています。
せっかく取り組んだのにもったいないと思う施策をご紹介しました。
健康管理・健康経営担当者はリソースが足りない中、必死に時間を割いて実施されている企業が多いと思います。
施策を有効的に活かせるように、
まずは、自社の従業員にどんな課題やニーズがあるのか
・ストレスチェック
・健康診断結果
└問診内容
などから課題特定。
ニーズはアンケ―ト等を行い把握したうえで、
施策を検討していきましょう。
また、効果検証においては、
施策のやりっぱなしにならないよう、成果を定量的に測定し、効果検証し、PDCAを回しながら改善していきましょう。
施策をサービス会社にお願いするなら、どのように効果検証をしたら良いかアドバイスや支援をもらって進めていくのも良いでしょう。
健康経営が普及してきたことで、取組む企業も増えてきましたが、
そもそも自社の課題やニーズが分からないまま
従業員向けの施策を始める企業や
施策を展開しても、そのままで効果検証ができていない企業が
増えている印象をうけます。
従業員がメリットを享受できるように何かしたい、とはやる気持ちもあると思いますが、現状把握・整理から戦略的に施策と検証が行えるように進めていきましょう。
FiNCでは、現状の課題整理の部分(健康情報の整備)から入らせて頂き、
具体的な改善施策・前後の効果検証
それを受けての次回改善案のご提案まで一気通貫したご支援が可能です。

金銭的な投資だけではなく、推進担当者のリソース投資においても
もったいない状況にならないように、戦略的に進められるよう
少しでもご興味ご関心をお持ち頂けた場合は、弊社までお問合せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
