
伸縮するカメラ ーータル・ベーラ『ヴェルクマイスター・ハーモニー』
ギリシア語には時間を表す語彙が2つある。一つはクロノス(χρόνος)、もう一つはカイロス(καιρός)だ。

ギリシア神話に登場する農耕の神。
クロノス的時間は過去から未来へと一定速度で一定方向に流れる時間の流れ、すなわち客観的時間を表しているのに対して、カイロス的時間は個々人が感じる時間の流れ、すなわち主観的時間を表している。

ギリシア神話に登場する機会(チャンス)の神。
20世紀文学最大の収穫は、このカイロス的時間が発見されたことだろう。バージニア・ウルフやジェイムズ・ジョイス、ウィリアム・フォークナー等に代表される「意識の流れ」文学然り、プルースト『失われた時を求めて』然り、「私」を一人称とした日本の私小説然り、語り手の主観的な「感じ」の強弱によって記述の密度が変化するような文学作品が多数登場し、主流化した。これによって文学は物理現象のみならず、個々の内面的な心理作用をも扱えるようになった。
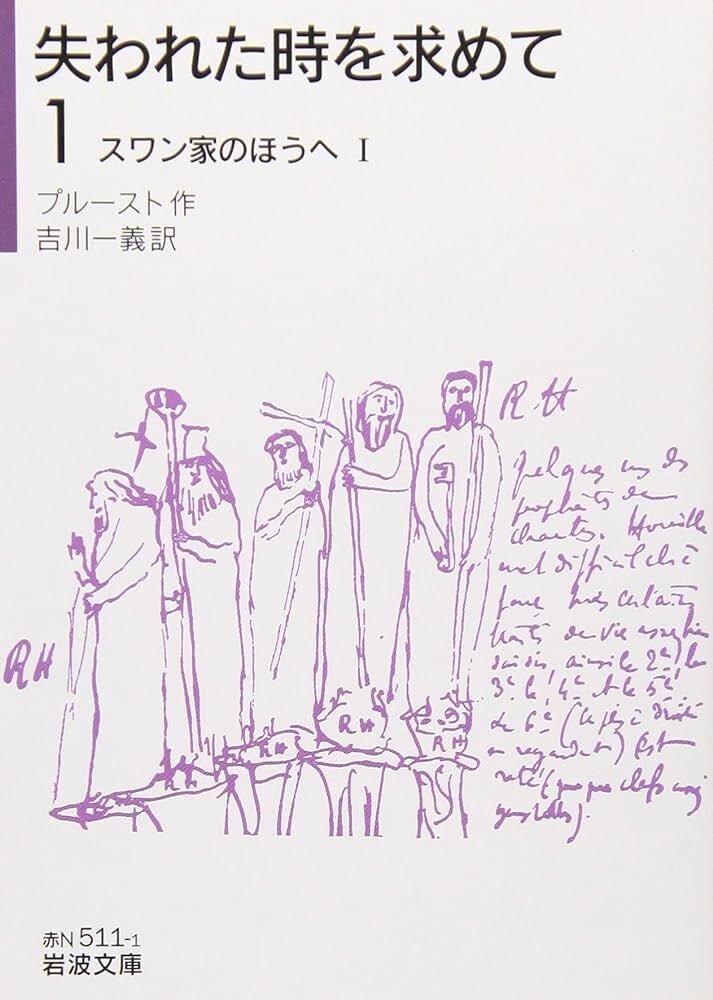
このように、今やカイロス的時間は文学上のレトリックとして広く流通しているわけだが、それというのも小説や漫画が物理世界の制約を受けない媒体であるからだ。小説や漫画の中の世界は個々の想像力の中だけで完結する空想世界であり、ゆえにカイロス的時間という超物理的な時間進行が許容される。
しかし現実世界(物理世界)において流れるクロノス的時間においては、一秒は絶対に一秒であり、罷り間違っても伸び縮みすることはない。ゆえに物理世界を部分的に転写し、それらを並べ替えることで初めて成立する映画という媒体において、クロノス的時間を描くことは非常に難しい。
というかそもそも映画は個々人の内面を描くことに強く抵抗してきた媒体だといえる。映画批評家の蓮實重彦あたりがいい例で、彼は徹底的に「映し出されているものだけを観ること」にこだわった(=表層批評)。彼にしてみれば心理描写を安易にモノローグで被せるような映画などはその時点で映画として「嘘臭い」のだろう。ここには映画という媒体におけるカイロス的時間の支配性が滲み出ている。

とはいえ自身の「感じ」によって眼前の世界が大きく変容するという事態は確かにある。でなければクロノスなどという概念は生まれない。
さて、映画という媒体において、主観的な「感じ」を表現する手立てはないのだろうか。本作『ヴェルクマイスター・ハーモニー』はこの問いに対する一つのラディカルなアンサーになり得ているように思う。

本作の特徴はなんといっても全編を通しての執拗なまでの長回しショットだ。長回しが印象的な映画作家は多いが、ここまでカメラ本体が多動する例は珍しい。たとえばテオ・アンゲロプロスなどはタル・ベーラに匹敵するほどに長回しの多い作家だが、しかし彼の場合は基本的にカメラは三脚に固定されている。
なぜタル・ベーラのカメラは多動するのか。もっといえば、なぜこれほど誇張的に対象への接近と離反を繰り返すのか。
先に私は文学における時間の伸縮とその効果について話したが、タル・ベーラはそれを時間ではなく空間という軸において成立させているのではないかというのが私の見立てだ。
郵便配達員ヤーノシュを追い続けるカメラは伸縮を繰り返す。たとえばヤーノシュが街にやってきた巨大鯨の見世物を見に行くシーンでは、カメラは遠巻きの位置からいつの間にかヤーノシュの目線そのものかと思われるくらい鯨の見世物に接近する。それはまるで鯨の見世物に対するヤーノシュの没頭ぶりを示しているようだ。ヤーノシュは鯨の見世物にオブセッシブな興味関心を示している。だからこそカメラという視界は近視眼的に局限される。

あるいはラスト、ヤーノシュの頭上をヘリコプターが旋回するシーン。線路上を歩くヤーノシュを追っていたカメラは次第に頭上のヘリコプターの方に引き付けられ、ズームインしていく。灰色一色の空に浮かんでいるヘリコプター、それを至近距離で見つめるカメラ。周囲との相対的な位置関係は失われ、ヘリコプターが画角の中を危うく揺れ動く。

「集中のあまり周囲が見えなくなる」という慣用表現があるが、これらのショットはまさにそれを技巧的境位において実現しているといえる。20世紀文学が時間を伸縮させることで主観的な「感じ」を効果した一方で、タル・ベーラは空間を伸縮させることでそれを成し得たのだ。
以下余談。
主観、という概念はタル・ベーラとアンゲロプロスの作家性を峻別するうえでも重要となる。
アンゲロプロスは映画を通じて歴史を記述することに腐心した作家だ。代表作『旅芸人の記録』や『ユリシーズの瞳』『こうのとり、たちずさんで』『シテール島への船出』からなる「国境三部作」が示す通り、彼の主たる関心は彼の故郷であるギリシャやその周辺国が経験してきた暗澹たる歴史のアレゴリカルな語り直しにある。

歴史は小説やエッセイとは異なり、記述の客観性によってその価値が担保される。ゆえに彼のカメラは常に被写体を遠く離れた位置に置かれる。恣意的なズームイン/アウトはしない。全体像をフィックスではっきりと見渡したうえで、そこに生成明滅する出来事を淡々と誠実に記録していく。
一方でタル・ベーラは「個人の感じ」(=小説、エッセイ)に照準を合わせる。ゆえに彼のカメラは自在に伸縮する。主体の心境に合わせて空間が恣意的に歪曲する。
アンゲロプロスもタル・ベーラも同じ「長回し作家」ではあるものの、両者の主眼は「客観-固定」、タル・ベーラは「主観-多動」というまったく正反対の系列をそれぞれ生成している。
さらに余談ながら、本作の技術的方法論は約20年の時を経てフー・ボー『象は静かに座っている』へと鮮やかに継承されることとなる。
極端な長回しといい伸縮するカメラワークといい、『象』はまさに本作の方法論でもって中国辺境に住む孤独な魂たちの呻吟を描き出した怪作である。

フー・ボーはタル・ベーラ本人をして「彼のまなざしにはある種の突出した個性があった。数百名の中国人映画関係者が私との共作を打診してきたが、私には疑いもなく胡波しかいなかった(http://indietokyo.com/?p=13133)」と言わしめたほどの俊英だった。そしてフー・ボーもまたタル・ベーラのことを「両親よりも大切な存在(同上)」であると崇敬している。
しかしフー・ボーは本作を最初にして最後の大作としてこの世を去ってしまった。タル・ベーラは彼の死を心の底から悔やんでいた。
「胡波(フー・ボー)から贈られた彼の本の献辞には「教父へ」とまで書いてあった。クソ、彼を救えなかった自分が残念だ。だが、誰が暴風のように荒くれた人間を救える?彼は世界を受け入れなかったんだ。世界もまた彼を受け入れないというものだ。」
近年ではタル・ベーラは監督業を事実上退き、世界各地で若手監督を発掘するワークショップを開催している。

日本人の中では『鉱』の小田香あたりが有名だろう。若手発掘に心血を注ぐタル・ベーラの脳裏には、ひょっとしたら中国の若き才人の死が常にちらついているのかもしれない。

今日はこの辺で。最後までお読みいただき、ありがとうございました〜。

(文責:第8電影支配人・岡本因果)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
