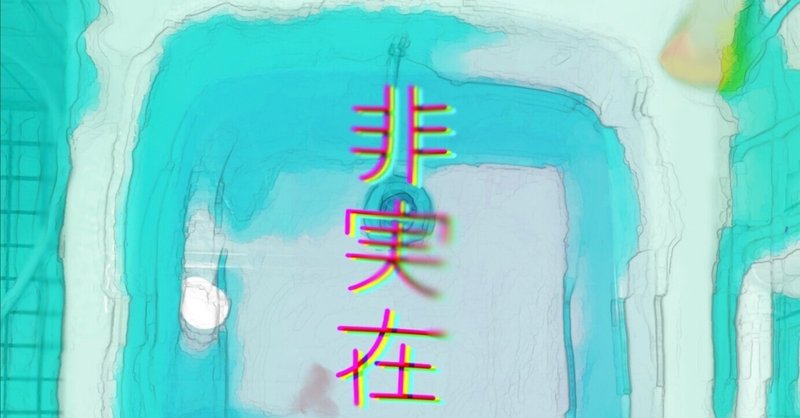
非実在院生
この物語はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は実在のものとは関係ありません。
俺の生き方だとか愛し方だとか愛され方だとか、俺の根幹に関わることを根掘り葉掘りきいてきた挙句にその主治医が「その考え方って今流行ってんの?」ときいてきたので俺はその病院には二度と行かなかった。病は気からというが違う。病は名からだ。名前がついたその時から、それは病になる。俺は病院にかかるのをやめて、その病名から逃れて、そうして「普通」の人間として生きている。二十三歳。K大学大学院の英文学研究室所属。専門は漠然と「アイデンティティ論」だと言っている。どの作家のどの作品で論じるかはまだ決めていない。ただ、その糸口は確実に文学にある筈だと信じている。それだけが確かだ。修士二年。季節は夏になろうとしていた。修論の提出は来年一月に控えている。焦りはある。生活は変わらない。
講義の受講態度は最悪のものだと自分でも思う。この間はある英文学作品に関するレジュメを邦訳版を参考にしながら書いたことが教授にバレて真面目にやれと釘を刺された。その教授は英文の精読にこそ重きをおく人だった。どうやらその話はその教授の弟子にあたる俺の担当教諭にまで及んだらしく、ある日の講義の後、俺は研究室に呼び出された。「アンドウさん、」と穏やかな口調でその人が言う。「どうやら〇〇先生に叱られたそうですね。」
「お恥ずかしい限りです。申し訳ありません。」
「何も僕に謝ることはありませんよ。」
俺は率直に恥入っていたし、この人が俺の罪の意識を罰してはくれないことも知っていた。ただ静かに、罰を求める自責の念が俺の瞳を泳がせる様を見ている。
「例の特質が出たんじゃないですか?」
俺がこの研究室にやって来たのは修士に上がってからで、つまり、今の担当教諭のもとでは二年目に入っていた。俺の「特質」については一年のうちから相談していて、今後「治療」によって「向き合っていく」のだとも言った。その時は真面目にそう思っていたのだ。向き合うも何も、そちらを向こうとする俺の中にこそ「それ」はあるのに。とにかく、俺の担当教諭はそういう事情を知っていて──病院を辞めたことについては話していないが──こうしてたまに気にかけてくださるのだった。
「……そうなんです。タスク管理が苦手で、特に忙しくなるとどれに手を付けていいか分からなくなってしまって──。」
そこでふいに涙腺が緩み、言葉を切った。流れるように口から洩れる言葉はまるで心理テストじみた「診断」サイトのチェック項目の受け売りだと気づいたのだ。俺の言葉で俺を語ることができなくなっていた。目の前のその人は微笑みとも真顔ともつかぬ顔をただこちらに向けている。
「僕の口から伝えましょうか、アンドウさんの事情を、〇〇先生に。」
「そうしていただけると、ありがたいです。」
後日、自室でレポートを書いているときに一通のメールが届いた。
「アンドウさんの多忙になるとタスク管理に支障が出る病について伺いました。事情を知らずに叱責して申し訳ありません。 〇〇」
病。俺は何も返さずにメールのウィンドウを閉じた。しばらく何もせず、座ったままただ天井を眺めていた。
深夜の研究室は大抵俺一人で使うことができた。俺はこの時間が好きだった。昼間は何もかもが俺の横をすり抜けてどんどん前に行ってしまう焦燥感が常に薄い膜のように俺を覆って、行動も思考も余計に鈍ってしまう。深夜は俺のための時間だった。一人暮らしのアパートから大学までは原付を運転して十五分。日付が変わってから大学まで出向き、研究室で紅茶を淹れ、そこで特段自分の修論とは関係のない本を読んで過ごす。そうしている間だけ、俺は俺のためだけの時間の流れに身を委ねることができた。しかし、その日は一学年下の後輩が遅くまで残っていた。同じ専門で、修論はソローで書きたいと言っていた気がする。この時間まで残っていることは珍しくなく、時折こうして顔を合わせるのだ。研究熱心で周囲からの信頼も厚い。俺とは対照的だ。俺はそれだけでこいつのことを嫌っていたし、その理由の浅ましさも理解していたので余計にバツが悪かった。要するにこいつへの嫌悪は俺自身への嫌悪なのだ。とはいえ、いやだからこそ、それを表に出すわけにはいかない。
「君も紅茶はいる?」
苦し紛れに、そして気を紛らわすために紅茶を淹れなおしに席を立つ。俺はいつもどこかに紛れることにばかり真摯だ。「お願いします」という短い返事を聞いてポットにティーバッグをたらす。沈黙。そいつに紅茶を差し出して席に着く。何か論文を読んでいるらしい。やめてくれ。それを目に入れないように本を開く。ふと何か会話をすることもあるが、それは次の日には忘れているような、そんな当たり障りのないものばかりだ。他の同期であれば研究の相談にでも乗れたのだろうが。しばらくはそうして粘っていたのだが、遂に俺はその時読んでいた『視覚論』から顔を上げ、ため息をつく。ゴングがわりである。ノックアウト。この空間に打ちのめされてしまったのだ。
「いい加減に帰ろうかな。」
事実、もう少し待てば日の出が見られるほどの時間だった。独り言ともつかぬそれに後輩が同意する。時の流れから俺を匿うシェルター──今日はまるで逆だったが──研究室はまたしばらく経てば足音と会話とキーボードのタイプ音に溢れた時の権化へと様変わりする。それまでの間、誰にも知られぬ真の沈黙をその内に宿すのだ。
六階の研究室から駐輪場までは結構な距離がある。他愛もない会話が続く。後輩は最近買ったばかりの車で通学しているらしい。俺は素直に羨ましがる。こんな時間の車も人気もない街を安全な箱の中から眺めながらただ気の赴くままに走り続けられたらどんなにいいだろう。「今度ドライブに行きましょう」とそいつが提案する。その突飛さにしばらく呆気に取られたが俺は同意する。大学から離れたどこかへ行きたかった。そうすれば案外こいつとも上手く話せるようなそんな気がしたのだ。原付のエンジンを入れつつ昼の講義までどれだけ眠れるかの算段を立てる。眠る前に薬を飲まなければならない。「普通」の俺はそうして「普通」に眠るほかないのだ。
キッチンの壁にマグネットでメモが貼り付けてある。「△△ 21時から22時服用 23時から24時就寝目標」。まだかかりたての頃の主治医の手書きだ。△△は錠剤の名前で紙はもう油染みでぎとぎとになっている。病院に行かなくなってからしばらく経つ。薬はもう底をつきかけていた。その事実が余計に俺の焦燥を掻き立てている。薬を貰うには病にたよらなければならない。どんなに逃げようと結局のところ病はそこにある。一度は名を与えられたのだから。薬を飲まずに眠れないよりも薬を飲んででも眠ってしまうほうがずっと健康的だ。知っている。この△△というのが俺に内在する病の治療薬で、といっても完治する病ではないので症状を和らげるものにすぎないのだが、一日に一度眠る前の服用を継続する必要がある。飲むと二時間後には猛烈な眠気がおとずれる。それがこの薬の副作用なのだが、不眠症でもあった俺にはプラスに作用するものだった。主作用は意欲障害の改善とだけされている。身体こそ最も身近な他者だ。俺はずっとそいつと折り合いがついていない。水を用意するのも面倒なので薬を口に放り、唾液を溜めて飲み込む。そういや次の講義で今期は終わりか、などと考えつつ寝支度をしているとやがてそれが効いてくる。入眠する瞬間に漠然とした、それでもどうしようもない焦燥感が押し寄せるが薬の効いた身体にねじ伏せられて無理矢理に鎮静させられる。ただ死んだように眠る。眠るしかないのだ。眠っている間だけ、俺は外からも内からも自由でいられる。
「担当範囲はp.485から本作最後までです。それでは要約から……。」
その日の講義はカズオ・イシグロの長編小説 Never Let Me Go の購読だった。講義では基本的に担当者が持ち回りで振り分けられた範囲の要約をし、所感と考察を交えたレジュメを配布して発表を行う。幸い今期最後の発表をすでに終えていた俺は消化試合よろしく同期の発表を聞き流していた。終わりが来ないのではないかと思われた長編小説にも最後のページは存在する。講義が終わる。前期が終わる。
「先輩!」
講義室を出ると件の後輩に話しかけられた。これから夏休みだという解放感が昼間のキャンパスを覆っている。講義室から研究室へと向かう道すがら、そいつと俺もいつになく打ち解けて話せていたように思う。明日にでもドライブに行こうと話が決まる。「寝坊するなよ。」「そちらこそ。」
研究室で少し資料の整理をしてから、もうしばらく残って論文を読む予定だというそいつと別れる。飲み物でも買おうかと構内の自販機の前で財布をあけた拍子に学生証を落とす。それを拾い上げ、何となしに時間をかけて眺める。深夜に大学に入るためのカードキー、それか学割を受けるためのクーポンと化していたそれを改めて見直す機会などそうない。まだ学部の時分に撮った青背景の俺が感情のない目でこちらを見返している。その横にそいつの身分を指す文言が続く。K大学20XX年度入学、学籍番号、人文科学府、英文学専攻、安藤瞳美、生年月日、上記の者は本学の学生であることを証明する。俺に俺自身を認識させるように注意深くそこに目を通す。Kダイガク、20XXネンドニュウガク──アンドウ、ヒトミ。平面の俺と今度は確実に視線がぶつかる。気味が悪くなり視線を逸らす。そいつはこちらを見つめ続けている。俺は学生証を財布にしまう。考える。この構内にいる限り俺を俺だと証明するのはいまここにいる俺自身では無くあの所在無げな目をした俺の方で──。「大丈夫ですか」と声をかけられて我に返る。学部生だろうか、自販機の前で立ち止まったまま動かなくなった俺を怪訝そうに見返している。「……買いたいんですけど。」そう言われてようやく意味を理解しその場を離れる。自分が結局何も買わずじまいだったことに気づいたのはその後だった。
自分の名前が好きではなかった。名前に持たされた意味への違和感。記号への嫌悪だった。それは名付け親の意図と関係なく、秩序の中に意味を持って俺を規範に縫い付ける。幸い、院の人間はどんなに親しくともみな名字で呼び合っていたし、それは気が楽でよかった。姓は名前よりもそこに伴う意味が希薄である気がしていたのだ。しかしそのことが皮肉にも「俺」という人格が「アンドウ」という音の元に確立させられることを俺に強いていた。名前から俺たちは逃げられない。俺の意識が音から、音が持ち始めた意味へと逸れていく。アンドウ、フランス語で1、2はun, deux——はじまりの音だ。それから、英単語のundo──結果を台なしにする。名前に対しランダムに割り振られたはずの姓が意味を持ちはじめる。まるでそこに俺の運命が紐付けられているかのように。高次元の支配者に貼られたラベルのように。俺が俺であるために、姓でも名でもなければ俺は何を依り代にすればいいのだろう。何かを依り代にしなければ俺は俺でいられないのだろうか。なぜ俺はそんなところに執着するようになったのだろう。
(喉が渇いたな。)
別の自販機を探そう。昼間のうちに軽く散歩するのも良いかもしれない。移動し続けることこそ唯一、時間から逃れる術なのだ。
俺がこの大学院に来る少し前にキャンパスごと移転してできたこの一帯の景観は山を切り拓いてできた土地に近未来的で巨大で無機質な建物が突然現れたような、都市開発シミュレーションゲームの途中で放棄された街のような、そんな歪さがある。歪さはどこから来るのか、それは不完全さに対する不安かもしれない。といっても人間は「完全」を知っているわけではない。人間が知り得るのは不完全さだけだ。不完全さから完全を汲み取り、そうしてできた不完全な物差しで不完全さを測るのだ。そんなことを考えながら歩を進める。移動に倣って思考は緩やかに転調する。F-E-Am……かと思えば突然脈絡なく過去の記憶のフラッシュバックに一人顔を顰めたり綻ばせたりする。思考はジャジーだ。コの字型の研究棟のうちに作られた中庭は Never Let Me Go に登場する寄宿舎ヘールシャムを想起させる。主人公らはそこで社会から断絶させられながら成長する。臓器提供用に生育させられているクローン人間なので、外界の人間の目に触れないように/外界の人間を目にしないように隔離されているのだ。物語は主人公キャシーの独白から始まる。「わたしの名前はキャシー・H。いま三十一歳で、介護人をもう十一年以上やっています。」
寄宿舎を出たクローンたちは臓器の〈提供者〉になるまでの間、「提供」を終えたものを介護する〈介護人〉を務める。〈提供者〉はその介護に頼りながら死ぬまで「提供」を続けなければならない。そして〈介護人〉もいずれ〈提供者〉側にまわる。そういう運命のもとに生まれてきたのだ。だから主人公らクローンは社会に反抗の声をあげることもない。それが運命だから。
中庭を通り過ぎながら子供の頃のことを思い出していた。俺は何かを部屋の中で探している。ちょうどそこにやってきた母にたずねる。「〇〇、見なかった?」。母は答えない。代わりに、俺の部屋の机の上を探り出す。俺は言う。「いいよ、自分で探すから」。母は叫ぶ。「あんたが探せっていったんでしょ!?」俺は面食らって何も言えなくなる。そしてなおも俺の机の上を漁り続ける母を見ている。俺の領域が荒らされていく。俺が俺のためだけに書いた文章が、描いた絵がむやみに暴かれ、価値を失っていく。秘匿によって美しさと価値を保っていた俺の世界が崩壊していく。それと一緒に俺自身がどんどん矮小になっていく。もはや母が〇〇を探しているのかも分からなかった。ただ俺の部屋、俺の机、俺の思想、俺の領域の全てを踏み荒らし、その無価値さを見せしめられている。俺はただ立ち尽くしている。俺はそもそも探してくれなんて頼んでいない。見たか、見ていないか、それだけを答えてほしかっただけなのに。俺が思い出せたのはそこまでで、その後結局〇〇が見つかったのか、そもそも〇〇が何だったのかすら思い出せない。母は何故、「〇〇見なかった?」を「〇〇ヲ探セ」に変換せざるを得なかったのか。理由は単純だ。そう変換することが、その変換を意識させないほどに当たり前になっていたからだ。それを通常とした異常な空間で俺たちが生きていたからだ。母はそもそも秘匿性を持ち得なかった。母は「母」でいなければならなかった。それは俺の存在のせいだ。そしてきっと父の。
十年前、俺が中学生の頃──過去のことを考えようとすると脳が締めつけられるような感覚をおぼえる——俺、母、父。三人家族、というよりはアンドウ夫妻と俺。その三人で暮らしていた。俺だけが戸で仕切られた、俺のための部屋を持っている。夫妻は基本的にリビングで過ごしている。食事の時間になれば俺は呼ばれる。三人で食卓を囲む、いや、はじめから三人であることはない。二人。俺と父。母はまだラップのかかった皿をレンジに入れたり、炊飯器から米を人数分よそったりしている。その間、俺は透明だ。夫妻と俺の間には同じ食卓を囲おうが、見えない壁がある。夫の方は、こちらに背を向けて台所で忙しくしている妻にむかって仕事の愚痴を吐き続けている。俺も知っている名前が出てくる。父は俺が通う中学の教師だった。俺の仲がいいクラスメイトの家庭事情が、成績が、嫌でも耳に入る。両親が離婚するらしい。私立には通えないらしい。公立には受かりそうにないらしい。それを聞いて俺は思う。ああ、もうあの子とは心底から仲良しだとは思い合えないのだな。俺は、あの子の許可なくあの子の領域に踏み入ってしまった。俺の意思とは関係なく。父が、人形のように動けない俺の足を何も言わずに掴んで、あの子の笑顔の写真を何度も何度も踏ませるイメージが頭に浮かぶ。あの子の顔が歪む。そしてもう戻らない。俺はあの子のことが好きだった。大好きだった。でももう駄目だ。もうあの子と対等に会話を楽しむことはできなくなってしまった。怒りがあった。殺意さえあった。それでも俺はその場では黙っているしかなかった。俺は透明なのだ。たとえ、俺の意思がどんなに濁った色をたたえていたとしても。父の目に俺はうつっていない。きっと母もうつっていない。父と、父の語りたいこと、それだけだ。俺は目の前の食事に手をつける。機械的に口に運び、咀嚼する。そこで父がはじめて俺を見て言う。「箸がない」。「取りに行きなよ」と台所を指す。父は動かない。やがて母がなにかおかずが盛られた皿を持ってこちらにやってくる。「ハシガナイ」。またその音が発せられる。妻は謝罪する、そして台所へ戻っていく。箸が持ってこられる。ようやく三人の食事がはじまる。くちゃくちゃという三人分の咀嚼音に気持ちが悪くなり、今飲み込んだばかりの食事とともに胃液が込み上げる。目に涙が滲む。それを無理矢理に飲み込む。何もかも飲み込むしかないのだ。
息苦しさをおぼえて意識は現在の俺へと戻ってくる。「ハシガナイ」は「箸がない」以上の意味を持たないはずだ。しかし母に対しては「箸ヲ持ッテコイ」という命令として作用する。母は言葉の元の意味をとうに忘れてしまったのだ。「ハシガナイ」という音と命令、それに対するプロトコルの実行。ただ従う。そして感情も意志も価値を無くす。異常だ。これを言語化しなければならない。漠然と、しかしある種の責任感と共にふとそう思った。俺は俺を語りたいのだ。音ではなく、文字として。時間を超越して、どんな抑圧にも抗って。それでも語りは言葉に依存しなければならない。語り自体が持つ抑圧から俺は逃れられない。無力だ。
前方に自販機を見つけてようやく冷たいコーラにありつく。額に滲んだ汗を手のひらで雑に拭う。プルタブを開け一度に天に向けて傾ける。喉が灼けるような炭酸の感覚にむせる。俺は生きている。己の感覚を伴って。
その日の帰り道に生理がきた。原付を運転する股に机の上でコップを倒したようにじわじわと血だまりができていくのが分かる。悟りと諦観。そのまま途中にあるスーパーに寄ってトイレにはいる。鮮血に染まっていた下着のクロッチに何度かトイレットペーパーを押し付ける。際限がないのでペーパーを四重五重に巻いたものを取り敢えず股とクロッチの間において個室を出る。その間も血は流れ続ける。血液を吸ったペーパーがすぐに重みをもっていくのが分かる。帰りついたらこの下着から血濡れてぐずぐずになったそれを取り除いて手洗いしなければならない。そのまま洗濯機にいれて回そうものなら白い布地は全て血染めになってしまう。
目には目を歯には歯を、血には血を。そのスーパーで豚レバーを買って帰る。自室のトイレで再び下着を確認すると、血で重くなったトイレットペーパーが下着にへばりついている。豚レバーみたいだなと思う。一連の作業を終えて、本物の豚レバーを適当にフライパンで焼きながら焼けた順に食べていく。米は面倒なので炊いていない。目の前に生の内臓がある。この赤黒くぬらぬらとした肉片は自分の中身とそう大差無いのだろう。豚レバーを噛みちぎりながら意識はめぐる。子宮──。Hysterie の語源は子宮を表す接頭辞 Hyster- からきているという。女とヒステリーは同義に語られる。女性身体の特徴としての子宮はその器官の名前とは全く異なる社会的意味に紐づいて女性特有の「病」とされたのだ。俺は咀嚼する。ただ飲み込み続ける。食事を終えて風呂に浸かる。張られた湯に血液が滲んでいく。股から龍が昇っていくような模様を描いて。鉄の匂いがする。羊水だ、と思う。ここは子宮だ。俺は胎児だ。胎児の俺の子宮は絶えず出血し、一層この湯船を子宮たらしめていく。俺はやがて自らの足でそこを脱する。羊水の浮力に頼らず、その足で重力に抗う。俺が俺として産まれる。脱衣所で自らの手で水滴を拭う。この部屋に一人でいる限り俺の精神に名前は無い。俺の身体は意味付けされない。俺はただ俺としてここに存在する。風呂場を振り返る。点々と血溜まりができた洗い場は出荷後の屠殺場のようだった。
翌朝、大学の駐車場で後輩と落ち合う。新車の助手席は汚すまいと大きなナプキンを股にあてがっている。それ以外は気分良好。日和も良い。大学を離れるごとに気は大きくなり、それは全能感の域にまで達する。海沿いの道を走りながら窓を全開にする。
「クーラー効かなくなるじゃないですか。」
「この空気を直にかがなくてどうするんだよ。」
目に映る何もかもが時速60キロで通り過ぎていく。その様を安全な箱の外だけの出来事にしておくにはもったいない。窓を開けたことで内と外の境はなくなる。髪をなびかせる風に潮が香る。
「先輩って存外、体育会系なんですね。」
車は行く宛もなく走り続ける。海沿いに道がなくなれば折れてもう一度海に向かって進む。そうやって蛇行しながら会話は移調していく。
「先輩は自分で小説書かないんですか?」
「書いたことはないな。なんで?」
「きっと向いてるだろうと思ったから。」
「君は書かないの?」
「僕は小説として書きたいことはないから。」
県境を越えて、さすがに戻ろうかときた道を引き返す。途中、適当に入った店でガソリン代にと飯を奢る。日が落ちる頃に大学に着く。また近いうちにどこかに出かけよう、と話して後輩と別れる。俺は研究室に向かい適当な本を開く。しかしその内容は読んだそばから抜けていく。後輩に言われたことがずっと気にかかっているのだ。
「先輩は自分で小説書かないんですか?」
「僕は小説として書きたいことはないから。」
俺には小説として書きたいことがあるだろうか。小説としてしか書けないようなことが。アイデンティティ。ふと、俺の研究テーマを思い出す。どうしてそれを論じたかったのか。
人と話すことが好きだった。俺が話す。相手が笑う。しかし徐々に異変に気づく。話が食い違っていく──人は話の理解が追いつかない時に笑うのだと知ったのは最近になってからのことだ。俺が話す。相手が笑う。理解できないので笑う。俺の語りは虚空に消える。チャイニーズルームという思考実験がある。人工知能は人間のようには物事を解さないと主張するために考案されたものだ。部屋に中国語を理解しない人間と、中国語の応答に関するマニュアルがある。外部から紙に中国語で書かれた質問が投げ込まれる。中の人間はその紙の文字をマニュアルに従って変換し、別の紙に書き、その紙を外に返す。外の人間からみれば中国語の質問に適切な答えが返ってきたようにみえる。しかし中の人間は実際にはなにも理解していない。そんな内容だ。それでも俺は語り続ける。部屋の仕組みを知ってもなおひたすら手紙を送り続ける。そしてとうとう部屋の中から出てきた人間が俺に向かって告げる。
「お前、何言ってるか分かんないわ。」
そこで俺の語りは無駄だったことを悟る。院に進学してからそのようなことは起きづらくなった。学問の話をしている間、俺と相手の間に壁はなかった。しかし周りと比べた俺の浅学さに段々と気づき始めてから今度は俺が壁を作るようになった。俺を守るための壁を。覆い隠す部屋を。相手が話す。俺が笑う。
俺は忘れていた。そして思い出した。俺は俺の言葉で俺自身を語りたかったのだ。たとえ言葉それ自体の抑圧に抗えなくとも。言葉を使って言葉を超えたかったのだ。
俺ならどんな小説を書けるだろう。私小説だ、と思う。俺による俺の一人称小説。例えば一人で思い耽る時に自らの一人称を気にする人間がいるだろうか。思考する主体である自分はただ一人だからそれと他者とを区別するための人称は必要なくなる。己が真に解放された個人になるのは己の思考のうちでのみだ。しかしテクストの上でそれを語るのは「俺」だ。 俺を「俺」と呼称することには特段意味もない。それでもつい先ほどまで自由だった俺の思考を言葉に変換していく過程で損なわれ、縛られていくものを出来る限り小さくする手段、それが一人称の選択なのだ。「書くこと」による表現は自由の体現ではない。むしろ型にはめていく作業なのだ。
本に集中できないので席を立ってぼうっと事務作業に手をつける。コピー機に用紙を補給する。用紙を包んでいた薄茶色の包装紙を雑巾絞りしてからゴミ箱に捨てる。人糞みたいだ、と一瞬思う。 それからまた俺のための一人称小説のことを思う。俺に書けるだろうか。俺は俺の存在を言葉にできるだろうか。
彼岸花が咲き、コスモスが咲いた。秋になった。俺の意識は修論のために割かれ、俺のための一人称小説には結局着手できないままでいた。俺が"I"と原稿にタイプするたびに、そのたった一画に集約されてしまった小さな俺があらわれる。I, I, I ……一枚の原稿の上に何体もの小さな俺が蠢いている。執筆内容よりもそんなところばかりを気にしている。書いては手をとめ、空想にふける。そういうわけで作業は全く進まない。俺たちは名前に取り憑かれている。固有名詞、そして代名詞──俺、私、貴女、貴方、彼女、彼……。神の名前を表す神聖四文字、テトラグラマトン。YHWH──ヘブライ語に母音はないので正確な音は分からない。ツイッターをひらき、「テトラグラマトン」と打ち込んでみる。なんとなくその下に「テクマクマヤコン」と打ち込む。俺が生まれるずっと前からあるアニメの魔法少女の呪文だ。「テトラグラマトン、テクマクマヤコン」、送信。そしてすぐに気恥ずかしくなり、ツイートを取り消す。時間はただ過ぎる。怠惰に過ごせるならよほどいいが、違う。焦燥があるのに身体が重く動かない。ただ怠惰に過ごす以上に俺は怠惰なのだ。観たいものもないのに動画サイトを行き来する。そのうちにある人についての短いドキュメンタリーにいきつく。
その人は七秒ごとに記憶を失う。脳に炎症があるのだ。今しがた会ったインタビュアーの顔もその役柄も七秒経てば忘れる。そこでメモをつけ続けている。似顔絵や席順にいたるまで。常に分厚い手帳を持ち歩く。そんな暮らしを十年以上続けている。まるで探偵だ。追跡対象のメモをつけつづけ、それと同時に対象によって残されたメモを解読しつづける。自らを追う探偵。その生活に強く興味をひかれる。長期記憶に残っているものについては問題ないらしい。例えば自分の名前を忘れることはない。しかし短期の記憶はできない。その人は病にかかって以来映画を観ることも小説も読むこともしていないという。携帯電話の使い方も覚えられないのですぐに解約。車の運転方法は覚えているが、新しい道を覚えるには何度も反復してそこを運転して記憶に定着させる必要がある。たとえ片道五分のスーパーまでであっても。初めて会う人間は写真を撮る。その人の部屋には十数年分のメモとさまざまな顔写真が月ごとで整理されて保管されている。それがその人の記憶なのだ。その人の内に無くとも外部に保存され可視化された記憶。確かに在ったもの。そして在りつづけるもの。
その人が引越しをすることになった。膨大な量のメモをそのまま持っていくことはできない。記憶の選別が始まる。メモを一枚一枚見返し、覚えておきたい記憶だけを手帳につけ直す。見返すことで記憶が蘇るわけではない。ただそうした事実があったということだけを受け止める。「形にのこす」、そのことが重要なのだ。そして「のこさない」側はシュレッダーにかけていく。記憶の削除。もう二度と参照されない確かに在ったもの。その人にとってはすでに自らの手を離れた記憶であったとしてもシュレッダーでばらばらにされ、形を失っていくことは耐え難いだろう。あまりにも呆気なく形あった記憶は紙屑になっていく。そしてその人自身の手でゴミ袋に押しやられ、捨てられる。
引越した先でまた一から生活を積み上げていく。周辺の道を覚えるためにその人は歩き回る。その先で友人もできる。人と会うとき、その人は相手との以前の会話のメモをまとめて手帳に挟んで持っていくのだという。「脳みそ作ってるんやな」と友人が言う。「脳みそ作っとんねん」その人がこたえる。その会話もまたメモにのこされる。「記憶とは人生だ」とその人はインタビュアーに語る。その力強い目。
動画サイトを離れる。しばらくぼうっと考える。人間はあまりに記憶に依存している。そして記憶を保存する内部メモリとしての脳に。ハードとしての身体に。内部メモリに問題があれば外部にハードを増やしていく。そして記憶を圧縮するための機能として名前がある。部屋を見渡す。テレビ、机、椅子、クローゼット、全てに名前がある。たった数文字の中にその役割まで全て語られる。先の人も自分自身の名前を忘れることはない。その名前のもとにその人が生きてきたからだ。だから短期記憶が消えていったとしても自分自身を失うことはない。俺たちは生きている。記憶に依存しながら。名前に依存しながら。
さらに日が経ちやがて薬が尽きる。怒り、悲しみ、焦燥、全てが増幅されて感じられる。眠れない。俺の内で思考する俺を常に感じる。それは攻撃的で感傷的で、そして真理と正義に飢えている。その俺に心身を預けているうちは不思議と心地が良い。薬によって抑えられていた生の実感が溢れ出したようにさえ思われる。憑かれたように出鱈目に文章をタイプし続ける。修論とも小説ともつかないそれを横断しながら言葉が溢れては止まらない。修正もない、註釈もない、引用もない。どこへ向かっているかも分からない。溢れた生の実感がそのまま指から流れ出し、キーボードを打ち、具現化していく。そうして時間は過ぎる。しかし時計の針にもその指す数字にもそれ自体に意味はない。俺が俺としていまここに生きているにすぎないのだ。この話に望まれる帰結はない。この話は、これで終わる。
非実在先輩
「君も紅茶はいる?」
英文学研究室、深夜一時。クーラーが低く唸っている。先輩がガラス製のポットにティーバッグを垂らしながら言う。お願いします、と返すとそこになみなみとお湯が注がれる。先輩の銀縁の眼鏡のレンズがその湯気に曇る。僕はこの時間が好きだ。つまり、この狭い研究室が世界の全てで、動的なものは僕にとっては先輩、先輩にとっては僕しかいない時間である。もっと近づきたい、と思う。その曇ったレンズの向こうにあるはずの長いまつ毛と、それに縁取られた瞳と白目のはっきりとしたコントラストを確認したい、と思う。先輩のレンズの曇りが晴れる。しばらくして一杯の紅茶が僕の前に差し出される。今度は僕の黒縁眼鏡のレンズが曇る。ありがとうございます。どういたしまして。緩やかに時が流れる。
先輩はいつも違う本を読んでいる。文庫だったりハードカバーだったり、小説だったり専門書だったりする。僕はその隣で論文を読んでいる。そういえば僕は先輩の専門をまだ知らない。アメリカ文学で、特にポストモダンが興味の対象であるらしいことは確かだ。僕は先輩のことを、僕が見ているあいだ分だけしか知らない。だから、その限られた情報からこの人を解釈するほかない。
僕はどうやら今まで触れてきた周りの人たちよりいくらか「解釈する」ということに長けているらしく、その能力を過信して文学者の道を志すに至ったわけだが、学部から修士にあがってから、どうにも文学をするということと解釈をするということは異なるらしいということを知った。文学をするには解釈で終わってはならない。その解釈を歴史や秩序のなかに位置づけなくてはいけないし、もっというと「身振り的」にしなきゃいけない。つまり、非言語的でありながら言語に対して強く作用する何か、理性を形づくる動物的な何か──であると僕は解釈しているのだが──そこまで落とし込まなければならない。僕に先輩を「文学する」ことは可能だろうか?先輩を解きほぐし、その本質を実存の先輩から解き放つ──ここで僕の思考は何故か先輩と僕を巡るエロティックな妄想に流れていってしまったため、慌てて中断せざるを得なかった。紅茶で唇を湿らす。視線を先輩に向ける。今日は図書館で借りたらしい、表紙のくたびれた洋書を読んでいる。先輩が僕なんかよりずっと「解釈する」ことに長けているらしいのは院の講義を通じて思い知らされた。四月の頃はすっかり自信を失ってしまってドロップアウトを本気で考えたほどだ。先輩は僕のことも解釈しているのだろうか。もっとその先、つまり僕を文学することもあるのだろうか。あるといいな、と僕は思う。僕から解き放たれた僕が先輩の「身振り」になっているならば、こんなに嬉しいことはないな、と思う。先輩は洋書に視線を向けたまま、時折紅茶を口にする。唾を飲みこむ。呼吸をする。この研究室に、この世界に、動的なものは僕と先輩以外に存在しない。一生このままでいい、と思う。この研究室だけが広い宇宙にぽかんと浮かんでいるところを空想する。それ以外は全て滅んでしまって、あらゆる学問もあらゆる権威も無くなってしまったあとに、僕らは笑いながら文学の話をする。僕らは一生この研究室の中にいるままに宇宙を旅する。カーテンを開ければ外を星が流れていく。先輩が尋ねる。君も紅茶はいる──?
ふぅ、と先輩が溜息をつき、それと一緒に僕は現実の研究室に引き戻され る。いい加減に帰ろうかなぁ、と席を立ちながら鞄から原付の鍵を取り出す。じゃあ、僕も帰ります。そして一緒に研究室を出る。電気を消す。人が消えた深夜の研究室は誰も知らない小さな宇宙になる。
六階の研究室から駐車場までは結構な距離がある。その道中、先輩は僕が最近車を買ってそれで通学していることをしきりに羨ましがる。今度ドライブに行きましょう、と提案する。先輩がそれに同意する。先輩を乗せた助手席を空想する。研究室なんかよりもずっと近くに先輩がいる。僕と先輩を乗せて車は走る。目に映る何もかもが忙しなく動いている。僕と先輩の間にだけ緩やかに時間が流れる。僕らは笑いながらおしゃべりをする。文学とは関係ない、他愛のないおしゃべり──。先輩は駐輪場の方へ、僕は駐車場の方へ歩いていく。お疲れ様。お疲れ様です。そうして帰路につく。
好きです、と呟くと狭い車内にその声が響き、誰もいない助手席に呪いのように染みついていく。僕の呪いが染みついたその席に何も知らない先輩の背中や尻が密着するところを想像して僕の口角が上がる。好きです、好きです、スキデス。口にするごとに意味よりも音に僕の意識が移っていく。丑の刻参りみたいだな、と思う。僕の口から絶えず打ち出される杭がその一言ごとに先輩を呪う。どうかこの呪いが先輩を殺してしまう前に、僕は先輩に殺されたいな、と望む。先輩の細い指が僕の喉元にかけられる。甘美な痛みと苦しみに酔いながら僕はうわ言のように溢す。スキデス。スキデス。そんな映像が頭の中を流れる。僕の視点で、先輩の視点で。僕はその日、眠りにつくまで何度も何度もその映像を脳内に流し続けた。朝起きてからは少し正気に戻って、昨晩の狂気を内省しながらパソコンで地図アプリを立ち上げてドライブの行き先を考えた。けれども、きっと先輩は──僕もだが──行き当たりばったりの方が好きだな、と思ってそれを閉じた。
よろしくお願いします。
