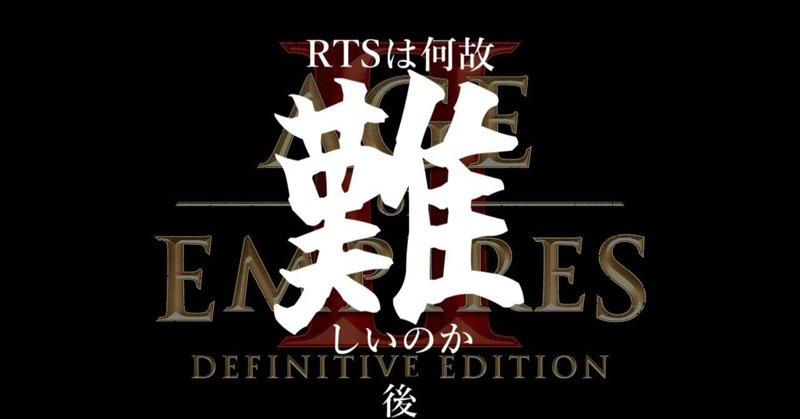
RTSは何故難しい?後編
前回はプレイする人がRTSを難しいと感じる原因となるであろう点を考えました。
今回は作品制作と観戦実況という面での難点を挙げていきます。
作品制作には動画や配信だけでなく、攻略サイトの運営なども含めていきます。ファン活動全般といったところでしょうか。
他人が作った物にただ乗っかっているというか間借りしているような立ち位置ではあるので、「コンテンツ発信」と呼ぶのは仰々しい感じがしてしまいます。
ですがそういった活動自体がその作品のファンがそこに住み続けるための一助となっているというのは、どの界隈を見ても疑いようがありません。
観戦実況も同じです。観戦のための映像は公式非公式関わらず、大会が開かれるという時には重要になりますし、そもそも観戦実況がしづらければ大会を開く意義も半減してしまいます。
この記事ではRTSのゲーム性がファン活動の内容や制作の難易度、成果にどう影響を与えるのかを考えていきます。
「製作する側の実力、努力が足りない」いう方面ではなく、「ゲームが悪い」という方面から話すことになってしまいますが、ないものねだりの愚痴話にならないようには気をつけたいと思います。問題点をはっきりさせておこうという話です。
なおこの記事は後編であり、さらに前々回の記事"何故AOE2なのか"の内容を踏まえての物となります。AOE3であればある程度解決することも多いのですが、プレイ人数も経過年数も多い以上、この記事でも前回同様RTS=AOE2として考えていきます。
■要素と原因
動画作成、配信、観戦実況の共通要素を抽象化すると、見る、見せる、説明するとなります。
動画と配信でそれぞれ分けて書いていきますが、抽象化された要素から見ると、ある程度は難しさの原因は共有している部分が出てきますので、書き出しておきます。
- リアルタイムである
- 戦略性を売りにしている
- 1ゲーム完結で、ゲーム時間が長く、ラウンド制ではない
- 見下ろし視点で絵が地味
■動画制作から見た難点
"4年間の活動を振り返る"という記事で過去の動画制作で何を思ったのかという分析を詳細に書きましたが、今回は別の角度から見た物を書いていきます。
・カットしづらい
前回、前々回とゲーム時間について触れてきましたが、この話は動画制作にも影響してきます。
一般的にプレイ動画はできれば10分程度に収めるのが望ましいとされています。ストレスなく見れるからです。
AOE2を1ゲーム収録すると、対戦人数やゲーム設定にもよりますが、元動画は40分くらいになります。
これでは長すぎるので、当然カットするという選択肢が生まれます。
しかしAOE2はカットしづらい作りになっています。
カットがしづらい、というのは2つの要因によります。
因果関係が遠く広いゲームであることと、ラウンド制ではないということです。
AOE2は多くの場面で、操作がその場で完結せずのちに影響を与える作りになっています。
内政時間であれば飛ばすこともできますが、攻略情報を必要としている人の事まで考えてしまうと内政構築手段もある程度納めたいところです。
ではパートを分割するかと言われれば、それはそれで内政や探索だけの動画が生まれてしまい見どころが作れません。
一般的な内政や探索をメインとしたシミュレーションのように、1マップをじっくり時間をかけて攻略するというゲームでもないのです。AOE2に「この動画の中で粉ひき所と伐採所を建てました!」という動画は存在しません。
まさに帯に短し襷に長しといった中途半端さです。
・ラウンド制ではない
ラウンド制のゲームであればこういったことは解決できます。ラウンド制とは格闘ゲームはもちろん、FPSでも古くからある形式で、1ラウンド数分程度のものを数本先取するとゲームに勝利するというゲームです。
もちろんAOE2のようなRTSにラウンド制など取り入れられるはずもありませんが、動画や実況といった面から見るとラウンド制は利点に思えます。
ここ数年は無料FPSと言えばバトロワ形式というイメージが強くとなっていますが、最近ではVALORANTが盛り上がっています。毎ラウンド武器やスキルを購入しなければならない、敵を倒してアルティメットスキルを溜めなければならないという、ラウンドに跨ったリソース管理が大きな特徴となっています。
ラウンド制は重厚な戦略性というものは無くなる一方、毎回ほぼイーブンな状況からスタートするので、ゲーム中にPDCAが回せるという利点があります。「さっきはこう行って敵がこう来たから今回はこうしよう」だとか、「ここからくる敵が上手い」だとか、そういう読みが生まれます。
ラウンド制のゲーム性は置いておいて、動画的に「ラウンド制ではないこと」の欠点は何でしょうか。
それはずっとプレイ画面を見せなければならないところです。
ゲーム全体とラウンドの勝敗が分かれていないので、見せ場が無かったラウンドはカットするといったことができません。
ラウンド制であれば2ラウンドほどカットしても、また同じ地点から映像は始まりますし、その間何があったかも勝敗だけ伝えればいいでしょう。
非常に状況を説明しやすいルールと言えます。
一方、RTSはカットした後二言三言で状況を説明できません。
カットしている時間に、後ろの通路を壁で塞いだかもしれませんし、何らかの技術を研究したかもしれません。そのすべてが見せ場ではなく、カットしたくなるシーンです。
しかしそこが無ければ、何故敵味方の軍隊がそこにいて、何故その勝敗になったのか説明がつきません。結果を説明するのに必要な要素は数分前に起こっています。
これは少し別の要素となりますが、因果関係を言い換えるとターニングポイントとなります。ターニングポイントが分かりづらいゲームなので、説明するにしても重点的に見せるにしても難しいのです。
ラウンド制は因果関係を近くしながらも1ゲームのプレイ時間を引き延ばすために有用な手法であると言え、AOE2のカットしづらさは"因果関係が遠い"ことが引き起こすものです。
後で観戦実況についても書きますが、「途中から見ても分からない、ずっと画面を見てないと分からない」という話にもつながります。
・テンポが悪い
そもそも動画における"カット"の意味合い、使用方法が変わってきているように見えます。
ニコニコ動画でゲーム実況が流行り始めたころ、カットとはゲーム中で必要になる稼ぎ作業や場所移動、リスタートからの復帰といった、いわゆる見せ場のない場面を動画に載せないための編集でした。
それがプラットフォームがYoutubeに移行して実写動画が多くなってからは、動画全般でカットはテンポ感をよくするために用いられるように感じます。
喋りの息継ぎや思考時間、小さな作業を細かく切るのがそうです。逆に長時間の作業場面に対しては俯瞰撮影からの倍速が多いように思えます。
実写動画を投稿されるようになって、ゲーム実況が数多くあるスタイルの中の1ジャンルに落ちた故の変化です。
前者は見せ場が無いところをカットするのに対して、後者はテンポをよくするためにカットしています。
この二つは似ているようで、カットする対象、目的が違います。
ロックマンのプレイ動画で例えるなら、ボスで残機が無くなってリトライするためにもう一度ステージをやり直す場面をカットするのがニコニコ時代、ボスの攻撃を避けたりフルチャージのバスターがヒットした部分以外をカットするのがYoutube時代のカットと言えます。
もちろん後者のカット方法も昔からある編集方法の一つですが、ゲーム実況にはそぐわないため、使う人は稀だった印象です。全部をカット編集したら大変なことになるのです。
このように、カットの目的が昔とは違ってきています。
カットは見せ場がない映像を切って動画時間を短くする手段ではなく、圧縮してテンポよく見せるための手法なのです。
これをゲーム実況に再輸入するとどうなるでしょうか。
話がまた戻りますが、FPSなら激しい撃ち合いができた場面やラウンドだけを見せることになります。
テンポよくするための編集はできて、つまり言ってしまえば、古来からあるフラグムービーがそもそもそうなのです。
一方でRTSではどうでしょうか。カットがしにくいためにテンポを良くすることができません。
それでも「クイックウォールで荒らしを防ぐ、マイクロ操作で矢を避ける」だとか、某AOE3プロの「町の人をデリートして人口枠をあける、攻められている時に一瞬で敵陣に攻撃指示をだして逆転する」などのビッグプレイならいいでしょう。ですが毎試合あるわけでもありませんし、"動画を作ろうと思う一般的なプレイヤー"に出せるプレイでもありません。
・絵が地味
仮にAOE2で良いプレイが取れたとします。
ではゲームをやってない人に見せて、その凄さや爽快感が伝わるでしょうか。
戦略を売りにするゲームはアナログデジタル問わず、大抵何しているのか、どんな操作をしているのかわかりませんし、どんな結果になったのかすら分かりません。
目の前にいる敵にビシバシ弾を当てて一人で次々に倒していくだとか、そういった分かりやすさや派手さがあればいいのですが、AOE2は地味です。
前の記事にも書いたように、AOE3では大砲で軽歩兵が派手に吹っ飛んだり、軍隊がどわっと出てきて敵を倒したりします。
とはいえ、そうなるように仕向けたところが凄いのであって、それ自体が凄いわけではありません。
もちろんそのような派手なプレイができるプレイヤーが凄い、ということになりますが、そこまで伝わるのはその難しさを知っている人だけです。
ここら辺は将棋やカードゲームに似た難しさを持っていると言えるでしょう。
将棋はAIによる評価値がリアルタイムで表示されるようになって、知ろうでも一手に対して驚けるようになったので、AOE2でももっと点数が分かりやすくなれば見やすくなるかもしれません。
これがプレイの結果に対する演出の地味さの話ですが、もう一つ映像面で地味と言う問題もAOE2は抱えています。
大軍同士がぶつかってもドット絵のユニットがぺしゃっとつぶれてくだけです。騎士が突撃していくときも地鳴りはしません。内政にしても畑を耕す人から、のどかな雰囲気を味わうことはできません。
映像として常に地味です。
ではかといって、投石機の石を射手が二手に分かれて避けた時に効果音がなったり、ズームしてスローモーションが掛かったりといった演出がついたとしたらどうでしょう。ゲームとして破綻するだろうということは容易に想像できます。
200ものユニットを操るのですから、簡素でなければなりません。
気持ちのいい場所に気持ちのいい音が鳴る、エフェクトで光るのが理想だとはいえ、そんなことにかまってられません。
そう考えて行くと、RTSはゲームとしてもはや詰んでいるとも言えます。
非常にesports適性の高いゲームとしてあげられていますが、見せる、説明するという点においては映像の地味さが足を引っ張ります。
・ストーリー性が希薄
AOE2のゲームの作りはコンテンツには有利に働くされている「ストーリー性」という面でもマイナスに働きます。
ストーリー性とはそれが成し遂げられるためにどれだけの事があったのかという過程の話です。
アスリートやアイドルの裏話が重宝されるのは、ストーリー性を求めるからです。
ストーリー性が強いゲームとは、例えばマインクラフトが挙げられます。
何もなかった土地に出来上がった街を見渡すとき、その過程を映していようがいまいが、視聴者は建造物を見てそこまでの経緯を想像し、成果をより特別なものとするのです。
別の方面では、苦境からの逆転劇というのも代表的です。
レベルや装備をガンガン整えてからボスを倒すのと、戦闘中に全ての手段を使ってぎりぎりボスを倒した場合では、その後に思い返す場面やそれに浸って出てくる感情は違うことでしょう。
このように、ストーリー性は結果に付加価値を与えますし、場合によってはストーリー性はメインコンテンツとなり得るほどの要素です。
例えばVtuberがマインクラフトやARKをプレイするだとか、大会に向けて練習する過程を配信するのがそうだと言えます。
ではAOE2はどうでしょうか。
AOE2は土台となる歴史があったとしてもゲーム毎には前後のつながりがありません。常に1から始められ、逆転もどんでん返しもありません。
実力に差があるとどうあがいても勝敗が覆らないのがRTSというゲームです。むしろ運で覆ってもらっては戦略ゲームとして困ります。
ゲームとしてはそれで面白いのですが、偶然必然関わらずスーパープレイが出しにくい、数十日のスパンでの経過も感じづらいとなれば、動画配信ともに難易度の高いゲームと言わざるを得ません。
「重厚な戦略が売りである」とは「展開の意外性に欠ける」と言い換えることもできるのです。
■ここまでのまとめ
主に動画を作る上での障害を取り扱ってきましたが、これは大体配信をする側の苦労にも当てはまることでしょう。
何をするにしてもオーディオコメンタリーのように操作を実況し、意図を説明しなければいけません。
ここまでを裏返して視聴する側から言うなら、次のようになります。
- 娯楽である以上、予想と結果の循環が必要
- 再現してみたいと思わせるかどうか
今の選択によってどうなるか、目の前にある画面からどう発展していきそうかというのが予想です。予想があれば結果が出た時に何らかの感情が生まれ、次の予想にフィードバックされます。
予想や結果は色々な言葉に置き換えられますが、これによって生み出されるのがワクワクやドキドキという感情で、ほとんどの作品で必要とされているものです。
そして再現してみたいという感情によって、製品を買ったりコンテンツを製作したりという行動の原動力が生まれることになります。
アリストテレスは詩学の序文で「創作は再現である」としています。ある対象を違う方法、媒体で再現することによって、作品が生まれていくのではないかという話です。
ゲーム自体やそのゲームを使った動画、配信が「見ている人に再現してみたいと思わせられるかどうか」はゲームが広まっていくには重要です。
これら2つをどれだけ高めることができるか、高めるチャンスがあるかどうかという点で、AOE2の作りは始めにも書きましたが、次のような原因によって苦しいのです。
- リアルタイムである
- 戦略性を売りにしている
- 1ゲーム完結で、ゲーム時間が長く、ラウンド制ではない
- 見下ろし視点で絵が地味
■攻略情報を出す立場として
ファンコンテンツの1ジャンルに攻略情報という物があります。攻略情報の内容にもゲーム性が関わってきます。
テーマと外れてしまうので、書くのは少しだけにしておきますが、AOE2のゲーム性はどんな弊害があるのでしょうか。大きく分けて3つになります。
- 体系化しづらい
- 普遍的に語ろうとすると漠然とする
- 前提知識が多すぎる
これらはマップ、文明などが多岐にわたるために、発生しうる状況が膨大な量になるためにおきます。よく将棋の戦術の寸評でも"変化が多彩で難しい"と書かれることがありますがそれに似ているかもしれません。20年以上の歴史があるゲームなのです。
また、プレイヤーも段階的に成長していくわけではないため、操作技量、知識、判断といった項目でレベルが様々です。できるだけ広い範囲を捉えようとすると輪郭がぼやけてしまうといったことが起こります。
攻略情報がほしいとは言っても、どういう形式で誰に向けて何を出すのが適切なのか、コンセプトを決めるところが大変になってきます。
■実況観戦について
すでに7000文字と長くなってきたので、ここからはできるだけ手短に行きます。
ゲームが盛り上がるには大会という手段があり、大会には実況解説が必要です。
実況解説は見せる、説明するという役割を持っているので、ある程度動画や配信と問題を共有します。
解説の役割はいくつかありますが、その中の一つに選手の特徴を説明するというのがあります。
この選手はこういう戦い方をする、今回はこの選手の○○(キャラ名)に期待したいという説明を視聴者に向かってすることで、見ている人に見どころを前もって意識させ、期待感を高めるのです。
出たプレイを解説するのは当たり前として、そのプレイが出る前に予感させるのが、解説の大きな仕事といってもいいでしょう。
そういう視点で見ると、AOE2はそれがやりにくいゲームです。
一般的な動画や配信をする場合でもそうですが、なんといってもAOE2はプレイヤー個人の特徴が出しづらいゲームです。役割、キャラ、武器専門職と言うのが無いからです。プレイの癖を見つけ、注目しどころとして挙げなければいけません。
以前、全選手が匿名状態でトーナメントを行う、という大会が開かれました。その大会では選手はもちろん、解説実況、視聴者も終わるまで誰がどのプレイヤーネームで出場しているのか分からないというルールでした。
そういう大会が開かれるということは、つまり相手の実力やプレイの癖があってその情報を元に戦っていくという、いわゆる人読みが存在するという事になりますが、多くの場合プレイヤーにしか分からないことです。
一応壁の張り方や兵の動かし方といったところに癖があるため、熱心なファンが集う配信では、プレイを見て誰かを的中させるという場面がよく見られました。
しかし言っても判断基準はそのあたりで、それはデータには表れてきませんし、そもそもそのような癖自体はあまり見どころにはなりえません。
これが解説の問題ですが、実況と言う面ではどうでしょうか。
実況の役割は、今何が起こっているのかという状況説明と、そして選手のプレイにリアクションして盛り上げるという物です。
ここまで読んでくださった方には、AOE2を実況するのが如何に難しいかわかるでしょう。ターニングポイントは分かりづらく、そして原因と結果が遠いためにそこにフォーカスしていいのかどうか分かりません。一手に対する点数の変動というのも、ゲーム中のインターバルもないため、状況説明も一苦労です。
また、一つ特殊な問題として、カメラの話があります。
AOE2はマップの様々なところを操作して戦っていくゲームです。そのため、どこで何が起こっているのかというのを見つけることができません。
岡目八目などと言いますが、どこを操作しているのかという点においては、俯瞰視点より選手の視点の方が分かりやすいというのは間違いありません。一瞬の作業で、裏取りしていたり町の人を何人か撃破しているという事が可能なのです。
これらの問題によって、解説実況をしようにも何が起こっているのか、どんなことが起こるのかということを喋りづらいという問題点があります。
喋りづらいと言えば、AOE2のゲーム性も実況者を困らせる要因の一つとなるでしょう。それは、ミスに対してのリアクションです。
AOE2はミスが良く起こります。
探索し忘れたりちょっとした手違いによって壁に穴が開いていただとか、町の人を格納したままにして遊ばせていたりだとか、軍隊を見ていなくて不必要なダメージを受けただとか、経済バランスが崩れたりだとか、理想のプレイを完璧にできている人というのはあまりありません。
素晴らしいプレイによって勝利するゲームももちろんありますが、ちょっとしたミスによって敗北するというゲームも非常にたくさんあります。
そういったプレイを選手が大会でしていた場合、実況者はどうすればいいのでしょうか。大会で人に見られてプレイするというのは尋常ではないプレッシャーがあると思うので、そういったことも普段より多くなることでしょう。
外国の実況者はそんなミスを激しい口調で咎めて盛り上げる格好のネタにしますが、日本人の感覚からすると気持ちのいい実況とはとても思えません。できれば良いプレイによって盛り上がりたいところです。
原因と結果が近いゲームで起きるミスなら見ないフリをしたり、惜しかったとリアクションを取ることもできますが、AOE2のミスは傍から見てたらどこまでも論うことができる代物です。
実況解説者にとって、これは苦しい問題なのではないでしょうか。これもラウンド制であれば解決できることだとも言えます。
■まとめ
見せる、説明するという立場だとRTSが何故難しいのか、というのをまとめてみます。
- リアルタイムと戦略ゲームの相性が悪い
- 1ゲームが長い
- 演出が簡素
- 操作キャラ(文明)の性能が独立していない
端的に言うとこの4点ですが、「AOE3より2だな!」という話でAOE2の特徴として挙げていた部分が、全て否定されるのが分かります。
これが実際にプレイするならAOE2、観戦するならAOE3という話の正体です。観戦により適しているのはAOE3ですが、プレイヤーからしたらAOE2が持つゲーム性の方が好みなのです。
RTSは広がりにくい構造になっているという話になります。随分と人口が多いのにいまいち盛り上がりに欠けるというのは、こういった原因によるものでしょう。
そんなこんなで、競技性が要らない層は時間の流れを排したTBS(ターン制ストラテジー)や4Xに行き、大会を重視する層はある程度簡素にして見やすくしたMOBAに行ったのだと思います。
次回は2と3の変化やトレーラーを見つつ、AOE4がどんなゲームになりそうかという事や、この記事を踏まえて何を求めるのかという事を書いていきます。
ここまでお読みくださりありがとうございました。
面白かった、役に立ったという方は"スキ"ボタンのクリックやフォローなど、よろしくお願いします。モチベーションアップにつながります!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
