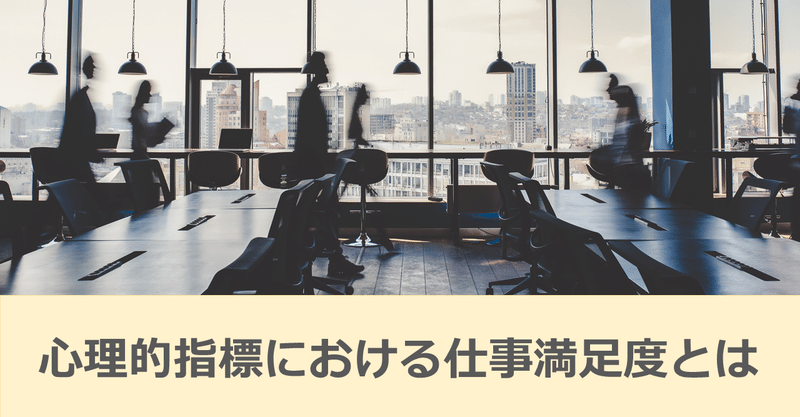
心理的指標における仕事満足度とは
「従業員の健康は企業の生産性を高める」という考え方のもと推進されつつある「健康経営」。健康経営は、従業員個人の健康増進や組織の活性化のみならず、企業イメージの向上により人材が集まるなど、長期にわたる企業の業績向上に効果をもたらします。健康経営のさらなる普及を目的に、プロセスの大枠が、経済産業省による「健康投資管理会計ガイドライン」で示されています。
健康経営の手段として、従業員調査が行われます。その調査項目の一つに「心理的指標」があります。この記事では、この指標をさらに細かく分け「仕事満足度」という概念にフォーカスし、個人の健康と企業価値との関係をまとめています。
健康経営に関するお役立ち情報をお届けする「健康経営のすすめ」は、健康経営支援ツール"FairWork survey"をご提供する株式会社フェアワークが運営しています。フェアワークへのお問い合わせはこちら。
心理的指標と投資対効果
■「心理的指標と分類」
心理的指標とは、健康投資効果を測定する際に判断材料となるものです。心理的指標はさらに、次の項目に分かれます。
・主観的健康感
・生活満足度
・仕事満足度
・ストレス反応
・ホープ(希望)
・セルフエフィカシー(自信)
・レジリエンス(耐難)
・オプティミズム(楽観)
(参照:経済産業省ヘルスケア産業課『健康投資管理会計ガイドライン』より)
■「投資対効果」
健康投資管理会計ガイドラインでは、健康状態調査を実施した結果、企業の目標に到達しない場合、個人の意識変容・行動変容に関する指標を把握しさらなる個別施策のPDCAサイクルをまわしていくことが重要だと示しています。
ジョンソン・エンド・ジョンソン発表資料によれば「1ドルの健康投資に対して3ドルのリターンがあった」とのことです。1ドルの健康投資には、健康管理に関わる人件費・健康指導システム運用費・フィットネスルーム費などが含まれます。3ドルの効果には、欠勤率低下・医療費削減・モチベーションアップ・求人数増加・企業ブランド価値向上などが含まれます。
日本での調査では、健康リスクが低くなれば1人あたり30万円の損失を阻止できると結論づけました。なお、健康リスクを測る基準には、血糖値など生物学的リスク、睡眠不足や喫煙など生活習慣リスク、仕事満足度など心理的リスクの項目があります。(参考:経済産業省商務情報政策局『健康経営の推進に向けた取組』)
仕事満足度について
■「仕事満足度とは」
心理的指標の中に「仕事満足度」という項目があります。仕事満足度というのは、勤務時間が生活のほとんどを占める日本人にとっては、重要性の高い項目です。
仕事満足度とは、職場の衛生環境や人間関係、やりがいといった、「報酬」「評価」「職場環境」「仕事内容」などを総じて、どのくらいその人が満足しているかを表す指標です。必ずしも、業務そのものに対する問いではなく、組織に対する想いでもあるでしょう。
■「調査について」
アンケートは、科学的エビデンスに基づいた内容になっています。アンケート内容は、厚生労働省による“職業性簡易ストレス調査票“や、心の課題を克服する認知行動療法分野で使われる“セルフエフィカシー尺度“などから構成されます。
職業性簡易ストレス調査票では、4件法という手法で問われます。心理カウンセリングなどでもよく使われる問われ方で、特徴は「普通」「わからない」といった中間回答ができないアンケート法です。
・満足度について
1.仕事満足度 満足 まあ満足 やや不満足 不満
2.生活満足度 満足 まあ満足 やや不満足 不満
このような形で、生活満足度と併せて問われます。
仕事満足度に関連した研究
■「職務特性理論」
かねてより、動機づけや職場環境が業績にどう影響するのか、さまざまな方面で調査研究が行われてきました。ここで、近年になって再注目されている「職務特性理論」(Hackman,J.R.&Oldham,G.R.,1975)を紹介します。
職務特性理論は、心理学者リチャード・ハックマンと経営学者オーダムによって、どのような職務が従業員の満足度を高め、業績向上につながるのかを検討したものです。次の5つの基本的な職務特性が効果的だと結論づけました。
・技能の多様性:職務を行うにあたり、さまざまな種類のスキルが使われること
・仕事の一貫性:仕事が全体的でまとまりがあり、最初から最後まで仕上げること
・仕事の有意味性:組織内外問わず、人々の役に立つこと
・自律性:進め方や決定について、自由裁量の幅があり、主体性・独立性があること
・フィードバック:自分と仕事とその結果について、明確なフィードバックがあること
これらの要素を職務設計に取り入れることで、従業員は、仕事に有意義性を見いだし、モチベーションと責任感を持って仕事に取り組むことができるとしました。(参考文献:宮城まり子(2013)『産業心理学 変容する労働環境への適応と課題』培風館)
他に、京都大学の研究では、操作変数法という研究手法を用いて、従業員の仕事満足度を高めることが、生産性を上昇させるという結論を出しています。(参考:参鍋篤司、齋藤隆志(2007)「仕事満足度の及ぼす企業業績への影響」『経営行動科学』、第20巻、 85−90頁)
これらの研究を含め多くの文献にある「達成感」や「責任感」は、モチベーション維持の大きな要因であることは時代背景や国が異なっても通じるものがあるはずです。
まとめ
心理的指標にある項目は、選択式とはいえ、どれも仕事への態度を振り返るのみならず、これまでの生き方を考えさせられるものとなっています。仕事に対する満足度が低ければ、それは人生そのものへの不満につながり、人生から自分という主役が消えてしまう危うさを孕んでいます。自己評価の低さやうつ病などのトリガーになりかねません。
誰かの犠牲の上にある企業の成績は、真の企業評価ではないとする未来も遠くないでしょう。真摯に調査結果レポートを現場にフィードバックし、仕事内容や労働環境の改善に役立てていくことが望まれます。もちろん、簡単にできるものではありません。しかし、個人を尊重した企業姿勢そのものが、社会からの評価尺度とされる現在、それぞれの企業が自分たちに合った環境を模索し続ける必要があるのでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
