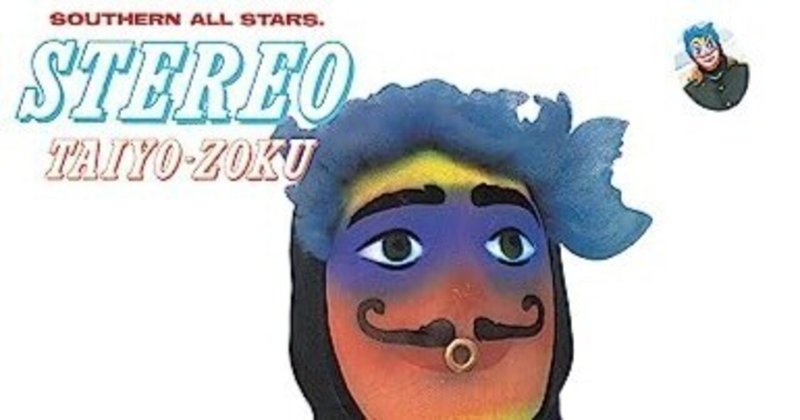
素顔で踊らせて
<詞>
歌詞に出てくる『2月26日には ささやかな二人の絆』に注目したい。
2月26日はご存じ桑田佳祐の誕生日。
この曲が収録された『ステレオ太陽族』のリリースが1981年7月。
それにさきがけた1981年の正月、桑田佳祐はハラボーの実家へ出向き両親に結婚の申し込みに行ったそうだ。
原由子(結婚当時のインタビュー)
「去年のお正月に桑坊が私の実家へ来て『じつは、あのぉー、来年のボクの誕生日に式をあげたいと思っているんですけど』って言ったんです」(1982年)
その後、1981年9月の桑田のインタビューでは
桑田佳祐
「式の時期はまだ決まっていないんです。でも、ぼくの誕生日にしようかなとも思っているのね。結婚記念日としても覚えやすいでしょ」(1981年)
と、どうやら、その頃から桑田の腹の中では「式を挙げるなら26歳の誕生日である2月26日に・・」という心づもりが固まりつつあったらしい。それを歌詞に反映させたわけである。
ところがカレンダーをめくってみると
1982年2月26日は仏滅でしかも平日の金曜日。
いろいろ考えた結果、1981年暮れに
2日ずらした2月28日の日曜日に決めたのだった。
-2月28日というのは?
桑田佳祐
「金屏風の前でれいれいしく、いかにも『結婚式です」』という形でやりたくないのね。そうすると、そこが終着点で、もう先がないみたいでしょ。
だからファンのみんなに集まってもらって、ドンチャン騒ぎをしてもらいたい。そうすると平日だと来れない人もいるから、日曜日の28日にしたわけ。」(1981年)
またハラボー著『娘心にブルースを』では
原由子
「結婚式の日取りは、式場の都合で二月二十八日になった。
本当は桑田の誕生日である二十六日にしたかったのだが、結婚式ができるだけで十分だった。」(1998年)
実は結婚をした1982年当時の女性週刊誌にはハラボーが度々インタビューで登場して、この類のエピソードはたくさん出てくるんだけど別の機会に。
そして桑田佳祐と原由子は1982年1月の武道館ライブステージ上で結婚宣言。2月28日に晴れて結婚式をあげる事になる。
それと前後して
1981年4月21日リリース原由子1stソロアルバム『はらゆうこが語るひととき』には桑田佳祐作の『Last Single X'mas 』を収録。
1982年3月21日には原由子作のシングル『誕生日の夜』をリリース。
何とも匂わせな2曲である。
この曲中のフレーズ「素顔のままでいい」「You May Be Right」はもちろんビリージョエルから。
<背景>
『素顔で踊らせて』でもう一つ話題に上がったのは桑田が登場したユニ・チャーム「アンネ」のCMである。
桑田佳祐
「この曲、仮のタイトルは『哀愁の生理用品』ってね、CMで使っているから…。 “そのようなレディ”っていうのはギラギラした成金趣味の女ってカンジね。」(1981年)
上の発言からCM用の書下ろし曲である事が判明。
男性が女性用生理用品のコマーシャルに出演する事は前代未聞の出来事でマスコミでは大きな話題にもなる。
桑田佳祐
「CMはね、あーいうのの依頼が来るっていうインスピレーションがあったからさ、即OKね。ちょっとあがったかもしれないけど、素直にやれたからね、よかったな。オレ、あれは正視できるもん、自分の顔。」(1981年)
桑田佳祐
「あれはあんまり抵抗なかったんですよね。かえって嬉しかったというかね(笑)」
ーーそれにしてもなんで白羽の矢が立ったのかしら?
「よくわかんないけど、ある程度安全圏だからじゃないかな。ああいうの、男くさい魅力のある人がね、渡哲也みたいのが出てきたらまずいんじゃないのかな(笑)」(1981年)
原由子
「桑田クンのCMね、画期的ですよね、男の人が出てくるなんてね。明るい話題にしちゃって、一人で暗い気持ちで悩むことないんだって気になりますよね。イヤラシイ連想する人いないんじゃないかな。だってねえ、なきゃ、困ることですよね。」(1981年)
前1980年の「恋するマンスリーデイ」
(この曲のリリース時も女性週刊誌を中心に「女性の生理をテーマにしている」事で話題に上った。)
そこからの波及か、それまで常識では考えられなかったこのCM出演は当時の性別を超えた桑田佳祐の好感度の高さを物語っている。
そして、このCMを境に女性雑誌から桑田佳祐への取材が一気に増え始める。
自分の記憶だと、この1981年あたりから「桑田佳祐は天才である」と各マスメディアが声を上げ始め、もちろん(音楽雑誌以外の)男性雑誌からも取材が殺到した時期でもあった。
桑田佳祐が出ると発行部数が伸びるという逸話が残され、なぜか創刊号に登場する機会が数多く見られる現象が起きたわけだ。
<曲>
桑田佳祐
「スローバラードで、ラテンのボンゴとかCPなんていうのがフィーチャーされているわけなんですけども、結局、これね、四部構成っていうのかな、僕たちはメロ、ワビ、サビ、とか言ってるんですけれども、メロディーが4パターン出てくるんですよね。
それで途中念願の転調を行いまして、多少南米の音楽的なものに近くなっていると思います。サビのところは実はラテン語でやりたかったんですけれど...。でも、ぼくはすごく気に入っている曲なんですよね。」(1981年)
<1999.10.08記>
<2024.02.25追記>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
