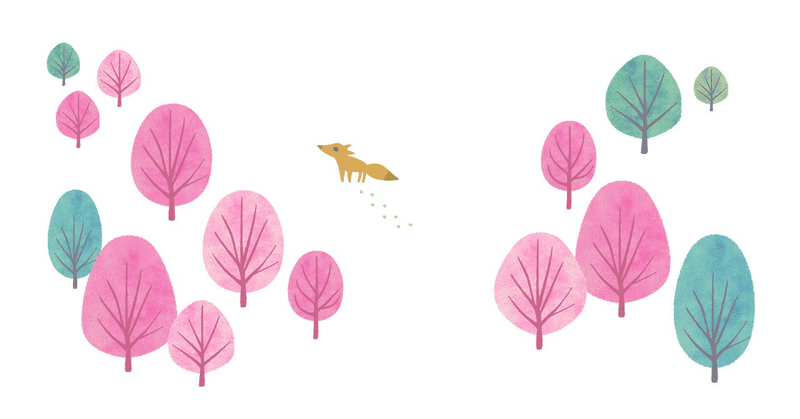
文芸における教訓とイデオロギー
読み終えたとき
「結局、何が言いたかったの?」
物語や小説を読み終えたときに、このような疑問が生じたことはなかっただろうか?
私は何度かあった。
そこでふと思った。
果たしてこの疑問は「正しい」のだろうか? と。
「結局、何が言いたかったの?」の答えを得ようとすることは、作品に「教訓」や「イデオロギー」を求めることを意味する。
「教訓」や「イデオロギー」をうまく言葉で表現できたとき、私たちはその作品を「読み解けた」と思いがちだ(と思う)。
でも、本当に「読み解けた」のだろうか?
何か大切なものを見落としてはいないだろうか?
こんな疑念が生じたことがあるのは、私だけではないはずだ。
『文学のふるさと』について
この疑念を解消するための手がかりを与えてくれたのが、坂口安吾の『文学のふるさと』だった。
安吾は童話『赤ずきん』を例に挙げ、「童話というものには大概教訓、モラル、というものが有るものですが、この童話には、それが全く欠けております。」と述べつつ、さらにこう続ける。
およそモラルというものが有って始めて成立つような童話の中に、全然モラルのない作品が存在する。しかも三百年もひきつづいてその生命を持ち、多くの子供や多くの大人の心の中に生きている――これは厳たる事実であります。
愛くるしくて、心が優しくて、すべて美徳ばかりで悪さというものが何もない可憐な少女が、森のお婆さんの病気を見舞に行って、お婆さんに化けている狼にムシャムシャ食べられてしまう。
私達はいきなりそこで突き放されて、何か約束が違ったような感じで戸惑いしながら、しかし、思わず目を打たれて、プツンとちょん切られた空しい余白に、非常に静かな、しかも透明な、ひとつの切ない「ふるさと」を見ないでしょうか。
安吾は教訓のない話に突き放されて戸惑いながらも、そこにひとつの切ない「ふるさと」を発見する。
それを「何か、氷を抱きしめたような、切ない悲しさ、美しさ」とも表現している。
この安吾がいう「ふるさと」こそが、「大切なもの」であり、私が見落としたものの正体だったのかもしれない。
そんなことを考えてから何年か経って、私はいくつかの「ふるさと」を発見することができたように思う。
その中の一つが『ごんぎつね』だった。
『ごんぎつね』の中の「ふるさと」
あなの中の「ごん」は、自分のいたずらによって「兵十」が母親にうなぎを食べさせることができなかったことと、そのまま「兵十」の母親が死んでしまったことに気がつき、それからこっそりと罪を償いはじめる。
そして、最終章にて、「兵十」の家に栗を持って行ったとき、それを知らない「兵十」によって撃たれてしまう。
少し長いが引用する。
兵十は立ち上がって、 納屋にかけてある 火縄銃 を取って、火薬をつめました。そして、足音をしのばせてちかよって、今、戸口を出ようとするごんを、ドンとうちました。
ごんは、ばたりとたおれました。兵十はかけよって来ました。家の中を見ると、 土間 に栗が、かためておいてあるのが、目につきました。
「おや。」と、兵十はびっくりして、ごんに目を落としました。
「ごん、お前だったのか。いつも、くりをくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。
兵十は、火縄銃をばたりと、とり落しました。青い煙が、まだ筒口から細く出ていました。
これを読んだとき、「結局、何が言いたかったの?」という疑問は出てこなかった。
一人の読者として、「兵十」の罪を、自分も引き受けなければならないと思ったからだ。
しばらく推し黙るしかなかった。
物語における教訓とイデオロギー
ここまで、教訓やイデオロギーを斥ける文学の「ふるさと」について書いてきた。
だが、人から人へと語り伝えられる「物語」が生き残るためには、教訓あるいはイデオロギーが必要になるのかもしれない。
村などの小さな共同体を維持していくためには、人々の結束が必要となる。
結束を強める要因の一つとして、人々が同様の価値観を持っていることが挙げられる。
物語は、教訓あるいはイデオロギーと結びつくことで、その共同体に生きる人々の価値観の形成を担ったのではないだろうか?
物語そのものが生き残るために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
