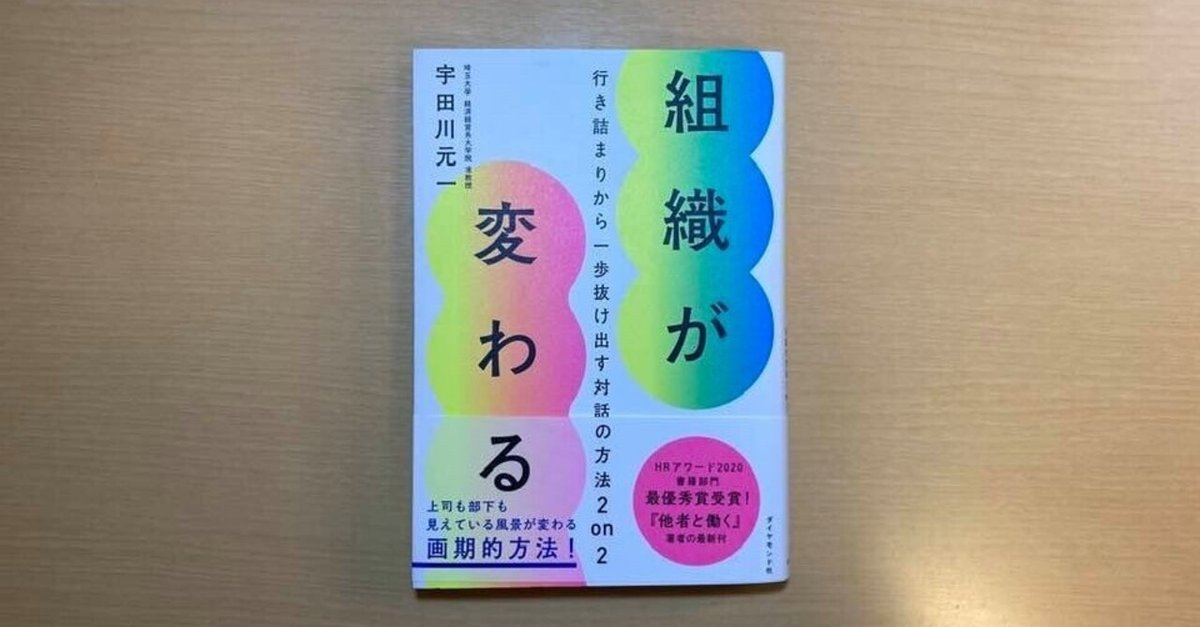
『組織が変わる』書評
ビジネス書には定番となっているテーマがいくつかある。「リーダーシップ」「人材育成」「論理的思考」などがそうだが、定番中の定番とも言えるのが、「組織を変える」ではないだろうか。もう聞き飽きたという人がいるかもしれない。それは、逆にこの言葉の実現がいかに難しいかを物語っている。
とりわけ大企業の組織改革は厄介である。積み上げてきた過去も大きくなると、それに従って組織は変化しづらくなる。暗黙知と呼ばれるものは強みにも弱みにもなり、人が入れ替わっても組織のカルチャーは変わりにくい。トップが変わっても制度が変わっても、根強く潜むのがカルチャーだ。大企業の組織変革はだからこそ難しく、だからこそビジネス書の定番テーマの座を下りないのであろう。
こんな定番テーマの中で、久しぶりに強力な説得力ある主張の本が出版された。埼玉大学大学院の宇田川元一先生による『組織が変わる』である。
本書では、大企業が変化できない課題を「組織の慢性疾患」と呼んでいる。慢性とは生活習慣病のように、時間をかけて常態化した症状であり、小さな変化の積み重ねから、健康体がいつの間にか疾患というレベルにまで悪化してしまう、その症状だ。
よく言われるが、どんな伝統ある官僚的な大企業であろうと、創業当時はベンチャーだった。ゼロから事業を作ろうとする創業者がいて、そのアントレプレナーシップが満ち溢れていたはずである。そんな出自の企業も大成功ととともに巨大で伝統ある企業へと変貌するプロセスの中、社内調整にコストがかかり、いつしか失敗を極度に避ける体質へと変貌してしまう。こんな例が珍しくないのではないか。
この「いつしか」がまさに組織文化の厄介なところで、新しいことを生み出す文化を阻害している要因が特定できない。特定の何かが問題なのでなく、全体を覆いかぶさるように染み付いてしまう。「組織を変える」とはそんな長時間積み重なってきた正体不明なものを変える行為なのである。
本書の著者、宇田川さんの前著は『他者と働く』である。組織において対話の重要性を問うた本だ。そして今回は、その重要性に留まらず、具体的にどう進めるかに言及した。それが『組織が変わる』である。
本書では対話とは、ディカッションとも雑談とも違うという。ディスカッションは、議題が明確でロジックが縦に通った話し合いのことである。そして雑談はむしろ議題がなく、話題を拡散させていく行為だ。それらと異なり対話とは、そもそものコミュニケーションの基盤となるナラティブ自体を変容させる行為だと定義する。
ここでいうナラティブとは、人それぞれが固有の経験や立場などから有する「解釈の枠組み」である。つまり同じファクトを受け取っても解釈の仕方は人それぞれなのだ。その上で、他者との対話によって、自らのナラティブに気づき、変容に結びつける。その効用について、以下の印象的な言葉が書かれている。
「私たちには他者というのは厄介な、しかし、とても大切な存在がいます。他者は私とは違う現実を見ている存在です。そのため、自分には気づけないことも案外簡単に気づいて指摘してくれます。」
このような対話の効果から本書は具体的な方法論の提示が始まる。
ここからが本書の真骨頂かもしれない。それは、聞き慣れない言葉だが、「2 on 2」という対話法の紹介である。
すでに人口に膾炙した「1 on 1」が対話の基本的な役割を広めたが、「2 on 2」はその発展形である。これは「2対2」による対話ではない。二人による「1 on 1」を他の二人が傾聴のみに徹し、その後傾聴していた二人が「1 on 1」する。その繰り返しにより、問題の保有者が徐々に他者のナラティブから、自分の問題の本質に気づくアプローチである。本書ではどのような組み合わせがいいのか、それらに要する時間、さらに座る位置まで具体的に紹介されている。
その詳細さは研究者が概念を紹介する類のものではなく、実務家による実践レベルの解説になっているところが驚く。おそらく読者は、本書を読んですぐに実践に移すことができるのではないか。経営学者がフィールドワークを積み重ね「学者の戯言」を越えようと取り組んだ意欲作であることがよくわかる。
本書では対話を「わかり合う」ことが目的ではないという。同じナラティブを共有することは、上司の考えを部下に押し付けるリスクも指摘している。むしろ異なるナラティブから、問題のありかや新しいやり方に気づくためのアプローチだと強調する。この文脈から読み取ると「2 on 2」という複数のナラティブに触れる対話の効果がさらに理解できる。著者は今日の「対話」ブームに警鐘を鳴らすかのように以下のように書いている。
「対話が大事だと言っている人たちが、まったく対話ができていない。こんな現実が少なからず見受けられます。この背景には、自分たちの「対話」は正しい。互いにわかり合うことは不可欠で、素晴らしいことだという前提が見え隠れします。「対話」という言葉の持つ理想主義的な響きに目を奪われ、大事なことを見落としているように見えます。」
この「対話という言葉の危うさ」に気づくだけでも、本書を読む価値はあると思う。
組織変革がビジネス書の定番テーマとなり続けている理由のもう一つは、一時的に流行した方法論が時間とともに陳腐化していくからだと思う。決定版かのように喧伝されたコンセプトや方法論が、話題になったことで消費されるかのように消えていく。そもそも「効果」が見えにくいのが組織変革であり、効果を約束できる方法論など存在しないのだろうか。同時に、誰しも即効性ある方法論を求めており、それは組織変革でも同じである。
本書で提唱する「2 on 2」に即効性は期待できないかもしれない。何しろ本書では「2 on 2」において、問題解決モードではなく対話モードを推奨している。「こうすれば変革できる」という問題解決の手法ではない。
表面化した問題について解決方法を考えていくアプローチでは、課題と問題がいたちごっこになってしまう。問題が出てくるたびに素早く解決策を作り実行していくことは大切だが、長年積み重なってきたものから発症した「慢性疾患」に対しては、即効薬は一時的な痛み止めにすぎないだろう。慢性疾患の背後にあるものは何か?その本質に迫ることから、この厄介な病に対する方法論はないのではないか。そしてそれは、プロジェクトのように一時期徹底的に取り組むものではなく、むしろ組織のルーティンに自然な存在となるように根づかせる方法論が必要なのではないか。2 on 2とは、まさにこの常態化した現象を変える、新たなルーティンではないか。その意味で組織の長年の課題に本質的な解を提示しているように思えてならない。
組織改革に付け焼き刃的な取り組みは通用しない。じっくりと根本から見直すような方法論が必要なのではないか。その意味で、本書は、本腰を据えて組織を見直そうとする人には、心よりおすすめしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
