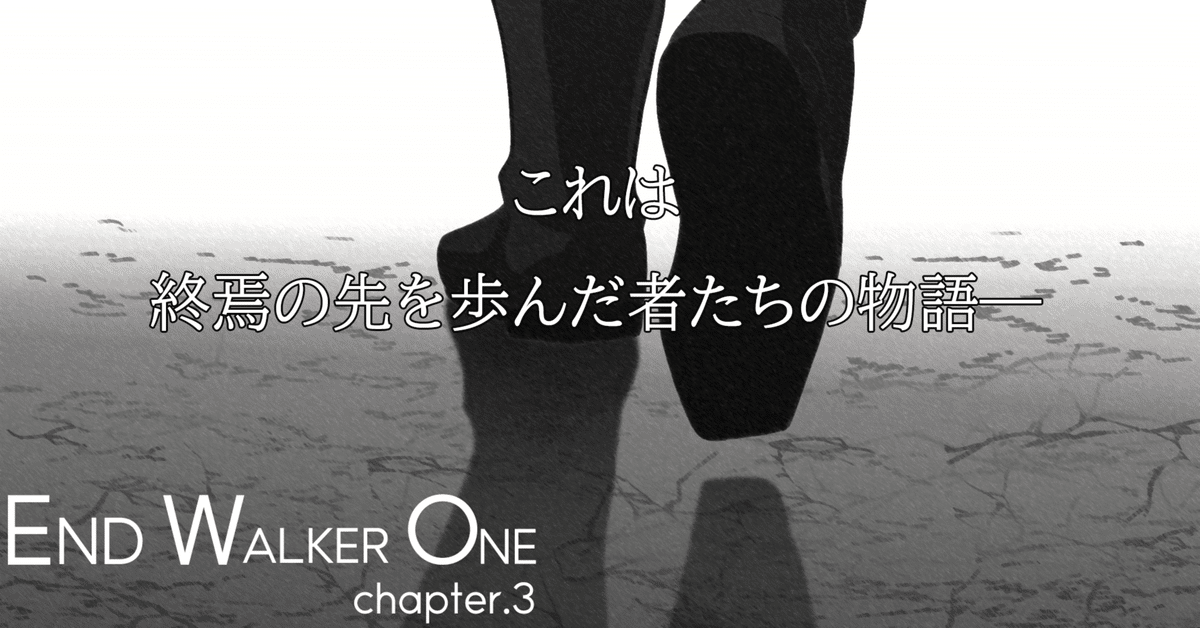
『エンドウォーカー・ワン』第45話
人類がかつて地球で繁栄していた頃。
無人兵器が猛威を振るった戦争があった。
高価な有人兵器をほぼノーリスクで破壊できるそれは瞬く間に進化し、AIゼロ年と呼ばれる技術的特異点において目覚ましい進化を遂げる。
後に第三次世界大戦と呼ばれる長きにおよぶ戦いにおいて、人々は不眠不休で戦い続けるその兵器群を「レギオン」と呼称した。
とある者は自分たちの代わりに戦地へ赴く軍団だと。
またある者はいずれ人類を滅ぼしかねない悪霊だと言った。
第三次世界大戦終結から時代は変わった。
それまでの人類が戦いにより科学技術を発展させてきたように、AIもまた進化を遂げる。
人々に寄り添い、より良い世界を目指して――誰しもが明るい未来を信じていた。
その機械生命体が創造主に反旗を翻すまでは。
「それで少年。この一件に地球が絡んでる線はどうなってる?」
「先輩、僕は成年ですって。ええと、通信手段が未だに確立されていませんので確かめる手段がないのが現状ですね。そもそも、人類がこの星に移住してきた理由も『外宇宙』への可能性を探りにとしか教えられていませんし」
「そうだよねえ」
車窓からはどこまでも牧歌的な光景が広がっている。
イリアは後部座席に寝転び、二人の会話をぼうっとだらけた顔で聞き流していた。
最初でこそ慣れない人間に対して肩肘に力が入っていたが、心を開いた途端にいつもの怠惰な魔女に戻ってしまう。
「でもですよ。それなら噂はどこから出てきたんですかねー」
イリアは自分の銀線の質感を確かめるように艶々の毛先を指でくるくると回しながら言う。
「この星、アルター7の初期移民は各種分野のエリートから選抜された文字通りの『選民』たちでした。そこから地球に残された人々を劣等種と見下す層が未だに居るのはご存じですよね」
「『持たざる者』たちですか。弱きが弱きを叩く……人の本能とはいえ、もうちょっとねぇ」
運転席から飛んでくるアレクの言葉にイリアは長い足をぱたぱたと動かしながら気だるげに返す。
レスティアはここひと月の彼女の変貌ぶりに大きくため息をはき、出会った頃には警戒心の塊だったというのにこの子ったら、と頭を抱える。
だが、本来のイリア・トリトニアはこういった人間なのだろう。
人懐っこくて、お人好しで、いつも口の端をだらしなく上げていて。
自分が大変な時も他人の為なら笑って手を差し伸べられる。そんな不器用な魔女。
それでも、レスティアにとっては年の離れた妹が出来たようでそう悪くはない時間が流れていた。
「でも、変わらないとね。アタシも、貴女も」
誰にも悟られないように呟いた彼女の呟きをイリアがそれとなしに拾うが、小言が増えるのは加齢の証拠だってさーという余計な一言を切っ掛けに女性同士の泥沼な戦いが勃発する。
「ああ、居心地悪い……」
アレクは二人が爪を出してじゃれついている様を横目に、ハンドルを握りしめて無心で運転に集中するのだった。
高速道路に入ったところで疲れか退屈なのかは定かではなかったが、女性二人は眠りに落ちていた。
「まあ、無理もないですね」
アレクは中々見ることができない上司の寝顔を横目でちらりと見ると、思わず心が綻んだ。
やはりレスティアのことを意識しているのだろうか。こんなにも身長も、立場も、年齢も離れている人のことを? 彼は自らに幾度となく問いかけてきた。
仕事に追われるフリをして考えないようにしていた巨大な無意識が頭の中をからんからんとけたたましく鳴っている。
「少し休憩するか……」
アレクは回転数が落ちてきた頭を抱え、サービスエリアの標識に引き寄せられるように駐車スペースに車を停める。
「先輩、イリアさん?」
彼は運転席のシートベルトを外し女性陣に声をかけるが、寝息しか返ってこない。
「うーん。ゲーム、積みゲーを崩さないとぉ……」
灰被りの魔女、イリア・トリトニアにいたっては夢の中で積み上げたゲームソフトの山が崩れ、うなされていた。
彼女がひとたび街を歩けば多くの人間の足を止めるほどの容姿の持ち主だが、皮を剥げばただのゲーム好きな女性だ。
魔女というのはもっとこう、高潔であるものだと思っていたのに……アレクは様々な感情を吐き出した。
アレクは二人を起こさないようにドアをそっと閉めると、温かな日差しの元に姿を晒す。
フロントガラス越しに散々浴びてきたものより一際強いそれに目を細め、フレイヤIIを見上げて歩き出す。
時代がいくら進もうが、費用対効果というものは付き纏う。
21世紀初頭に人類が思い浮かべた未来は今はなく、デジタルとアナログが混合した徹底された効率化の世の中だ。
自動販売機の決済方法もサイバー攻撃などによるシステムダウンを考慮し、前時代な現金を未だに導入している。
アレクは折り畳み財布を懐から取り出して硬貨をじゃらじゃらと投入する。
レスティアにはストレートティー、イリアには日本茶。自分は派手なパッケージのエナジードリンクを買い車へと戻る。
「ああ少年、済まないね」
丁度起きたところなのだろうか。
レスティアは欠伸をくあっと噛み殺し、アレクから冷えた飲料を二本受け取ると軽く頭を垂れた。
「ほら、魔女様も」
レスティアは意地悪そうな笑みを浮かべ、後部座席で器用に眠るイリアの顔あたりにそれを投げつける。
「ひぃあっ!?」
ぶよぶよのペットボトルが頬に当たり、情けない悲鳴があがる。
口の端を拭いながらあたふたとする様は普通の――いや、少し間が抜けたただの女性だった。
「少しは水分補給しなさい。お手洗いも行っとかないと」
レスティアが手を伸ばし、怠惰の魔女の乱れた着衣を手早く正す。
何かと世話を焼いてくれる年上の女性に対し、イリアは「えへへ……」と顔を綻ばせた。
甘える相手のいなかった彼女はあの取り調べ室の一件以降、元敵対国の人間に対してぶんぶんと尻尾を振っている。
イリアが弱っていたところに手を差し伸べてくれたということもあるが、信用に足りうる人物だと認識するが早いか、ごろんと寝転がり腹を見せた。
レスティアたちにとってはサウストリアの特殊作戦群といえば精鋭中の精鋭で、その実力や一騎当千とも言われている。
最初は自分たちを騙すための演技ではないか、と訝しんでいたがそれも僅かな時間だった。
「お腹すいてきたし、何か食べない?」
ペットボトルを両手でごろごろと転がしていたイリアが二人にたずねる。
目の前に居る灰色の女性は誰よりも子供だったのだ。
戦場では敵味方から恐れられ、畏怖の念で見られていた魔女の真の姿がこれだ。
束の間の平和な時間、彼女は失ったものを取り戻すように明るく振舞っていた。
アレクとレスティアは目配せをし、緩い笑顔につられるように口の端を折る。
「そうですね。予定より早いですが、お昼にしましょうか」
アレクに連れられ、一行はレストランに向かった。
「あぁ……このステーキ、クソほどうめぇ」
その男性はナイフとフォークを交互に繰り出しながら皿の上にあるものと戦っていた。
食事中とは思えぬほどの殺気をぎらつかせ、呆れ顔の相棒を余所に三枚目のステーキ皿に取り掛かる。
「ランス、本国に帰ってきてやりたいこととはこれですか。全く、お前は」
一心不乱に食戟を奏でるランスとは対照的に、理性で塗り固めたようなヴァッツが呆れ顔でホットコーヒーを啜る。
伊達眼鏡に蒸気がつくのも厭わず、彼は香りと苦みを楽しみながら食後の余韻に浸っていた。
「ああん? 世界的チェーンの『それとなくステーキ』をバカにすんのか?」
「馬鹿になどしてませんよ。お前の底無しの胃袋に呆れ果てているだけです」
「一皿500グラムをこれだけだからな! まだまだイケるが、国際平和監視機構の給料じゃこれが精々か」
ランスはよくローストされた肉塊をいとも簡単に平らげると、少しだけ膨れた腹を満足そうに手で擦る。
「はあ、ベルハルトが車で待ってます。さっさと――」
ヴァッツはそこまで出かけた言葉を飲み込み、閉じかけていた目を見開いた。
「わーい、パフェだー」
「はしゃがないの」
彼らのすぐ後ろの席にその女性たちは居た。
家族連れなどで混雑するレストランで一際目立つ艶やかな銀髪に端正な顔立ち。
幼子のようにジャンボパフェに噛り付く若い女性はかつての南北戦争で「灰被りの魔女」としてその名をはせたイリア・トリトニアと瓜二つだった。
ランスは凍り付いたままのヴァッツの視線を追い、何気なく後ろを向いてぎょっとする。
「お、おい」
ランスはヴァッツの襟首を掴んで近くまで引き寄せると「なんでアイツがこんな所に居るんだよっ」と焦りを顕わにして耳打ちした。
「あ、慌てないでください。他人の空似ということもあります。ましてや戦略級魔女があどけない少女のような顔で甘味を食べているなどあり得ません」
ヴァッツは冷静を装いながらずれていた眼鏡を人差し指で正す。
「……それに、彼女からは魔力を殆ど感じませんし」
「そうは言うが、ベルハルトに報告しておいたほうがいいんじゃねえか」
男二人が顔を突き合わせいる中、彼らの背後では空高くそびえたつパフェが倒壊し、女性の金切り声のちに嗚咽が入り混じる。
「……」
「……」
あんなお子様が、高名な魔女であってたまるか。と言わんばかりに二人は重い腰を上げてその場を後にした。
執筆・投稿 雨月サト
©DIGITAL butter/EUREKA project
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
