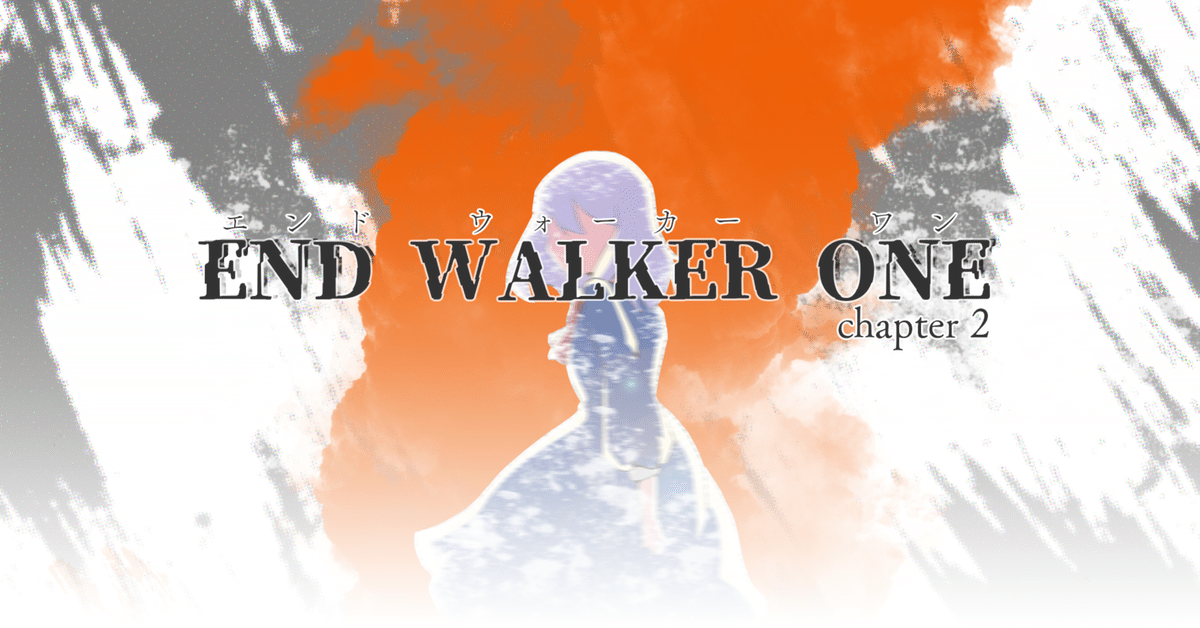
『エンドウォーカー・ワン』第30話
「ノイン、来たよー!」
「あ、アルファさん。無断で男子寮に入っちゃっていいんですか」
金属扉が叩かれると同時に二つの声が飛び込んできた。
「ここが一番防音効いてそうだからね。お邪魔しますー」
「理由になってません、それ」
シルバーアッシュロングヘアのアルファに続き、ブロンドショートヘアのフォリシアが大きなビニール袋を手に室内にずかずかと侵入してくる。
髪も肌色も異なる見た目麗しい女性たちに部屋の主は「アルファ、端末を見ろ」と不機嫌そうに睨み付けた。
「んん?」
アルファは小首を傾げ、肩に下げていたポーチから携帯用端末を取り出した。
未読通知がある旨を知らせる緑色のライトが点灯していることを確認した彼女は、内容も確認せずに「あ、ごめんごめん。準備で忙しくてね」と少しも悪びれた様子もなくローテーブルに手荷物を置いていく。
「お、もう来たのか?」
ノインが苦い顔をしていると不意に入り口扉近くの個室トイレ扉が開き、レックスが顔を覗かせた。
「げぇっ」
その途端、フォリシアがウシガエルを潰したような濁った声を出した。
小皺一つない艶やかな小麦色肌を思い切り歪め、アメシストの光を絞る。
「えぇ……魔女の連れってお前かよ。期待してて損したぜ」
嫌悪感を顕わにすることにおいてはレックスも負けてはいない。
眉を思い切り顰め、苦虫を口で反芻して毒を吐き出す。
「なにぉ! わたしのどこが不満なのよ!」
「すぐ怒るところだよ! もう成人してんだろ、大人になれよ」
「はぁ? あんたより半年早く生まれてるんですけどぉ? 入社だって早いし」
「ほぼ同期だろうがよ!」
いがみ合う二人。
フォリシアは白い歯を噛みしめ、拳を強く握って青年の胸元に突き付ける。
「まあ、いつものことだ」
「そうなの?」
すっかり保護者目線のノインはため息を一つ。
試合をするには狭すぎるリングで血気盛んな男女が組み合っている。
純粋な力勝負は互角といったところで、レックスは女性相手に男性としてのプライドが許さなかった。
「あいつらは置いておくとして……レクリエーションとして『サメ映画爆音上映会』というのはどうなんだ?」
「昔はよく一緒に観たじゃない。げらげら笑っちゃってさ」
「あれ、隊長とアルファさん知り合いだったんですか?」
悪魔すらも滅ぼしかねない形相だった小麦肌のフォリシアが一瞬で素顔に戻り、踊るように腕を絡ませて相手を床に押し付ける。
そして少女のようにぱあっと顔を輝かせて風見鶏を決め込んでいたノインとアルファの間に割って入った。
「え、あ……うん。ちょっとね?」
「アルファ、含みのある言い方をするな。昔からの友人だ」
「へぇー? そうなんですね?」
ノインのさり気ない一言にほんの僅かに表情を陰らせるアルファ。
青年に対する好意を隠しきれていない――いや、むしろ長年の鬱積したものを晴らすかのように思いを前面にだしていた紅色が僅かにくすむ。
「なるほどねぇ」
前々からそれを感じ取っていたフォリシアが目を細め、悪戯を思いついた子どものように口角をあげる。
頭の中を青春時代の青い記憶が吹き抜けていき、朱色が僅かに差し込んだ。
「オレは放置かよ!」
床に這いつくばっていたレックスが身を起こし、叫ぶ。
「舐められるお前が悪い。だが、フォリシアもいい加減にしろ。嫌味を言ったところで何が変わるわけではあるまい」
「でもたいちょー。コイツ、女の子のこと本気で叩いてくるんですよー?」
「だからっ、本気じゃねぇって!」
「あははぁ……お友達。そう、私達はお友達……」
場が騒然とする中、映像投影機材と共に持ち込まれた映画「恐怖! サメ神父!」のホロディスクパッケージが寂しげに佇んでいた。
「久々だな、ハンドラー。お前のほうから連絡を寄越すとは珍しい」
いつかの高級レストランで無精髭の男がリカルドの前の席に腰を落とした。
彼はこの店のドレスコードに引っかかるような恰好で、黒革のジャンバーにラフなデニム、スニーカーといった出で立ちだ。
「ドミニク、身嗜みは確りとしておけとあれほど」
「こうしていれば老けて見えるだろう? 情報屋としてはそちらのほうが都合が良いんでな」
彼はそう言うと、泥の底から這い出るようなトーンを少しだけ地声に戻し、ニヤリと笑ってみせる。
「お前は役者にでもなればよかったのだろうに」
「生憎と鉄の味が恋しくてなあ」
ドミニクは席にやって来たウェイターからガラスコップを受け取り、中身を一気に呷った。
「それで、何を知りたい?」
「『サウストリア解放戦線』についての情報を集めてほしい。金と人員、物資の流れ。政治的背景から何から全てを」
「テロリスト狩りでも命じられたか、リカルド」
それまではどこか遠くで高いところで風見鶏を決めてたドミニクが地上に音もなく降り立ち、リカルドと視線を合わせる。
彼自身、この男に執着心に似たものを持ってはいる。
それを悟られまいと距離を保ち、毒を吐き続けてきた。
しかし、そんな彼でも解放戦線の面々には煮え湯を幾度となく飲まされてきた。
「ふん。吹っ掛けてやりたいところだが、あいつらには俺も借りがあってな。格安で請けてやる。着手料で100だ」
「50」
「……80だ。ハンドラー、分かるだろう。先はテロリストと呼んだが今のあいつらは小国以上の戦力を保有している。地球の技術も提供されているという噂がある」
「噂は噂だろう。60」
「70。これ以上は無理だ、嫌なら他を当たれ」
執拗な値引き交渉に椅子を引いて席を立とうとするドミニク。
「こちらの提示額は60だ。お前も世界がどう動いているか知りたいだろう」
リカルドはテーブルの上でゆっくりと手を組む。
そして「542」とかつての戦友の識別番号を口にした。
「……独立戦争での功績を認められた俺たちには市民権が与えられ、それぞれ第二の人生を送れるはずだった」
ドミニクはこれまでの熾烈で苦難に満ちた人生を掻き混ぜた様々な顔を覗かせて、苦渋を絞り出すが如く言葉を吐き出し始めた。
「だが、現実はどうだ。軍属経験というだけで一般企業からは門前払い。舞い込んでくるものと言えば裏社会の汚れ仕事ばかり。所詮、時代が変わろうとも猟犬は猟犬。飼い犬のような安寧は到底訪れないのだろうな」
二人がまだ若かりし頃、リカルドと共に将来の夢を語り合ったドミニクの表情が曇る。
「飲め。今夜ぐらいは奢ってやる。が、60だ」
リカルドは通りがかったウェイターを呼び止め「ツァイスのシングルモルトを。ロックで」と注文し、間もなく運ばれてきた氷の水晶になみなみと注がれた琥珀色のグラスを旧友の前へ差し出す。
「……企業人は余裕だな」
「軍隊時代にでもお前を掬い上げることができれば良かったのだが」
「思ってもいないことは口に出さないほうがいいぞ、ハンドラー」
昔馴染みの男たちの夜は淡々と、しかしどこか愉しげに更けていく。
執筆・投稿 雨月サト
©DIGITAL butter/EUREKA project
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
