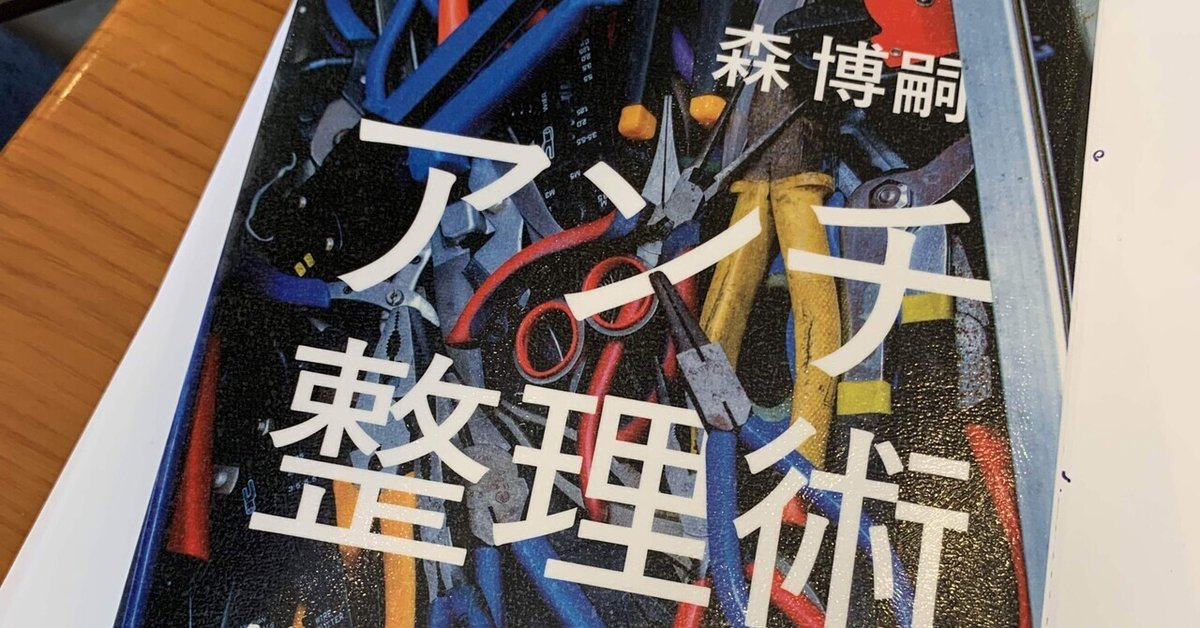
アンチ整理術、その2。
『著者34歳、息子さん8歳のときの話。
息子が欲しいプラモデルを買って、つくり方を教えた。
最初だから、基本的なことを指導。
パーツを無くさないために、袋から出したパーツは、一つ切り離したら、残りはまた袋にしまう。散らかさないことを説明。
説明後、子どもを残し自分は書斎に入る。
しかし、ここで自分の昔のやり方を振り返る。せっかちな自分は息子に説明したやり方でやっていないことを思い出す。袋から取り出したパーツは最初に全部切り離した。
作ることに夢中で、周りは散らかし放題だった。マニュアル通りにはやっていなかった。そして何度も失敗した。
だから、息子にその失敗をさせたくなかったので、アドバイスをしたつもりだった。
しかし、そんな几帳面なつくり方で、はたして面白いだろうか、と思い直す。
自分は無心につくっていた。夢中になることで周りが見えず失敗を何度もした。
でも、つくっている最中本当に楽しかった。だから、いまでも工作を続けている。
一番大事なことは、「片付けて部品を無くさないことではない」』
(以上、P71〜72から主旨を引用しました)
さすがアンチ整理術だ(笑)
この後、整理・整頓の利点も付け加えているので、整理術を全面否定しているわけではない。
しかし、闇雲に整理術のノウハウを信じて実践してしまうことの怖さをしっかりと指摘してあり面白い。
しかも、自己体験からの展開のため、読んでいて面白いし、とても説得力がある。
この章のまとめとして、
自分の子どもに「片付けなさい」「きれいにしなさい」と叱るときがあったら、それよりも大事なことはないか、と一瞬で良いので考えているいただきたい、と添えてあります。
要は、整理整頓するべきものは、自分の部屋より、自分の精神ではないだろうか、と述べています。
感情的に叱ってしまう、親側の精神状態を常日頃からチェックしておくことの方が大切なのではないか・・・とやや控えめに述べています。(笑)
ここから、部屋の整理・整頓から、頭の中の整理・整頓へと話が展開していくようです。
つづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
