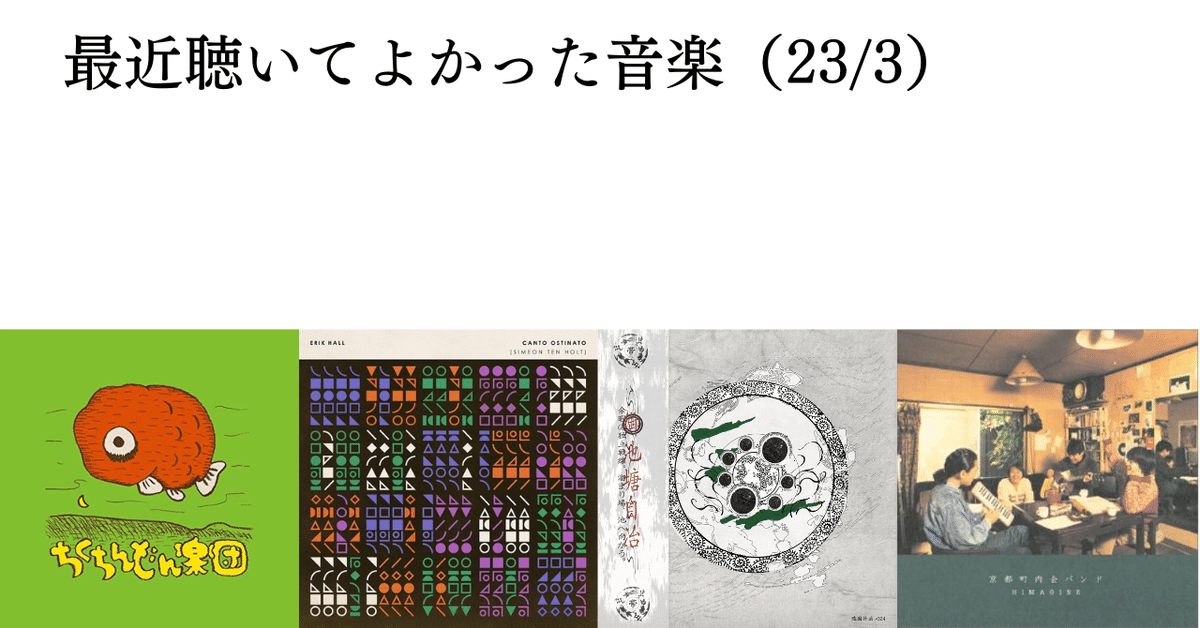
最近聴いてよかった音楽(23/3)
最近聴いてよかった音楽を並べていきます。新旧混合。
3/Czerwone Gitary
人呼んでポーランドのビートルズ。なるほど確かにポップで楽しいブリティッシュロック。初期ビートルズを彷彿とさせる音楽だ。当時のポーランドでは大変人気があったバンドそうで、この3作目まで素朴なビートポップが楽しめる。が、この後リードギターが脱退しサイケデリックな方面に行くことになる。今作でもコーラスワークにサイケの萌芽が。
サイケ期には名盤SPOKOJ SERCAを残している。ファズの利いたサイケサウンドなので世間からの評判は良くなかったそうだが、今でもポーランドロックの代表作として知られている。こちらもおすすめ。
いずれ「○○のビートルズ」だけを集めた特集を作りたい。
悪魔とドライブ/ヘノモチン井上
友人から教えてもらったこちらのアルバム。手作り感満載のジャケ写、珍妙なアーティスト名と見るからに自主制作なアルバムだが、なかなか面白い音楽だ。
白眉なのは、一曲目の「月面温泉」。初期細野晴臣や久保田麻琴に比肩するエキゾチックポップスに仕上がっている。音作り自体も808ライクなドラムマシンや妙にノイズかかったボーカルなど宅録での制約を感じさせるものの、それを逆手に取って味としてしまうゆるゆる退廃SFな世界観が癖になる。この空気感はその後もアルバム全体で繰り広げられ、気づいたらアルバムが終わっていること請け合い。
総じて核戦争後のカクバリズムから出てそう。このアルバムしか出していないようだが、まだ音楽活動しているのだろうか。
ちくちんどん楽団/ちくちんどん楽団
たまでの活動で非常に著名な知久寿焼氏の新ユニット、1stアルバム。ちんどん太鼓やチューバを用いたユニークな編成だが、なんでもちんどん太鼓を使ったバンドは知久氏が長年あこがれていたらしい。
たまでも演奏していた曲を含めた既発曲が中心だが、それによってかえってこの編成のユニークさが際立つ。知久寿焼氏の世界観はそのままに祝祭のような雰囲気が足し合わされ、明るい薄気味悪さに拍車がかかる。一曲目の「ここはもののけ番外地」はまさにコンセプトの説明として機能している絶妙な配置。
また知久氏以外のメンバーの個性も垣間見られるのも高評価。沖縄民謡だったり大正琴だったり、知久氏に負けない各員の個性もこのユニットを唯一無二のものにしている。
怪譚奇譚 マツゑツタヱ/志人
異形のラッパー・志人のアルバムだが、今作は彼の中でも突出した異色作になっている。なんでも全編を通して志人自身が体験した不思議な話を聞かせるだけなのだから。内容も村のよそものについての話や神社についての話など、怪談というより親戚のおじちゃんの話のムードに近い。少なくともラップではない。でもなぜか繰り返し聴きたくなる魔力がある。ただの話し言葉でも志人にかかればラップになるのかもしれない。
とあるBook Offでは民俗学コーナーに置いてあったといういわれもある今作だが、「志人は音楽家として一体何を目指しているのか」を垣間見られるとも思う。それについては別名義でこの前記事を書いたので是非読んでください。
御池塘自治/帯化
インダストリアルで土着なサイケバンド・帯化の新譜。今まではライブ感の強い作品だったが、今作ではよりエレクトロニカやドローンなどの方面に寄っている。なんでも2年かけて作った渾身作だそうで、なるほど確かに今までの帯化とは一風違う。
前作でも見られたフィールドレコーディングの要素をさらりと使いつつ民謡風のバンドサウンドに混ぜ合わせた結果、山奥の祭祀か何かのような世界観が生まれている。ドローンとハードロックの混ざり合った様はドゥームメタルも感じるね。また要所要所にアンビエントを意識した音作りも散見され、意外とその手の筋から評価が高そうだ。
かなり重苦しい音楽性だが、カセット版には水引がついていて可愛い(大事)。カセットで買った。
HIMAGINE/京都町内会バンド
まあまあ有名なバンドらしいが、何気に先日初めて聴いた。確かに何曲か聞き覚えのある曲が。
SSWの笹野みちる氏が鬱にだった頃に誘われて作ったバンドらしい。町内会というだけあって出音はジャケット写真の雰囲気のような、フォーキーで優しい音色。その優しい音楽の上、ちょっとしたおふざけを交えた関西弁で語られるのは否応なく絶望を感じさせる人生における無念と諦念。
「あせりながら暇人」
「引き起こす涙を振り切りながら前だけ見つめて歩くのでしょうか」
「間違い探しはもうやめよう 正解探しももうやめよう」
こういった歌詞は才能ある若者からは絶対に出てこない。そしてこういう音楽こそ本当に必要とされるべきであるし、大切にしたいものである。
六大 水/菊地雅章
稀代のジャズピアニスト・菊地雅章によるアンビエント作品。「六大」というシリーズの中の一作である。六大は名盤Susuto後に久々に発表したシリーズ。手法としてはアナログ・シンセをシーケンサーでループさせながらインプロしていく、というもの。Paul Breyがやっていたのと似た手法である。が、内容は当時としてはかなり先進的な前衛アンビエントであったため理解されず、ファンにとってはガッカリだったらしい。
今作「水」は洞窟の中の水音のようなシンセサイザーの冷徹な音響が聴いていて心地よい。アンビエントのようだが、時折気づいたように新しい手弾きの演奏(と思わしきシンセ)を挟んでくるので意外と気が抜けない。かなり素敵な音楽。
アンビエントファンにとって、六大はなかなかの傑作ぞろいであり揃えていきたい所存。だがCDがまだ普及していない時代にLDとCDのみの発売だったためほとんど出回っておらず、かなりのレア盤だ。僕はまだ地と水しか手に入れられていない。残り火・風・空・識を手に入れられるのはいつの日か。因みに菊地雅章の娘さんも全部は持っていないらしい。
Siemon Ten Holt: Canto Ostinato/Erik Hall
数年前ミニマル音楽の名曲「18人の音楽家のための」を一人で多重録音したことで話題を搔っ攫ったErik Hallがまたやってくれた。今回彼が取り上げたのはヨーロッパのミニマルミュージックの名曲・Canto Ostinatoである。
原曲は四台のピアノ演奏が三時間続く超大作。ミニマルでよくあるダダイズム的実験ではなく、調性音楽への回帰というちょっと変わったコンセプトが特徴だ。明確なメロディーパートが出てくることさえある。過剰に前衛な雰囲気はあまりなく、お洒落で楽しいクラシカルな作品となっている。Erik Hallはこれを七台のキーボード作品へとアレンジ。ピアノ以外もハモンドやローズエレピなども使い、よりミニマル音楽らしい解釈で聴かせている。
これを聴いて思い出したのは昨年横浜での公演を見に行った「浜辺のアインシュタイン」。あれもフィリップグラスのミニマルの名曲だが、生で聴くとミニマル由来の無機質さと生演奏によるクラシカル要素がうまく調和されていた。今作では逆に無機的な演奏と有機的なミニマルである原曲との調和を図っているのかもしれない。
EMAHOY TSEGE MARIAM GEBRU/EMAHOY TSEGE MARIAM GEBRU
エチオピアの女流ピアニスト。エチオピアといえばコンピシリーズ・Ethiopique。ボブディランもフェイバリットに挙げるこのコンピはエチオ・ジャズの再評価やエチオピア民謡の発掘にも一役買った非常に影響力のあるシリーズとなっている。その中でもとりわけ異色とされたのが彼女。ポストクラシカル風味の非常に強いピアノ曲が持味だ。
ユニオンではエチオピア meets サティと紹介されているが、似た作風のサティのサラバンドより全然音数が多い。サティとドヴォルザークの中点といった趣。そのためアンビエントというのはちょっと違うかもしれない。しかし南米の民俗音楽の背景を感じさせながら、西洋クラシックの歴史上にあるこれらの曲は唯一無二。
アンビエントファンにもまあおススメして損はないが、やはりポストクラシカルなのかな。民俗的なポストクラシカルを求めている人には良い提案となりえそうだ。
Poil Ueda / Poil & Junko Ueda
プログレ界隈では有名なフランスのバンドPoil。フランスのバンドは妙に日本好きなことが多いが彼らも例にもれず、雅楽や長唄のフレーズを使って曲作りするなど日本の音楽を取り入れた音楽を数多く出してきた。今作ではついに本物の琵琶奏者・上田淳子とタッグを組み、平家物語をハードロックで語っている。ちなみに上田氏は薩摩琵琶で最も重要な人物の一人らしい。
上田氏の琵琶と語りを中心に、Poilはお得意のプログレッシブなハードロックで従に徹する。語りが戦いのシーンに入ると変拍子の利かせ、平家滅亡ではまるで壇之浦の波音のようなドローンを仕掛けていくのは日本のバンドかと思わせるほどの対応っぷり。内容相まってフラワー・トラベリン・バンド「Satori」を思い出させる程の好作となっている。
プログレのニューカマーは個人的にはあまりピンとこないものが多かったのだが、今作はちゃんと「プログレッシブ」なロックに仕上がっている。非プログレファンも是非。
その他細かな諸々
・デラソウルだの間宮貴子だのマニュエル・ゲッチングだの、サブスクにいなかったあの名盤たちが世に解き放たれつつある。約束の時は近い。
・人死にすぎ
・いつの間にかGEZANが新作を出していた。やはり良いね。
・今度出る大滝詠一のノヴェルティ・ソングブックのDisk2にさいざんす・マンボの大滝詠一Remixバージョンが入るらしい。今までめったに聴けなかったが、87年の日本でヒップホップライクなリミックスをやっていた大滝詠一の先進性を表す重要な作品なのでうれしい。
・インディーの雄であり私の直接の先輩にあたるバンド・Khakiが新曲を出すが、この曲は個人的に因縁がある。この曲を聴いた大学一年のEPOCALCは「東京にはこんなやばい曲を作る人がいる、音楽の知識量で超えないと一生追いつけない」と思い一回音楽制作をあきらめ、音楽ブロガーに転身したからだ。この曲がなければこのnoteを含めた私のあらゆるブログ活動はなかったはずだ。
\ ニューリリース&記念公演開催決定!🪷/
— Khaki (@khaki_band) February 13, 2023
2023.3.13
2nd シングル
「 Undercurrent 」をリリースします
 ̄ ̄ ̄ ̄
それに伴いリリース記念公演開催決定🥚
本日よりチケット受付開始!
____
チケット受付https://t.co/bymkOjQNU0 pic.twitter.com/vmSuRUHsGD
・ちなみにKhakiのフロントマン・中塩氏の作品に一番最初に評をつけたのは私である。(下記の記事の「仮病な僕ら」)
・CDショップ大賞が発表されていた。カネコアヤノの翌年からCDショップ大賞の選考が変わったような気がしている。個人的にはあまり好きではないやり方。
・別名義で曲を出しました。この名義でちょくちょく音楽活動していきます。よろしくね。
・ちなみに上記の作はフォークチャートで最高全国26位だったそうです。ありがとうございます。
・このネタツイができなかったことをまだ悔やんでいる
チャーハン
— ナツイ (@natsui_tanoshi) March 6, 2023
チャーハン ひとりでに pic.twitter.com/RPH8Bq21tM
サポートしていただくとマーマイトやサルミアッキなどを買えます。
