
音楽づくし:「音風」&「いろいろ」
音景楽団「音風」
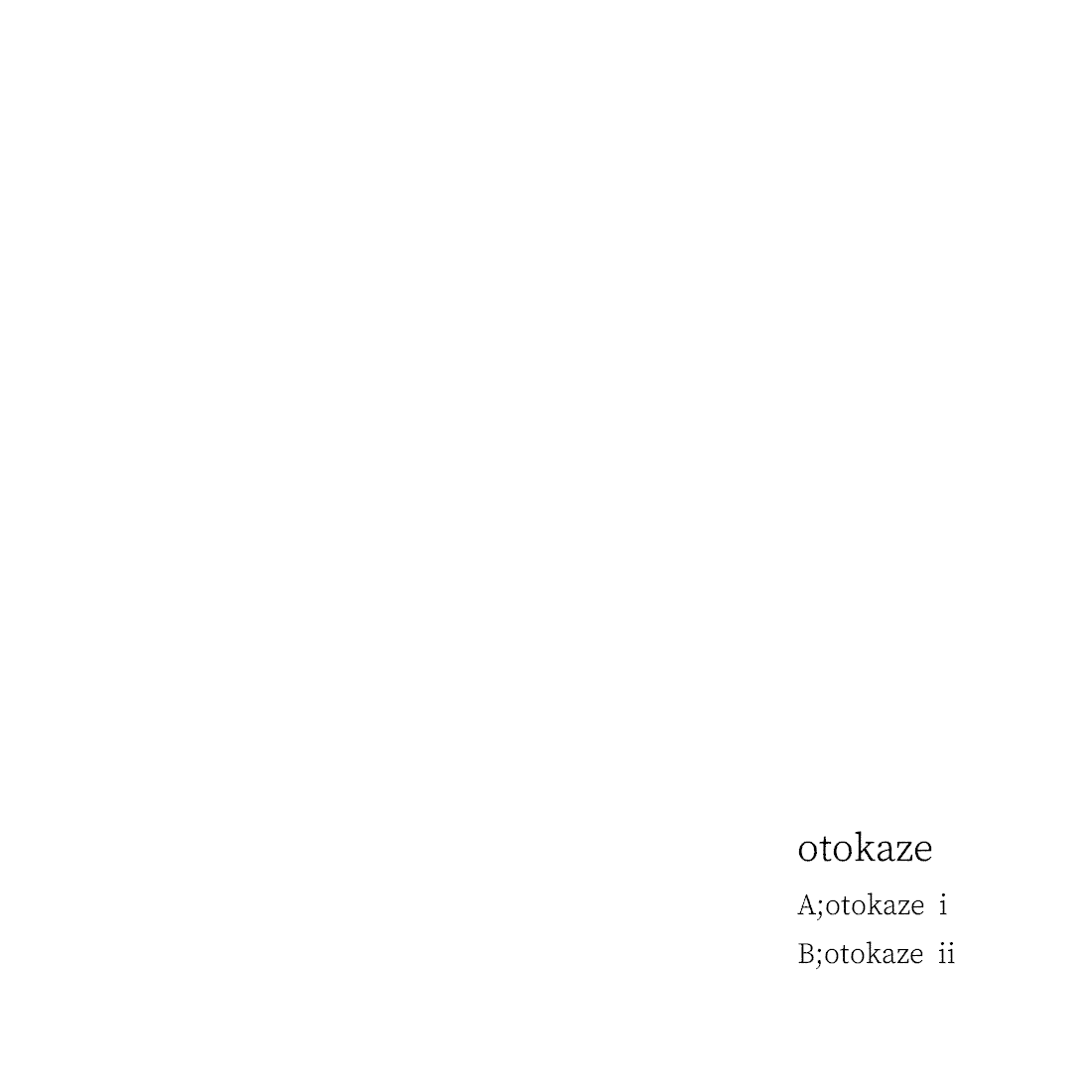
数年前から始まったアンビエント・リヴァイバルの中で、多くの音楽家が才発見された。吉村弘、高田みどりなどはその典型例だろう。ともに現在の音楽ファンなら多くが知る名前だが、ほんの数年前までは殆ど誰も聴いていない音楽だったのだ。
彼らの存在が示しているように、まだ然るべき評価をされずレコード屋の奥底に眠っている音楽も多い。その代表が音景楽団だろう。
音景楽団は1980年に当時都内の美術大学に在学していた紺野利典によって友人たちと結成された楽団である。当初はBrian Enoのレーベル・Obscureに影響を受けたポスト・クラシカルを志向していた。しかしながらBrian Enoの名作"Music For Airport"、そして紺野が卒業論文で扱った「サウンドスケープ」の概念に影響され特異な音楽へと深化していくことになる。その成果がアルバム「音風」だ。約500枚、自主制作で作られた。A面とB面それぞれに「音風i」「音風ii」が収録されている。
さてこのアルバムの内容は45分にわたる無音とちょっとしたノイズである。
これをインターネット等で試聴した者からは4;33の再生産と呼ばれることがあるが、それは大きな間違いと言えよう。なぜならばこのレコードには芳醇なサウンドスケープが収録されているからである。
「音風」では音をほとんど出さずにサウンドスケープのみを収録する、世界的にも類を見ない大変前衛的な試みが行われている。これはアナログレコードという媒体だからこそできる表現であり、MP3などのデジタルファイルにしてしまうと失われてしまう。デジタルマスタリングの過程でもやはり失われてしまい、これが本作が再発できない大きな原因になっている。
私は本作を聴いた時非常に感銘を受けたのだが、表現されているのが極めて概念的なものである都合上実際私と同じように他の人に「聴こえている」かは未知数である。そこで友人を集めて鑑賞会を行った。
するとはたして、友人全員が僕と同じように「聴こえて」いたらしい。A面の4分ごろに収録された神社のサウンドスケープに多くの人がノスタルジーを覚え、13分ごろに登場するミカン畑のサウンドスケープにすがすがしい香りを感じたと答えた。そしてB面17分30秒前後から始まる宇宙のサウンドスケープを皮切りに、月、太陽、神、夢、憧憬、愛、現在、実存、構造のサウンドスケープが畳みかけられるシーンでは友人は口々に「世界ってそんなものだったのか」「全てを知るのは虚しい」とブッダのような眼で呟いていたのが印象的だった。
たった45分でLSDを軽く凌駕する体験を得られるこのレコードだが、その後解散しメンバーも音楽活動を止めてしまったため知る人は少ない。しかしコアな音楽ファンの間ではカルト的人気を誇る。稀に中古レコード屋にノイズ音楽と紛れて置いてある。8000円ほどで買えたらラッキーだと思おう。
いろいろ -Sota Sato
音楽にちょっとでも詳しい人なら、この問題作の名前くらいは知っているだろう。このアルバムは二年ほど前からYoutube上に公開されていた音源である。最近になって話題になったきっかけは「人によって全く違く聞こえる」との、信じがたい情報が飛び込んできたからである。
事はこのアルバムについて二つの言及がなされたところから始まった。
ある批評家のブログ記事で、「デジタルコアとアフリカ北部の民謡を違和感なく溶け込ませた傑作」と評された。一方、全く別の著名音楽家のTwitterでも言及されたのだが、そちらでは「英アシッドフォークの伝統に則りつつも、どこかブラックメタル的解釈も可能なフォークロックアンサンブル」との内容。そう、二人ともまるで言っていることが違うのだ。
某音楽雑誌編集長がこれを疑問に思った。評がここまで食い違うことがあるだろうか。そして実際彼が聴いてみたところ「後期渋谷系と60年代歌謡曲の融合」といえるものであり、この二人とも全くの別解釈であったのだ。そこで同僚の編集者たちに聴かせたところ、全員から全く別角度の評が飛び出してきた。この衝撃的な内容が彼の雑誌に特集されたのが約半年前。以降、この20分弱の動画は物議を醸し続けている。
その特集の中では一体どのような仕組みでこの音楽は作られているのか、音響研究のエキスパートによって解析されてもいた。なんでも「様々な形の音波が、ほぼすべての可聴帯域の周波数において鳴っている」とのこと。本来ならば単なるノイズになってしまうはずだが、上手い具合に各々の音のバランスを保っているため脳の錯覚で一つの音楽に聴こえるらしい。永遠に下降しつづけるように聞こえてしまう無限音階と同じ原理らしい。もっともこれはあくまで仮説の域を出ない。
こうなると作曲したというSota Satoの素性が気になるが、本人は一切のインタビューに応えていない上どこにいるかさえ分からない。彼の作ったとされる音楽もこれ以外見当たらない。筋によれば音響系の研究者を目指し博士を目指していたが精神を病み大学院を中退、以降消息不明だったらしい。もっとも真実は分からない。
インターネット上の不特定多数に晒された昨今、この音楽への奇怪な評は増え続けている。「back numberを彷彿とさせる甘いJ-POP」から「Merzbowの再来」まで。しかしながら概ね一致しているのは「その人にとっての大傑作」であるということ。ある人は「これ以上の音楽は今後出てこない」と言ってしまったほどである。
もしかすると彼は何らかの復讐でこれを作ったのかもしれない。今後絶対に超えられない「名盤」を作り、音楽制作者をあざ笑うために。完璧なアルバムが存在してしまった今、音楽家たちはどこへ向かうのだろうか。
※以上の音楽たちは存在しません。
サポートしていただくとマーマイトやサルミアッキなどを買えます。
