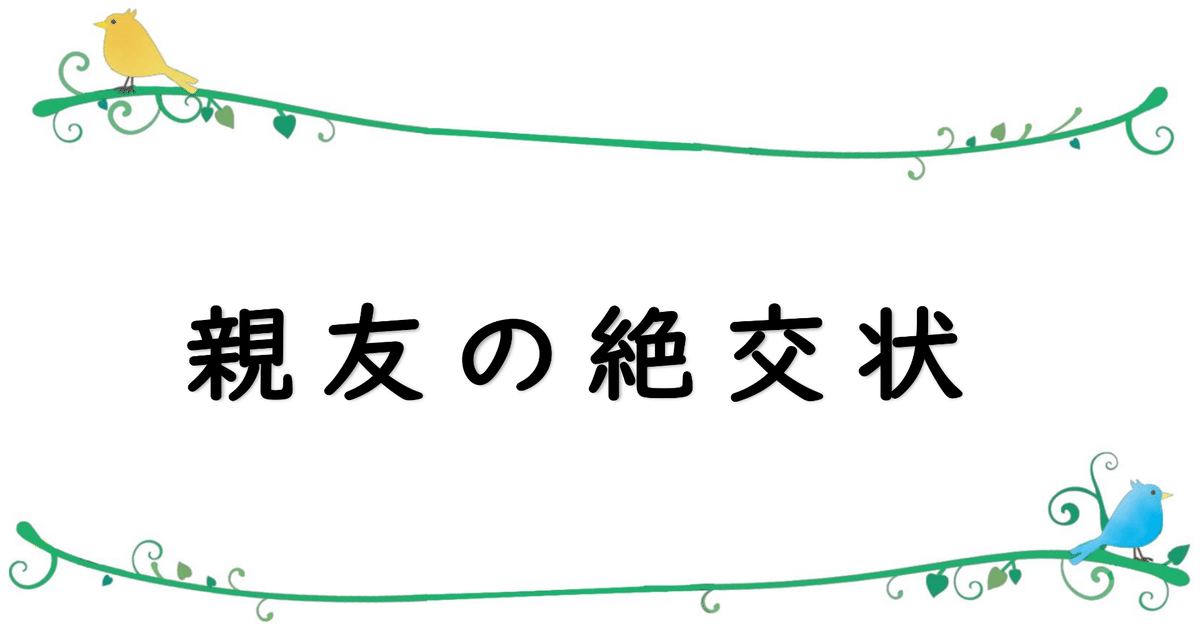
(私のエピソード集・7) 親友の絶交状
女子大生になった私は、倉敷の親友Mに、大きな段ボール箱を、満杯にさせたほど手紙を送り続けた。
彼女とは、高2の頃、共に『風と共に去りぬ』のレット・バトラーに熱烈と知り、手紙で言いたい放題、語り合ったのが始まりの仲だった。
彼女は経済的理由で、進学は諦めていたので、3年時に進学クラスに引き抜かれた私とは、別クラスになったが、変わらずランチを共にしたり、私の部屋でいっしょに勉強したりしていた。
彼女はすべての科目のノートに、〈最終授業〉と付記していた。高校での授業が、自分にとってはこれで最後だから、一時間一時間を大事にしたいの、と真剣なまなざしでそう言った。
私は彼女の自分の人生への向き合い方に、強く胸打たれ、尊敬するようになった。進学クラスでは、受験に無関係の授業になると、バカにしたり、無視する人がいて、Mと比較せずにはいられなかった。
彼女は水島にある大企業に、私は東京の女子大学に進路が決まった3月、二人でいろいろ話し合った。
「お金がないから、ブラウスとタイトスカートを一着作って、それを毎日着て行くつもりよ」と彼女は言った。その一着の服を、どう着こなすかを、真剣に考えているらしい。私の数少ない服についても考えてくれた。「白い手袋を買えば、ぐんとステキになるよ」とも言った。
別れる前に約束したのは、私は大学での授業のこと、寮生活について手紙を送ること。彼女は毎月のお給料で、寮におやつを送ってくれることだった。
そして四月から、約束は実行された。
私は寮生活の初日から、知らせること満載で、便箋なんかしゃらくさい、安くすむレポート用紙に10枚から15枚ほどの手紙を送り始めた。1週間に一度かそれ以上送ったはずだ。
なにしろ、寮の初日の夜、停電が起こり、真っ暗な中で、新入生37名が、寮役員に率いられて、地下室へ連れていかれ、寮内の規則をエンエンと告げられたのだ。
暗やみにおびえながら、自室に戻ってみたら、窓際には白シーツをかぶったお化けが! 足元や首筋をニュルッと冷たい物がかすめるし・・。他の部屋からは、叫び声や泣き声が響きわたっていた。 電気がぱっとついて、さっと逃げてった人たちは、なんと、上級生だった!
こんな寮の歓迎ストームに始まって、その後2,3日は、笑っちゃう出来事が続いた。大きな名札を、自分で作って胸につけて、同じキャンパス内にある、大学の教室へ行って、通学生たちに笑われたり、新米の寮監先生に、朝と寝る前の挨拶に行ったり・・みんな上級生のでっち上げの、嘘っぱち〈寮規則〉にすぎなかった。
Mには、寮そのものについても、説明しておかなくてはならなかった。 寮は東寮と西寮と、100人づつ入寮していて、私は西寮!100人が10の〈列〉に分けられ、1年から4年生10人のグループで〈1列〉と名づけられていた。
朝6時から二人づつ掃除当番で、廊下や洗面所トイレ掃除が課せられる。朝夕の食事後の〈お洗い〉と称する〈食器洗い当番〉も、列毎に回ってくる。
さらに寮の入り口の、週番室に待機して〈来客応対〉や〈電話取次ぎ〉などを担当する〈週番〉の当番も、列毎に巡ってくる。テキストや授業の内容、アルバイトの話、お金のこと、書くことだらけだった。
一方Mの方は、最初の2,3ヶ月、本当にブラウス一着で、通勤を続けていた。会社から帰るとすぐに洗濯し、翌朝には同じのを着るのだが、会社のバッジを、アクセサリー代わりに、あちこちにつけ場所を、変えて楽しんでいた。涙ぐましい、と言えるほど、節約を貫いているのに、月末には私に、ピーナツやお菓子などの、食べ物が詰まった荷物を、忘れず送ってくれた。
でも、こんな楽しい関係は、一年とちょっとで、途切れてしまった。安保闘争のせいだった。
女子大の中では、当時いくつもの派に分れて、デモ隊が繰り出していた。体力のない私は、寮の友に誘われて、時折参加する程度だったが、それを知ったMは、絶交状を送って来たのだ。
学生の身で、政治に口出しする資格なんてない! 独り立ちしてもいないし、親にも政府にも、支援されているのに、よくそんなことできるわね。もう手紙は送ってこないで、と強い口調だった。
大企業に勤める彼女らしい意見だな、と思うと同時に、説得力もあるなあと、感心もしていた。
後に、お互い子どもを育てるようになってからは、子育てに振り回されていた彼女に、相談されたりして、いつのまにか親友に戻っていた。
そして40代の頃、私は寮物語を書きたくなり、彼女に送った手紙を思い出して、問い合わせてみた。彼女は結婚する時、段ボール箱に満杯にあった私の手紙を、すべて焼いてしまったと答えた。
青春の数頁が消されたようで、がっかりしたが、一度言葉にしたものは、心に根付いているとみえ、『あじさい寮物語3巻』にまとめることができた。
今は亡き友人の児童文学作家、堀内純子(すみこ)は、若い頃、死期間近い恩師宛てに、手紙を書き続け、それが先生を慰め、元気づけ、死期も延ばせたと、ご家族に感謝されたそうだ。
葬儀の時、奥様が「あなたの手紙はもったいなくて、燃やせなかった」と、すべて返してくれて、その手紙のおかげで、何作か作品を書けたそうだ。
私の手紙には、それほどの力がなかったのだ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
