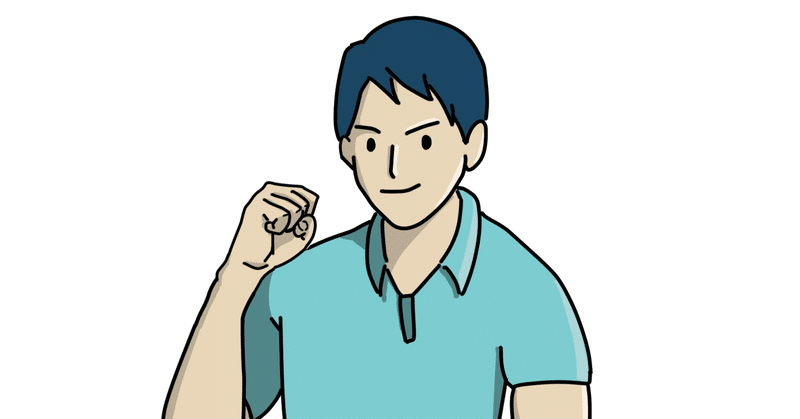
子どもたちが職員会議でプレゼンをします!~最終回~
プレゼンで一番伝わるのは”想い”を伝えたとき。
そしてひとつの壁を乗り越えた先に待っていたのは、
”達成感”と”「もっともっと」という欲”。
前回の内容は、こちら↓
実際に職員会議を行う際に、教職員側の聞くスタンス、立ち振る舞いの確認をしたうえで、いざ本番です。
伝える術を知り、より高い意欲喚起へ
職員会議が定刻通りに始まり、早速子どもたちの提案発表が始まります。
今回の企画提案、つまりプレゼンを行う場合に大事にしていたこと。
それは、
子どもたちには、大人に負けない”伝えたい想い”がある。
ただ、その伝え方を知らない。
知らないがゆえに、上手く出来ずに諦める。もどかしくなる。
ならば、子どもたちには「伝え方」をアドバイスしよう。
武器を持った状態にして、それを使いこなす訓練は自身に任せよう。
ただし、決してその武器は万能ではないことも伝えよう。
知らないを知る、知って更に知りたくなるを生む。
できるようになりたい!
伝わるようにしたい!
もっともっと!
これを生むことです。
本来は、1回目より2回目、2回目より3回目と回を重ねるごとにブラッシュアップを図っていくことまでしたかったのですが、1回限りの大勝負。
この1回でどれだけ磨き上げられるかです。
資料に対するこだわりと、どこに”想い”をのせるか
プレゼンテーションなどでは、以下の3つが大事と言われています。
エトス(道徳・倫理・人柄)※これの解釈が私の中では難しい
パトス(情熱)
ロゴス(論理性)
子どもたちに大事にしてほしいのは、
持っている"パトス(情熱)"を存分に伝えること。
それを”伝える”から”伝わる”に変えるには
・ロゴス(論理性):構築の方法を学び、組み立てること
を、持てるかです。
※エトスに関しては、以前子どもたちと一緒に考えた難しい言葉でした。
今回はある程度作られている関係性の中での発表なので、ここでは割愛しました。
改めて、何を伝えたいか、どのように伝えることが、より相手に伝わるかということは考えてもらうには、既に「企画書」でかなり練ってくれています。
となると、今回の範囲内では”視覚効果”、つまり見やすさにこだわってみては?と一つアドバイスをしました。子どもたちに何を見てもらったか。
例えばこういう本です。
つまり高校生だから、子どもだから…社会人向けの本はという”思い込み”は除外です。
こういう素材があるだけで、子どもたちは、すぐに考えます。
そしてそれが本番でも発揮されました。
どうしても動きがあった方がいいんじゃないか?とか
文章があった方がわかりやすいんじゃないか?という
知識が何もない状態だと陥りやすい”蛇足”から抜け出したスライドを準備してくれました。
終了後の振り返りで、感心した内容は、以下のもの
・手元に細かい資料があるのだから、スライドの文字は最小限にした
・文字は職員室の広さを考えて、絶対に20pt以上は守った
・強調したいところだけ色を付けて、他は灰色の配色にしてみた
・スケジュールを表形式から、数直線形式にした
・どうしてもやりたい想いを伝えたかったから、今回のメンバーの写真をいれたかった。
・出来れば動画までやりたかったけど、その技術がなかったのが残念。
・スライド番号をいれるということだけで、説明が更にしやすくなるというのは気づきだった。だからプリントにページ数とか入れているんだという納得感。
・先生たちが、たまに職員室で話している「板書計画」って言葉の意味がなんとなく分かった気がする。
・出来れば、発表の仕方・しゃべり方も教えてほしかった。多分、緊張して上手く喋れていない気がする。
素晴らしい振り返りだと思います。
自分たちの意図したものを言語化できること。
反省点やこれからのことを踏まえた分析。
実施したものに対して、私は、
ある程度の満足感(80~90%)と、ある程度の残念に思う気持ち(10~20%)が残るのが理想だと思っています。
それは、後悔ではなく反省。
悔いを残すのではなく、”まだ”足りなかった自分を次のステージへ上げるための材料。
そうした口惜しさを、持ち続けることも必要だと思います。
結果、今回の生徒発案のイベントは、満場一致賛成。
そして
「高校生活の想い出になる、全員参加できるイベント」
は無事に実施されることになりました。
後日談にはなりますが、その年の卒業式終了後、今回の発表をした生徒と少し雑談をする機会がありました。
貴重な経験させてもらいました!ありがとうございました!
貴重な経験と言ってもらえたことが、全てだったような気がします。
でも、口惜しさもあります。
これをもっと定例化、もっと多くの人に。
まだまだできるはず。
子どもたちだけではなく、大人の我々も
ある程度の満足感(80~90%)と、ある程度の残念に思う気持ち(10~20%)を残して、次のステージに向かわないといけませんね。
ご覧いただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
