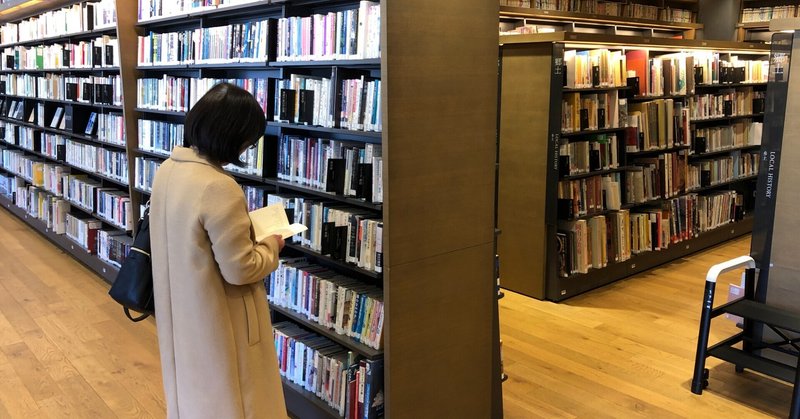
現象学的人間学
書庫の整理をしていたら,一時期傾倒していたビンスワンガー(Ludwig Binswanger)や木村敏などの著作が書棚の一角を占めていた。懐かしくて,暫しの間読み耽っていた。
ビンスワンガーの著作で,最初に読んだのは『現象学的人間学』だった。本書は,彼の代表的な講演と論文をまとめたものである。フッサールの現象学を精神医学のなかに方法としてとり入れ,人間存在の根本構造への探究をテーマとする思索が語られている。ハイデガーやサルトルなど実存主義に傾注していた私は,それ以後,彼の著作や関連書を読み漁った。
『夢と実存』『精神分裂病』『失敗した現存在の三形式』『メランコリーと躁病』『妄想』などが,メモやノート類とともにあった。読み返していると,気恥ずかしくなるような文章だが,当時の自分が思い出されて懐かしい。
木村敏氏の著作からも随分と影響を受けた。『自覚の精神病理 自分ということ』『人と人との間 精神病理学的日本論』『異常の構造』『分裂病の現象学』などが書棚に並んでいる。特に,自己・あいだ・時間 現象学的精神病理学』『時間と自己』『人と人とのあいだの病理』など,木村氏独自の「時間論」や「対人関係論」には多くの示唆を受けている。
他にも,ヴァイツゼッカーやテレンバッハ,ブランケンブルグ,荻野恒一,宮本忠夫など,懐かしい名前が並んでいる。それらを手にとって開くと,若き日の自分が蘇ってくる。ブランケンブルク(Wolfgang Blankenburg)の『自明性の喪失』は,原書と木村敏の翻訳本とを比較しながら,ドイツ語の勉強も兼ねて読んだ。悪戦苦闘の日々であったが,精神医学から哲学(現象学・実存主義)とドイツ語を学んだ面もある。
今は違う方向に進んでいるが,私の精神構造や思考形成に多大な影響を与えていることは事実である。ものの見方・考え方,思想形成には,若い日の思索が重要である。どんな本を読み,何に興味をもち,どんなことを考えていたか,思考訓練がその人間形成に及ぼす影響は大きい。
いくら専門的な学術書を読もうとも,偏った読解や独断的な読み方をすれば,その理解も解釈も歪んだものになる。書を求める目的や意図が偏向していれば,書から得られる知もまた屈折したものとなる。
それを補正してくれるのが,学問上の師であり,学究上の友であり,忌憚のない意見を述べてくれる仲間である。自分と異なる思考や意見を受け入れながら自分を変革する心理が働かなければ,意固地な偏狭さに陥ってしまい,人との関係性を自ら断ち切ってしまうことになる。
「孤立無援」など決して自慢できるものではない。人に理解されないのは,理解しようとしない他者のせいではなく,理解されない自分のあり方に起因すると思う。人を理解しようとしない者は,人から理解されることもないだろう。
かつて恩師から臨床心理学・精神分析学を学ぶ際に注意すべき心得として教えられたのは,研究対象あるいは患者は「自分と同じ人間」であるという認識を常に自覚しておくこと,決して「モルモット」のように見てはならないということであった。
分析・考察することにとらわれすぎると,症例や事例を比較検証して合致する「タイプ」や「病名」を見つけ出すこと,心理状態や精神構造をあれこれと論じること自体が目的と化してしまい,研究のための対象としてしか見えなくなってしまうことがある。
臨床心理や精神分析,精神医学の目的は,その人間の心や精神を苦しめる悩みや障害を取り除くことにある。人間を「もの」のように分析・考察・検証することが第一義の目的ではない。手段と目的を混同してはならない。分析・考察・診断することが目的ではない。それらは「手段・方法」であって,「治療すること」が目的である。それゆえに,生半可な自覚で臨床心理や精神分析を学ぶべきではない,そう教えられた。知識の生半可ではなく,目的意識と自覚の重要性を諭された。
現在,学校現場における重要な課題の一つが「特別支援教育」である。ADHDや自閉症など多様な「発達障害」への対応が求められている。その際,対応には専門的な知識が必要であるが,不十分な知識から「分析」することに偏った事例研究が行われてしまう恐れがある。だからこそ,専門機関との連携を密にし,専門家を招いての事例研修などを繰り返すのである。診断については必ず専門医への受診を促すことになっている。教師が診断することは絶対に許されることではない。
血液型占いのように心理学を応用した心理テストの類なら遊びの範疇だろうが,専門書をかじった程度の知識で人間を分析することなどできないし,するべきではない。人間はそんなに単純な精神構造ではない。人が人を裁くと同じように,それ以上に人の心理や精神に対して診断を下すことは危険なことなのだ。
何でもかんでも書に頼ること,専門書を読んだことで理解できたと思い込み,独断・偏見で決めつけて論ずることに一抹の危惧を感じている。同様に,本来まったく別の事柄ついて別の高説を引き合いに出して,無理矢理にこじつけて断定する論法にも違和感を感じている。
たとえば,教師という職業の属性から陥りやすい心理的・精神的疾患を分析・考察してcategorizeしても,それがすべての教師に合致するわけではない。あくまでも属性からの一般的傾向を提示しているにすぎない。いくつかの特質や特徴を組み合わせたり,それに合致する事柄を摘出したりして,だから「この人間(個人)」はこうであると決めつけて論じること自体が危険性をはらんでいる。なぜなら,個別の「診察」もせずして,教師という属性のもつ一般的傾向にすぎないことを「個人」にあてはめようとしているからだ。それは「こじつけ」と変わらない。
臨床心理学や精神分析学,精神医学は「個人」を対象としているのであって,その「個人」を直接に診察もしていないのに一般論から「その個人」に関して診断的見解を述べることは絶対にしない。それは個人の尊厳を冒涜する行為であり,許されざる行為である。医者でもない人間が特定の人間に病気であると告知するのと同じである。
心理学や精神分析学,精神医学において,その研究方法や分析手法,理論を他の分野に生かすことは有用性があると考えている。
実際,ユング派の分析家であって臨床心理学の第一人者であった故河合隼雄氏やフロイト派の小此木敬吾氏など多くの心理学者や木村敏氏などの精神科医が,人間論や文明論,社会論,教育論に関する論考や評論を多く発表している。私は学問的応用として他分野に適用することを否定してはいない。
しかし,それはあくまでも学問としての応用であって,他者の人間像や心理・精神構造を考察するために,専門家でもない素人が安易に使うべき方法ではない。なぜなら,病気と同じく,素人の「診断」ほど的外れなことはないからだ。
専門書に載っている症例や病状,事例を参照し,似たような兆候・状態を見つけ,専門家の分析と考察を引き合いに出して当てはまっていると独断してしまうことは,その人間に対する偏見につながる。
特に,専門書に載っている精神病理や精神障害,精神異常等に関する症例や事例を参考にしたり,専門家の分析手法や考察を真似たりして,素人が他者に対して専門的な判断を軽率に行うことは,実に危険なことである。
専門書を何冊か読めば,ある程度は知識としては理解できる。だが,専門書を読んだ程度で「診断」したり「断定」できるほど,人間の精神構造,精神病理は簡単なものではない。理解することと「診断」できることはまったく別である。
もし,そうした素人考えを「公言」するならば,その責任は多大である。学者や専門家の一人二人が言っていたことを鵜呑みにし,それを都合よく一般化して事実であるかのように,皆がそう判断しているかのように吹聴する。責任はその専門家に被せて,自分はそう聞いたから,そう理解したから,その専門家が述べているからと責任転嫁する。「そのように聞きましたので」とか「かもしれない」「思われます」とかで誤魔化せるような問題ではない。安易な言動は人権侵害になるからだ。
自己正当化は,時として他者に対する人権侵害にまで及ぶことがある。自分を正しいと思い込むことで他者に対して攻撃することさえも肯定してしまう。「目的が手段を正当化する」ことは絶対に許されることではない。目的の正しさと手段の正しさは別のことだ。
もし臨床心理学や精神分析学,精神医学を悪用するならば,それは犯罪行為に等しい。たとえば,特定の人間に対して「精神的疾患」「精神病的傾向」があるなどと意図的に公言すれば,明らかな人権侵害である。巧妙な手法を用いたり,間接的な表現を使ったりして,暗に感じさせても同じである。姑息な分だけなお質が悪い。
同様のことは,教育に関しても言える。「教える」という行為には常に最新の専門知識と検証が求められる。まちがった内容を教えることの責任は大きい。今,自分が生徒に伝えている情報は正しいのか,正確なのか,教科書記述に従ってよいのか,この教授法でよいのか…等々,常に悩む。専門文献や最新の資料を調べてもなお不安は尽きない。
だからこそ研修を積み重ねることが責務なのである。「研修」とは「研究」と「修養」を意味する。そして,まちがっていれば,潔くあやまり改める勇気をもちたいと思っている。詭弁を弄して自己正当化をはかる意固地さは愚かな驕りでしかない。
私はそう自戒している。
部落史・ハンセン病問題・人権問題は終生のライフワークと思っています。埋没させてはいけない貴重な史資料を残すことは責務と思っています。そのために善意を活用させてもらい、公開していきたいと考えています。
