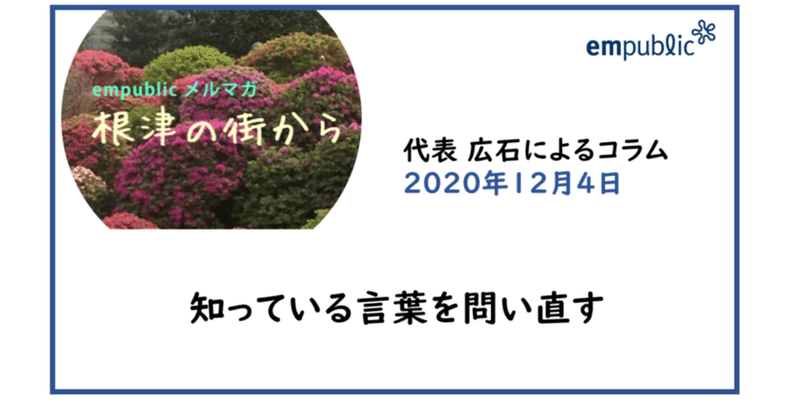
「新しい知恵に向けて(1)」ーempublicメールマガジン「根津の街から」(2020年12月4日発行)
最近、テレビでもSDGs関連の話題が増えたと思います。
その話題が「エコが大切ですね」と締め括られるのを何度か見ました。
やはりサステナビリティが「エコ=地球に優しく」というイメージが根強いのかな、と思いました。
10/16のコラムで紹介したように「持続可能性」は90年代の「地球に優しくする」から、環境問題に加え、様々な人権や社会課題、経済のあり方そのものを問う言葉となっています。
*コラムをnoteで公開中! https://note.com/empublic/n/nf6295eb8bfd9
「経済のあり方そのものを問う」というと難しそうに思いますが、今年はそれを身近に感じる出来事が2つ起きました。
一つは、COVID-19感染拡大によって、感染症・健康の問題が経済社会を止めるリスクとなることを世界が同時に体験したことです。
このパンデミックは最後のパンデミックではなく、これからも起きる可能性があります。
気候変動、貧困・格差などの数多くの環境・社会の問題が起き、それらがビジネスや地域に影響を与える可能性が高まっていることの実感が高まったと言えるでしょう。
そして、COVID-19によって東京の人口は転出が増え、4か月連続で減少しています。
今は一時的かもしれませんが、「東京の人口減少は未だ先」と思われていたことが実際に起きています。
もう一つは、政府が「2050年の炭素排出量の実質ゼロを目指す」ことを宣言したことです。
日本は、世界全体の二酸化炭素排出量の約3.4%を排出しています。
最も多かった2013年から2018年は12%削減しましたが、これまでの流れでは無理です。
産業も、エネルギー構成も、ライフスタイルも大きな転換が必要となります。
この2つは、まだ目に見える影響まではなっていないまでも、流れが変わってきたと感じる人が増えるきっかけにはなっているでしょう。
それは、前例がない事態、つまり従来の正解が通用しない変化に対応する場面が増えていることも意味します。
それは、「分野別の与えられた問題を間違えずに解く力」「事前に計画を決め、それを確実に実行する力」という従来の優秀さだけでは通用しない場面が増えていることを意味します。
環境、社会、経済を別に考えるのでもなく、環境・社会か経済か、ではなく、環境や健康・人権に配慮しながら経済社会を機能させる“新しい知恵”が必要とされています。
そのような正解のない状況で、多様かつ複雑な問題を乗り越え、持続可能な経済社会を実現できる人は、どのような人なのでしょうか?
その人物像を、UNESCOの「持続可能な開発のための教育(ESD)」の経験からまとめられた「持続可能性キー・コンピテンシー」を軸に描きたいと考え、書籍を出しました。
それが、新刊「SDGs人材からソーシャル・プロジェクトの担い手へ ~持続可能な世界に向けて好循環を生み出す人のあり方・学び方・働き方 」です。
「ソーシャル・プロジェクトを成功に導く12ステップ」を共に書いた佐藤真久さんとの共著で、姉妹本として執筆しました。
国際的なESDの議論に参画してきた佐藤真久さんと一緒に書くことで、私自身が現場で考えてきたことを整理でき、また共に具体化していきました。
執筆は、正しさとは? 問題解決とは? 計画とは?などを改めて考え、深めていく時間になりました。
この本の執筆の背景、伝えたいことを、このコラム、note、イベントでお伝えしていければと考えています。
*書籍は12月25日発売で、現在、empublic STOREでは予約割引販売中です。
姉妹本セット割もあります! https://empublic.stores.jp/
(エンパブリック代表 広石)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
